過去問をいつからやるのか?早稲田大学に合格した講師に聞いてみた
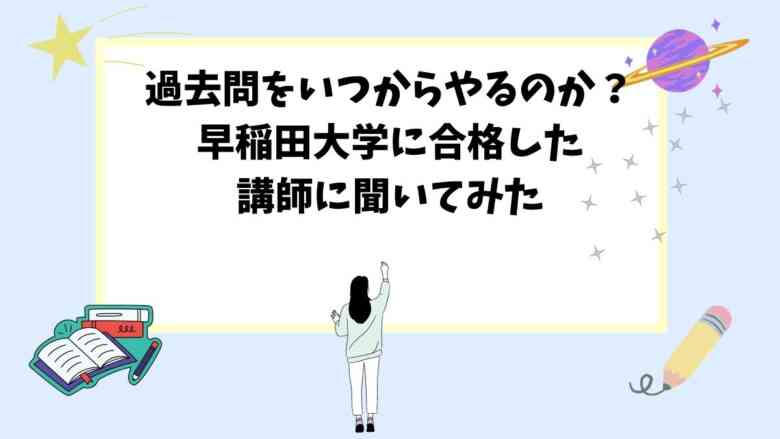
※この記事には一部PRが含まれます。
こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。
受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。
今回のお悩みはこちら。
過去問の使い方って?
過去問を使って便給した体験談を聞きたい
大学受験勉強していると、過去問対策って気になりますよね?
実は、今回紹介する「過去問をいつからやるのか?早稲田大学に合格した講師に聞いてみた」を読めば、過去問をいつからやるのか、わかります。
なぜなら、過去問対策をしっかりして、早稲田大学に現役で合格した講師に聞いた内容だからです。
この記事では、過去問をいつからやるのか?具体的に紹介しています。
記事を読み終わると、過去問をいつからやるのか?わかります。
過去問の勉強の仕方と使い方
過去問をいつからやるのか?早稲田大学の講師に聞いてみた!
今回取材した、早稲田大学の学生が
通っていた予備校!
東進は現役合格実績No.1の大学受験予備校
あなたの夢もきっと叶うはず!
圧倒的No.1、日本一の【現役合格実績】
資料請求はスマホで1分!無理な営業も一切なし!
近くの東進を検索してみよう!
Contents
過去問をいつからやるのか?早稲田大学に合格した講師に聞いてみた

過去問をいつからやるのか?についてまとめてみました。
以下のポイントについて説明しています。
過去問題集(赤本)とは
過去問はいつからやるのか
過去問は何年分やるのがおすすめ?
過去問題集(赤本)とは
受験生なら誰しもが聞いたことのある赤本(過去問題集)は、赤い表紙でおなじみの教学社が発行している大学入試の過去問題集です。
大学・学部別に分かれており、378大学614点の赤本があり、日本の大学の過去問が網羅されています。
赤本には各大学や学部の対策や傾向、解答・解説が記載されており、大学や学部によって異なるものの、過去3年〜10年分の問題が収録。
したがって、志望大学合格のための対策には必要不可欠なものとなります。
人気のある大学や学部は売り切れることもあるので、夏までには購入するのがおすすめです。
そのためには、夏までには進路を決めておく必要があります。
赤本は受験勉強で一番大切だと言われている過去問対策を効率よくできる問題集です。

参考記事:文系高2、受験勉強「何から?」合格への年間計画と先輩の実践ロードマップ
過去問はいつからやるのか
最初は1年生と2年生の復習が終わっていなくても夏休みには、第1志望校の赤本を1回分は解いてください。
理由は、夏休みまでに赤本を解くことで、現在の自分の実力や、苦手分野を知るためです。
また、早い時期に過去問に触れておけば、どのように勉強していけばいいのかがわかり、学習計画が立てやすくなります。
本格的に赤本を開始するのは、11月から12月がおすすめです。
なぜなら、11月から12月は大学入学共通テストや二次試験の過去問を本格的に始める必要があるからです。
基礎勉強ばかりをして、ぎりぎりになって過去問題を解くと、そこではじめて自分の弱点を知ることになります。
しかし、それでは弱点克服や受験対策をする時間がありません。自分の現段階の実力を客観視するためにも、余裕を持って取り組みましょう。
第一志望以外の赤本も、11月ごろに解き始めるとよいでしょう。
私立大学を希望している場合は、大学によって出題傾向が異なります。
それらを把握するためにも、なるべく早く取り組んで分析しましょう。

参考記事:高校1年生の勉強時間と勉強法!現役で合格するために大切なポイントはこれだ!
過去問は何年分やるのがおすすめ?
第1志望の大学では10年、それ以外の大学でも最低5年は解いてください。
理由は、10年分解くことによって試験や出題傾向、問題形式に慣れることが挙げられます。
また、繰り返し過去問を解くことで、落ち着いて試験に対応できるでしょう。
正しい使い方をして、過去問演習することで、点数アップが期待できるでしょう。
国公立大学でも、私立大学でも第一志望以外の過去問は5年以上解くことがおすすめ。
理由は、大学受験は何があるかわかりません。
第1志望に失敗したときのことも考えて、滑り止め対策をする必要があるのです。
第2志望の過去問を解くことは、受験勉強にもつながるので受験する予定の大学の過去問はすべてやるのがポイント。
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ
※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
過去問を使う目的を考える

大学受験の過去問を解く目的は、大きく分けて以下の3つです。
実力測定
題傾向分析
時間配分戦略の立案
実力測定
過去問を解く目的の1つである「実力測定」について、詳しく解説します。
実力測定とは、自分の現在の学力や能力を客観的に測ること。
志望校の過去問を解くことで、合格ラインに達しているかを判断できます。
実力測定を目的として過去問を解くことで、以下のメリットがあります。
・現状の学習状況を把握できる
・学習計画を修正できる
・合格ラインを把握できる
過去問を解くことで、自分の実力をしっかりと理解しておきましょう。

参考記事:【必見】模試の復習法はこれで完璧!教科別の具体的な勉強法!次回の模試は成績アップ!
出題傾向の分析とは
過去問を解く目的の1つである「出題傾向の分析」について、詳しく解説します。
出題傾向の分析とは、志望校がどのような問題を、どのような出題形式で出題するのかを把握すること。
出題傾向を把握することで、効率的な学習につながります。
出題傾向の分析を目的として過去問を解くことで、以下のメリットがあります。
・志望校の入試問題を理解できる
・効率的な学習計画を立てられる
・本番で力を発揮できるようになる
出題傾向の分析を目的として過去問を解く際には、以下のポイントを押さえましょう。
・志望校の過去問を複数年分解く
・出題形式や頻出分野を把握する
・出題の傾向やねらいを理解する
出題傾向の分析をすることで、志望校の入試問題を理解し、効率的な学習計画が立てられます。

参考記事:【必見】早稲田大学に合格した学生が使っていた英語の参考書を紹介!
時間配分戦略の立案とは
過去問を解く目的の1つである「時間配分戦略の立案」について、詳しく解説します。
時間配分戦略の立案とは、試験当日にどの問題にどれくらいの時間をかけるのかを決めること。
時間配分戦略を立てることで、本番で焦らずに問題を解き進められます。
時間配分戦略の立案を目的として過去問を解くことで、以下のメリットがあります。
・本番で焦らずに問題を解けるようになる
・合格ラインに達するために必要な時間配分がわかる
時間配分戦略を立てる際には、以下の点に注意しましょう。
・時間配分は、過去問を解いて自分の実力に合わせて調整する
・時間配分は、各科目の難易度や所要時間を考慮する
・時間配分は、余裕を持った計画を立てる
時間配分戦略は、本番で合格するために重要な要素です。
過去問を解いて、自分に合った時間配分戦略を立てましょう。
参考記事:GMARCHに合格できる塾・予備校・コーチング塾おすすめ20選!
参考記事:日東駒専合格者が選んだ塾・予備校とは?おすすめ20選!実績豊富な塾・予備校
過去問の勉強の仕方と使い方

過去問の勉強の仕方や使い方についてまとめてみました。
以下の悩みを解決します。
時計を用意して取り組む
過去問は繰り返し解くのが基本
問題傾向を知る
時計を用意して取り組む
過去問(赤本)に取り組む場合には、必ず時計を用意してから挑戦してください。
なぜなら、問題を解く時の時間配分を体で覚えるためです。
ただ解くのではなく試験本番を想定して、時間的に余裕があるのか?もう少し問題を解くスピードを早める必要があるのか?時間配分を気にしてください。
試験当日に時間が足りなくなると、平常心を保つのが難しくなります。
そのため、ケアレスミスなどの間違いが起こることもあるのです。
大問ごとに時間の目安を決めて取り組むことで、苦手分野を特定することもでき、試験当日の効率の良い解き方をマスターしてください。
試験当日の試験時間を守って過去問に取り組み、時間配分を覚えるのがポイントです。

参考記事:偏差値50から早稲田大学に合格した講師に勉強時間と勉強法を聞いてみました!
過去問は繰り返し解くのが基本
過去問は繰り返し解くのが基本です。
理由は、過去問で間違えた問題は、すべて解答できるようにするのがポイントだからです。
大学入試では似たような問題が出題されることもあります。
過去に出題されたから、この問題はやらなくて大丈夫だろうという気持ちが合格の可能性を下げるのです。
過去問では正解した問題に注目するのではなく、わからない問題や苦手な問題にこそ重点的に取り組みましょう。
ただ答え合わせをしただけ、解説を読んだだけでは、いつまでも克服できません。
実際に何度も繰り返して解くことで、苦手な問題をなくしていきましょう。

参考記事:【必見】早稲田大学に合格した!英語の勉強法と勉強時間をマネすることは良いことだ!
過去問で出題傾向を知る
過去問に取り組む目的には出題傾向を知ることがあります。
なぜなら、過去問に目を通したり実際に解いたりすることで、どの単元からどんな問題がよく出るのか、どのような形式で出題されやすいのか、出題傾向を把握できるからです。
過去数年分の過去問を解くことで、どのような問題がどのような形式で出題されるのか、その大学の出題傾向がわかるようになります。
大学によって出題傾向はさまざま。
志望大学の受験で合格するためには、過去問で出題傾向をしっかりと把握し、それにあった対策をするのが基本です。
現役合格実績No.1!東進ハイスクール・東進衛星予備校
※全国から選りすぐりの予備校界最強【実力講師陣】
駿台では100年以上積み上げてきたノウハウ!駿台予備校
※個別指導でどんな志望校でも合格を目指せます!
過去問の勉強法を早稲田大学の講師に聞いてみました

早稲田大学の講師に過去問の勉強法について聞いてみました。
以下のポイントについて説明しています。
過去問に取り組む目的や注意点
何年分やったの?
過去問をやり始めた時期
過去問を最初にやったのは、高校3年生の夏休みです。
夏休みにやった理由は、とりあえず、夏までには1回解いていたほうが良いと言われたので、早稲田大学の直近の過去問を解きました。
この時はまだ、受験勉強の基礎固めをすべて終えていなかったので、自信はありませんでしたが、正答率は50%以下だったのを覚えています。
センター試験の過去問では8割以上の正答率だったので、ちょっとショックでした。
始めて早稲田大学の過去問を解いた時の印象は、「超難しい!」の一言です。
しかし、早い段階で早稲田大学の過去問を解くことで、入試の難易度が理解できたので良かったと思っています。

参考記事:受験でメンタルがボロボロになった時に読めば効果あり
過去問に取り組む目的や注意点
過去問に取り組む目的は、自分の現在の学力と志望校との距離を測るのが目的。
過去問を解くことで、自分の苦手分野がわかったので、効率よく苦手分野の克服に時間を費やせました。
過去問の正答率には一喜一憂せずに、間違えた問題をしっかりと理解することを繰り返して実施。
また、過去問を解く時の注意点としては、必ず時計を横に置いてから取り組みました。
理由は、時間配分を覚えるためです。
過去問を解く時は、時計は必需品となりますので、時間を気にしながら取り組むことがおすすめです。

参考記事:【古典の勉強法】古文漢文が苦手な高校生!効率的にテストの点数を爆上げ
何年分やったの?
最初に過去問をやったのは8月ですが、本格的に過去問に取り組んだのは、11月頃からです。
基礎固めがすべて終わってから、過去問に取り組みました。
第1志望の早稲田大学の過去問は10年分を各1回解きましたが、直前の過去問だけは2回解きました。
早稲田大学は3学部を受験する予定だったので、30年間分以上の過去問を解いたことになります。
第2志望の赤本は5年分解きました。
内訳は、明治2学部分、青学2学部分、立教2学部分、法政1学部です。
第2志望だけでも、35年分の過去問を解いたことになります。
とにかく時間配分を気にしながら、黙々と集中して過去問に取り組みました。
現役合格実績No.1!東進ハイスクール・東進衛星予備校
※全国から選りすぐりの予備校界最強【実力講師陣】
駿台では100年以上積み上げてきたノウハウ!駿台予備校
※個別指導でどんな志望校でも合格を目指せます!
過去問対策で有効的な勉強法

最後に、過去問の有効的な勉強法を紹介します。
塾で過去問の添削を受ける
苦手分野の克服
過去問の勉強法で苦手分野を克服するためには、以下のポイントを押さえましょう。
【間違えた問題の原因を分析】
過去問を解いて間違えた問題は、必ず原因があります。その原因を分析することで、苦手分野を明確にする。
間違えた問題の原因は、大きく分けて以下の3つです。
・知識不足
・解法がわからない
・計算ミス
知識不足の場合は、その分野の知識を復習。
解法がわからない場合は、参考書や問題集で解法を学び直し。
間違えた問題は、必ず復習。
復習することで、正解する力が身につきます。

塾で過去問の添削を受ける
塾で過去問の添削を受けるメリットは、以下の3つです。
1.プロの講師から的確なアドバイスがもらえる
塾の講師は、過去問を解くためのノウハウや、苦手分野の克服方法を熟知しています。添削を受けることで、自分の答案を客観的に分析し、適切な対策を立てられます。
【2.他の受験生の答案と比較できる】
塾によっては、過去問の添削を他の受験生の答案と比較して行う場合があります。他の受験生の答案と比較することで、自分の答案の強みや弱みを客観的に把握できます。
3.モチベーションを維持できる
塾で過去問の添削を受けると、自分の答案を講師に評価してもらえます。評価してもらうことで、モチベーションを維持し、学習意欲を高められます。
塾で過去問の添削を受けると、プロの講師から的確なアドバイスが受けられます。検討してみてはいかがでしょうか?
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ
※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
まとめ:過去問をいつからやるのか?早稲田大学に合格した講師に聞いてみた

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「過去問をいつからやるのか?早稲田大学に合格した講師に聞いてみた」は参考になりましたでしょうか?
まとめ:過去問をいつからやるのか?早稲田大学に合格した講師に聞いてみた
大学受験の過去問は、志望校の入試の難易度や出題傾向を知るために重要なツールです。そのため、過去問を解く時期や勉強法は、志望校や自分の学力レベルに合わせて検討することが大切です。
【過去問を解く時期】
一般的には、高校3年生の夏休み頃から解き始めるのがおすすめです。基礎学力が十分に身に付いていないと、過去問を解いてもなかなか理解できないでしょう。
ただし、基礎学力が十分に身に付いていると判断できる場合は、高校2年生の夏休み頃から解き始めてもよいでしょう。また、志望校の入試難易度が高い場合は、早めに過去問を解いて対策を立てることも大切です。
過去問を解く際には、以下のポイントを押さえましょう。
【時間を計って解く】
本番の試験時間と同じように、時間を計って解くことで、本番に備えられます。
【間違えた問題の原因を分析する】
間違えた問題は、必ず原因があります。その原因を分析することで、苦手分野を明確にできます。
【間違えた問題を復習する】
間違えた問題は、必ず復習しましょう。復習することで、正解する力が身につきます。
【苦手分野を克服する】
苦手分野は、他の分野よりも重点的に対策しましょう。
【塾で過去問の添削を受ける】
塾で過去問の添削を受けることで、プロの講師から的確なアドバイスを受けられ、他の受験生の答案と比較して自分の答案を客観的に把握できます。また、モチベーションを維持し、学習意欲を高められます。
過去問は、志望校合格への近道です。しっかりとした計画を立てて、過去問を活用して効率的な学習を進めましょう。
予備校オンラインドットコムおすすめ塾の紹介
【オンライン学習塾】
大学受験に強い!オンライン家庭教師おすすめ40選!合格実績・料金を比較
【学習管理塾】STRUXはおすすめ?評判・料金・特徴を塾経験者が取材してわかったこと
【必見】スタディコーチの口コミ・評判が気になる方!塾経験者が調査しました!
オンライン家庭教師高校生におすすめ20選!ランキング形式で解説!
キミノスクールに興味のある方必見!【口コミ・評判・料金】を徹底調査!おすすめできるオンライン塾?
モチベーションアカデミア│評判・口コミ・料金・合格実績を徹底調査
【アガルートコーチング】評判・口コミ・料金・特徴を調査した結果?
トウコベの料金(月謝)を調査・比較した結果は?東大生によるオンライン個別指導を解説
早慶専門塾HIROA CADEMIAの口コミ・評判は高い?料金も徹底調査
メガスタの料金(入会金・授業料)はいくら?他のオンライン家庭教師と比較
オンライン家庭教師WAMの料金は高い?他塾と料金を徹底比較!割引情報あり
ホワイトアカデミー高等部の料金・口コミ・評判を担当者に直接取材!
【必見】オンライン家庭教師e-Liveの口コミ・評判・料金を徹底調査してみた!
【オンライン塾】
高校生の英語に強いオンライン塾【OUTCOME】の料金・口コミ・特徴を徹底調査
オンライン自習室が無料で使える!高校生におすすめできる塾8選
【大学受験】オンラインコーチング塾徹底比較!高校生・浪人生の選び方・費用
コーチング塾とは?高校生におすすめ!オンラインコーチング塾20選
キミノスクールに興味のある方必見!【口コミ・評判・料金】を徹底調査!おすすめできるオンライン塾?
AOI塾の料金は高い!他の総合型選抜専門塾と比較した結果は?
【武田塾みたいな塾】塾経験者がおすすめする塾10選!優れた指導で効果抜群
浪人生に人気のあるオンラインコーチング塾14選!料金や特徴を解説
【必見】オンライン家庭教師e-Liveの口コミ・評判・料金を徹底調査してみた!
AOI塾の料金は高い!他の総合型選抜専門塾と比較した結果は?
浪人生におすすめオンライン家庭教師26選!ランキング形式で徹底比較
浪人生の皆さん予備校はオンライン塾がおすすめな理由知ってます?
【オンライン予備校】
総合型選抜(旧AO入試)対策塾【安い!おすすめ15選】受験生必見!料金相場とは?
【浪人生・現役生】月謝が安いオンライン塾・予備校おすすめ16選
【オンライン予備校厳選25社】浪人生に塾経験者がおすすめするオンライン塾の紹介
ホワイトアカデミー高等部の合格実績は?メリット・デメリットは?
MeTULAB(ミートゥーラボ)【料金・評判・口コミ】東大生講師によるオンライン個別指導塾を徹底調査
東進ハイスクール・東進衛星予備校【料金表まとめ】入学金・授業料を徹底解説
プリンターを持っている方なら純正インクを使用するよりも安く印
互換・リサイクルの格安プリンターインクの専門通販サイトインク
現在メーカーでは生産終了してしまっているインク型番まで幅広く

