【大学入試小論文の書き方】構成・例文・書き出し・結論まで徹底解説
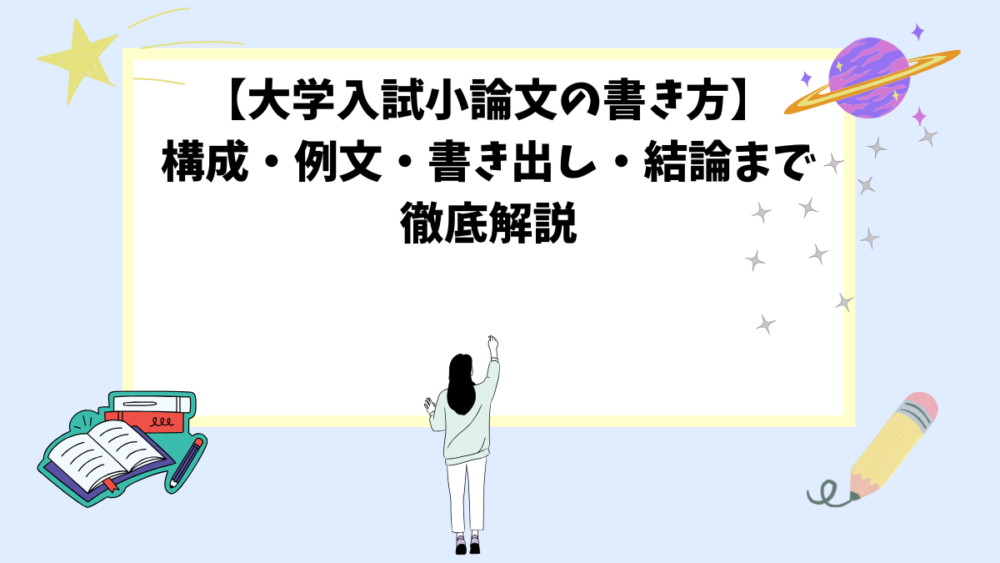
「※この記事には一部PRが含まれます」
大学入試における小論文は、多くの受験生にとって対策が難しい科目の一つかもしれません。
「何を書けばいいの?」「どうやって構成すればいいの?」「作文と何が違うの?」そんな疑問や不安を抱えている高校生も多いのではないでしょうか。
この記事では、大学入試の小論文で合格点を取るための基本的な書き方から、評価される構成のコツ、すぐに使える例文、そして多くの受験生が悩む書き出しと結論の作成方法まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。
この記事を読めば、小論文の全体像が掴め、自信を持って対策を始められるはずです。
一緒に小論文の不安を解消し、合格への一歩を踏み出しましょう!
小論文と作文の違いを理解し、大学入試に求められる小論文の基本がわかる
高評価につながる小論文の構成と、各パート(書き出し・本論・結論)の書き方がわかる
頻出テーマに対応できる論理的な思考力と、説得力ある文章表現のコツがわかる
実際の例文から学び、実践的な小論文対策を始められる
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
Contents
小論文の基本と評価基準(書き方・構成・例文・書き出し・結論)

小論文とは何か、大学入試でなぜ重要なのか、そしてどのような点が評価されるのか、基本的な知識をしっかりと押さえましょう。
大学入試での小論文の目的
合否を分ける評価ポイント
小論文とは?作文との違い
小論文とは、与えられたテーマや課題に対して、自分の意見や主張を明確にし、その根拠を論理的に述べる文章のことです。
客観的な事実やデータに基づいて、筋道を立てて説明する能力が求められます。
一方、作文は、自分の経験や感想、考えなどを比較的自由に表現する文章です。
感情表現や描写の巧みさが重視される傾向にあります。
大学入試で求められる小論文と作文の主な違いは以下の通りです。
| 比較項目 | 小論文 | 作文 |
|---|---|---|
| 定義 | 与えられたテーマに対して、自分の意見や主張を論理的に述べる文章 | 自分の経験や感想などを自由に表現する文章 |
| 目的 | 読者を説得すること、問題提起と解決策の提示 | 自己表現、感情や体験の伝達 |
| 内容の根拠 | 客観的な事実・データ・論理的な推論 | 個人的な経験・感想・主観的な意見 |
| 文体 | 論理的・客観的な表現(「だ・である調」または「です・ます調」)※文体は統一が必要 | 比較的自由な文体 |
| 構成 | 序論・本論・結論など、明確で論理的な構成が必要 | 起承転結など、比較的自由な構成が可能 |
| 大学入試で求められること | 考えの深さ、論理的な説明力 | ※作文は一部の推薦入試等で使われるが、一般入試では小論文が主流 |

大学入試での小論文の目的
大学がなぜ入試で小論文を課すのでしょうか?
それは、学科試験だけでは測れない受験生の能力を見極めるためです。
具体的には、以下のような目的があります。
・思考力・判断力:物事を多角的に捉え、本質を見抜く力、自分の頭で考える力。
・論理的構成力: 自分の考えを筋道立てて分かりやすく構成する力。
・表現力・文章力:自分の意見や主張を的確な言葉で表現する力。
・課題発見・解決能力: 社会の出来事や課題に関心を持ち、自分なりの解決策を考える力。
・学習意欲・適性:大学での学びに必要な基礎的な素養や、学部・学科への関心の度合い。
つまり、大学は小論文を通じて、「自ら考え、学び、表現できる学生」を求めているのです。

合否を分ける評価ポイント
では、具体的にどのような小論文が高く評価されるのでしょうか?
合否を分ける主な評価ポイントは以下の通りです。
| 評価ポイント | 内容・チェックポイント |
|---|---|
| 課題の正確な理解 | 設問の意図を正しく読み取り、何が問われているかを的確に把握しているか |
| 明確な主張 | 自分の立場や意見がはっきりと示されており、曖昧な表現がないか |
| 論理的な構成と展開 | 序論→本論→結論の流れが自然で、主張と根拠が矛盾なくつながっているか |
| 根拠の妥当性と具体性 | 主張を支える理由や例が、具体的かつ客観的で説得力があるか(体験談だけでなく、社会的事実やデータも活用できているか) |
| 独創性・多角的な視点 | ありがちな意見だけでなく、自分なりの考察や他とは違う視点が盛り込まれているか |
| 文章表現の適切さ | 文法ミスや誤字脱字がないか、文章が読みやすく、専門用語の使い方が適切か |
| 指定条件の遵守 | 文字数、テーマ、資料の使い方など、出題時に指示された条件を守っているか |
これらのポイントを意識して小論文対策を進めることが、合格への近道となります。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
小論文の書き方7ステップ(書き方・構成・例文・書き出し・結論)

小論文をいきなり書き始めるのは難しいものです。
ここでは、質の高い小論文を効率的に書き上げるための7つのステップを紹介します。この手順に沿って練習を重ねれば、誰でも論理的な文章が書けるようになります。
2.自分の意見・主張決定
3.構成案(プロット)作成
4.序論(書き出し)執筆
5.本論(理由・具体例)執筆
6.結論(まとめ)執筆
7.推敲・最終確認ポイント
1.設問・課題文の読解
小論文作成の最初のステップは、設問や課題文を徹底的に読み解くことです。
ここで何が問われているのかを正確に捉えなければ、的外れな内容になってしまいます。
・何について書くべきか(テーマの把握)
・どのような立場で書くべきか(賛成・反対、問題提起など)
・どのような形式で書くべきか(意見論述、課題解決など)
・文字数制限やその他の条件は何か
これらの点を意識し、課題文に線を引きながら重要なキーワードや論点を見つけ出しましょう。
出題者の意図を正確に読み取ることが、高評価の第一歩です。

参考記事:大学の指定校推薦で落ちる確率は?落ちる理由と合格率を高める対策を解説!
2.自分の意見・主張決定
課題文の読解が終わったら、次に自分の意見や主張を明確に決定します。
「私はこの問題についてこう考える」「この課題の解決策はこれだ」という核となるメッセージを一つ決めましょう。
・賛成か反対か?
・どのような解決策を提案するのか?
・何が最も重要だと考えるのか?
主張が曖昧だと、小論文全体がぼやけた印象になってしまいます。
自信を持って言い切れる意見を固めましょう。

3.構成案(プロット)作成
本格的な執筆に入る前に、必ず構成案(プロット)を作成しましょう。
構成案とは、小論文全体の設計図のようなものです。
| 構成要素 | 書く内容(目的・ポイント) | メモ作成時のチェックポイント |
|---|---|---|
| 序論 | 問題提起と自分の立場・主張を示す | ・何について書くのか明確か?・自分の主張が伝わるか? |
| 本論 | 主張を支える理由や根拠を順序立てて述べる具体例(社会的事実・データ・体験など)を入れる | ・理由や根拠が論理的につながっているか?・具体例が説得力を持っているか?・順番が自然か?(論点の流れ) |
| 結論 | 全体のまとめと主張の再確認 | ・主張をもう一度強調できているか?・序論・本論とのつながりは自然か? |
メモ書き程度で構いませんので、各パートで何を書くのかを具体的に書き出しておくと、論理の矛盾や飛躍を防ぎ、スムーズに執筆を進めることができます。
特に本論の骨子をしっかり作ることが重要です。

4.序論(書き出し)執筆
構成案ができたら、いよいよ執筆開始です。
まずは序論(書き出し)から。
序論は、読者の興味を引きつけ、小論文全体の方向性を示す重要な部分です。
| 序論の要素 | 内容・目的 | 書くときのポイント |
|---|---|---|
| 問題提起 | テーマに関連する現状の課題や疑問点を示す | ・読者が関心を持つような切り口にする・社会的な背景を簡潔に伝える |
| 意見提示 | 自分の主張・立場を明確に述べる | ・自分が何を主張したいのかをはっきり書く・あいまいな言い方を避ける |
| 課題文の要約(※必要な場合のみ) | 課題文がある場合に、論点を整理し要約する | ・長文の課題文では要点を簡潔にまとめる・内容を正確に捉えた要約にする |
書き出しで読者の心を掴み、これから何を論じるのかを明確に伝えましょう。
具体的な書き出しのパターンは後ほど詳しく解説します。

5.本論(理由・具体例)執筆
本論は、小論文の中核となる部分であり、序論で提示した主張を具体的な理由や根拠、事例を用いて論証するところです。
構成案で考えた論点を、一つひとつ丁寧に展開していきましょう。
| 本論の要素 | 内容・目的 | 書くときのポイント |
|---|---|---|
| 理由・根拠の提示 | 自分の主張を支えるための論拠を示す。客観的なデータや事実が中心。 | ・「なぜそう言えるのか?」に答える・信頼性のある情報を使う(統計・研究・報道など) |
| 具体例の提示 | 読者が納得しやすいように、主張に合った事例を紹介する。 | ・自分の体験だけに頼らず、社会的・歴史的な事例も活用する・例と主張が結びついているか確認する |
| 論理的なつながり | 文章全体が自然に流れるよう、段落や文の関係性に注意する。 | ・接続詞(たとえば、しかし、したがって 等)を効果的に使う・話の順序に矛盾や飛躍がないかチェックする |
本論の説得力が、小論文全体の評価を大きく左右します。

6.結論(まとめ)執筆
結論は、小論文の締めくくりです。
本論で展開した議論をまとめ、序論で提示した主張を再度明確に示します。
| 結論の要素 | 内容・目的 | 書くときのポイント |
|---|---|---|
| 主張の再確認 | 序論で述べた自分の意見・立場をもう一度明確に示す | ・話がぶれていないか確認する・結論だけが新しい主張にならないように注意 |
| 本論の要約 | 論じた内容や根拠の要点を簡潔に振り返る | ・繰り返しではなく、要点をギュッとまとめる・読み手が納得できる流れにする |
| 今後の展望・提案 | 読者に思考を広げさせるような提案や希望を述べる | ・自分なりの視点で、未来や社会への影響を示す・説得力のある締めくくりを意識する |
読者に強い印象を残し、納得感を与える結論を目指しましょう。
具体的な結論の書き方も後ほど解説します。

7.推敲・最終確認ポイント
小論文を書き終えたら、必ず推敲(すいこう)と最終確認を行いましょう。
時間を置いて客観的な視点で見直すことが大切です。
・誤字・脱字はないか?
・文法的な誤りはないか?
・論理の矛盾や飛躍はないか?
・主張は明確か?根拠は十分か?
・設問の意図に沿った内容になっているか?
・文字数制限は守られているか?
・原稿用紙の使い方は正しいか?(句読点の位置、段落の始めの一字下げなど)
・「だ・である調」または「です・ます調」で統一されているか?
推敲によって小論文の質は格段に向上します。
時間に余裕を持って取り組みましょう。
総合型選抜で逆転合格するなら!
「逆転コーチング総合型選抜」
プロのコーチが生徒をサポート
リーズナブルな料金設定
自分の可能性に挑戦しよう!
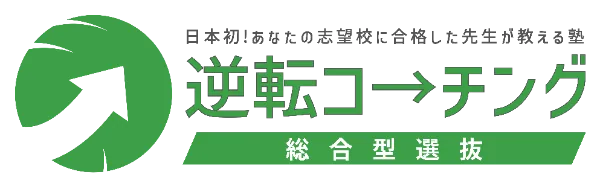
「逆転合格」で未来が変わる
総合型選抜に強い!逆転コーチング
↓↓↓
参考記事:逆転コーチング総合型選抜はやばい?口コミ・評判・料金を徹底取材!
小論文の基本構成と型
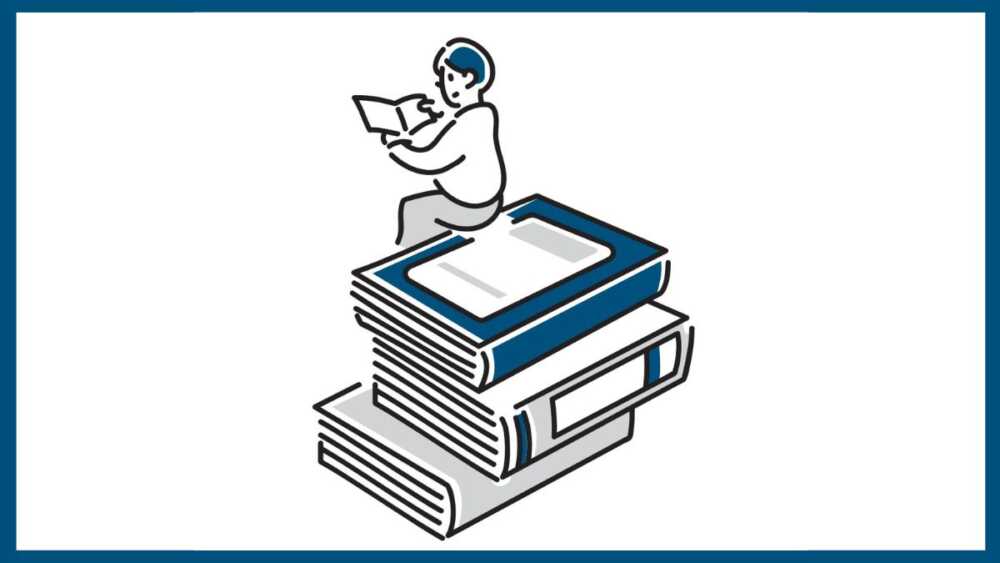
多くの大学入試小論文では、基本的な構成の型があります。これを理解し、自分の意見を効果的に伝えるための枠組みとして活用しましょう。
文字数配分の目安(800字)
PREP法を用いた論理構成
問題解決型の構成パターン
序論・本論・結論の役割
小論文の最も基本的な構成は、「序論」「本論」「結論」の3部構成です。
それぞれの役割を再確認しましょう。
| 構成 | 役割 | 書くことの例 |
|---|---|---|
| 序論 | ・問題提起・テーマの背景説明・自分の立場・主張の提示※読者の関心を引きつけ、「これから何を論じるか」を示す導入部 | ・テーマに関する現状や社会的背景・そのテーマの問題点や課題・課題文の要約(必要に応じて)・本論で論じるポイントの予告・自分の主張・基本的な考え |
| 本論 | ・序論で示した主張を 具体的な理由・根拠・事例を使って論理的に展開する※小論文の中心で、説得力を生む部分 | ・主張を支える複数の理由・各理由に対する具体例(体験・データ・社会的事象など)・反対意見への言及とその反論(必要に応じて)・多角的な分析・視点の提示 |
| 結論 | ・本論での議論をまとめる・序論の主張を再確認する・小論文全体の締めくくりとして読者に印象を残す | ・本論の要点・まとめ・自分の意見や主張の再強調・今後の展望や課題の提示・社会への提案や読者への問いかけなど |
この3部構成を意識するだけで、論理的で分かりやすい小論文が書けるようになります。

文字数配分の目安(800字)
小論文には文字数制限がある場合がほとんどです。指定された文字数の中で、各パートにどれくらいの分量を割くべきか、目安を知っておくと構成が立てやすくなります。
例えば、800字の小論文の場合、一般的な配分は以下の通りです。
・序論:100字~120字程度(全体の約10~15%)
・本論:560字~640字程度(全体の約70~80%)
・結論:100字~120字程度(全体の約10~15%)
これはあくまで目安です。
テーマや論じる内容によって調整が必要ですが、本論に最も多くの文字数を割き、主張を十分に展開することが重要です。
600字の場合は序論・結論を各80~100字、本論を400~440字程度、1000字の場合は序論・結論を各120~150字、本論を700~760字程度と考えると良いでしょう。

PREP法を用いた論理構成
PREP(プレップ)法とは、分かりやすく説得力のある文章を書くための代表的な構成モデルの一つです。
小論文にも応用できます。
| 構成要素 | 内容・役割 | 書くときのポイント |
|---|---|---|
| P = Point(結論・要点) | 最初に自分の主張や結論をはっきり示す | ・読者に「何を伝えたいのか」がすぐに伝わるように書く・あいまいな表現を避け、立場を明確にする |
| R = Reason(理由) | その主張に至った理由や背景を説明する | ・なぜそう考えるのかを論理的に示す・主張と理由の関係が明確になっているか確認する |
| E = Example(具体例) | 主張と理由を裏付ける具体的な事例やデータを挙げる | ・自分の体験、社会的事象、統計などを活用・理由と具体例がしっかりつながっていることが重要 |
| P = Point(結論・再確認) | 最後にもう一度主張をまとめて強調する | ・冒頭の主張を簡潔に繰り返すことで、説得力と印象を高める・一貫性を保ったまとめ方を意識する |
このPREP法を意識すると、論点が明確で、話の筋道が通りやすい小論文になります。
特に本論の各段落をPREP法で構成したり、
小論文全体を大きなPREP法の流れで書いたりすることも可能です。

問題解決型の構成パターン
社会問題や課題に対する解決策を問うタイプの小論文では、問題解決型の構成パターンが有効です。
| 構成ステップ | 内容・役割 | 書くときのポイント |
|---|---|---|
| ① 問題提起(現状分析) | 現在どのような問題があり、それがなぜ課題なのかを具体的に説明する | ・データや事例を使って現状をリアルに描写・「なぜそれが問題なのか」を明確にする |
| ② 原因分析 | 問題が生じた背景や要因を多角的に分析する | ・一つの視点に偏らず、複数の視点(社会・経済・歴史・制度など)から原因を探る・因果関係を論理的に説明する |
| ③ 解決策の提案 | 原因を踏まえた具体的な解決策を示す。複数あればより良い | ・「何をすべきか」を具体的に書く・メリットや実現可能性に触れることで説得力が増す |
| ④ 結論(まとめと今後の展望) | 提案をまとめ、実現後の望ましい未来や追加で考えるべき課題を述べる | ・希望や前向きな視点で締めくくる・読み手に考えを広げさせる問いかけも効果的 |
このパターンは、論理的に問題解決への道筋を示せるため、説得力が高まります。
印象的な書き出しのコツ

小論文の書き出し(序論)は、読者の第一印象を決定づける非常に重要な部分です。
「この小論文を読んでみたい」と思わせるような、魅力的な書き出しを目指しましょう。
問題提起型の書き出し例文
意見提示型の書き出し例文
避けるべきNGな書き出し
書き出しの重要性と種類
書き出しの主な役割は以下の通りです。
・読者の注意を引く: テーマに対する関心を喚起する。
・問題の所在を明らかにする: 何について論じるのかを明確に示す。
・自分の立場・主張の方向性を示す: これからどのような意見を展開していくのかを予告する。
効果的な書き出しにはいくつかのパターンがあります。
代表的なものをいくつか紹介します。
| 書き出しの型 | 内容・特徴 | 書くときのポイント |
|---|---|---|
| 問題提起型 | テーマに関する社会的な問題点を示し、関心を引く | ・「確かにその通りだ」と共感を呼ぶ書き出しを意識する |
| 意見提示型 | 冒頭で自分の主張・結論を明確に述べる | ・立場をはっきりさせて論点を絞るのに効果的 |
| 定義型 | キーワードや用語の定義から書き始める | ・テーマの理解を深めやすく、論点が整理されやすい |
| 具体例提示型 | 実際の出来事や自分の体験などの具体例で始める | ・読みやすく、共感を得やすい・テーマとのつながりを忘れずに |
| 引用型 | 名言・統計データ・報道などを引用して始める | ・引用の信頼性と出典の明記が重要・引用に頼りすぎず、自分の主張につなげる |
| 問いかけ型 | 読者に問いを投げかけ、思考を促す | ・「問い」だけで終わらず、すぐに自分の意見に繋げるのがポイント |
どのパターンを選ぶかは、テーマや自分の書きやすいスタイルに合わせて決めましょう。

問題提起型の書き出し例文
問題提起型の書き出しは、読者の共感を得やすく、スムーズに本論へつなげることができます。
テーマ例:スマートフォンの普及が現代社会に与える影響
近年、スマートフォンの急速な普及は、私たちの生活を劇的に変化させた。情報収集やコミュニケーションが格段に便利になった一方で、歩きスマホによる事故の増加や、SNSを通じたいじめ、情報過多による精神的な疲弊といった新たな問題も深刻化している。はたして、私たちはこの便利なツールとどのように向き合っていくべきなのだろうか?本稿では、スマートフォンの普及がもたらす負の側面に焦点を当て、その適切な利用方法について考察したい。
この例文では、スマートフォンの利便性と問題点を対比させ、読者に課題を意識させています。

意見提示型の書き出し例文
意見提示型の書き出しは、自分の主張を最初に明確にすることで、論旨がはっきり伝わるメリットがあります。
テーマ例:高校生にボランティア活動を義務化することの是非
私は、高校生にボランティア活動を義務化することには反対である。確かに、ボランティア活動を通じて社会貢献の意識を高めたり、多様な価値観に触れたりする機会が得られるという意見もある。しかし、本来自主的な意志に基づいて行われるべき活動を強制することは、かえって生徒の主体性を損ない、活動の形骸化を招く可能性があると考えるからだ。
この例文では、冒頭で「反対である」という立場を明確に示し、その後の論の方向性を読者に伝えています。

避けるべきNGな書き出し
一方で、以下のような書き出しは評価を下げてしまう可能性があるため注意が必要です。
・課題文の丸写し:自分の言葉で問題提起できていないと見なされます。
・一般的すぎる表現:「現代社会は複雑だ」「グローバル化が進んでいる」など、誰でも書けるような抽象的な表現は避けましょう。
・辞書的な定義の羅列: キーワードの定義から入る場合も、それが本論とどう繋がるのかが重要です。単なる説明に終始しないように。
・個人的な感想のみ:「私は~が好きだ」「~は面白いと思う」といった主観的な感想だけで始まると、小論文としての客観性が損なわれます。
・結論が不明確な問いかけ: 問いかけで始めるのは良いですが、その問いに対する自分の考えの方向性を示さないと、読者は何を論じたいのか分からなくなります。
・いきなり本論に入る:問題提起や背景説明なしに、唐突に自分の主張や具体例から入るのは避けましょう。
書き出しは、あなたの小論文の「顔」です。
工夫を凝らして、読者の心を引きつけましょう。
説得力のある結論の書き方

小論文の結論は、それまでの議論をまとめ上げ、読者に納得感と深い印象を残すための重要なパートです。
書き出し同様、最後まで気を抜かずに取り組みましょう。
主張再確認型の結論例文
将来展望型の結論例文
避けるべきNGな結論
結論の役割と重要性
結論の主な役割は以下の通りです。
・主張の再確認:本論で展開した自分の意見や主張を改めて明確に示す。
・議論の要約:本論の主要なポイントを簡潔にまとめる。
・小論文全体の締めくくり:読後感を良くし、論旨を印象づける。
・今後の展望や提案(オプション): 問題解決に向けた未来への視点や、自分なりの提言を加えることで、より建設的な小論文になる。
結論が弱いと、せっかく本論で良い議論を展開しても、全体としてぼやけた印象になってしまいます。

主張再確認型の結論例文
主張再確認型の結論は、最も基本的な結論の書き方です。
本論で述べたことを踏まえ、自分の考えを再度強調します。
テーマ例:AI技術の発展と人間の仕事(本論で、AIは人間の仕事を奪うだけでなく新たな仕事も創出し、人間はAIと協調すべきと論じた場合)
以上、AI技術の発展が人間の仕事に与える影響について考察してきた。確かに一部の定型的な業務はAIに代替される可能性があるが、AIが生み出す新たな産業や、人間にしかできない創造性や共感性を活かした仕事も増えていくだろう。したがって、AIの進化を脅威と捉えるのではなく、人間がAIを有効活用し、より付加価値の高い仕事へとシフトしていくことが重要であると私は結論づける。
この例文では、本論の内容を簡潔に振り返りつつ、筆者の最終的な考えを明確に示しています。

将来展望型の結論例文
将来展望型の結論は、問題解決の先にある未来の姿や、今後取り組むべき課題などを示すことで、読者に希望やさらなる思考を促します。
テーマ例:地球温暖化対策の推進(本論で、再生可能エネルギー導入の重要性や国際協力の必要性を論じた場合)
地球温暖化は、私たち人類全体の喫緊の課題である。本稿で述べたように、再生可能エネルギーへの転換を加速させ、国際的な枠組みの中で各国が協調して対策を講じることが不可欠だ。これらの取り組みを着実に進めることで、私たちは持続可能な社会を実現し、未来の世代に豊かな地球環境を引き継ぐことができるはずだ。そのためには、私たち一人ひとりが当事者意識を持ち、日々の生活の中で環境負荷の低減に努めることもまた重要となるだろう。
この例文では、対策の実行によって実現する未来像を示し、個人の行動変容も促しています。

避けるべきNGな結論
以下のような結論の書き方は、小論文の評価を下げる原因となるため避けましょう。
・新たな論点の追加:結論部分で、それまで触れてこなかった新しい話題や主張を持ち出すのはNGです。議論が拡散し、まとまりがなくなります。
・本論との矛盾:本論で述べたことと異なる意見や、矛盾する内容を結論で書かないように注意しましょう。
・尻切れトンボ・要約不足:主張を再確認せず、単に「以上、~について述べた」だけで終わったり、本論の要約が不十分だったりすると、読者に物足りない印象を与えます。
・過度な一般化や飛躍:本論で述べた範囲を超えて、あまりにも大げさな結論や根拠のない断定をするのは避けましょう。
・感情的な表現に終始する:「~であってほしい」「~だといいな」といった願望や、過度に感情的な言葉遣いは、小論文の客観性を損ねる可能性があります。
・謝辞や反省の言葉:「つたない文章でしたが」「勉強不足を痛感しました」などの言葉は不要です。
結論は、あなたの小論文の「着地点」です。
力強く、そして明確に締めくくりましょう。
合格保証がある!総合型選抜専門塾!ホワイトアカデミー高等部←おすすめ!
※安心できる社会人のプロ講師がマンツーマンで指導!
フルオーダーメイドの授業で合格に導く!総合型選抜専門塾AOI
※小論文、志望理由書など総合型選抜のことならお任せください!
小論文対策に絶対の自信がある!小論文専門:翔励学院
※合格できる小論文の書き方を丁寧に指導!合格率94%
テーマ別小論文の例文と解説

ここでは、大学入試でよく出題されるテーマの傾向と、具体的な例文(良い例・悪い例)を通じて、実践的な書き方のポイントを解説します。
良い例文の共通点と活用法
社会問題テーマの例文と構成
教育・自己PRテーマの例文
NG例文と改善ポイント
頻出テーマの傾向と分析
大学入試の小論文では、以下のようなテーマが頻出です。
これらのテーマについて日頃から関心を持ち、自分なりの意見をまとめておくことが重要です。
【大学入試小論文の頻出テーマ一覧】
| ジャンル | 主なテーマ例 | ポイント・備考 |
|---|---|---|
| 社会問題 | 少子高齢化/格差社会/貧困問題/地方創生/労働問題(働き方改革・非正規雇用など)/ジェンダー平等 | 現代日本が抱える課題に対する自分の考えと解決策が求められる |
| 環境問題 | 地球温暖化/プラスチックごみ問題/生物多様性の損失/再生可能エネルギー | 科学的な理解と、持続可能性に関する自分の意見がポイント |
| 情報・コミュニケーション | インターネット社会の功罪/SNSの影響/フェイクニュース/情報リテラシー/AIの活用と課題 | 情報社会に生きる自分の姿勢や、テクノロジーとの関わり方が問われる |
| 教育問題 | グローバル人材育成/アクティブラーニング/ICT教育/いじめ/学力格差 | 生徒としての立場から、教育に対する考察や改善提案がしやすいテーマ |
| 医療・福祉 | 高齢者医療/地域医療/予防医学/介護問題/健康寿命 | 社会的な制度と個人の意識の両面からアプローチできるテーマ |
| 国際関係・グローバル化 | 異文化理解/国際協力/グローバル経済/紛争と平和 | 世界とのつながり、自国の役割、平和や協力の在り方を考える問題が多い |
| 文化・倫理 | 伝統文化の継承/生命倫理/科学技術と倫理 | 倫理的なジレンマや文化的価値について、自分なりの価値観を述べる力が問われる |
| 自己PR・志望理由(進学動機) | 大学で学びたいこと/将来の夢/社会にどう貢献したいか | 特に推薦入試や総合型選抜で頻出。自分の経験や目標と学部のつながりを明確にする必要あり |
これらのテーマは、単独で出題されることもあれば、複数のテーマが絡み合って出題されることもあります。
新聞やニュース、専門書などを通じて、幅広い知識と多角的な視点を養っておきましょう。

良い例文の共通点と活用法
評価される良い小論文には、いくつかの共通点があります。
・主張が明確で一貫している:何を言いたいのかがすぐに分かり、最初から最後まで論旨がぶれない。
・論理的な構成がしっかりしている:序論・本論・結論の流れが自然で、各段落のつながりもスムーズ。
・根拠が具体的で説得力がある:主張を裏付ける理由や事例が適切で、客観性がある。
・多角的な視点が含まれている:一つの側面だけでなく、複数の視点から物事を捉えようとしている。
・独自の考察や提案がある:ありきたりな意見に留まらず、自分なりの考えや解決策が示されている。
・文章が平易で分かりやすい:専門用語を使いすぎず、誰にでも理解できる言葉で書かれている。
模範例文を読む際は、これらの共通点を探しながら分析しましょう。
そして、良いと思った構成の仕方、論の展開方法、表現方法などを自分の小論文に取り入れられないか考えてみてください。
単に内容を覚えるのではなく、「なぜこの例文が良いのか」を理解することが重要です。

社会問題テーマの例文と構成
テーマ:日本の少子高齢化問題について、その原因と対策を述べよ。(800字想定)
【構成案】
| 構成 | 文字数の目安 | 内容・書くべきポイント |
|---|---|---|
| 序論 | 約100字 | ・日本の少子高齢化が深刻であるという現状の提示・原因と対策を論じることを明示 |
| 本論1:少子化の原因 | 約250字 | ・晩婚化・未婚化(経済的負担や価値観の多様化)・子育てコストの増加(教育費・保育不足)・育児と仕事の両立の難しさ(長時間労働・女性のキャリア) |
| 本論2:高齢化の原因 | 約100字 | ・医療の進歩による寿命の延び・出生率低下に伴う高齢者比率の増加 |
| 本論3:対策提案 | 約250字 | ・子育て支援の強化(保育・経済支援・男性の育児参加)・働き方改革(多様な働き方・長時間労働の見直し)・高齢者の活躍支援(健康寿命延伸・就労機会の創出) |
| 結論 | 約100字 | ・少子高齢化は複合要因であり、総合的な対策が必要・社会全体の支え合いと持続可能な未来への決意 |
【例文(一部抜粋)】
(序論)
我が国は、世界でも類を見ない速さで少子高齢化が進行しており、社会経済システム全体に深刻な影響を及ぼし始めている。このままでは、労働力不足や社会保障制度の持続可能性への懸念がますます高まるだろう。本稿では、この喫緊の課題である少子高齢化の主な原因を分析し、その上で実効性のある対策について考察したい。
(本論1:少子化の原因より)
少子化の背景には、まず晩婚化・未婚化の進行が挙げられる。経済的な不安定さや、結婚に対する価値観の多様化により、結婚を選択しない、あるいは時期を遅らせる若者が増えている。また、子育てにかかる経済的負担の大きさも深刻だ。特に教育費の高騰は、多くの家庭にとって大きなプレッシャーとなっている。さらに、依然として女性に偏りがちな育児負担や、長時間労働が常態化している職場環境も、仕事と育児の両立を困難にし、第二子以降の出産をためらわせる要因となっている。
(結論)
少子高齢化は、経済、社会、個人の価値観など、様々な要因が複雑に絡み合って生じている問題である。したがって、その対策も、子育て支援の抜本的拡充、働き方改革の断行、そして高齢者が生きがいを持って活躍できる社会の構築といった、多岐にわたるアプローチを同時に進める必要がある。重要なのは、この問題を社会全体の課題として捉え、世代を超えて支え合う意識を醸成することであり、それこそが持続可能な未来を築くための第一歩となるだろう。
【解説】
この例文では、序論で問題の重要性を明確にし、本論で原因を多角的に分析(少子化と高齢化を分けて記述)、具体的な対策を複数提示しています。
結論では、議論をまとめ、社会全体の意識改革の必要性にも言及しており、論理的で説得力のある構成になっています。
太字部分は、特に筆者の主張が込められた箇所です。

教育・自己PRテーマの例文
テーマ:あなたが大学で学びたいこと、そしてそれを将来どのように活かしたいか述べなさい。(600字想定)
【構成案】
| 構成 | 文字数の目安 | 内容・書くべきポイント |
|---|---|---|
| 序論 | 約100字 | ・日本の少子高齢化が深刻であるという現状の提示・原因と対策を論じることを明示 |
| 本論1:少子化の原因 | 約250字 | ・晩婚化・未婚化(経済的負担や価値観の多様化)・子育てコストの増加(教育費・保育不足)・育児と仕事の両立の難しさ(長時間労働・女性のキャリア) |
| 本論2:高齢化の原因 | 約100字 | ・医療の進歩による寿命の延び・出生率低下に伴う高齢者比率の増加 |
| 本論3:対策提案 | 約250字 | ・子育て支援の強化(保育・経済支援・男性の育児参加)・働き方改革(多様な働き方・長時間労働の見直し)・高齢者の活躍支援(健康寿命延伸・就労機会の創出) |
| 結論 | 約100字 | ・少子高齢化は複合要因であり、総合的な対策が必要・社会全体の支え合いと持続可能な未来への決意 |
【例文(一部抜粋)】
(序論)
私は貴学の国際文化学部で、異文化コミュニケーション論を深く学びたいと考えている。高校時代の海外研修で、言葉の壁だけでなく文化的な背景の違いから生じる誤解を痛感した経験が、この分野への強い関心を抱くきっかけとなった。
(本論1:大学で具体的に学びたいことより)
特に、グローバル社会における多様な価値観の共存や、文化摩擦の解消に向けた実践的なコミュニケーション手法に関心がある。貴学の「比較文化論」や「国際紛争解決論」といった講義を通じて、文化の相対性を理解し、異なる背景を持つ人々と効果的に対話し、相互理解を深めるための知識とスキルを習得したい。また、少人数制のゼミで積極的に議論に参加し、多角的な視点を養いたい。
(結論)
貴学での4年間を通じて、異文化理解の専門性と実践的なコミュニケーション能力を磨き、将来的には国際協力の現場で、異なる文化を持つ人々の架け橋となれるような人材へと成長したい。そのために、主体的に学び続ける姿勢を持ち続けたい。
【解説】
この例文は、具体的な経験を交えながら学びたい分野を明確にし、大学のカリキュラムにも触れることで入学への熱意を示しています。
そして、将来の目標と大学での学びが具体的に結びつけられており、説得力があります。
自己PR型の小論文では、自分の経験と大学での学び、そして将来の展望を一貫して語ることが重要です。

NG例文と改善ポイント
テーマ:SNSの功罪についてあなたの考えを述べよ。(600字想定)
【NG例文】
現代社会においてSNSは多くの人が利用している。私も毎日使っていて、友達と連絡を取ったり、好きな情報を集めたりするのに便利だと思う。しかし、SNSには悪い面もある。例えば、SNSいじめが問題になっているし、知らない人と簡単につながれるのは危険だと思う。だから、SNSを使うときは気をつけるべきだ。メリットもデメリットもあるので、うまく使うことが大切だ。
【NGポイント】
・主張が曖昧:「うまく使うことが大切だ」という結論は具体的でなく、誰にでも言える内容。
・論理展開が浅い:メリットとデメリットを並べているだけで、深い考察や分析がない。
・具体例が個人的な範囲に留まっている:「私も毎日使っている」という記述は良いが、社会的な影響についての具体例が乏しい。
・表現が稚拙:「~だと思う」「~べきだ」という表現が多く、断定的な意見や客観的な分析が少ない。
・構成が不明確:序論・本論・結論の区切りが曖昧で、論の流れが分かりにくい。
【改善の方向性】
・主張を明確にする:例えば、「SNSは情報伝達の速度と範囲を飛躍的に向上させたが、その匿名性と拡散性がデマや誹謗中傷を助長する危険性を内包しており、利用者の情報リテラシー向上が急務である」など、より具体的な主張を立てる。
「功罪を具体的に分析する」
・功(メリット):情報収集・発信の容易化、多様なコミュニティ形成、災害時の情報共有など、社会的な側面にも言及する。
・罪(デメリット):プライバシー侵害、フェイクニュースの拡散、依存症、精神的ストレスなど、具体的な問題点を挙げる。
・自分なりの解決策や提言を加える:「情報リテラシー教育の重要性」「プラットフォーム事業者の責任」「法整備の必要性」など、より踏み込んだ考察を示す。
・客観的な言葉遣いを心がける:「~と考えられる」「~と指摘されている」「~という課題がある」など、より分析的な表現を用いる。
「序論・本論・結論の構成を意識する」
・序論:SNSの普及状況と、本稿で論じる問題点を提示。
・本論:功と罪をそれぞれ具体的に論じ、その背景や原因にも触れる。
・結論:全体をまとめ、SNSとの適切な向き合い方や今後の課題について提言する。
NG例文を反面教師として、どこをどう改善すればより良い小論文になるのかを考えることも、有効な学習方法です。
合格保証がある!総合型選抜専門塾!ホワイトアカデミー高等部←おすすめ!
※安心できる社会人のプロ講師がマンツーマンで指導!
フルオーダーメイドの授業で合格に導く!総合型選抜専門塾AOI
※小論文、志望理由書など総合型選抜のことならお任せください!
小論文対策に絶対の自信がある!小論文専門:翔励学院
※合格できる小論文の書き方を丁寧に指導!合格率94%
大学入試小論文(書き方・構成・例文・書き出し・結論)注意点

最後に、小論文で高得点を狙うための具体的な対策方法と、執筆時に気をつけるべき注意点をまとめました。
減点されないためのルール
使える表現・言い回し集
図・グラフの読み取りと活用
倒置法、体言止め、比喩などは使わない
口語、擬態語、若者言葉は使わない
時間配分のコツと練習法
小論文は制限時間内に書き上げる必要があります。
本番で焦らないためにも、時間配分を意識した練習が不可欠です。
一般的な時間配分の目安(例:60分の場合)
| ステップ | 時間配分 | 内容・やるべきこと | ポイント |
|---|---|---|---|
| ① 設問・課題文の読解 | 5~10分 | ・設問の意図を正確に読み取る・キーワードや制約条件を把握する | ・問いのズレを防ぐために、ここを丁寧に読むことが重要 |
| ② 構成案(プロット)作成 | 10~15分 | ・序論・本論・結論の骨組みを考える・本論で使う理由や具体例をメモする | ・この段階で全体の論理が整理できていれば、執筆がスムーズに進む |
| ③ 執筆(序論・本論・結論) | 30~35分 | ・構成案に沿って、一気に本文を完成させる | ・最初から完璧を目指さず、「まずは書き切る」ことを優先する |
| ④ 推敲・最終確認 | 5~10分 | ・誤字脱字の修正・論理の流れや表現の見直し | ・主張の一貫性、接続詞の使い方、文末表現の統一などもチェックする |
練習法としては、以下の点が効果的です。
・過去問や類似問題に数多く取り組む:様々なテーマに触れ、時間内に書き上げる練習を繰り返す。
・時間を計って書く:本番と同じ制限時間で書く練習をする。
・書いた小論文を添削してもらう:学校の先生や塾の講師など、第三者に見てもらい、客観的なアドバイスをもらう。自分では気づかない弱点や改善点が見つかります。
・模範解答を分析する:良い解答の構成や論理展開、表現方法を学ぶ。
・日頃から社会問題に関心を持つ:新聞やニュースを読み、自分なりの意見を持つ習慣をつける。
継続的な練習が、小論文の実力向上の鍵です。

減点されないためのルール
どんなに良い内容の小論文でも、基本的なルールが守られていないと減点対象となることがあります。
以下の点に注意しましょう。
【小論文で減点されないためのチェック項目】
| 項目 | 内容・注意点 | ポイント |
|---|---|---|
| 誤字・脱字 | 書き終えた後に丁寧に見直す | ・焦らず確認する習慣を持つ |
| 正しい日本語 | 文法ミス、ら抜き言葉、誤用敬語に注意 | ・「見れる」→「見られる」など、正しい表現に |
| 原稿用紙の使い方 | ・題名は不要(指定がなければ)・段落の最初は一字下げる・句読点・カッコは1マス使用(行頭には置かない)・「!」や「?」は基本的に使わない | ・見た目の整った原稿は評価が上がりやすい |
| 文体の統一 | 「だ・である調」か「です・ます調」どちらかに統一(混在NG)※大学入試では「だ・である調」が一般的 | ・書き始めから意識することが大切 |
| 指定文字数の遵守 | 指定文字数の8割以上は必ず書くオーバーも厳禁 | ・600字指定なら最低でも480字以上 |
| 設問の指示に従う | 「〜について述べよ」「〜字以内で書け」などの条件を正確に守る | ・設問を読み飛ばさず、条件をよく確認 |
| 話し言葉・略語の回避 | 「めっちゃ」「ウケる」「JK」などは使用不可 | ・書き言葉としてふさわしい表現を選ぶ |
| 引用のルール | 引用が必要な場合は出典を明記する※大学によって形式が異なるため、指示に従う | ・不明な場合は明記を避け、要約にとどめるのも手 |
これらの基本的なルールは、練習段階から意識して身につけましょう。

使える表現・言い回し集
小論文で使えると便利な表現や言い回しをいくつか紹介します。
これらをストックしておくと、文章がスムーズに書けるようになります。
【小論文で使える表現・言い回し一覧】
| 用途 | 表現例 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 問題提起 | ・近年、〜が社会問題となっている。・〜ということについて、私たちはどのように考えるべきだろうか。・本稿では、〜という観点から考察したい。 | ・序論の冒頭に使うと自然な導入に・「考察したい」は論文らしい語調で好印象 |
| 意見表明 | ・私は〜と考える。・私の意見は〜である。・〜と言えるのではないだろうか。・〜と結論づけることができる。 | ・自分の立場をはっきり示したいときに有効・曖昧な表現を避けて断定的に述べると説得力が増す |
| 理由・根拠 | ・その理由は〜だからである。・なぜなら〜だからだ。・第一に〜、第二に〜が挙げられる。・〜という事実がそれを裏付けている。 | ・論理的な展開の軸として使いやすい・順序を示す表現(第一に〜)は構成の明確化に役立つ |
| 具体例 | ・例えば、〜という事例がある。・具体的には、〜のような状況が見られる。・私の経験では〜であった。 | ・主張に説得力を加える際に使用・「自分の経験」は客観性を意識して簡潔に |
| 比較・対比 | ・〜である一方、〜という側面もある。・〜と〜を比較すると、次のような違いが見られる。 | ・多角的な視点やバランスの取れた論述が求められるときに有効 |
| 譲歩・反論 | ・確かに〜という意見もある。しかし、〜と考える。・もちろん、〜という側面も無視できない。だが、〜 | ・反対意見を認めつつ自分の主張を強化したいときに使える |
| 結論・まとめ | ・以上のことから、〜と言える。・したがって、〜という結論に至る。・今後、〜していくことが求められるだろう。 | ・小論文の締めくくりで主張を再確認・明確化する表現として有効 |
これらの表現を丸暗記するのではなく、文脈に合わせて自然に使えるように練習しましょう。

図・グラフの読み取りと活用
課題文に図やグラフが含まれるタイプの小論文では、それらを正確に読み取り、論じる内容に効果的に活用する能力が求められます。
【図・グラフ付き小論文でのポイント】
| 項目 | 内容・やるべきこと | 活用のポイント |
|---|---|---|
| 図・グラフの読み取り①タイトルと単位の確認 | ・何のデータか、単位は何かを確認(%、人、円、年など) | ・タイトルにテーマのヒントが隠れていることが多い |
| 図・グラフの読み取り②傾向を掴む | ・数値の増減、横ばい、急変化などを見つける・最大・最小の項目や特徴的な動きに注目 | ・数字だけでなく、「なぜそうなっているか」に注目すると良い視点が生まれる |
| 図・グラフの読み取り③複数データの関連性 | ・2つ以上のグラフがある場合、どう関連しているかを考える | ・組み合わせて読むと、より深い分析が可能になる |
| 活用法①客観的根拠として使う | ・「図1が示すように〜」とデータを引用して主張を補強 | ・自分の意見に信頼性を持たせられる |
| 活用法②問題点の発見に使う | ・データの異常値や偏りから課題を見つける | ・問題提起のきっかけとして効果的 |
| 活用法③背景要因の考察に使う | ・なぜその傾向が出ているのか、社会的背景や政策との関係を分析 | ・分析の深さで評価が上がりやすい |
図やグラフは、あなたの主張に客観性と説得力を与える強力なツールです。
読み取りの練習を積み、自分の言葉で説明できるようにしておきましょう。
大学入試小論文(書き方・構成・例文・書き出し・結論)よくある質問
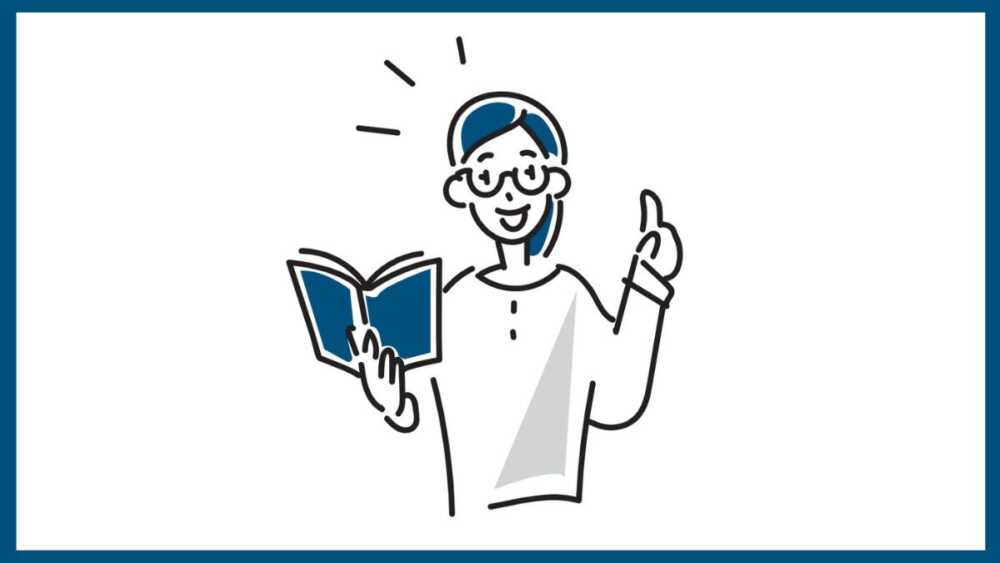
小論文は大学入試で問われる「考える力」を見られる大切な試験です。でも「どう書けばいいの?」「何から始めたら?」と不安な人も多いはず。
小論文の書き方や構成、書き出しや結論の工夫、そして上達法まで、よくある疑問をわかりやすく解説します。
小論文の書き始めは何を書く?
小論文でやってはいけないことは?
小論文の基本的なルールは?
小論文で大切なことは何ですか?
小論文は2時間で何文字くらいですか?
小論文の練習はいつから始めればよいですか?
小論文を上手くなるコツは?
小論文が上手くなるには、「論理的に考える練習」と「構成力を身につけること」が大切です。
書きたいことを思いつきで書くのではなく、「序論→本論→結論」という流れを意識し、主張に根拠や具体例を添えるクセをつけましょう。
新聞記事を読んで要約する、身近な話題について自分の意見を書くなど、日常的なアウトプットの積み重ねが力になります。
誰かに添削してもらうのも大きな効果があります。

小論文の書き始めは何を書く?
書き出しで迷う人は多いですが、最初に大切なのは「何について書くかを明確に示すこと」です。
一般的には、現代社会の課題や身近な問題を取り上げて問題提起し、その背景を簡単に説明した上で自分の主張を予告する形が理想です。
例:「近年、少子化が社会問題として注目されている。本稿ではその原因と解決策について考察したい。」といった書き出しは自然で論理的な流れが作れます。

小論文でやってはいけないことは?
小論文で避けるべきことはいくつかあります。
「話し言葉」や「略語」の使用はNGです。
「めっちゃ」「ヤバい」などは論文にふさわしくありません。
主張があいまいなまま話を進めたり、感情的に書きすぎると説得力を失います。
設問からズレた内容や、文字数制限を守らないことも大きな減点対象になります。
内容以前に「形式面」で減点されないよう注意が必要です。

小論文の基本的なルールは?
小論文には守るべき基本ルールがあります。
文体は「だ・である調」が基本。
原稿用紙では段落の初めは1マス空ける、句読点は1マス使うなど形式にも注意が必要です。
「!」「?」などの記号は基本的に使わず、客観的で論理的な文章を意識しましょう。
設問で求められていることに正確に答えることが最優先です。
これらの基本を守ることで、内容がきちんと評価されやすくなります。

小論文で大切なことは何ですか?
小論文で最も大切なのは、自分の主張を筋道立てて「納得できる形で伝える力」です。
どんなに立派な意見でも、理由や根拠、具体例がなければ説得力は生まれません。
「読み手(採点者)」を意識し、分かりやすく伝える工夫も必要です。
社会への視点や他者の立場も踏まえて書くと、より深みのある論述になります。
「何を書くか」より「どう伝えるか」が合否を分けるポイントです。

小論文は2時間で何文字くらいですか?
大学入試で出される小論文は、600〜1200字程度が多く、2時間で書く場合は800〜1000字程度が目安になります。
ただし時間には「構成を考える時間」「見直す時間」も含まれるので、単に字数だけで考えず、時間配分の練習が重要です。
たとえば60分なら構成に15分、執筆に35分、見直しに10分といった配分が理想です。
日頃から模試形式で練習することで、本番の時間感覚が身につきます。

小論文の練習はいつから始めればよいですか?
本格的な小論文対策は、高2の終わり〜高3の春から始めるのが理想ですが、早すぎることはありません。
まずはニュースや社会問題に関心を持ち、自分の意見をノートに書き出すなど、日常の中で「考える力」を鍛えることから始めましょう。
特に総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜を目指す場合、夏〜秋に本番を迎えるため、高3の夏前までに型や書き方に慣れておくことが合格への鍵です。
まとめ:【大学入試小論文の書き方】構成・例文・書き出し・結論まで徹底解説

最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今回の記事、「【大学入試小論文の書き方】構成・例文・書き出し・結論まで徹底解説」は参考になりましたか?
まとめ:【大学入試小論文の書き方】構成・例文・書き出し・結論まで徹底解説
大学入試の小論文は、一朝一夕に上達するものではありません。
正しい書き方の基本を理解し、適切な手順で練習を重ねれば、必ず合格レベルの小論文を書けるようになります。
この記事で解説した、小論文の基本と評価基準、書き方の7ステップ、基本構成と型、印象的な書き出しと説得力のある結論のコツ、そしてテーマ別の例文や対策のポイントを、ぜひあなたの小論文対策に役立ててください。
特に重要なのは、以下の3点です。
1. 設問を正確に理解し、自分の主張を明確に持つこと。
2. 序論・本論・結論という論理的な構成を意識すること。
3. 主張を支える具体的な根拠や事例を示すこと。
そして、書いた小論文は必ず誰かに読んでもらい、フィードバックをもらうようにしましょう。
客観的な視点からのアドバイスは、あなたの成長を大きく助けてくれます。
大学入試の小論文は、あなたの思考力、表現力、そして社会への関心の深さをアピールする絶好の機会です。
この記事を参考に、自信を持って小論文対策に取り組み、志望校合格を勝ち取ってください!
応援しています。
総合型選抜とは?おすすめの記事
「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
【総合型選抜】受かる確率を上げる!受験生なら知っておきたい7つのポイント!
【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは
大学面接で聞かれることランキング【質問と回答例】入試対策にもすぐに使える
総合型選抜(AO入試)に向いている人・向いてない人・落ちる人の特徴を解説
【総合型選抜】落ちる確率が高い理由と突破の秘策!大学受験を推薦で合格
評定平均とは?計算方法とは?大学推薦入試で差をつける評定対策をアドバイス
総合型選抜(AO入試)対策!いつ始める?時期と学年別戦略を徹底解説
【総合型選抜】自己PR文の書き方完全ガイド|必見!例文付きで解説
総合型選抜のエントリーシートの書き方&例文で夢の大学合格を掴む!
総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリット!学校推薦型選抜の違いを解説
総合型選抜に落ちたら!次は何の対策をすべきか?落ちる人の特徴も紹介
【総合型選抜対策】成績が悪い受験生必見|今の評定平均は関係ない
総合型選抜面接を突破する自己PR作成術と例文!大学受験攻略ガイド
総合型選抜おすすめ塾
ホワイトアカデミー高等部の料金・口コミ・評判を担当者に直接取材!
ホワイトアカデミー高等部の合格実績は?メリット・デメリットは?
ルークス志塾の料金はリーズナブル?塾経験者が他塾と料金比較した結果
【ルークス志塾】の評判・口コミ10選!塾経験者が徹底調査
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
AOI塾の料金は高い!他の総合型選抜専門塾と比較した結果は?
【注目】総合型選抜おすすめ塾ランキング!専門家が選んだ11社紹介
小論文対策に強い塾おすすめ10選!短期間で成績アップも夢じゃない
総合型選抜(旧AO入試)対策塾【安い!おすすめ15選】受験生必見!料金相場とは?
【総合型選抜に強い塾】塾に行くべき?塾経験者がおすすめする!【総合型選抜対策塾の紹介】
総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
浪人生が総合型選抜で合格する方法とは?実績豊富なおすすめ塾10選
総合型選抜専門塾【KOSKOS】ってどうなの?口コミ・評判・料金を調査した結果は?
自己推薦書の書き方を例文付きで解説!大学に合格できる「書き出し」


