総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリットとは?知らないと損!
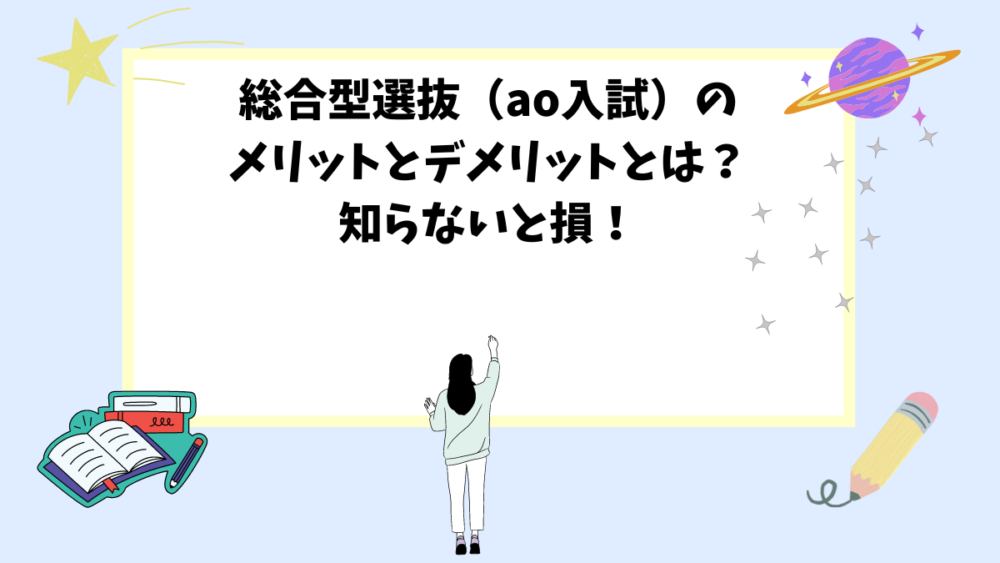
「※この記事には一部PRが含まれます」
こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。
受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。
今回のお悩みはこちら。
総合型選抜のメリット・デメリットが知りたい
総合型選抜で合格するためには?
今回の記事の担当は進路アドバイザースタッフです。
総合型選抜について、簡単にわかりやすく解説しています。
今回紹介する「総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリットとは?知らないと損!」を読めば、総合型選抜のメリット・デメリットを具体的に紹介しています。
この記事を読み終わると、総合型選抜のメリット・デメリットを理解でき、合格が近づくはずです。
また、記事の後半では、おすすめの総合型選抜専門塾を紹介しています。
総合型選抜のメリット・デメリット
総合型選抜とは?簡単にわかりやすく解説
総合型選抜で受験するかどうかの判断
総合型選抜対策
おすすめ総合型選抜専門塾
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
Contents
- 1 総合型選抜(AO入試)とは?わかりやすく解説
- 2 総合型選抜(AO入試)・推薦入試・一般入試の違い
- 3 総合型選抜(ao入試)のメリットとは?
- 4 総合型選抜(ao入試)のデメリット5つ
- 5 総合型選抜のメリットとデメリットをバランス良く理解する方法
- 6 総合型選抜のメリットとデメリットを踏まえた対策
- 7 総合型選抜に合格するための対策とは?
- 8 総合型選抜(旧AO入試)対策:よくある質問
- 9 総合型選抜・合格保証付き!ホワイトアカデミー高等部
- 10 オンラインで総合型選抜対策:総合型選抜専門塾AOI
- 11 アガルートコーチング|おすすめオンライン塾
- 12 英語の成績を短期間でアップ【LIBERTY ENGLISH】
- 13 総合型選抜専門塾:ルークス志塾
- 14 まとめ:総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリットとは?知らないと損?
総合型選抜(AO入試)とは?わかりやすく解説
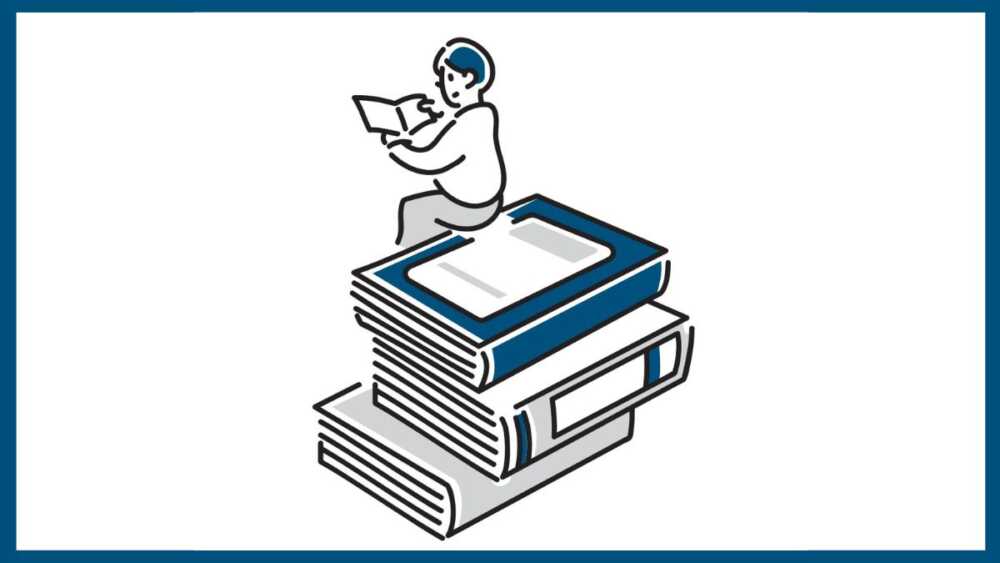
総合型選抜は、2021年度入試から、これまでのAO入試が「総合型選抜」に名前が変わりました。
以下、総合型選抜についてわかりやすく解説します。
総合型選抜は学力も評価される?
総合型選抜のスケジュールは?
総合型選抜で合格するためには?
総合型選抜とは?
総合型選抜は、大学側が求める学生を見つけるための入試です。
書類提出だけでなく、面接や論文、プレゼンテーションなどを通じて、受験生の能力や意欲をしっかりと評価します。
総合型選抜の入試方式は、受験生が大学のアドミッションポリシー(大学が求める学生像)に合っているかを総合的に判断する仕組みです。

総合型選抜は学力も評価される?
文部科学省の大学入試改革により、総合型選抜でも学力評価が行われます。
例えば、語学試験や大学入学共通テストを使う場合もあります。
また、小論文や面接なども含まれるので、総合的な力が求められます。

総合型選抜のスケジュールは?
総合型選抜は、9月以降に試験が行われ、12月までに結果が出ます。
一般入試が1月や2月に行われるため、総合型選抜は早めに進路が決まるのが特徴です。
総合型選抜で合格するためには?
総合型選抜で合格するためには、「自分がその大学で何を学びたいか、将来どう活かしたいか」を具体的に伝えることが大切です。
アドミッションポリシーを理解し、志望動機や学びたい内容をしっかり説明できるよう準備しましょう。
参考記事:翔励学院の口コミ・評判・料金は?小論文対策におすすめできる塾?
総合型選抜(AO入試)・推薦入試・一般入試の違い

総合型選抜のメリット・デメリットを理解する上で、総合型選抜の入試制度をしっかりと理解してください。
総合型選抜と一般入試の違い
総合型選抜と公募制推薦・指定校推薦の違い
総合型選抜と学校推薦型選抜の違い
総合型選抜と学校推薦型選抜は、推薦入試ですが異なる選抜方法です。
| 項目 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 |
| 選考基準 | 大学独自 | 高校の推薦 |
| 出願条件 | 出願条件を満たしていれば誰でも応募できる | 学校長の推薦が必要 |
| 出願時期 | 9月以降 | 11月以降 |
| 選考方法 | 書類選考や面接など | 学力試験や面接など |
| 併願 | 原則専願 | 不可 |
| 目的 | 多様な人材の受け入れ | 高校の成績優秀者の受け入れ |
| 重視するポイント | 志望動機や課外活動などの自己PR | 高校での学習や課外活動などの実績 |
| 向いている人 | 自分の強みや将来の夢をアピールしたい人 | 高校での成績優秀者で、大学の推薦を受けられる人 |
| 合否のポイント | 大学のアドミッションポリシーにマッチしているかどうか?大学独自の選抜方式で合否判定 | 3年間の学校生活での実績が評価される |
総合型選抜は、大学が独自の選考基準を設けて、多様な人材を受け入れることを目的としています。
そのため、志望動機や課外活動などの自己PRを重視する傾向があります。
一方、学校推薦型選抜は、高校の推薦を受けて、大学が合否を決めます。
そのため、高校での学習や課外活動などの実績を重視する傾向があります。
総合型選抜と学校推薦型選抜のどちらを受けるかは、自分の志望校や自分の強みに合わせて判断しましょう。
なお、総合型選抜と学校推薦型選抜の両方を受けることも可能です。
この場合、総合型選抜で合格しなかった場合に、学校推薦型選抜で合格する可能性が残ります。

参考記事:【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
総合型選抜と一般入試の違い
| 項目 | 総合型選抜 | 一般入試 |
| 評価項目 | 学力だけでなく、志望動機や課外活動など | 学力のみ |
| 選考基準 | 大学独自 | 大学入学共通テストや各大学の個別試験の成績 |
| 選考方法 | 書類選考や面接など | 大学入学共通テストや各大学の個別試験 |
| 併願 | 原則専願 | 可能 |
| 目的 | 多様な人材の受け入れ | 学力優秀者の受け入れ |
| 重視するポイント | 志望動機や課外活動などの自己PR | 学力試験の成績 |
| 向いている人 | 自分の強みや将来の夢をアピールしたい人 | 学力に自信がある人 |
総合型選抜は、学力だけでなく、志望動機や課外活動などの総合的な力を評価して入学を決める方式の入試です。
一方、一般入試は、学力試験のみで合否を決める方式の入試です。
総合型選抜と一般入試のどちらを受けるかは、自分の志望校や自分の強みに合わせて判断しましょう。

総合型選抜と公募制推薦・指定校推薦の違い
総合型選抜 と 公募制推薦・指定校推薦の違いを表にまとめてみました。
| 項目 | 総合型選抜 | 公募制推薦・指定校推薦 |
| 選考方法 | 学力と個性を総合的に評価 | 高校や大学の推薦が必要 |
| 応募方法 | 志望校ごとに独自の基準がある | 高校が推薦する場合や大学が特定の高校を指定する場合がある |
| 審査基準 | 学力と成績の他に独自の基準が存在する | 学力以外にも独自の基準がある |
総合型選抜と公募制推薦・指定校推薦の違いは、選考方法と応募方法にあります。
総合型選抜は学力や個性を総合的に評価する入試方法で、志望校ごとに独自の選考基準が設けられています。
一方、公募制推薦・指定校推薦は、高校が推薦する場合と大学が特定の高校を指定する場合があります。
学力や成績は重要ですが、それ以外にも独自の審査基準が存在し、推薦を受けるには高校側や大学側の推薦が必要です。
総合型選抜(ao入試)のメリットとは?
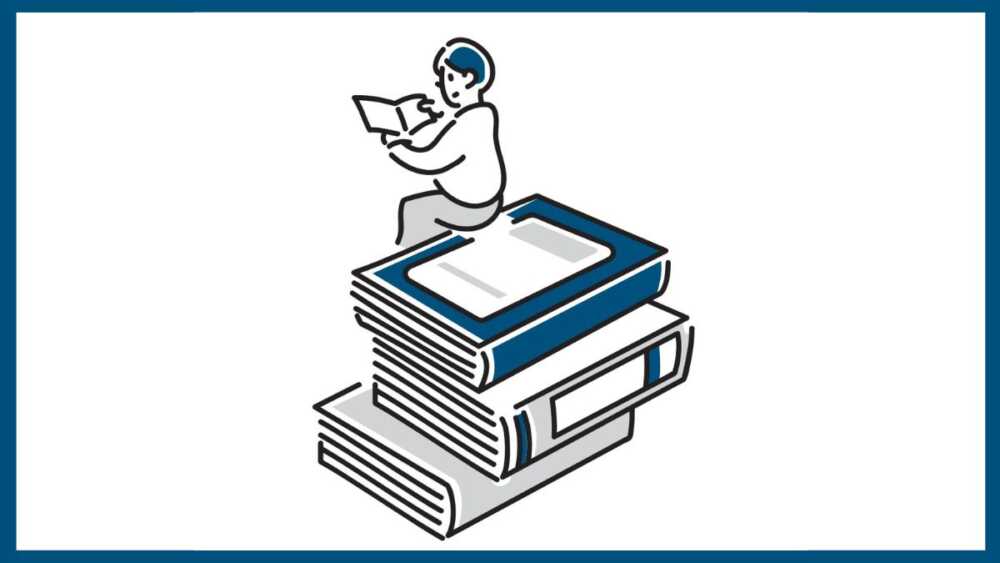
総合型選抜のメリットを5つ紹介します。
メリット②自己表現の機会が豊富
メリット③早期に進路を決定できる
メリット④志望大学との親和性が高い
メリット⑤就職活動でも有利になる
メリット①学力以外の多様な評価基準
総合型選抜の最大のメリットは、学力だけで評価されない点です。
一般入試ではテストの点数が重視されますが、総合型選抜では、課外活動や部活動、ボランティアなど、あなたの経験やスキルが評価されます。
例えば、部活動でリーダーシップを発揮した経験や、ボランティアで社会に貢献した実績があれば、それが合否の大きなポイントになります。
自分の個性や取り組みを通して、学力以外の面も評価してもらえるのが魅力です。

参考記事:総合型選抜(AO入試)面接のコツ【知らないと損】大学入試面接を攻略
メリット②自己表現の機会が豊富
総合型選抜では、志望理由書や面接、小論文などを通じて、自分自身をしっかりアピールできる機会が多くあります。
総合型選抜は、自分の言葉で「なぜこの大学で学びたいのか」を伝えられるチャンスです。
例えば、将来の夢や目標に向けてこれまでにどのような努力をしてきたのか、どんな学びを深めたいのかを具体的に表現できれば、大学側にも強い印象を与えられます。
自分らしさを伝えたい人にとって、とても有利な入試方式です。
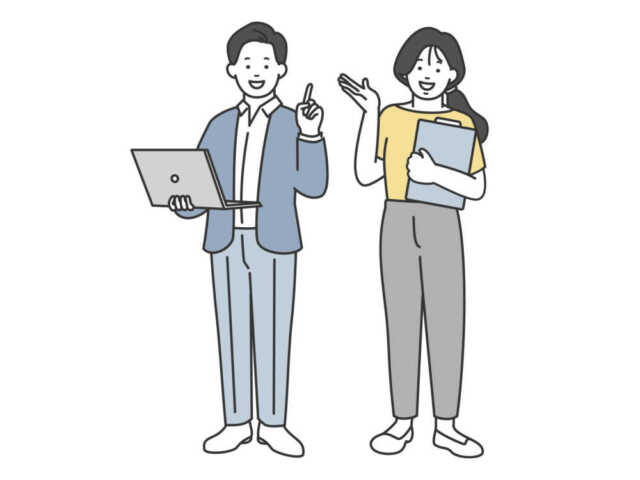
参考記事:総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
メリット③早期に進路を決定できる
総合型選抜のもう一つの大きなメリットは、早期に進路を決められることです。
一般入試が1月以降に行われるのに対し、総合型選抜は秋から冬にかけて結果が出ます。
例えば、10月に合格が決まれば、その後の数ヶ月は勉強や進路に対する不安がなく、自由な時間を過ごすことができます。
この期間を使ってアルバイトや留学準備、資格取得など、有意義な活動に取り組めるのも大きな魅力です。
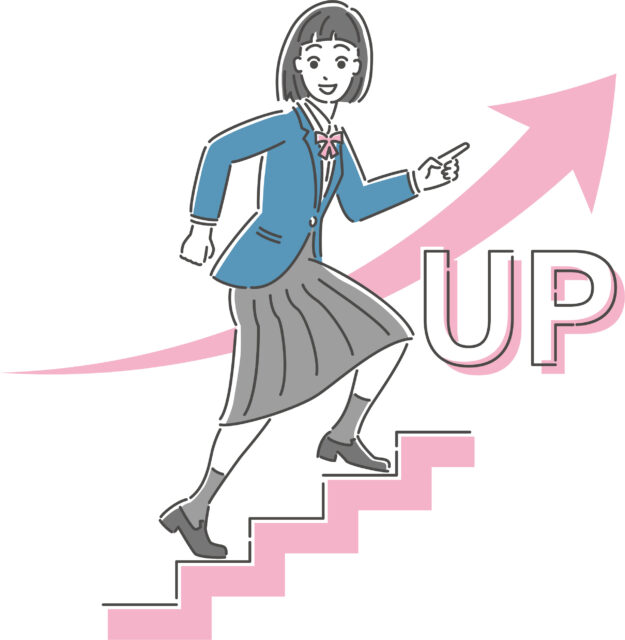
参考記事:総合型選抜塾|おすすめ人気厳選11社|料金・特徴・コースを解説
メリット④志望大学との親和性が高い
総合型選抜では、大学が求める人物像(アドミッションポリシー)に自分がどれだけ合っているかが重要です。
自分の学びたいことと大学が勉強する学びが一致している場合、合格の可能性が高くなります。
例えば、環境保護に興味があり、それを専門に学べる大学にアピールできれば、学びたい分野に最適な環境を見つけられるでしょう。
大学と自分の将来のビジョンが一致することが、合格への大きな一歩になります。

メリット⑤就職活動でも有利になる
総合型選抜で得られる経験は、就職活動にも役立ちます。
自己分析や志望理由書の作成、面接対策を通じて得たコミュニケーション能力や自己表現力は、企業の面接でも高く評価されます。
例えば、総合型選抜の面接で自分の強みや将来の目標をしっかりアピールできた人は、就職活動でも同じスキルを発揮し、企業からの評価を得やすくなります。
このため、総合型選抜で培ったスキルが将来の就職にも役立つのです。
参考記事:翔励学院の口コミ・評判・料金は?小論文対策におすすめできる塾?総合型選抜(ao入試)のデメリット5つ

総合型選抜のデメリットを5つ紹介します。
デメリット②専願制による進路の制約
デメリット③面接や小論文の準備が大変
デメリット④学力の一部が求められる場合がある
デメリット⑤合格後の学力差への不安
デメリット①選考基準が曖昧で対策が難しい
総合型選抜のデメリットの一つは、選考基準がはっきりしていないことです。
一般入試のようにテストの点数で合否が決まるわけではなく、面接や志望理由書、小論文などで「どれだけ大学が求める人物像に合っているか」が評価されます。
そのため、具体的にどうすれば合格できるかが見えにくく、対策が難しく感じられることがあります。
自分自身をどうアピールするか、深く考える必要があるため、事前の準備が重要です。

デメリット②専願制による進路の制約
総合型選抜には「専願制」というルールがある場合が多く、これが進路の選択に制約をもたらします。
専願制とは、一度合格したら他の大学を受験できず、その大学に必ず進学することを意味します。
つまり、進路を他の選択肢と比べてから決めることができません。
自分の進路が本当にその大学でいいのか、しっかり考えた上で決断する必要があるため、慎重な選択が求められます。

参考記事:【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
デメリット③面接や小論文の準備が大変
総合型選抜では、面接や小論文が重要な評価項目となるため、その準備に時間と労力がかかります。
特に、小論文では自分の考えを論理的にまとめ、説得力のある文章を書く必要があります。
面接でも、大学で何を学びたいか、将来どのように活かしたいかを自分の言葉でしっかり説明しなければなりません。
こうした準備には慣れが必要で、練習を重ねることが成功のカギになります。

参考記事:小論文対策に自信あり!おすすめ塾9選|総合型選抜対策塾の選び方
デメリット④学力の一部が求められる場合がある
総合型選抜は学力よりも個性や意欲が重視される入試ですが、全く学力が必要ないわけではありません。
大学によっては、特定の学力テストや語学力の証明を求めることがあります。
また、書類選考や面接でも、基礎的な学力や知識が必要とされる場合があります。
そのため、学力面での対策も必要な場合があり、総合型選抜を受けるからといって勉強を完全に避けられるわけではない点に注意が必要です。
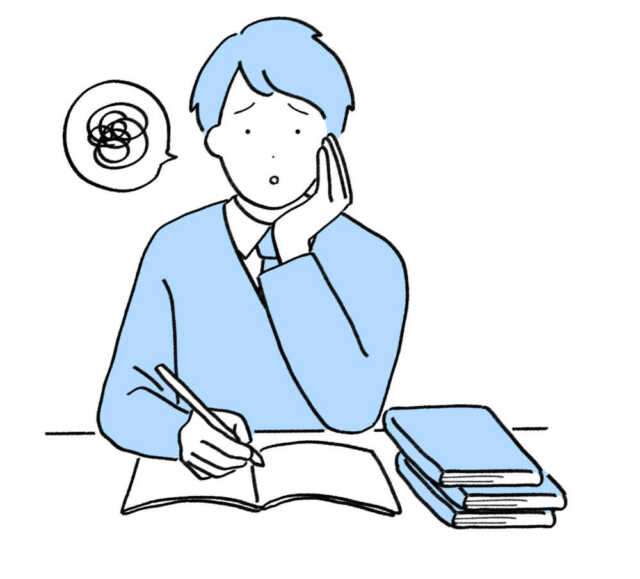
デメリット⑤合格後の学力差への不安
総合型選抜で合格した後、他の学生と学力差を感じることがあるかもしれません。
特に、一般入試で合格した学生は高い学力を持っていることが多く、授業についていけるか不安になることもあります。
入学後に困らないように、合格後も一定の学習を続けて基礎学力をしっかり身につけておくことが大切です。
また、大学に入ってからも自主的に勉強する姿勢が必要です。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証制度あり!

総合型選抜のメリットとデメリットをバランス良く理解する方法
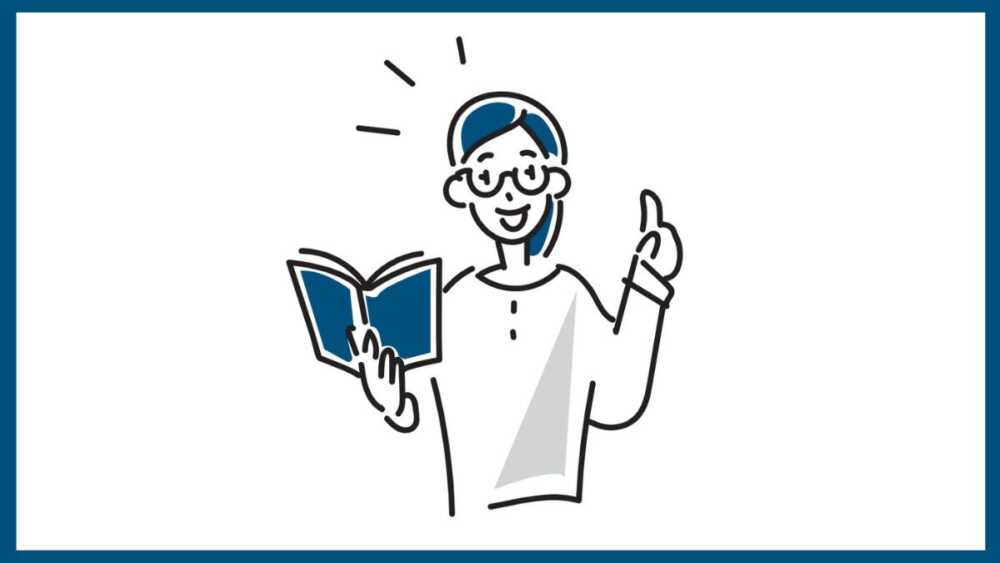
総合型選抜のメリットとデメリットをバランス良く理解する方法について解説します。
効果的な対策と準備方法
他の入試方法との併用戦略
実際の体験談から学ぶメリット・デメリット
アドミッションポリシーを活用した戦略的アプローチ
自分に合った選択肢を見極めるポイント
総合型選抜のメリットとデメリットを理解するためには、まず自分に合った選択肢を見極めることが大切です。
自分が得意とする分野や興味を持っている活動が評価されやすいかどうかを考えることが重要です。
例えば、部活動やボランティア、特技を生かしてアピールできる人には向いていますが、もし学力を中心に勝負したい場合は、一般入試が合っているかもしれません。
自分の強みと進路の希望を照らし合わせて、最適な入試方法を選びましょう。

参考記事:総合型選抜|プレゼンテーション完全ガイド!5つのテクニックで合格
効果的な対策と準備方法
総合型選抜では、面接や志望理由書、小論文の準備が大切です。
効果的な対策を行うためには、まず志望大学のアドミッションポリシーを読み込み、自分がその大学で学びたいことを具体的に伝える準備をしましょう。
例えば、志望理由書では、自分の経験や興味を具体的に書くことがポイントです。
面接練習や模擬試験を活用して、実際の場面で自信を持って自分を表現できるように準備を進めましょう。

他の入試方法との併用戦略
総合型選抜だけに頼らず、他の入試方法との併用も戦略の一つです。
例えば、総合型選抜で受験しながら、一般入試や推薦入試も視野に入れて準備しておくと、リスク分散ができ、より安心して受験に臨めます。
特に総合型選抜は専願の場合が多いので、複数の選択肢を確保しておくことは大切です。
万が一不合格になっても、他の入試で再挑戦できるように準備しておくのが効果的です。

実際の体験談から学ぶメリット・デメリット
総合型選抜を受けた先輩たちの体験談を参考にすることで、メリット・デメリットをよりリアルに理解することができます。
成功例だけでなく、苦労した点や難しかったことも聞くことで、自分の対策に役立てることができます。
例えば、面接で何をアピールすればよいか、志望理由書を書く際のポイントなど、実体験に基づくアドバイスは非常に有効です。
実際に合格した先輩たちの話を積極的に調べてみましょう。
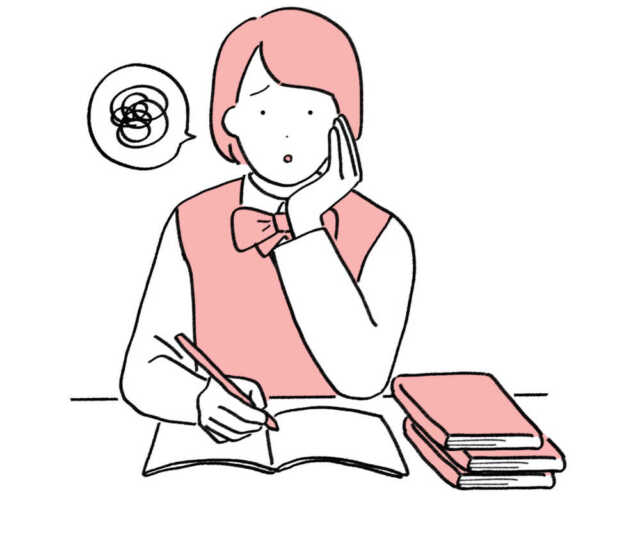
アドミッションポリシーを活用した戦略的アプローチ
総合型選抜では、大学のアドミッションポリシーをよく理解し、自分の強みと結びつけてアピールすることが非常に重要です。
各大学が求める学生像に自分がどれだけ合っているかを、志望理由書や面接で明確に伝えるためには、事前にしっかりとリサーチを行いましょう。
例えば、大学のオープンキャンパスに参加し、教授や学生と直接話をすることで、大学の雰囲気や方針を理解しやすくなります。
オープンキャンパスに参加することで、自分がその大学にどれだけ貢献できるかを具体的に伝えられるようになります。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜のメリットとデメリットを踏まえた対策

総合型選抜のメリットとデメリットを踏まえた対策について解説します。
志望大学のアドミッションポリシー理解
長所を最大限に活かす活動選び
デメリットを補うための具体策
家族や先生との相談で最適な選択を
自己分析を通じた適性の確認
総合型選抜を選ぶ際、まずは自分自身を深く理解することが大切です。
自己分析を通じて、自分がどんな強みを持っているのか、どんなことに興味があるのかを明確にしましょう。
例えば、課外活動でリーダーシップを発揮してきた経験や、ボランティア活動に熱心に取り組んできた実績があれば、それを活かせる入試方法かどうか判断することができます。
自己分析をしっかり行うことで、総合型選抜が自分に合っているかを見極めることができます。
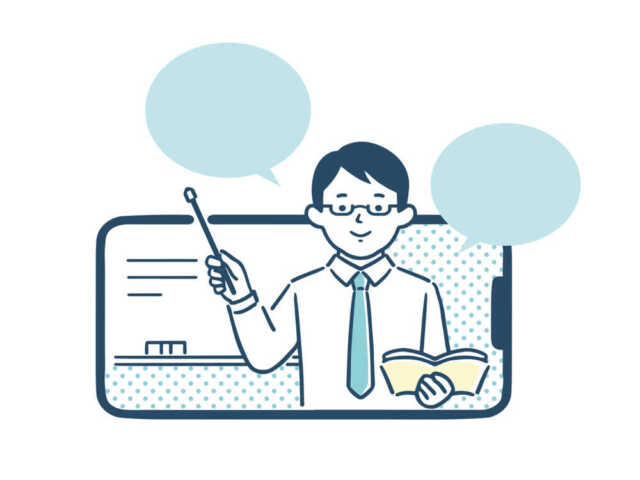
志望大学のアドミッションポリシー理解
総合型選抜では、志望大学が求める「アドミッションポリシー」をしっかり理解することが非常に重要です。
大学ごとに「どんな学生を求めているか」が明確に示されていますので、自分がその大学の求める人物像と合致しているかを確認しましょう。
例えば、国際的な視野を重視する大学なら、留学経験や英語力がアピールポイントになります。
このように、大学の方針に合わせて自分の経験や強みを結びつけることが合格への近道です。

長所を最大限に活かす活動選び
自分の強みを活かせる活動を選ぶことが、総合型選抜では大切です。
例えば、リーダーシップを発揮できる部活動や、社会貢献活動に積極的に参加することで、自分の長所を具体的にアピールできます。
学校のクラブ活動やボランティア、地域活動など、どんな活動でも「自分がどのように貢献したか」を考え、それを大学に伝えることが評価につながります。
自分が輝ける場所を見つけて、その活動に積極的に取り組みましょう。

デメリットを補うための具体策
総合型選抜には、選考基準が曖昧で対策が難しいというデメリットがありますが、それを補うための具体策もあります。
例えば、面接や小論文対策をしっかりと行い、自分の考えを論理的に伝えられるように準備することが大切です。
また、学力の一部が求められる場合もあるため、基本的な学力の維持も忘れずに行いましょう。
早めに準備を始めることで、デメリットを補い、総合型選抜に備えることができます。

家族や先生との相談で最適な選択を
総合型選抜を受けるかどうかを決める際には、家族や先生としっかり相談することが大切です。
自分一人で考えるのではなく、家族の意見や先生のアドバイスを聞くことで、進路選びの視野が広がり、最適な選択をすることができます。
特に、志望校や入試の方法について悩んでいる場合は、家族や学校の先生に相談することで新しい視点やアドバイスが得られることがあります。
周囲のサポートを活用して、最適な進路を見つけましょう。
総合型選抜に合格するための対策とは?

総合型選抜に合格するための対策について解説します。
自分の強みや将来の夢をアピールする材料を準備
過去問や模擬試験で対策
総合型選抜専門塾に通って対策
アドミッションポリシーを理解する
総合型選抜に合格するための最初のステップは、志望大学のアドミッションポリシーを理解することです。
アドミッションポリシーとは、大学が「どんな学生を求めているか」をまとめた方針です。
これをしっかり読み込み、自分がその大学でどのように学びたいか、大学に貢献できるかを考えましょう。
例えば、国際的な視野を持つ学生を求めている大学なら、留学経験や英語力を強調すると効果的です。この理解が合否に大きく関わります。

参考記事:【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
自分の強みや将来の夢をアピールする材料を準備
総合型選抜では、自分の強みや将来の夢をしっかりアピールすることが重要です。
自分が高校生活で取り組んできた活動や成果を振り返り、それをどのように大学での学びに繋げるかを考えましょう。
例えば、リーダーシップを発揮した経験や、ボランティア活動を通じて学んだことなどを具体的に述べると、大学側にも説得力のある印象を与えることができます。
自分の経験を志望理由に結びつける準備が合格の鍵です。

参考記事:小論文対策に自信あり!おすすめ塾9選|総合型選抜対策塾の選び方
過去問や模擬試験で対策
総合型選抜でも、面接や小論文などの試験が課されることが多いため、過去問や模擬試験を活用して対策を進めることが大切です。
特に、小論文では論理的に自分の考えをまとめる力が求められます。
過去の試験問題を解くことで、出題傾向や自分の弱点を把握し、効率的に準備することができます。
また、面接の練習も欠かせません。
模擬試験や練習を通じて、本番で自信を持って挑めるようにしておきましょう。

参考記事:【浪人生】総合型選抜おすすめオンライン塾10選|推薦入試で志望校に合格
総合型選抜専門塾に通って対策
総合型選抜試験に合格するための対策として、総合型選抜専門塾に通うことは有効な方法の一つ。
専門塾は、専門的な指導やサポートを提供し、合格への準備を強化する場所として役立ちます。
以下は、総合型選抜専門塾に通う際の注意点とメリットについての情報です。
メリット
専門的な指導:総合型選抜専門塾は、この試験に特化した指導を提供します。指導者は試験の出題スタイルや内容を深く理解しており、生徒に合わせた学習プランを作成します。
模擬試験:多くの専門塾は模擬試験を実施し、生徒の実力を測定し、弱点を特定するのに役立ちます。模擬試験を通じて、試験の雰囲気に慣れるでしょう。
個別指導:一部の専門塾は個別指導を提供し、生徒の個別のニーズに合わせたサポートをします。これにより、弱点の補強や進度の調整が可能です。
学習環境:専門塾は集中して学習できる環境を提供します。他の受験生と共に学ぶことで、モチベーションが高まります。
アドバイスとカウンセリング:専門塾の指導者やカウンセラーは、大学選択や志望校のアドミッション・ポリシーに関するアドバイスを提供することがあります。
注意点
コスト:総合型選抜専門塾は通常費用がかかります。学費、教材費、通学費などを考慮し、予算を立ててください。
時間:塾通学には時間がかかります。通学にかかる時間やスケジュールを考慮し、日常生活と調和させることが必要です。
効果的な選択:塾を選ぶ際には、評判や合格実績、指導法などを検討し、信頼性の高い塾を選ぶことが重要です。
自己学習:塾に通うだけでなく、自己学習も欠かさないことが大切です。塾の指導を補完し、試験範囲全体に対する理解を深めるために自己学習しましょう。
総合型選抜試験に対する準備には、総合型選抜専門塾が役立つことがありますが、個々の状況や目標に合わせて、適切な学習方法を選択することが大切です。
参考記事:翔励学院の口コミ・評判・料金は?小論文対策におすすめできる塾?
総合型選抜(旧AO入試)対策:よくある質問

総合型選抜(旧AO入試)対策:よくある質問を紹介します。
高校1・2年生からできる総合型選抜(旧AO入試)の対策は?
総合型選抜がいい理由は何ですか?
AO入試で受けるメリットは?
総合型選抜と一般選抜のどちらがいいですか?
総合型選抜は学力重視ですか?
総合型選抜対策はいつから始めるの?
総合型選抜対策をいつから始めるかは、受験生によって異なりますが、出願条件によっては、高校に入学してから、すぐに準備を始める必要があります。
なぜなら、志望する大学の評定平均や特定科目等の出願条件があると、高校1年生から対策を開始しないと間に合わないからです。
一方、書類の準備などは、出願の約半年前から始めるのがベストです。
つまり、高校2年生の2〜3月頃です。
志望校が求める学生像や自己分析も同時に進めましょう。
そして、エピソードを蓄積し、志望理由書を強化するために、早めの行動が大切です。

高校1・2年生からできる総合型選抜(旧AO入試)の対策は?
高校1年・2年生からできる総合型選抜(旧AO入試)対策を紹介します。
・オープンキャンパスに積極的に参加しよう
大学選びは重要です。自分の志望校や学部を深く知るために、オープンキャンパスに参加しましょう。ここで得た情報は、志望校選びやエントリーシートの記述に役立ちます。
・志望する大学のアドミッションポリシーを理解しよう
大学が求める理想の学生像を知ることは大切です。各大学のアドミッションポリシーを確認し、自分の適性と照らし合わせてみましょう。大学のウェブサイトや募集要項で情報をチェックしましょう。

総合型選抜がいい理由は何ですか?
総合型選抜(AO入試)の主な利点は、学力以外の要素も重視される点です。
例えば、部活動の成果やボランティア活動、独自のプロジェクトなど、学業以外の実績や人間性が評価されます。
これにより、単なる試験の点数だけではなく、自分の個性や興味をアピールできるチャンスが広がります。
また、自己推薦やプレゼンテーションを通じて、自分の強みを直接伝える機会があるため、自分に合った大学や学部を見つけやすくなります。

AO入試で受けるメリットは?
AO入試のメリットには、受験生自身の特性や興味に応じた選考が行われることが挙げられます。
学業成績だけでなく、自己推薦やエッセイ、面接などを通じて、自分の意欲や能力を評価してもらえるため、自分の強みをしっかりアピールすることができます。
また、早期に合格が決まるため、受験勉強のプレッシャーを軽減できる場合もあります。
さらに、大学生活においても自分の関心や目標に合った学びができる可能性が高くなります。

総合型選抜と一般選抜のどちらがいいですか?
総合型選抜と一般選抜にはそれぞれ異なる特長があります。
総合型選抜は、学力だけでなく多様な実績や個性を評価してもらえるため、学業以外の努力を評価されたい人に向いています。
一方、一般選抜は、試験の点数で評価されるため、学力を強化することで合格を目指せます。
自分の得意分野や強み、志望校の入試方針に合わせて選択することが大切です。
自分の学習スタイルや進路の希望に応じて、どちらの選抜方法が適しているかを考えると良いでしょう。

総合型選抜は学力重視ですか?
総合型選抜(AO入試)は、学力だけでなく、その他の要素も重視されます。
もちろん学力も評価の一部ですが、総合型選抜では、それ以外の活動や経験、意欲なども評価されます。
例えば、部活動での成果や地域活動、自己PRや面接での表現力など、学力以外の面が重視されるため、学業だけではなく、幅広い経験や個性をアピールするチャンスがあります。
そのため、学力重視の一般選抜とは異なり、多角的に自分をアピールできるのが特徴です。
参考記事:【総合型選抜に強い塾】塾に行くべき?塾経験者がおすすめする!【総合型選抜対策塾の紹介】
総合型選抜・合格保証付き!ホワイトアカデミー高等部

ホワイトアカデミー高等部の基本情報
| ホワイトアカデミー高等部の基本情報 | |
| 運営会社 | Avalon Consulting株式会社 |
| ホワイトアカデミー高等部公式ホームページ | https://whiteacademy-ao.com/ |
| 指導形式 | 講師と生徒が1対1のマンツーマン指導 |
| 指導内容 | ・スタンダードコース |
| 授業料 | 生徒によって授業料は設定。 |
| 講師 | 社会人プロ講師 |
| 合格実績 | 難関国公立大学、早稲田大学、慶應義塾大学、GMARCH、日東駒専 |
| サポート体制 | 合格保証制度・返金制度、一般入試のサポートもあり |
| オンライン対応 | ◎ |
合格保証付き!ホワイトアカデミーの特徴
合格保証付きの総合型選抜・学校推薦型専門塾
ホワイトアカデミーは他塾にはない志望大学の合格保証制度があります。カリキュラムを消化した上で受験した大学に一校も合格しなかった場合は授業料を全額返金。それだけ、授業に自信がある証拠と言えます。
社会人のプロ講師が授業を担当
ホワイトアカデミー高等部は総合型選抜・公募推薦の対策に特化した社会人のプロが講師を務めます。毎回の授業は総合型選抜・公募推薦を知り尽くした講師とマンツーマンなので志望大学の合格に繋がる最高の授業が受けられます。
生徒一人ひとりに対して講師が志望校に合格するためのロードマップを作成
ホワイトアカデミーは一人ひとりの生徒様に対して個別のカリキュラムを作成。初回の授業で現時点でのあなたの実力と志望校の現役合格に必要な実力の差分を明らかにし、その差を受験日までに埋めるためのカリキュラムをゼロから作ります。
予備校オンラインドットコムがおすすめする!公式ホームページからホワイトアカデミー高等部の説明会に参加してみましょう!
きっと、現役合格が近づくはずです。
参考記事:ホワイトアカデミー高等部の【料金・評判・特徴】を塾経験者が徹底取材!
合格保証と返金制度で万全のサポート体制
※講師は全員社会人のプロ講師!高い合格率!
※総合型選抜・学校推薦型選抜に特化した授業
ホワイトアカデミー高等部の公式ホームページをチェックする!
オンラインで総合型選抜対策:総合型選抜専門塾AOI

総合型選抜専門塾AOIの基本情報
| 総合型選抜専門塾AOIの基本情報 | |
| 運営会社 | 株式会社花形 |
| 総合型選抜専門塾AOIの公式ホームページ | https://aoaoi.jp/ |
| 指導形式 | 個別・少人数の授業体系 |
| 指導内容 | ・自己分析 ・キャリア ・ロジカルシンキング ・志望理由書 ・小論文 ・面接 |
| 授業料 | 年間39万円〜 |
| 講師 | メンターの約80%が総合型選抜で合格を掴んだ現役の大学生 |
| 合格実績 | 合格率97%、関関同立、早慶上智、国公立大学 |
| サポート体制 | 生徒専用のチャット、自習室使い放題、 メタバース校、渋谷校、大阪校、京都校、西宮北口校の校舎あり |
| オンライン対応 | ◎ |
総合型選抜専門塾AOIの特徴
<AOIの強み>
・一人ひとりに合わせたフルオーダーメイド授業
・150本以上もの総合型選抜対策に特化したAOI独自制作の映像授業と対話形式のドリル、さらにメンター とのコンサル授業で、どこよりもインプットとアウトプットの質が高められる。
・志望理由書、小論文はそれぞれ100ページを超える独自で制作したガイドブック。
・生徒に寄り添い続ける総合型選抜合格者のメンター(講師)
・壁がなく暖色照明の中あかるく開放的な塾っぽくない教室が総合型選抜に最適な学習環境
フルオーダーメイド授業
総合型選抜で重要な「志望理由」は、生徒それぞれ異なります。
そのため、一人ひとりの生徒に向き合い、個人の進捗に合わせた安心のフルオーダーメイド授業を採用。
書類添削や映像授業の補足、併願校戦略なども行います。
メタバース校は全国どこからでもオンライン受講可能
メタバース校ではビデオ通話を用いて、リアルタイムでの志望理由書や小論文の添削、面接練習などの授業を1対1の形式で行います。
オンライン上の授業にご不安を感じられる方は多くいらっしゃいますが、毎年の合格率は現地校舎と同等のため、オンラインでも質の高い授業の受講が可能です!
メンター&校舎の雰囲気
合格の鍵となる「将来の夢」を見つけられるよう、生徒に本気で向き合い寄り添う「メンター」があなたをサポート。
また、校舎も総合型選抜に特化した仕様で、生徒の好奇心・自走力・学問意欲を高められるよう、仕切りのない開放的で自由に学べる環境を提供しています。
総合型選抜専門塾AOIが気になる方は、公式ホームページをチェックしましょう。
参考記事:総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
参考記事:総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
アガルートコーチング|おすすめオンライン塾
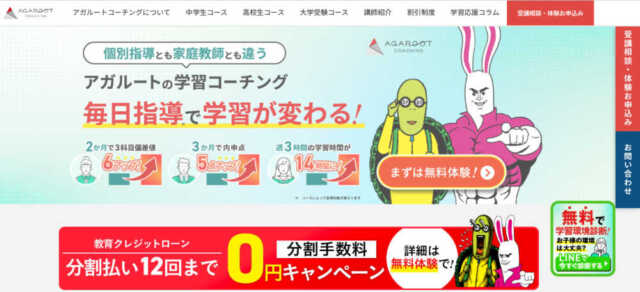
(アガルート:公式ホームページ)
毎日の指導で学習が変わる!アガルートコーチングの基本情報
| アガルートコーチングの基本情報 | |
| アガルートコーチングの公式ホームページ | https://agaroot.co.jp/coaching/ |
| 対象学年 | 小学3~6年生・中学生・高校生・既卒生 |
| 指導教科 | 受講者の学力・ご状況により、1~3科目の指導になります。 (途中での変更可能です) |
| 指導形式 | 完全1対1・個別コーチング |
| 授業料 | 60,280円〜 |
| 講師 | プロ講師 |
| 使用端末・アプリ | スタディサプリ、Comiru、Edv Path |
| サポート体制 | 正社員の講師がチームを組んで生徒をサポート |
| 無料体験授業 | 1週間の無料体験実施中 |
\毎日の学習管理で成績アップ/
↓↓↓
アガルートコーチングの公式HP
アガルートコーチングの特徴
アガルートは、オンラインを中心とした資格試験講座「アガルートアカデミー」を通じて、毎年数多くの合格者を輩出しております。
アガルートコーチングでは、その指導経験や合格者実績から得たメソッドやノウハウを活かして、内申点や偏差値のアップ、志望校合格をフルサポートします。
【月額利用料金のみのシンプルな料金体系】
アガルートコーチングは、入会金、管理費、教材費などのサービスと無関係な料金は一切不要。また、夏期講習、冬期講習などの講習代も一切不要です。
月額利用料金のみの安心の月謝制となっております。
※教材については、学校で配布されている教材等を参考にしながら、生徒の学力等に応じて、市販の教材を推薦することもあります。
【毎日の指導で学習習慣を定着、早期の成功体験を実現】
勉強ができるようになるための最短ルートは、「正しい方向で、学習を継続すること」×「学習の継続により、成功体験を得ること」。そうすれば、必ず学力は伸び、目標に到達できます。しかし、1人で毎日学習を継続することはなかなかできません。アガルートコーチングでは、毎日の学習習慣を身につけ、成功体験を積み上げ、自分で勉強方法が分かる、楽しめるようにサポートします。
【正社員のみのオリジナルチームで日々の学習から進路指導まで徹底サポート】
アガルートコーチングでは「生徒」「コーチ」「家庭」が1つのチームとなり、一丸となって学習に取り組むことを大切にしています。
また、1人に対して複数人のコーチがつき、そのコーチ同士の情報共有・連携も徹底しています。アガルートコーチングでは、生徒ごとのオリジナルチームを作り生徒をサポートするのが特徴です。
\毎日の学習管理で成績アップ/
↓↓↓
アガルートコーチングの公式HP
英語の成績を短期間でアップ【LIBERTY ENGLISH】

LIBER
| LIBER | |
| サービスの特徴 | リバティは独自の学習メソッドで英語学習を支援 |
| 対象学年 | 高校生・社会人 |
| 指導教科 | 英語 |
| 指導形式 | 通学クラス・オンラインクラス |
| 授業料 | 336,000円〜(24回コース) |
| 講師 | 藤川学長自らが指導 |
| 使用端末・アプリ | パソコン・タブレット・スマホ |
| サポート体制 | 成果保証・点数保証・延長保証 |
LIBER
リバティは、英語学習におけるあらゆる悩みを解決するために設計されました。
例えば、時間がなくて学習に十分な時間を割けない方や、英語の本質を理解したい方、さらには高いスコアを目指す方にも最適です。
リバティのカリキュラムは、短期間でも効果的な学習を実現するために設計されています。
一般的には3ヶ月から半年かかると言われている英語学習を、最短1ヶ月で効果的にスコアアップすることが可能です。
また、忙しい社会人や大学生、受験生にも対応できるよう、1日平均1.5時間以下の学習時間で効率的に学習を進めることができます。
これにより、仕事や勉強の合間に効果的な学習ができ、ストレスを感じることなく成果を上げることができます。
さらに、リバティのカリキュラムはハイスコアの獲得を目指す方にも最適です。
TOEFLやIELTS、TOEICなどのテストにおいて、目標スコア以上の成績を収めることが可能です。大学英語試験で満点レベルのスコアを目指すことができます。
リバティでは、あなたの英語学習の目標に合わせたカスタマイズされたカリキュラムを提供し、確実な成果をお約束します。
点数保証・成績保証・延長保証で安心
↓↓↓
LIBER
総合型選抜専門塾:ルークス志塾

総合選抜塾:ルークス志塾の基本情報
| ルークス志塾の基本情報 | |
| 運営会社 | Loohcs株式会社 |
| ルークス志塾の公式ホームページ | https://aogijuku.com/ |
| 指導形式 | 個別・少人数の授業体系 |
| 指導内容 | ・自己探求講座 ・大学探求講座 ・活動計画講座 ・志望理由書 ・自己アピール書類対策 ・知識インプット講座 ・面接対策講座 ・小論対策講座 |
| 授業料 | 月4コマコース : ¥54,780(税込) 月6コマコース : ¥76,780(税込) 月8コマコース : ¥87,780(税込) 月10コマコース : ¥98,780(税込) |
| 講師 | 総合型選抜で合格した講師陣 |
| 合格実績 | 東京大学5年で50名、慶應義塾大学10年で1,000人以上、MARCH |
| サポート体制 | 無料体験、キャンペーン実施中 |
| オンライン対応 | ◎ |
総合選抜塾:ルークス志塾の特徴
<あなたの志を一緒に見つける、最高の仲間がいる>
総合型選抜は自分を見つめなおすという「自分との戦い」が必要な入試です。
そんな孤独な戦いにも、ルークス志塾の講師陣は生徒に寄り添い授業します。
講師陣の多くは、総合型選抜入試の合格者。自身の志と向き合い仲間と切磋琢磨して合格を掴んだ当事者であり、最も身近な最高の仲間です。そんな講師たちがあなたと向き合い、対話を通してあらゆる角度からあなたの志や魅力を引き出します。
他にも、実際にあなたが志望する大学・学部に通っている講師から大学の雰囲気や講義、研究などさまざまな情報をあなたに提供することで、より深く志望校について考えられます。
また、志の実現や志望校合格を目指す仲間たちと切磋琢磨することで、お互いに刺激しあい成長できます
<あなたの今の状況に最適な、あなただけの計画が作れる>
総合型選抜入試は、志望大学の入試内容によって必要な準備や対策が異なります。
ルークス志塾では、あなたとの対話を通して、あなたの今の状況に合わせたオリジナルの計画を策定。
計画は、過去の活動や得意・不得意、これから必要になる取り組み等を踏まえて作成します。
志の実現に向け、調査活動やフィールドワーク等の活動予定を作成、支援します。これらの取り組みが、結果として総合型選抜への対策につながります。
これらの取り組みを一緒に決めていくことで、一つひとつにしっかりとした目標や意味を持ち、主体的な学びが得られます。
<総合型選抜入試対策のプロが作る対策講座が受けられる>
ルークス志塾は、総合型選抜入試の専門塾として立ち上げ今年で12年目。
これまで難関大学を中心に多くの塾生の合格を支え、難関大学進学率は86.1%に達しています。
ルークス志塾には、長年の対策・指導で培ってきたノウハウや膨大な合格者のデータがあります。
これらの知見を活かし、常に最新の対策へとアップデートするからこそ、ルークス志塾の合格率は高いままで推移しています。
参考記事:ルークス志塾の料金はリーズナブル?塾経験者が他塾と料金比較した結果
総合型選抜専門塾で合格実績NO.1のルークス志塾
※難関校への進学率「86.1%」全国オンライン対応!
※夢を叶えたいなら!ルークス志塾へ
まとめ:総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリットとは?知らないと損?

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリットとは?知らないと損?」は参考になりましたでしょうか?
まとめ:総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリットとは?知らないと損?
大学の総合型選抜入試とは、日本の大学入学試験の一形態で、高校時代の学業成績や試験の成績だけでなく、面接や小論文、個別の選考要件に基づいて入学者を選ぶ方法です。以下は、総合型選抜入試についてのメリットとデメリットをまとめた文です。
メリット
総合的な評価:総合型選抜入試は学業成績だけでなく、面接やエッセイ、個別の選考要件を通じて個々の学生を総合的に評価します。これにより、個々の能力や人間性が考慮され、多様なバックグラウンドを持つ学生にチャンスが提供されます。
個性の発揮:総合型選抜入試は、学生が自分の個性や特技をアピールできる機会を提供します。面接やエッセイを通じて、将来の夢や志向を伝えられます。
多様な選考要件:多くの総合型選抜入試は、学校ごとに異なる選考要件を持っています。これにより、学生は自分に適した大学を見つけるための選択肢が広がります。
学業成績以外の要因の重視:総合型選抜入試では、学業成績以外の要因も重要視されるため、学生は単なる点数競争から解放され、自分の強みや意欲を強調できます。
デメリット
試験対策の複雑さ:総合型選抜入試には面接やエッセイなど、さまざまな要素が含まれるため、試験対策が複雑になることがあります。
不透明さ:各大学が異なる選考要件を持つため、志望校によってはどの要件が評価基準になるのか不透明な場合があります。
評価の主観性:面接やエッセイの評価は主観的であるため、公平な評価を受けることが難しい場合があります。
競争が厳しい:総合型選抜入試は、競争が激しいことが多く、志望校に合格するためには十分な準備が必要です。
総合型選抜入試は、学生が自己表現や個性を発揮し、多様な選考要件を通じて大学に合格する機会を提供する方法です。しかし、それに伴う試験対策と競争も厳しいため、適切な準備が不可欠です。
総合型選抜とは?おすすめの記事
大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
【総合型選抜】受かる確率を上げる!受験生なら知っておきたい7つのポイント!
【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
【現役高校生】総合型選抜で大学に受かる人はみんなやっている総合型選抜対策!
総合型選抜(AO入試)面接のコツ【知らないと損】大学入試面接を攻略
【必見】大学受験:総合型選抜とは?総合型選抜に向いている人!向いてない人
【総合型選抜】落ちる確率が高い理由と突破の秘策!大学受験を推薦で合格
評定平均とは?計算方法とは?大学推薦入試で差をつける評定対策をアドバイス
総合型選抜(ao入試対策)いつから始めるべき?最適なスタート時期
【総合型選抜】自己PR文の書き方完全ガイド|必見!例文付きで解説
【総合型選抜】エントリーシートの書き方を例文でポイントを解説!
総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリットとは?知らないと損!
総合型選抜に落ちたら!次は何の対策をすべきか?落ちる人の特徴も紹介
総合型選抜おすすめ塾
ホワイトアカデミー高等部の【料金・評判・特徴】を塾経験者が徹底取材!
ホワイトアカデミー高等部の合格実績は?メリット・デメリットは?
ルークス志塾の料金はリーズナブル?塾経験者が他塾と料金比較した結果
【ルークス志塾】の評判・口コミ10選!塾経験者が徹底調査
【総合型選抜対策塾】ルークス志塾の合格実績・メリット・デメリットを徹底調査
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
AOI塾の料金を調査!メリット・デメリット|オンライン校の料金は?
【注目】総合型選抜おすすめ塾ランキング!専門家が選んだ11社紹介
小論文対策に自信あり!おすすめ塾9選|総合型選抜対策塾の選び方
総合型選抜塾|おすすめ人気厳選11社|料金・特徴・コースを解説
【総合型選抜に強い塾】塾に行くべき?塾経験者がおすすめする!【総合型選抜対策塾の紹介】
総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
【浪人生】総合型選抜おすすめオンライン塾10選|推薦入試で志望校に合格
総合型選抜専門塾【KOSKOS】ってどうなの?口コミ・評判・料金を調査した結果は?
総合型選抜専門塾!英検対策にも強い!合格実績豊富な塾15社を厳選




