「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
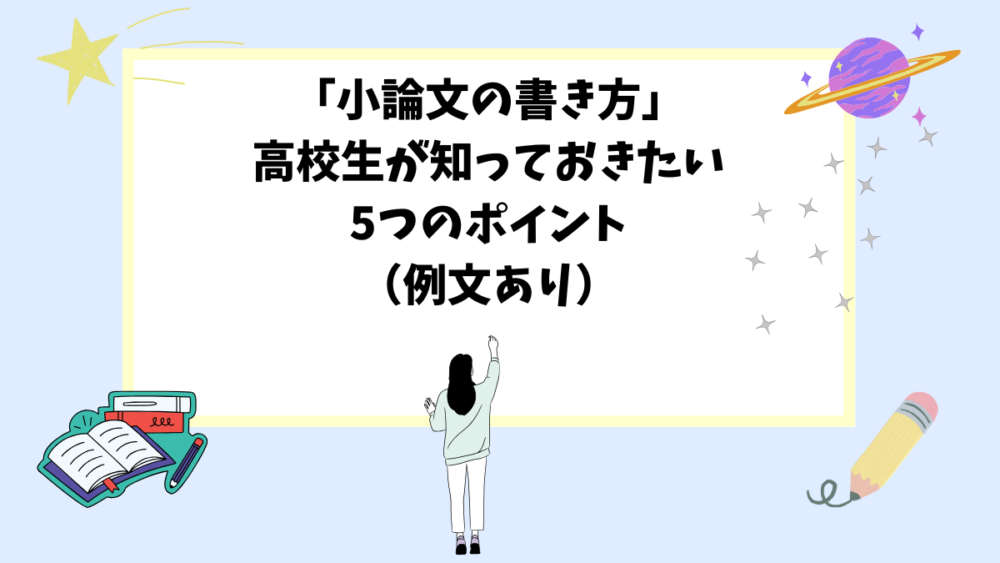
「※この記事には一部PRが含まれます」
こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。
受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。
今回のお悩みはこちら。
小論文の書き方?
小論文を書く時の注意点を知りたい
受験生の皆さん、小論文の書き方って学校で教えてもらいましたか?
実は、今回紹介する「「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)」を読めば、小論文の書き方がわかります。
なぜなら、今回紹介する、小論文の書き方のポイントを知っていると、小論文が書きやすくなるからです。
この記事では、小論文の書き方を具体的に紹介しています。
記事を読み終わると、小論文の書き方について初心者の高校生にもわかる内容になっています。
「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
小論文の書き方のアドバイス
評価を高くする小論文の書き方の実例
小論文の書き方の基本
Contents
- 1 「小論文の書き方」高校生編
- 2 小論文で問われるポイント
- 3 「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
- 4 小論文の書き方のポイント5つ
- 5 評価を高くする小論文の書き方の実例:序論編
- 6 評価を高くする小論文の書き方の実例:本論編
- 7 評価を高くする小論文の書き方の実例:結論編
- 8 小論文の書き方の基本
- 9 小論文の出題パターン
- 10 小論文で出題されるテーマ【学部別】
- 11 総合型選抜で小論文対策したい高校生
- 12 おすすめ小論文対策対応!総合型選抜塾の紹介
- 13 合格保証制度あり!ホワイトアカデミー高等部
- 14 専門家による小論文専門個別指導塾:翔励学院
- 15 総合型選抜に強い「逆転コーチング」で小論文対策!
- 16 フルオーダーメイド授業!総合型選抜専門塾AOI
- 17 小論文対策なら!オンライン予備校「Studyコーデ」
- 18 やる気が上がる!学び方が身につく!モチベーションアカデミア
- 19 総合型選抜塾:オンライン家庭教師メガスタ
- 20 総合型選抜で合格実績NO.1のルークス志塾
- 21 まとめ:「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
「小論文の書き方」高校生編

大学入試で問われる小論文とは?
小論文は、論説文やレポート、論文などといった説明的文章の一種。
大学受験での小論文は、「明確な理由、根拠」を示した上で、なぜそう考えるか、なぜその内容が正しいと判断したのかを、順を追って説明しなくてはいけません。
このように筋道を立てて述べることを「論じる」といいます。自分の考えを、根拠を基に論じることは小論文の必須条件です。
ちなみに、小論文の多くが社会的な出来事を出題したり、あなた自身について表現することが求められます。
小論文は、与えられたテーマに対して答えを示し、そう考えた理由を述べる点がポイント。
参考記事:翔励学院の口コミ・評判・料金は?小論文対策におすすめできる塾?
小論文で問われるポイント

小論文で問われるポイントについて紹介していきます。
①小論文は、論理的な文章構成能力と的確な表現力
②小論文は、読み手を納得させる、具体的で客観的な論証方法
③小論文は、具体例から抽象化し、自分と考えの異なる反論を論破しながら自説を述べ、結論を導く力
上記3つのポイントを考えながら文章を書く練習を積み重ねることで文章能力がアップして、小論文の対策にもなりますのでしっかりと練習してください。
「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)

「小論文の書き方」、ポイント5つについてまとめてみました。
以下のポイントについて説明しています。
小論文と作文の違い
小論文の書き方の対策
小論文の書き方とは
小論文試験は、一般選抜(一般入試)・学校推薦型選抜(推薦入試)・総合型選抜(AO入試)などで課され、読解力・思考力・論述力を試す試験。
小論文とは与えられたテーマに対して、自分の意見とその理由を制限文字数内で論述するものです。
また、説明的文章といわれる、特定のテーマに対する書き手の主張を、読み手に説明する文章を論述するため、論述問題とも言われます。
指示されたテーマについて自分で見解を考え、それを論理的に文章で表現できるかどうかで、知識の総合的な応用力が問われるのです。
そして、主張を説明するためには、なぜその内容が正しいと判断したのかを理由や根拠を挙げながら、論理的に説明しなくてはいけません。
このように、自分の考えを、理由や根拠を考えて論じることが小論文の必須条件です。
主観的な感想や断片的な意見を書き連ねるだけですむ作文とは、要求レベルがまったく違うので注意してください。

参考記事:大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
小論文と作文の違い
作文と小論文の違いを知れば、小論文を理解しやすくなります。
作文は、体験談や読書感想文に代表されるように、出来事から心境や感想を述べ、表現の旨さなどがポイントになる文章のこと。
一方で小論文は、先程も説明しましたが、自分の考えを、理由や根拠を考えて論じることが小論文の必須条件です。
したがって、作文では自分の思っていることや感想を感性豊かに表現できますが、小論文では自分の意見について根拠を示して論じなければなりません。
作文と小論文の違いを理解できれば、小論文も書けるはずです。

参考記事:【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
小論文の書き方の対策
小論文に対して初心者の高校生は、小論文の書き方を学ぶ前に志望校の過去問をチェックしてください。
理由は、過去の小論文のテーマを確認すると、テーマの傾向が見えてくるからです。
例えば国際系であれば、「最近の国際情勢について」、社会学系であれば「最近の円安傾向について」などのテーマが出題されます。
出題されるテーマの傾向を分析してみてください。
次に、小論文対策の参考書を購入するのもおすすめです。
最近の入試傾向を分析した参考書も出版されているので、効率よく小論文の書き方の対策ができるはずです。
小論文を書く際に何が求められているのかをきちんと理解したい方、高得点を取りたい方は、ぜひ小論文の参考書を読んでみてください。

参考記事:大学受験に強い!オンライン家庭教師おすすめ40選!合格実績・料金を比較
小論文の書き方のポイント5つ

小論文の書き方の5つのポイントについてまとめてみました
以下の項目について説明しています。
1.小論文の構成
2.段落に沿ってメモする
3.書き出しのポイント
4.本論の書き方
5.結論の書き方
小論文の書き方:文章の構成
小論文の書き方で最も重要なのは、「構成」です。
小論文をうまく書けない人の多くは、構成を決めずに書き始めてしまいます。
大学入試でおすすめの構成は大きく3部に分かれ、問題提起(序論)→原因分析(本論)→結論という順になっているのが一般的です。
この小論文の3部構成は、「序論→本論→結論」と呼ばれることもあります。
それぞれの概要を確認していきましょう。
| 問題提起(序論) | 与えられた設問に対して問題点を見つけ出し、論文のテーマと結論を決めます。 |
| 原因分析(本論) | 基本的に本論は「問題に対する原因分析」を行う段落で、知識・情報、体験・経験、引用・資料のことを中心に書いていきます。 |
| 結論 | 自分の意見と結論を述べて、締めくくります。 |
小論文の問題は600~800字が一般的なので、構成を決める際は序論100字、本論400字、結論100字など、段落ごとの文字数を事前に割り振って考えましょう。
この構成に従って書けば、的外れなことを書くこともなくなるため、基本的な小論文の構成となります。

参考記事:【総合型選抜対策】成績が悪い受験生必見|今の評定平均は関係ない
小論文の書き方:段落に沿ってメモする
小論文をいきなり書き始めるのではなく、まずは構成に沿ってメモすると小論文が書きやすくなります。
最初に出題の主旨、すなわち「何を聞かれているのか?」を把握することが大切です。
主旨を理解したうえで、書き出しはどうするのか?(序論)、原因分析をどうするのか?(本論)、結論を導き出すために、どのような構成にすべきか?(結論)を考えて、構成メモは箇条書きにして洗い出すのがおすすめです。
構成が固まったら、どんどんメモを書いて文章に肉づけしていくことが、結果的にうまく、早く書くことにつながるのです。

参考記事:総合型選抜(AO入試)対策!いつ始める?時期と学年別戦略を徹底解説
小論文の書き方:書き出しのポイント
小論文は、書き出しが書ければ、後はスラスラ書けるのに、最初の書き出しがかけないことがあります。
小論文の序論は文章の印象を決めてしまう場合があるので、特に注意が必要です。
小論文は、序論と結論を書き、書き出しが難しい場合は、本論から書き始めると書きやすくなります。
小論文の序論はあくまで問題提起を担う部分なので、ここで主観を入れすぎないように書くことが大切です。

参考記事:大学の指定校推薦で落ちる確率は?落ちる理由と合格率を高める対策を解説!
小論文の書き方:本論の書き方
本論は、結論に沿って自分の意見を述べ、論理的に話を広げていく部分です。
小論文は、自分の意見だけでなく、体験談や客観的な証拠などが提示できると、説得力が増します。
また、調査や分析して分かった事実を基に、主張を裏付ける根拠を述べていき、論述に必要であれば2つ以上の段落になるケースもあります。
本論の字数配分は65%~80%を目安にすると良いでしょう。

参考記事:総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
小論文の書き方:結論の書き方
小論文の結論を「まとめ」と勘違いしている高校生も多くいます。
小論文の結論は、必ず問題に対する答えを書くことが必要です。
そのため、追加の内容や感想などを書く必要はありません。
小論文は、序論と結論で答えを述べ、本論で理由を説明する構成になっていることがポイント。
小論文の構成は、序論と結論が「伝えたいこと」で、本論は「それを証明する根拠」。
小論文の書き方で、覚えておきたいのは、基本的に序論と結論は同じ内容になるのがポイントです。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
参考記事:ホワイトアカデミー高等部の料金・口コミ・評判を担当者に直接取材!
評価を高くする小論文の書き方の実例:序論編
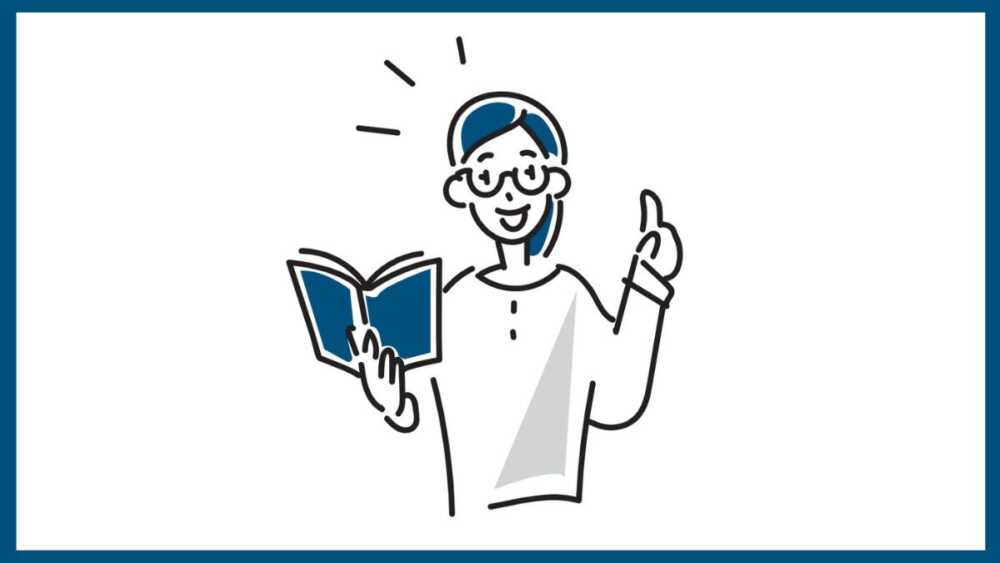
小論文の序論においては、書き出しのパターンを活用することで読者の興味を引きつけることができます。
以下に一部の一般的な書き出しのパターンをご紹介します。
実例や具体的な事実の引用する小論文
小論文に「問いかけ」を使う
引用や名言を使った小論文
エピソードやパーソナルストーリー
実例や具体的な事実の引用する小論文
例えば、問題の背景や関連する出来事、統計データなどを小論文に引用することで、読者の関心を引きつけることができます。
例文
「20㉓年に行われた調査によれば、若年層の失業率は過去10年間で急増しており、深刻な社会問題となっています。」

小論文に「問いかけ」を使う
小論文は、読者に問いかける形式で始めることで、関心や共感を喚起することができます。
問いかけは、具体的な状況や社会的な課題に関連させることが効果的です。
例文
あなたの周りにも、高齢者を支えるための適切な介護施設が不足していると感じたことはありませんか?

引用や名言を使った小論文
小論文は、有名な引用や名言を使用することで、テーマに関連する重要な考え方や価値観を示すことができます。
例文
ジョン・F・ケネディは「地球上で最も重要なリソースは人間の才能です」と述べていますが、この言葉は現代の労働市場における若者の就職難を強く指摘しています。

エピソードやパーソナルストーリー
自身の経験や身近な人のエピソードを紹介することで、読者の共感や興味を引くことができます。
例文
私自身、SNSの普及によって友人とのコミュニケーションが大きく変わった経験があります。
この小論文のパターンは、序論の最初の数文において活用されることが一般的です。
書き出しの目的は、読者の注意を引きつけることであり、テーマや問題の重要性を示すことです。
その後、具体的な背景情報や問題の提起、論点の設定など、序論の主要な要素を展開していくことが求められます。
ただし、書き出しのパターンはあくまで参考であり、テーマや文体によって使い分けることが重要です。
読者の興味を引きつけつつ、論文の主題に即した明確な導入を心がけてください。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
評価を高くする小論文の書き方の実例:本論編

小論文の本論においても、いくつかの一般的な書き方のパターンがあります。
以下に代表的なパターンをいくつかご紹介します。
小論文の問題解明・分析
小論文は前提条件・証拠の提示
論点の反論・反対意見への対応
小論文に比較・対照を用いる
小論文の問題解明・分析
小論文は、まず論文のテーマや問題点を明確にし、その背景や要因を分析します。
その後、それぞれの要因や要素について詳しく説明し、関連する情報やデータを示します。
【テーマ:若者のストレスとメンタルヘルスの関係】
例文
若者のストレスが社会問題となっている現代において、その要因や影響について深く分析する必要があります。学業や就職のプレッシャー、SNSの影響など、さまざまな要素が若者のメンタルヘルスに与える影響を明らかにすることが重要です。

小論文は前提条件・証拠の提示
小論文は、論文の主張や立場を明確にし、その根拠となる前提条件や証拠を提示します。
具体的な例や統計データ、専門家の意見などを用いて、主張の信憑性を裏付けます。
【テーマ:健康的な食生活の重要性】
例文
健康的な食生活は身体的な健康だけでなく、心理的な健康にも大きな影響を与えます。栄養バランスの取れた食事は、認知機能や集中力の向上につながるとされています。さらに、多くの研究が、野菜や果物の摂取がうつ病や不安障害のリスクを低減する効果があることを示唆しています。

論点の反論・反対意見への対応
論文の主題についての反論や反対意見を取り上げ、それに対して自身の主張を強化するための反論を行います。
相手の意見を尊重しながら、自身の立場を明確にし、妥当性を示します。
【テーマ:勉強時間と学習効果の関係】
例文
一部の人々は、長時間の勉強が高い学習効果につながると主張しています。しかし、実際には長時間の勉強が必ずしも学習効果に直結するわけではありません。疲労や集中力の低下により、長時間の勉強がむしろ学習効果を低下させる場合もあります。適切な休憩や効果的な学習方法の導入が必要です。

小論文に比較・対照を用いる
論文のテーマに関連する異なる要素や視点を比較・対照することで、読者に洞察を与えます。
共通点や相違点を明確にし、それぞれの要素の重要性や影響を考察します。
【テーマ:都市部と地方の教育格差】
例文
都市部と地方における教育格差は、さまざまな要素により引き起こされます。都市部では教育機関の充実度やアクセスの良さが高い一方、地方では教育資源の不足や教師の確保の難しさが課題となっています。このような状況を比較・対照することで、教育格差の是正に向けた具体的な施策や支援策の必要性が浮き彫りになります。
これらのパターンは、本論の構成や展開において活用されます。
小論文は、主題に応じて最適なパターンを選び、論文の論理的な流れを確立することが重要です。
また、適切な順序や結びつきを持たせながら、具体的な例やデータ、論理的な説明を用いて主張を展開していくことが求められます。
ただし、これらのパターンはあくまで一例であり、論文のテーマや目的によって使い分ける必要があります。
より効果的な論文を書くためには、テーマに関する情報を十分に収集し、自身の主張を明確にすることが重要です。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
評価を高くする小論文の書き方の実例:結論編

小論文の結論の書き方にはいくつかのパターンがあります。
以下に代表的なパターンをいくつかご紹介します。
小論文:結論のまとめ
小論文:問題意識の強調
小論文:提言や展望
小論文:結論のまとめ
結論のパターンの一つは、論文で議論したポイントや主張を簡潔にまとめる方法です。
このパターンでは、論文の主題や目的に基づいて、議論の結果や重要なポイントを繰り返し強調します。
例文
以上から、若者のストレスとメンタルヘルスの関係についての研究を通じて、多くの要因が若者のメンタルヘルスに影響を与えることが明らかになりました。学業やSNSの使用などの要素が重要であり、これらの要素への対策やサポートの充実が求められます。

小論文:問題意識の強調
結論のパターンのもう一つは、論文で取り上げた問題の重要性を再度強調する方法です。
このパターンでは、論文で議論した問題の背景や影響について再度触れ、読者にその重要性を印象づけます。
例文
以上の分析から、健康的な食生活の重要性が明らかになりました。食事は単なる身体の栄養補給だけでなく、心と身体の調和を促す重要な要素であり、私たちの健康と幸福に直接関わっています。

小論文:提言や展望
結論のパターンの中には、今後の展望や提言を述べる方法もあります。
このパターンでは、論文で議論した問題の解決策や改善策について提案し、将来の方向性を示します。
例文
今後は、教育格差の是正に向けた具体的な施策や支援策の実施が求められます。都市部と地方の教育環境の均衡化や教師の配置の改善など、様々なレベルでの取り組みが必要です。また、地方の教育資源の活用や地域と学校の連携強化など、地域特性を生かした取り組みも重要です。
これらのパターンは結論の書き方の一例です。
結論は論文のまとめとして重要な役割を果たすため、読者に強い印象を与えるような言葉遣いや表現を選ぶことが求められます。
論文のテーマや目的に応じて、適切なパターンを選び、明確かつ締めくくりのある結論を書くことが重要です。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
参考記事:ホワイトアカデミー高等部の合格実績は?メリット・デメリットは?
小論文の書き方の基本

入試で減点されないように小論文の書き方の基本についてまとめてみました。
以下のポイントについて説明しています。
文字数不足や大幅な文字数オーバー
小論文の書き方「語尾の統一」
小論文の書き方「原稿用紙」
・書き出しは一字下げる
・段落を変える場合も改行して一字下げる
・アルファベットの大文字は一マスに一つ、小文字は一マスに二つ
・「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」は一文字として扱います。
・句読点やカギカッコは一文字として扱い、行の一番上にくる場合は、前の行の一番下に入れる
・「!」「?」「…」などの記号的表現は使いません。
・縦書きの場合、数字は必ず漢数字を使い、横書きの場合は、漢数字・算用数字どちらでも可

参考記事:総合型選抜面接を突破する自己PR作成術と例文!大学受験攻略ガイド
文字数不足や大幅な文字数オーバー
小論文にはあらかじめ文字数の制限があります。
そのため、求められる文字数に不足している、または文字数をオーバーすると減点の対象になります。
問題によって文字数は変わりますが、以下を参考におおよその文字数を知っておきましょう。
| 必要な文字数の目安 | ポイント |
| ○○字以内 | 〇〇字の9割以上 |
| ○○字程度 | ○○字の前後1割以内 |
| ○○字~●●字 | その範囲内 |
小論文の初心者の高校生は、文字制限に文字数が達しないことがよくあります。
その場合は構成力が不足している可能性が高いので、あらためて構成を組み立てる練習をしましょう。
逆に文字数がオーバーしてしまう場合は、簡単に表現できる箇所や省略できる箇所を見つけて修正することで、密度の濃い文章に変えられます。

参考記事:総合型選抜に落ちたら!次は何の対策をすべきか?落ちる人の特徴も紹介
小論文の書き方「語尾の統一」
小論文を書く際には語尾を統一することで、文章の統一感が図られ、読みやすい文章になります。
小論文は「~です。~ます。」調の語尾ではなく、「~だ、~である」で全て統一。
小論文で使うべき語尾、「~だろう」「~ない」、「~べきだ」。
決して「~だ、~である」と「~です、~ます」が混ざった文章にならないように注意してください。
話し言葉・略語は使わないのが鉄則です。
総合型選抜で逆転合格するなら!
「逆転コーチング総合型選抜」
プロのコーチが生徒をサポート
リーズナブルな料金設定
自分の可能性に挑戦しよう!
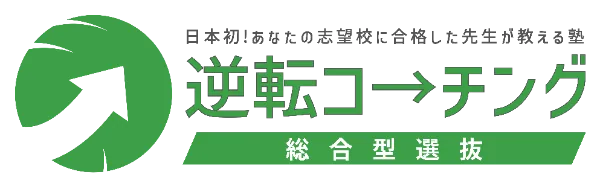
「逆転合格」で未来が変わる
総合型選抜に強い!逆転コーチング
↓↓↓
参考記事:逆転コーチング総合型選抜はやばい?口コミ・評判・料金を徹底取材!
小論文の出題パターン

小論文のテーマにはよく出題される、3つの決まったパターンがあるので、そのパターンを理解して小論文を書くことが攻略の近道といえます。
テーマを見たら、どのパターンなのか判断して取り組むと効率的です。
| 課題型(テーマ型) | 「〜について述べよ」「~について論じなさい」と、テーマだけが提示される出題形式。与えられたテーマについて、社会的背景や多くの人が知っている事実のうちから、自分の論じようとする問題点をピックアップして、意見を述べていくというパターンです。 |
| 課題文型 | 「次の文章を読み、自分の意見を述べよ」「○○について述べよ」、一定のまとまった文章が提示される出題形式。最近の大学入試用小論文で一番多い出題形式です。あらかじめ課題文が与えられ、それをふまえた上で、設問にそって自分の考えを述べていくというパターンです。課題文の内容を的確に把握し、それに基づいて自分の主張を組み立てなければならないので、「書く」能力とともに「読む」能力が必要とされているといえるでしょう。また、このパターンの場合、小問で課題文の「要約」が求められることもあります。 |
| 資料分析型 | 図やグラフ、写真などのデータを示され、それをもとに自分の意見を述べる出題形式。「資料を読み取り、〇〇について述べよ」、課題文読解型の「文章」が「図・写真」や「データ」に変わった出題形式といえるパターンです。 |
小論文で出題されるテーマ【学部別】

大学入試における小論文の出題テーマは、学部や系統によって異なることがありますが、一般的なテーマや実例を以下に示します。
ただし、具体的なカリキュラムや学校によって異なる可能性があるため、出題例はあくまで一般的なものです。
また、学部や系統によってテーマが異なるため、全ての学部や系統を網羅しているわけではありませんが、参考にしてください。
| 学部 | 出題事例 | 出題実例 |
| 文学部系統 | ロマンチック期の文学と現代文学の比較 文学作品のキャラクター分析 文学作品における象徴主義の使用 文学作品の社会的な影響 | ・フェミニズムの文学運動について論じ、その影響を考察せよ。 ・シェイクスピアの戯曲の中で権力と野心がどのように描かれているか分析せよ。 |
| 社会科学系統 | 社会的不平等の原因と影響 現代の政治的な課題に関する意見 犯罪と社会的環境の関連性 現代の国際政治の課題 | ・世界的な気候変動に関連する政府の政策の効果を評価せよ。 ・社会メディアが若者の意識形成に与える影響を検討せよ。 |
| 自然科学系統 | 環境問題と持続可能性に関する考察 新興技術の倫理的な側面 有名な科学者や発見に関する論文 未解決の科学的謎についての議論 | ・遺伝子組み換え作物の安全性に関する科学的証拠をまとめ、その利点とリスクについて説明せよ。 ・人類の健康に対する新興感染症の脅威について論じ、予防策について提案せよ。 |
| ビジネス・経済系統 | グローバル経済の影響と機会 企業の倫理と社会的責任 経済学的モデルの評価 イノベーションと競争力の関係 | ・デジタル経済が伝統的なビジネスモデルに与える影響を分析し、企業が競争力を維持するためにどのように適応すべきか考察せよ。 ・持続可能なビジネス実践の成功事例を挙げ、その理由を説明せよ。 |
これらは一般的なテーマの例ですが、実際の出題テーマは大学によって異なります。
小論文対策として、特定のテーマについての調査と分析を行うことが重要です。
また、出題されたテーマに関する実際の小論文例を参考にすることも役立つでしょう。
総合型選抜で逆転合格するなら!
「逆転コーチング総合型選抜」
プロのコーチが生徒をサポート
リーズナブルな料金設定
自分の可能性に挑戦しよう!
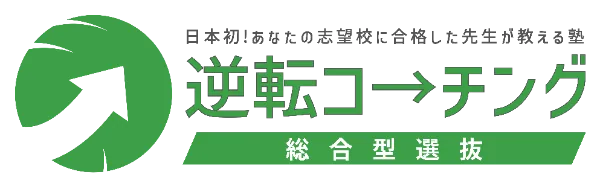
「逆転合格」で未来が変わる
総合型選抜に強い!逆転コーチング
↓↓↓
参考記事:理系学部におすすめ!塾・予備校ランキング厳選23社!理系大学を目指すならこの塾!
総合型選抜で小論文対策したい高校生

総合型選抜で合格する高校生がやっている対策についてまとめてみました。
以下のポイントを参考にして、取り組んでみてください。
総合型選抜対策一人では難しい
総合型選抜対策で塾に通うメリット
総合型選抜対策
総合型選抜で受かった高校生がやっていた対策を紹介します。
1.大学のアドミッションポリシーを理解する
総合型選抜においては、各大学のアドミッションポリシー(入学試験の方針や基準)に合わせた対策が必要。
アドミッションポリシーに合わせた対策としては、各大学のアドミッションポリシーを早めに入手し、建学の精神・教育理念・教育目標などからアドミッション・ポリシーとの関連性を考えながら、一読んでいくと、大学が求めている人物像が理解できるでしょう。
2.小論文対策
総合型選抜の小論文は、指定されたテーマについて自分の意見を述べるものです。
対策としては、以下のポイントに注意することが重要です。
・テーマについて十分な調査
・論点を整理し、論理的な構成を考える
・自分の意見を明確にする
・読みやすく、わかりやすい文章を書く
・問題提起や結論など、最後までしっかり書く
3.面接の対策
面接では、自己PRや志望理由、将来の目標などについて話すことが求められます。
そのため、自己分析して自分の強みや弱み、やりたいことなどを明確にし、自分自身のアピールポイントを作り上げることが大切。
また、大学の特色や学部・学科の研究内容についても理解しておく必要があります。面接の練習をすることで、自分の話し方や表現力を磨けるでしょう。

総合型選抜対策一人では難しい
総合型選抜対策は、一人で行うことも可能ですが、効率的に取り組むためには、以下のような点に注意する必要があります。
【勉強仲間を作る】
総合型選抜は、単独での勉強よりもグループでの勉強が有効です。勉強仲間を作り、情報や知識を共有し、励まし合いながら取り組むことが大切。
【塾や予備校に通う】
総合型選抜は、高校の勉強だけでなく、適性検査や面接に対応する必要があるため、塾や予備校に通うことで対策できます。
【受験対策の書籍や問題集を利用する】
総合型選抜に特化した受験対策の書籍や問題集を利用することで、適性検査や面接対策のポイントを押さえた勉強が可能です。
【オンライン授業やチューターの活用】
近年では、オンライン授業やチューターの利用が一般的になってきました。自宅で受講できるため、効率的に勉強時間を確保できます。
以上のような方法を活用することで、総合型選抜対策を効率的に進めることができる。

総合型選抜対策で塾に通うメリット
総合型選抜の対策において、塾に通うことには以下のようなメリットがあります。
【経験豊富な講師による指導が受けられる】
塾には、経験豊富な講師が多数在籍しています。
これらの講師は、総合型選抜の対策についての知識や経験が豊富であり、適切なアドバイスや指導を受けられます。
【グループ学習ができる】
塾では、複数の生徒が同時に学習を行うグループ学習が行われることも。
このグループ学習によって、他の生徒の考え方や意見を聞け、自分自身の学習に役立つでしょう。
【総合型選抜に必要なスキルを練習できる】
総合型選抜には、小論文や面接など様々な試験科目があります。
塾では、これらの科目に必要なスキルやテクニックを練習でき、総合型選抜に向けたスキルアップを目指せます。
【モチベーションを維持できる】
塾では、独学で学習するよりも、仲間や講師と一緒に学習することで、モチベーションを維持しやすい環境が整っています。
また、塾でのテストや模擬面接など、実際の試験に近い形式での練習も行われるため、緊張感を持って勉強できます。
【自分自身の弱点や課題を把握できる】
塾では、模擬試験や課題提出などを通じて、自分自身の弱点や課題を把握できます。
この情報をもとに、自分自身の勉強計画を立て、効率的な学習ができるでしょう。
おすすめ小論文対策対応!総合型選抜塾の紹介
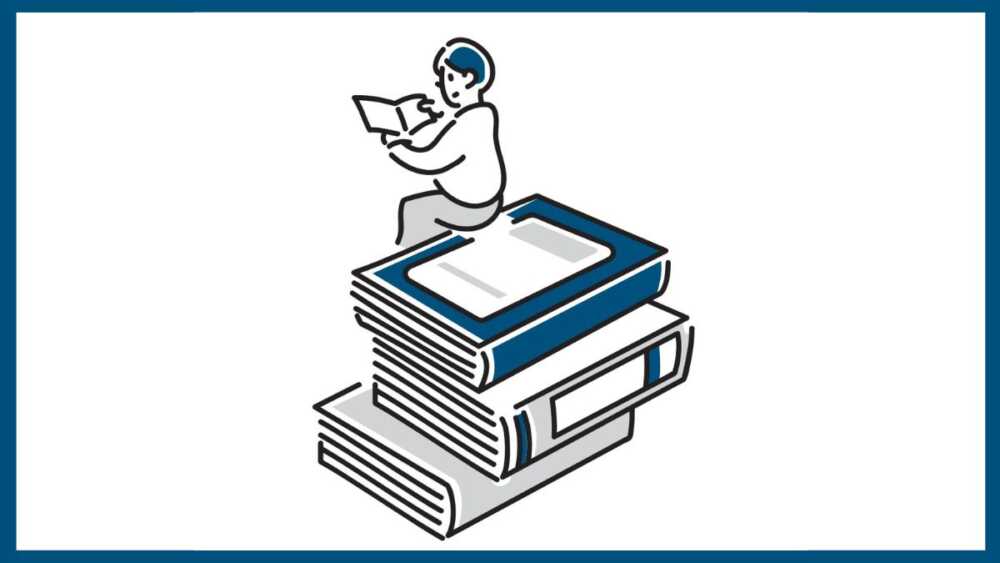
総合型選抜対策として、おすすめできる塾を紹介。
小論文対策に悩んでいる皆さん!志望校に合格したいですよね?
そこで、合格するための最初のアドバイス!
それは、気になる総合型選抜塾に、まずは資料請求だけしてみること。
もちろん、資料請求するだけなら無料、しかも、スマホで簡単にできます。
そして、今回紹介する、総合型選抜塾を利用すれば、個人情報の取り扱いについても安心。
また、無理な営業等一切ありませんのでご安心ください。
資料を受け取ることで、総合型選抜塾のサービスについてより詳しく理解できるでしょう。
合格保証制度あり!ホワイトアカデミー高等部

社会人のプロ講師が現役合格を導いてくれる、ホワイトアカデミー高等部の特徴について紹介。
【合格保証と返金制度】
ホワイトアカデミーは、他の塾ではマネのできない、安心サポートが用意されています。その1つ目は、生徒の志望大学群への合格を保証するというものです。ホワイトアカデミー高等部では、生徒一人ひとりの成績向上と合格を真剣に考えています。2つ目は、カリキュラムを消化し、現役で受験校に1校も受からなかった場合、授業料を全額返金する制度です。適切な指導法とプログラムで生徒を合格に導く自信があるからこそできるサポートと言えます。
※合格保証・返金制度には適用条件があります。詳細についてはお問い合わせください。
【講師は全員社会人のプロ講師】
他の塾はアルバイトの大学生が指導することが多いのに対し、ホワイトアカデミー高等部の講師は全員社会人。この違いが何を意味するかというと、受験の世界や社会の厳しさを熟知し、専門知識と実務経験を持つプロが生徒たちを指導する安心感です。ホワイトアカデミー高等部の講師陣は、志望校への合格を高い確率で導くために、実践的なアドバイスを行い、その結果、高い合格率を実現しています。
【一般選抜入試に切り替えて対応】
ホワイトアカデミー高等部は、総合型選抜へのサポートがメインですが、もし万が一、総合型選抜で合格できなかった場合でも、一般入試に向けて切り替えてサポートします。ホワイトアカデミー高等部では、生徒たちが志望する大学への現役合格を実現するために、総合型選抜と一般入試の両方の試験対策を重視しています。
ホワイトアカデミー高等部は、予備校オンラインドットコムがおすすめする総合型選抜専門塾です。
| ホワイトアカデミー高等部の基本情報 | |
| ホワイトアカデミー高等部公式ホームページ | https://whiteacademy-ao.com/ |
| 指導教科 | 総合型選抜・学校推薦選抜対策専門 |
| 指導形式 | オンライン個別指導 |
| 授業料 | 要問い合わせ |
| 講師 | 社会人のプロ講師 |
| 使用端末・アプリ | スマホ・タブレット・PC・Zoom |
| サポート体制 | 合格保証・返金制度あり |
| 無料体験授業 | 無料相談会実施中 |
小論文の添削サービス:回数無制限
総合型選抜を利用する受験生の多くが課題とする小論文。
ホワイトアカデミー高等部では、学部ごとによく出題されるテーマを選択し、小論文の書き方を回数制限なくサポート。
小論文の「型」を理解することで、志望大学から求められるスコアを確保できるように指導します。
予備校オンラインドットコムがおすすめする!公式ホームページからホワイトアカデミー高等部の説明会に参加してみましょう!きっと、現役合格が近づくはずです。
参考記事:ホワイトアカデミー高等部の料金・口コミ・評判を担当者に直接取材!
合格保証と返金制度で万全のサポート体制
※講師は全員社会人のプロ講師!高い合格率!
※総合型選抜・学校推薦型選抜に特化した授業
専門家による小論文専門個別指導塾:翔励学院

【小論文専門:翔励学院の特徴】
小論文に特化した個別指導
翔励学院は小論文対策に特化し、生徒一人ひとりの考え方や個性に合わせた指導を行う専門学院です。その理念「覚悟の小論文個別指導」のもと、真剣に生徒と向き合い、高い合格実績を持っています。講師陣は小論文の知識に深く精通し、継続的なサポートも提供。生徒の志望先や学習状況を考慮し、最適な指導を実施しています。
小論文のプロ講師による指導
翔励学院は小論文のプロ講師による専門指導を行っています。各講師は小論文の深い知識と経験を持ち、一人ひとりの生徒の考え方や個性を尊重したカスタマイズされた指導を実施。その結果、生徒たちは入会当初とは比べ物にならないほどの成長を遂げ、多くの合格者を輩出しています。学院の指導は単なるテクニック伝授ではなく、深い理解とともに生徒の表現力や思考力を高めることを目的としています。
志望大学への高い合格率94%
翔励学院の最大の特徴は、高い合格実績にあります。これは、独自の指導メソッドと経験豊富な講師陣による質の高い授業が組み合わさっているからです。過去の生徒たちの多くが、学院の指導のもとで小論文のスキルを飛躍的に向上させ、志望校に合格しています。
小論文専門:翔励学院の基本情報
| 翔励学院の基本情報 | |
| 翔励学院の公式ホームページ | https://www.syorei-gakuin.com/ |
| 指導教科 | 小論文対策に特化 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 授業料 | 34,800円〜 |
| 講師 | 社会人のプロ講師、 |
| 使用端末・アプリ | 対面指導、渋谷校舎のみ |
| サポート体制 | 面接・志望理由書の指導もあり |
| 無料体験授業 | 無料体験授業実施中! |
小論文専門:翔励学院の料金
| コース名 | 料金 | 回数 | 内容 |
| 入門コース | 34,800円 | 月4回 | 基礎学習と進路選択のサポート |
| 標準コース | 67,200円 | 月8回 | 小論文の基礎から応用までの指導 |
| お急ぎコース | 83,500円 | 月10回 | 速やかな対策と書類作成サポート |
| 緊急対応コース | 99,600円 | 月12回 | 短期間での徹底的な対策と書類作成サポート |
総合型選抜に強い「逆転コーチング」で小論文対策!

逆転コーチングの基本情報
| 逆転コーチングの基本情報 | |
| 逆転コーチングの公式サイト | https://gyakuten-coaching.com/sogo |
| 対象学年 | 高校生、既卒生 |
| 指導教科 | 総合型選抜対策 |
| 指導形式 | オンラインコーチングとリアルタイム授業 |
| 授業料 | 48,000円〜 |
| 講師 | プロコーチ、難関大学に在籍している講師 |
| 使用端末・アプリ | パソコン・タブレット・スマホ |
| サポート体制 | オンライン自習室、全国80ヶ所に対面式の自習室を完備 |
| 無料体験授業 | 無料体験実施中 |
「逆転コーチング」総合型選抜とは?
逆転コーチング総合型選抜は、早慶、上智、MARCH、関関同立などの難関私立大学の総合型選抜に特化したオンライン塾です。
プロのコーチが1対1で、総合型選抜に必要なすべての対策をサポートしてくれるので、合格に向けてしっかり準備できます。
オンライン指導だから、地方や海外に住んでいる人でも、質の高い指導が受けられます。
忙しい高校生でも、好きな時間や場所で効率よく学習できる環境が整っています。
以下のような悩みを抱えている受験生にピッタリの総合型選抜を実施してくれるはずです。
・総合型選抜に合格したいけど何から始めればいいのかわからない
・学校では総合型選抜の対策をしてくれない
・スポーツやコンテストで結果を残したことがないけど、総合型で大学を目指したい
・家の近くに総合型の対策ができる塾がない
総合型選抜で逆転合格できるノウハウ
公式サイトをチェック!
↓↓↓
フルオーダーメイド授業!総合型選抜専門塾AOI

総合型選抜専門塾AOIの特徴を紹介。
一人ひとりの生徒に向き合ったフルオーダーメイド授業
総合型選抜専門塾AOIの一人ひとりの生徒に向き合ったフルオーダーメイド授業とは、生徒一人ひとりの学力や学習状況、興味・関心に合わせて、授業内容や指導方法をカスタマイズした授業です。フルオーダーメイド授業では、生徒一人ひとりの特性やニーズに合わせて、授業内容や指導方法をカスタマイズすることで、より効果的な学習が実現できます。
総合型選抜の合格者がメンターとしてサポート
総合型選抜専門塾AOIは、総合型選抜の合格者がメンターとしてサポート。総合型選抜を受験する受験生にとって、大きなメリット。なぜなら、総合型選抜の合格者の経験やノウハウを活かして、合格するために必要な力が身につき、受験に関するさまざまな悩みや不安を、メンターに相談できるからです。
最新の入試情報や受験ノウハウを提供
入試制度や出題傾向は、年々変化しています。そのため、最新の情報を把握しておくことで、より効果的な受験対策ができます。受験ノウハウは、勉強法やメンタルコントロールなど、受験に役立つさまざまな方法をまとめたものです。総合型選抜専門塾AOIの受験ノウハウを活用することで、効率的に学習を進めたり、不安を解消できます。
総合型選抜専門塾AOIの基本情報
| 総合型選抜専門塾AOIの基本情報 | |
| 総合型選抜専門塾AOIの公式ホームページ | https://aoaoi.jp/ |
| 指導教科 | 総合型選抜に特化 |
| 指導形式 | オンライン個別指導、全国に校舎あり |
| 授業料 | 44,000円〜 |
| 講師 | 社会人のプロ講師、 |
| 使用端末・アプリ | スマホ、タブレット、PC |
| サポート体制 | オンライン授業対応 |
| 無料体験授業 | 無料体験授業実施中! |
総合型選抜専門塾AOIの料金
【高校2年生】
月額:44,000円〜
【高校3年生】
年間:39万円〜
AOIの小論文対策
総合型選抜では、スコアが明示されず、自身の実力が見えにくいという不安が生じます。
そこで、AOIでは独自の取り組みとして、「模擬出願・小論文模試」を実施しています。
模擬出願では、志望理由書などの書類をAOIに提出し、自分の実力を評価する手助けを行います。
また、小論文模試では、本番と同様の環境で小論文を執筆し、採点。
これにより、受験当日までに自身の実力を明確に把握し、合格への自信を高めることが可能です。
参考記事:総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
小論文対策なら!オンライン予備校「Studyコーデ」

小論文対策なら!Studyコーデのおすすめポイント
「合格だけをゴールにしない」探究型の指導スタイル
Studyコーデの総合型選抜コースでは、志望理由書やプレゼン対策だけでなく、「自分はなぜこの大学に行きたいのか」「どんなことを学びたいのか」といった本質的な探究心を深掘りしてくれます。ただの書類作成サポートではなく、将来の目標や価値観に向き合いながら準備できるのが大きな特徴です。
プロ講師がマンツーマンで面接や書類の添削までサポート
総合型選抜では、志望理由書や活動報告書など、書類の完成度が合否を大きく左右します。Studyコーデでは受験のプロが一貫して指導するため、書き方から内容の深掘り、面接練習まで、すべてマンツーマンで対応してくれます。自分一人では気づけないポイントを客観的にアドバイスしてもらえるのが強みです。
時間や場所にとらわれず準備ができるオンライン体制
部活や学校の課題、他の受験準備と並行して総合型選抜を進めるのは大変です。Studyコーデは完全オンラインなので、自分のスケジュールに合わせて柔軟に受講可能。LINEやZoomで24時間相談もでき、忙しい高校生にとって非常に効率的です。
【合格保証制度】
MARCHや日東駒専など一部の大学を対象に合格保証制度があります。これはStudyコーデが生徒の合格に責任を持って取り組んでいることを示しています。
\日本のオンライン塾TOP5/
↓↓↓
「Studyコーデ」の公式HPをチェック!
小論文対策なら!オンライン予備校「Studyコーデ」の基本情報
| Studyコーデの基本情報 | |
| Studyコーデの公式ホームページ | https://studycoorde.com/ |
| 対象学年 | 高校生、既卒生 |
| 指導教科 | 私立文系専門・総合型選抜に対応 |
| 指導形式 | マンツーマン個別指導 |
| 授業料 | 26,400円〜 |
| 講師 | 専属のプロ講師 |
| 使用端末・アプリ | ZOOM、パソコン、スマホ、タブレット |
| サポート体制 | Lineで24時間質問OK |
| 無料体験の有無 | 無料体験実施中 |
やる気が上がる!学び方が身につく!モチベーションアカデミア
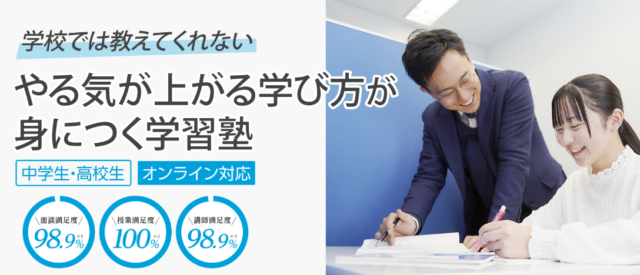
(モチベーションアカデミア:公式ホームページ)
受験だけでなく、社会で活躍できる人財を育む為の進学塾【モチベーションアカデミア】の特徴
モチベーションアカデミアは、
・文部科学省が提唱する「生きる力」
・経済産業省が公表する「社会人基礎力」
・そして個人の「モチベーション向上」
を社会人教育に取り入れたパイオニア、(株)リンクアンドモチベーション(東証一部)が設立した、中高生向けの進学塾です。
【PDCA学習サポート】
受験生に限らず、目標を達成したいのに実行できない、やる気が続かないと悩んでいる受験生が多いため、モチアカでは、社会人の目標達成プロセスとして用いられる「PDCAサイクル」を成績アップ・志望校合格への学習プランニング・習慣創りに活用しています。
【定期テストから難関大学受験までをカバーする!完全1対1 オーダーメイドの個別指導!】
モチアカでは「完全1対1の個別指導」で最適な授業スタイルを提供。生徒一人ひとり現状の課題も目指す目標も異なります。だからこそモチアカは完全1対1の個別指導にこだわり、生徒ごとに設計するオーダーメイドカリキュラムに沿って講師が授業を実施。
定期テスト対策はもちろん、最難関大を含めた受験対策にも対応しています。
「これからの入試」に完全対応! 主体性に学ぶ力を育む【モチアカの総合型選抜・推薦入試対策】
総合型選抜・推薦入試対策に強いモチベーションアカデミア!偏差値重視と言われてきた日本の大学入試は、今大きな変化を迎えています。
例えば、「総合型選抜(旧AO入試)」に代表される、従来の筆記型学力試験とは異なる入試の増加。
モチアカでは、この入試の変化に完全対応。総合型選抜や推薦入試対策カリキュラムを充実させています。
モチベーションアカデミアの基本情報
| モチベーションアカデミアの基本情報 | |
| モチベーションアカデミアの公式ホームページ | https://m-academia-s.com/ |
| 対象学年 | 中学生・高校生・浪人生 |
| 指導教科 | 主要5教科 |
| 指導形式 | 完全1対1の個別指導 |
| 授業料 | 生徒一人ひとりにカリキュラムが違うため、お問い合わせ願います。 |
| 講師 | 厳しい採用基準を満たしたプロ講師 |
| 使用端末・アプリ | パソコン・タブレット・スマホ |
| サポート体制 | 自習室完備、オンライン対応 |
| 無料体験 | 実施中 |
モチベーションアカデミアの小論文対策
モチベーションアカデミアの小論文講座は、大学入試の「小論文」科目に加え、将来の大学生活や社会人としての必須スキルを養うための力を養います。
文章表現力は、レポートや企画書の作成など、コミュニケーションにおいて非常に重要。
モチベーションアカデミアの講座では、生徒たちが文章を書くだけでなく、思考力を鍛え、言葉で考えを表現する能力を高める方法を指導しています。
思考を言葉にすることで、新しいアイディアが生まれ、相乗効果が生じる仕組みがあります。
モチベーションアカデミアの小論文講座は、これらのスキルを磨くための秘密を教えています。
参考記事:モチベーションアカデミア│評判・口コミ・料金・合格実績を徹底調査
勉強のやる気が上がる!モチベーションアカデミア
※総合型選抜・オンラインにも対応
※モチアカの学習システムで学び方が身につく
総合型選抜塾:オンライン家庭教師メガスタ

メガスタは総合型選抜専門塾ではありませんが、総合型選抜での合格実績が豊富なため紹介します。
ただし、料金についてはホームページに記載がないため、目安として参考にしてください。
オンライン家庭教師メガスタの基本情報
| オンライン家庭教師メガスタの基本情報 | |
| サービスの特徴 | 慶應・早稲田・上智などの難関大学を中心に4,500人以上の生徒さんを合格させてきたノウハウに基づいた「総合型選抜(AO)・推薦専門指導」を全国どこからでもオンラインで受けられます。 |
| 対象学年 | 高校生、浪人生 |
| 指導教科 | 主要5教科 |
| 指導形式 | 講師一人につき生徒5人までの少人数制 |
| 授業料 | ・志望理由書作成コース 1回100分全18回(少人数指導16回+個別指導2回):272,800円 ・面接強化コース 講座+実技指導:少人数指導1コマ:15,400円×6回=92,400円 ・受かる小論文強化コース 週1回100分×月4回・月謝制:67,540円~ |
| 講師 | プロ講師が多数在籍 |
| 使用端末・アプリ | パソコン・タブレット・スマホ、双方向型のリアルタイムのオンライン指導 |
| サポート体制 | 授業満足度96.3% |
オンライン家庭教師メガスタの特徴
オンラインで圧倒的な合格実績!メガスタの総合型選抜対策で合格できる8つの理由!
理由1.大学受験に圧倒的な専門性があります!
理由2.多くの大学が使用している採点方式で受かるよう指導します!
理由3.実は、人数が重要!1対5の少人数のオンライン指導!
理由4.実績ゼロ・経験ゼロでも大丈夫!アピールポイントを見つけます!
理由5.1対1のマンツーマンで「志望理由書」を添削します!
理由6.受かるノウハウを伝授!入試さながらの面接対策
理由7.1対1でプロが指導!受かる小論文の書き方が身につく!
理由8.対面と同じ指導ができます!
オンラインプロ教師合格実績No.1のメガスタ!公式ホームページをチェックしてください。
参考記事:メガスタの料金(入会金・授業料)はいくら?他のオンライン家庭教師と比較
総合型選抜で合格実績NO.1のルークス志塾

総合型選抜専門塾で合格実績NO.1のルークス志塾について紹介します。
総合型選抜・AO入試に特化したカリキュラム
ルークス志塾のカリキュラムは、総合型選抜・AO入試に必要な学力と思考力を養うことを重視しています。そのため、小論文や面接などの対策はもちろん、基礎学力や大学研究などの対策も充実しています。
1対1の個別指導と少人数制のグループ指導を組み合わせた指導
ルークス志塾では、1対1の個別指導と少人数制のグループ指導を組み合わせた指導。1対1の個別指導では、一人ひとりの学力や志望校に合わせたきめ細やかな指導を受けられます。少人数制のグループ指導では、他者との交流を通して、自分の考えが深められるでしょう。
豊富な合格実績
ルークス志塾は、総合型選抜専門塾の合格実績がNO.1の実績を誇っています。憧れの難関大学への合格実績も多数有しています。2023年度には、東京大学、京都大学、慶應義塾大学、早稲田大学など、難関大学への合格者を輩出しています。
これらの特徴を踏まえると、ルークス志塾は、総合型選抜・AO入試で難関大学を目指す受験生におすすめの塾と言えるでしょう
総合型選抜:ルークス志塾の基本情報
| ルークス志塾の基本情報 | |
| ルークス志塾の公式ホームページ | https://aogijuku.com/ |
| 指導教科 | 総合型選抜に特化 |
| 指導形式 | オンライン個別指導、全国に校舎あり |
| 授業料 | 16,500円〜 |
| 講師 | 社会人のプロ講師、難関大学の学生講師 |
| 使用端末・アプリ | スマホ、タブレット、PC |
| サポート体制 | オンライン授業対応 |
| 無料体験授業 | 無料体験授業実施中! |
ルークス志塾の料金
高校1年・2年生の料金
【自分のペースで通塾できる:月極パック】あらかじめ、月の受講回数を決めていただくプラン。
月4コマコース : ¥44,000円
月8コマコース : ¥74,800円
高校3年生の料金
【1.コマ単位での受講コース】1ヶ月で授業を受講する回数により、料金が決まるプラン。
・入塾料 ¥33,000
・在籍基本料 ¥11,000
・授業1コマ ¥16,500
ルークス志塾の小論文対策講座
ルークス志塾の小論文対策講座は、生徒のレベルや志望校に合わせた完全カスタマイズのカリキュラムで指導。
ルークス志塾では、主にマンツーマンまたは少人数指導を中心に行っており、一部、大人数のクラスも設けています。
そのため、生徒自身の実力や志望校にピッタリ合った効率的な小論文対策を実現できます。
推薦入試から一般入試まで、幅広いニーズに対応し、個別に合わせた指導ができるのが強みです。
参考記事:ルークス志塾の料金はリーズナブル?塾経験者が他塾と料金比較した結果
総合型選抜専門塾で合格実績NO.1のルークス志塾
※難関校への進学率「86.1%」
※夢を叶えたいなら!ルークス志塾へ
まとめ:「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)」は参考になりましたでしょうか?
まとめ:「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
大学入試の小論文は、自己表現や論理的思考能力を評価するための重要な要素です。以下に、大学入試の小論文を書く際のポイントを5つご紹介します。
【テーマの明確化と構成の工夫】
与えられたテーマに対して明確な立場を取り、主張や意見を明確にすることが重要。また、論文の構成も整理されていることが求められます。導入部で読者の興味を引き、本文では主張を展開し、結論でまとめるようにしましょう。論理的な流れを持たせることで、読みやすく理解しやすい論文が書けます。
【具体的な例や事実の使用】
主張や意見を支えるために、具体的な例や事実を挙げることが重要。自身の経験や読んだ本、ニュース、研究結果などを引用して論文を裏付けましょう。これによって、論文がより具体的で説得力のあるものになります。
【論理的な展開と引用の活用】
論文を書く際には、論理的な展開や引用を活用することが求められます。論理的な展開では、前提や根拠を明示し、段落ごとに主題文を設定して一貫性を持たせましょう。また、信頼性のある情報源からの引用を適切に活用することで、主張を裏付けできます。
【独自性と個人の視点の表現】
大学入試の小論文では、自身の個性や視点を表現することが重要です。他の人とは異なる独自のアプローチや視点を持ち、それを論文に反映させましょう。個人の経験や考えを通じて、自己表現力を示すことが求められます。
【文章の正確性と表現の工夫】
正確な文章と適切な表現を使用することも重要なポイント。文法や句読法のルールに従い、明確な文章を書くように心掛けましょう。また、冗長な表現や曖昧な言葉遣いを避け、簡潔かつ明快な表現を心がけましょう。これによって、読み手にとって分かりやすく魅力的な論文となるでしょう。
これらのポイントに留意しながら、自身の考えを明確に表現し、論理的な構成を持った小論文を書くことが大切です。
総合型選抜に関する人気の記事
総合型選抜面接を突破する自己PR作成術と例文!大学受験攻略ガイド
小論文対策に強い塾おすすめ10選!短期間で成績アップも夢じゃない
受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは
大学面接で聞かれることランキング【質問と回答例】入試対策にもすぐに使える
総合型選抜(AO入試)に向いている人・向いてない人・落ちる人の特徴を解説
総合型選抜(旧AO入試)対策塾【安い!おすすめ15選】受験生必見!料金相場とは?
【総合型選抜に強い塾】塾に行くべき?塾経験者がおすすめする!【総合型選抜対策塾の紹介】
総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
浪人生が総合型選抜で合格する方法とは?実績豊富なおすすめ塾10選
【総合型選抜】受かる確率を上げる!受験生なら知っておきたい7つのポイント!
【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
ルークス志塾の料金はリーズナブル?塾経験者が他塾と料金比較した結果
ホワイトアカデミー高等部の料金・口コミ・評判を担当者に直接取材!
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
予備校オンラインドットコムおすすめ塾の紹介



