総合型選抜(ao入試)プレゼンテーション対策【効果抜群】5つのコツ
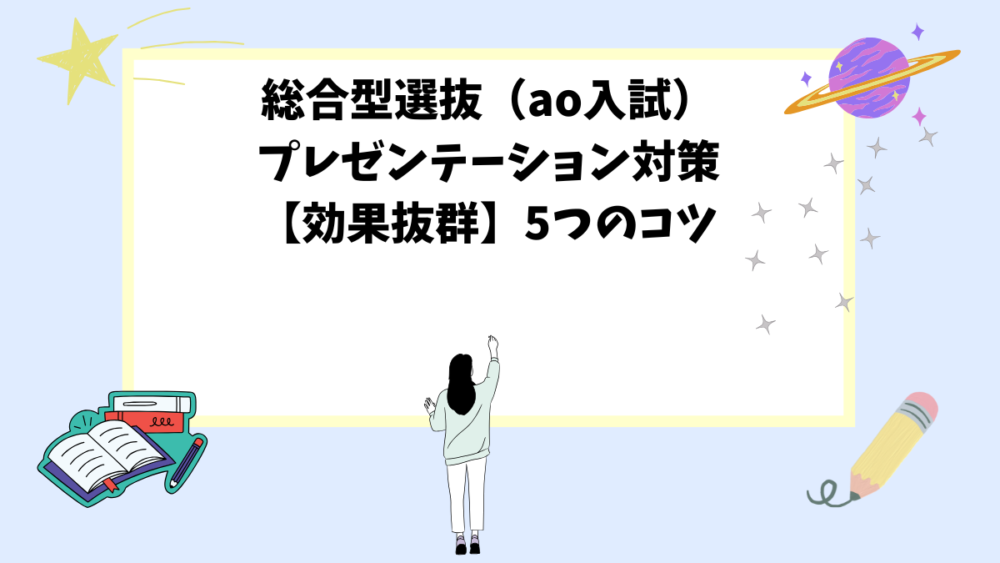
「※この記事には一部PRが含まれます」
監修:進路アドバイザー資格保有者
本記事は、高校生の進路指導において豊富な経験と専門知識を有する、進路アドバイザー資格保有者の監修のもと作成されています。
皆さんが自信を持って総合型選抜に取り組めるよう、具体的かつ分かりやすい情報をお届けします。安心して読み進めてください。
Contents
はじめに:総合型選抜のプレゼン、不安を自信に変える第一歩

総合型選抜のプレゼンテーションは多くの受験生にとって大きな挑戦です。
しかし適切な準備と戦略があれば、不安を自信に変え、あなたの個性や能力を最大限にアピールするチャンスとなります。
この記事では、プレゼンテーションで合格をつかむための効果的な対策法を、具体的なステップとともに紹介します。
大学側が重視するポイントを押さえながら、あなたらしさを発揮できるプレゼンテーションを目指しましょう。
あなたもこんな悩み、ありませんか?
あなたもこんな悩み、ありませんか?
「プレゼンテーションの経験がほとんどない」「何をテーマにすればいいのか分からない」「人前で話すと緊張して頭が真っ白になる」—このような不安は多くの受験生が抱えています。
特に初めての総合型選抜では、どのように準備すればよいのか分からず戸惑ってしまうことも珍しくありません。
たとえば、文系学部志望なのに数字やグラフを使った発表が苦手と感じたり、自分の考えを論理的に伝える自信がなかったりするかもしれません。
「質疑応答で想定外の質問をされたらどうしよう」という不安を抱える人も多いでしょう。

この記事を読めば、プレゼン対策の具体的な方法がわかる
この記事では、初めてプレゼンテーションに挑戦する方でも実践できる具体的な対策方法をご紹介します。
テーマ設定から資料作成、話し方のコツ、質疑応答の準備まで、総合型選抜で求められるプレゼンテーションのポイントを網羅しています。
具体的には、
・大学側が評価するポイントを踏まえたテーマ選びの方法
・短時間で伝わる構成と原稿の作り方
これらを実践することで、自分の強みを最大限に活かしたプレゼンテーションが可能になります。
あなたの不安を自信に変えるための第一歩を踏み出しましょう。
まずは知っておこう!総合型選抜におけるプレゼンテーションとは?

総合型選抜のプレゼンテーションは、ペーパーテストでは測れない皆さんの能力や資質を評価するための重要な選考方法です。
このセクションでは、なぜ大学がプレゼンテーションを課すのか、どのような形式で行われるのか、そして評価される具体的なポイントについて解説します。
プレゼンの本質を理解することで、効果的な対策の土台を築きましょう。
一般的な形式と流れ(時間、質疑応答、オンライン形式など)
ここで差がつく!評価されるポイントとアピールすべきこと
なぜプレゼンテーションが課されるの?大学が見ているポイント
大学がプレゼンテーションを課す最大の理由は、思考力・表現力・コミュニケーション能力を総合的に評価するためです。
単なる知識量ではなく、情報を整理し自分の考えを論理的に伝える力や、質問に対して臨機応変に対応できる柔軟性を見ています。
特に注目されているのは以下のポイントです。
・専門分野への関心度と理解度
・論理的思考力と問題解決能力
具体的には、「なぜこの学部・学科を志望するのか」「どのような研究や活動に興味があるのか」という点について、あなたの熱意と具体性のある計画性が評価されます。

一般的な形式と流れ(時間、質疑応答、オンライン形式など)
総合型選抜におけるプレゼンテーションは、大学によって形式が異なりますが、一般的には次のような流れで進行します。
基本的なプレゼンテーション時間は5〜10分程度が多く、その後に質疑応答が5〜10分程度設けられています。
最近では、オンライン形式でのプレゼンテーションを実施している大学も増えており、その場合はZoomなどのビデオ会議ツールを使用することが一般的です。
形式としては、パワーポイントなどのスライドを使用するケース、事前に提出した資料をもとに説明するケース、その場でテーマが与えられるケースなど、大学や学部によって多様です。必ず志望校の要項で確認しましょう。

ここで差がつく!評価されるポイントとアピールすべきこと
総合型選抜のプレゼンテーションでは、内容の独自性と伝え方の工夫が大きな差となります。
合格者のプレゼンには、以下の共通点があります。
【アピールすべきポイント】
・志望動機と将来ビジョンの一貫性
・高校時代の経験と大学での学びの接続性
たとえば、「単に知識を述べるだけでなく、自分なりの問題意識や解決策を提示できているか」「データや具体例を効果的に活用できているか」といった点が評価されます。
質問に対して誠実に応答する姿勢も重要です。
参考記事:総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリット!学校推薦型選抜の違いを解説
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
参考記事:ホワイトアカデミー高等部の合格実績は?メリット・デメリットは?
合格を掴む!効果抜群のプレゼンテーション対策【5つのコツ】

プレゼンテーションで合格をつかむためには、準備と練習が欠かせません。
このセクションでは、他の受験生と差をつける5つの具体的なコツをご紹介します。
テーマ選びから資料作成、話し方まで、それぞれのステップで実践できる効果的な方法を解説します。
これらのコツを取り入れることで、あなたの魅力を最大限に引き出すプレゼンテーションが可能になります。
コツ2:構成で納得させる!論理的で分かりやすいストーリー作り
コツ3:資料(スライド)で惹きつける!視覚的な工夫
コツ4:話し方で心を掴む!自信と熱意を伝える表現力
コツ5:質疑応答で評価を高める!的確な対応力を身につける
コツ1:テーマ設定で魅せる!独自性と熱意の伝え方
プレゼンテーションの成功は、テーマ設定で大きく左右されます。
あなただけのユニークな視点と強い熱意が伝わるテーマ選びが重要です。
自分の経験や関心と学問分野を結びつけることで、オリジナリティのあるプレゼンテーションが実現します。
自分ならではのテーマを見つけるヒント
テーマ選びで悩んだら、まずは自分の「なぜ?」を探ることから始めましょう。
「なぜこの学問に興味を持ったのか」「なぜこの大学・学部を志望するのか」という原点に立ち返ることで、あなたならではのテーマが見えてきます。
【効果的なアプローチとしては】
・高校での学び・課外活動と志望分野の接点を探る
・日常生活での疑問と専門分野の知識を結びつける
たとえば、英文学専攻を志望する場合、単に「シェイクスピアについて」ではなく「地元の方言から考える言語の多様性とシェイクスピアの表現技法」といった独自の切り口を考えてみましょう。
テーマを深掘りし、オリジナリティを出す方法
テーマが決まったら、次は深掘りと差別化です。
インターネットで検索すれば出てくるような一般的な情報だけでは、印象に残りません。
【オリジナリティを出す方法としては】
・複数の分野や概念を独自に組み合わせる
・具体的な事例や自分の体験と結びつける
たとえば、経済学部志望なら「地元商店街の活性化」というありふれたテーマも、「高校生の視点から見た商店街活性化—SNSマーケティングの可能性」と具体的な提案を含めることで独自性が生まれます。

コツ2:構成で納得させる!論理的で分かりやすいストーリー作り
どんなに素晴らしい内容でも、構成が整っていなければ相手に伝わりません。
聞き手を納得させる論理的な構成と、心に残るストーリー性を兼ね備えたプレゼンテーションを目指しましょう。
適切な時間配分と伝わりやすい原稿作りがポイントです。
基本構成をマスターしよう(PREP法、ストーリーテリングなど)
効果的なプレゼンには構成が重要。初心者にはPREP法、個性を出すにはストーリーテリングがおすすめです。
【PREP法:結論から話すシンプル構成】
・Point(結論): 最初に最も伝えたいことを明確に。 例:「私は〇〇大学で△△を研究したいです。」
・Reason(理由): なぜそう考えるかの根拠を具体的に。 例:「高校時代の〇〇経験から、この分野が重要だと感じました。」
・Example(具体例): 理由を裏付ける具体的な事例やデータ。 例:「〇〇ボランティアで△△という問題に直面し、〇〇を学びました。」
・Point(結論の再提示): 最後に再び結論を強調。 例:「この経験が、貴学での研究に活かせると確信しています。」
【ストーリーテリング:物語で共感を呼ぶ構成】
・導入: 興味を引くオープニングで聴衆の心を掴む。 例:「私の〇〇への関心は、高校時代の〇〇という出来事がきっかけでした。」
・展開: 具体的な経験や出来事を詳細に語る。 例:「その時、私は〇〇という課題に直面し、〇〇という行動を取りました。」
・山場: 最も重要な転換点や感情が高まる瞬間を描写。 例:「しかし、〇〇という壁にぶつかり、〇〇を通して乗り越えました。」
・結末: 学びや成長、将来への展望を示す。 例:「この経験から〇〇を学び、貴学での研究に活かしたいです。」
状況に合わせてPREP法とストーリーテリングを使い分け、効果的なプレゼンを目指しましょう。
PREP法は論理的に、ストーリーテリングは感情的に訴えかけます。
時間配分を意識した構成案の作り方
限られた時間内で効果的に伝えるには、適切な時間配分が重要です。
一般的な5分間のプレゼンテーションでは、次のような配分が効果的です。
【時間配分の目安】
・導入(問題提起・自己紹介):30秒〜1分
・本論(内容の説明・分析):3分程度
実際に時間を計りながら練習することで、内容と時間のバランスを調整していきましょう。
「この部分は1分以内で話す」といった具体的な目標を設定すると、メリハリのある発表ができます。
伝わるプレゼン原稿作成のポイント
原稿作成では、話し言葉で書くことを心がけましょう。
文章として美しくても、口頭で伝わりにくい表現は避けるべきです。
【効果的な原稿のポイント】
・1文を短くシンプルに保つ
・専門用語を使う場合は必ず説明を加える
たとえば、「したがって」よりも「つまり」、「~において」よりも「~では」など、口語的な表現の方が聞き取りやすくなります。
強調したいポイントには「特に重要なのは」「ここがポイントです」といった合図を入れると、聞き手の注意を引きつけられます。

コツ3:資料(スライド)で惹きつける!視覚的な工夫
プレゼンテーションでは、聴覚だけでなく視覚にも訴えかけることが重要です。
効果的な資料作りによって、あなたの主張がより明確に、より印象的に伝わります。
このセクションでは、見やすいスライド作成のコツとビジュアル要素の活用方法について解説します。
見やすいデザインの基本原則(フォント、色、レイアウト)
スライドデザインは、シンプルさと一貫性が基本です。
情報過多のスライドは逆効果になります。
【デザインの基本ルール】
・1スライドにつき1つのメッセージに絞る
・フォントは2種類まで、サイズは24ポイント以上を基本とする
たとえば、タイトルには明朝体、本文にはゴシック体というように統一感を持たせましょう。
色使いも3〜4色程度に抑え、背景は白や淡い色、文字は濃い色というコントラストを確保することで視認性が高まります。
図やグラフを効果的に使うテクニック
数字やデータを示す場合は、図やグラフの活用が効果的です。
複雑な情報も視覚化することで、直感的に理解してもらえます。
【効果的な視覚化のコツ】
・棒グラフ:比較を示す時に最適
・円グラフ:全体に対する割合を示す時に効果的
たとえば、「日本の18歳人口の推移と大学進学率」を説明する場合、折れ線グラフと棒グラフを組み合わせることで、少子化の中での進学率上昇という傾向が一目で伝わります。
グラフには必ずタイトルと出典を明記しましょう。
文字とビジュアルの最適なバランスとは?
スライドの情報量は少なめに抑え、話す内容と視覚情報のバランスを取ることがポイントです。
【バランスの良いスライドの特徴】
・キーワードや要点のみを箇条書きにする
・詳細な説明は口頭で行い、スライドには載せない
具体的には、1スライドあたり5〜6行程度、1行あたり5〜6単語程度を目安にしましょう。
「このスライドで何を伝えたいのか」が3秒で理解できるくらいがちょうど良いバランスです。
写真やイラストを使う場合も、装飾ではなく内容理解を助けるものを選びましょう。

参考記事:総合型選抜の面接!自己PRの仕方&自己PR文の書き方【例文付き】
コツ4:話し方で心を掴む!自信と熱意を伝える表現力
プレゼンテーションの説得力は、内容だけでなく「どう話すか」にも大きく左右されます。
聞き手の心に届く話し方を身につけることで、あなたの熱意と自信が伝わります。
このセクションでは、声の使い方や身体表現のテクニック、そして緊張を味方につける方法を解説します。
聞き手を引きつける声のトーン、スピード、間の取り方
声の使い方一つで、プレゼンの印象は大きく変わります。
抑揚をつけ、適切なスピードと間を意識しましょう。
【効果的な話し方のポイント】
・重要なポイントでは声のトーンを変える(少し低く、ゆっくりと)
・一般的な情報は通常の速さ、重要な点はやや遅めに話す
たとえば、「この問題について、特に注目すべき点が3つあります」と言う時に、「特に注目すべき点」の部分でスピードを落とし、少し間を取ることで、聞き手に「ここが大事だ」と印象づけられます。
一文の終わりには小さな間(1秒程度)を意識的に置くと、聞き手が情報を整理する時間になります。
視線やジェスチャーの効果的な使い方
非言語コミュニケーションも、メッセージの伝達に大きく影響します。
適切な視線配布とジェスチャーで、より生き生きとしたプレゼンテーションになります。
【効果的な身体表現】
・視線は特定の人に固定せず、全体に配る
・重要なポイントを強調する際に簡潔なジェスチャーを使う
たとえば、「3つのポイントがあります」と言いながら指で「1、2、3」と示したり、「大きく成長しています」という言葉に合わせて上向きの動きを手で表現したりすることで、言葉の意味が強化されます。
過剰なジェスチャーは逆効果なので、自然な範囲に留めましょう。
緊張しても大丈夫!落ち着いて話すための準備
緊張は誰にでもあるものです。むしろ適度な緊張は集中力を高める効果があります。
大切なのは、緊張と上手に付き合う準備をすることです。
【緊張を抑える具体的な方法】
・本番前に深呼吸を3回程度行う
・最初の一文は完全に暗記しておく
特に発表の冒頭は緊張しやすいものです。
「本日は○○についてお話しします」といった導入部分を完璧に暗記しておくことで、スムーズにスタートできます。
メモを見る際も「次に○○について説明します」といった繋ぎの言葉を入れることで、自然な流れを作れます。

参考記事:【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
コツ5:質疑応答で評価を高める!的確な対応力を身につける
プレゼンテーションの真価が問われるのは、実は質疑応答の場面です。
想定される質問に準備するだけでなく、予期せぬ質問にも柔軟に対応する力を身につけることで、評価を一段高めることができます。
このセクションでは、質疑応答を成功させるための実践的なテクニックを紹介します。
想定される質問とその準備方法
質疑応答の準備で最も効果的なのは、予想問答集の作成です。
自分のプレゼンを客観的に見直し、質問されそうなポイントをリストアップしましょう。
【準備すべき質問の例】
・「なぜこのテーマに興味を持ったのですか?」
・「このデータの出典は何ですか?」
特に、プレゼンの中で「ここは詳しく説明していない」と感じる部分や、論理の飛躍がある部分は質問されやすいので注意が必要です。
自分の主張に対する反論を想定し、それに対する回答も用意しておくと安心です。
鋭い質問や意図しない質問への対応策
どんなに準備をしても、予想外の質問や難しい質問を受けることがあります。
そんな時こそ冷静さと誠実さが評価されます。
【対応の基本姿勢】
・質問の意図を確認する時間を作る
・わからない部分は正直に認める
たとえば、「それは興味深い視点ですね。ご質問の意図を確認させていただきたいのですが…」といった言葉で始めると、考える時間を確保できます。
質問の一部だけでも答えられる場合は「○○についてはこのように考えています。
△△については、現時点では十分な知識がないため、今後調べていきたいと思います」と、知っている部分と知らない部分を明確に区別して回答しましょう。
「わかりません」をチャンスに変える答え方
知識不足を指摘されるような質問を受けた場合でも、学ぶ意欲と誠実さを示すことで、むしろ好印象を与えることができます。
【効果的な回答例】
・「現時点では明確な回答ができませんが、重要な視点だと思います。入学後はぜひ△△の授業で学びを深めたいと考えています」
・「その点については十分な知識がありませんが、○○という関連分野についてはこのように考えています」
このように、完全な回答ができなくても、関連する知識を示したり、学習意欲をアピールしたりすることで、前向きな姿勢を伝えられます。
質問を投げ返したり、誤魔化したりするのではなく、素直に現状を認めた上で、自分の思考プロセスを示すことが重要です。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
参考記事:ホワイトアカデミー高等部の料金・口コミ・評判を担当者に直接取材!
実践あるのみ!効果的なプレゼンテーション練習方法

プレゼンテーションの成功には、入念な準備と繰り返しの練習が欠かせません。
このセクションでは、効果的な練習方法と自己改善のテクニックを紹介します。
一人でできる基本練習から、フィードバックを活用した実践的なトレーニングまで、段階的に練習を積み重ねることで、自信を持って本番に臨める力が身につきます。
声に出して時間を計ることから始めよう
録画・録音で客観的に自分の発表をチェック
模擬発表でフィードバックをもらい改善する
声に出して時間を計ることから始めよう
プレゼン練習の第一歩は、声に出して読み、時間を測定することです。
頭の中で考えているだけでは、実際の所要時間や言いにくい表現は分かりません。
【基本練習のステップ】
・最初は原稿を見ながら通して読む
・タイマーで時間を測り、予定時間内に収まるか確認する
たとえば、5分間のプレゼンテーションなら、実際に話してみると6分30秒かかった場合は、内容を約25%削減する必要があります。
声に出すことで「言いにくい言い回し」や「息継ぎが難しい長文」も発見できるので、そうした部分は修正しましょう。
特に意識したいのは、序盤でのペース配分です。
緊張すると話すスピードが速くなりがちなので、導入部分はややゆっくり目に話す練習をしておくと良いでしょう。

参考記事:評定平均とは?計算方法とは?大学推薦入試で差をつける評定対策をアドバイス
録画・録音で客観的に自分の発表をチェック
次のステップは、自分の姿を客観的に確認することです。
スマートフォンの録画・録音機能を使えば、簡単に自分のプレゼンテーションを振り返ることができます。
【チェックすべきポイント】
・声の大きさやスピードは適切か
・視線や姿勢、ジェスチャーは自然か
実際に録画を見ると「思ったより早口だった」「原稿を見すぎている」「同じフレーズを繰り返している」など、自分では気づかなかった癖が見えてきます。
特に気をつけたいのは「えーと」「あのー」などの無意識の言葉で、これらが多いとプレゼンが散漫な印象になります。
改善のコツは、問題点を1つずつ意識して練習することです。
たとえば、「今回は視線配布だけに集中する」といった具体的な目標を立てて練習し、次は別の要素に焦点を当てるといった段階的なアプローチが効果的です。

参考記事:【必見】大学受験:総合型選抜とは?総合型選抜に向いている人!向いてない人
模擬発表でフィードバックをもらい改善する
最終段階として、実際に人前で発表する練習が重要です。
家族や友人、先生など、できるだけ多くの人に聞いてもらいましょう。
【効果的なフィードバックの集め方】
・具体的な質問をする(「分かりにくかった部分はどこか」など)
・質疑応答の時間も設け、想定外の質問に対応する練習をする
たとえば、「内容は面白かったが、スライドの文字が小さくて読みづらかった」「序盤は良かったが、後半になるとスピードが速くなった」といった具体的なフィードバックが得られると、効果的に改善できます。
聞き手の表情や反応を観察することも大切です。「説明している時に聞き手が混乱した表情をしていた」などの非言語的なフィードバックも、発表の改善に役立ちます。
模擬発表を重ねるごとに自信がつき、本番での緊張も軽減されるでしょう。
これで安心!プレゼン本番前の最終チェックリストと注意点

いよいよプレゼンテーション本番を迎える前に、最終確認をしておきましょう。
このセクションでは、特に注意すべきポイントや持ち物リスト、よくある失敗例とその対策について解説します。
オンラインプレゼンテーション特有の注意点も含め、万全の準備で本番に臨めるようにしましょう。
オンラインプレゼンテーション特有の注意点と対策
服装や身だしなみで気をつけること
よくある失敗例とその回避策
当日の持ち物チェックリスト
オンラインプレゼンテーション特有の注意点と対策
コロナ禍以降、多くの大学でオンラインプレゼンテーションが導入されています。
対面とは異なる環境に対応するための準備が必要です。
【オンラインプレゼンの注意点】
・通信環境の安定性を事前に確認する
・バーチャル背景ではなく、シンプルで整った実際の背景を用意する
たとえば、プレゼン当日は家族にも協力してもらい、通信環境への負荷を減らすよう依頼しておきましょう。
カメラの角度も重要です。
目線の高さにカメラを設置し、画面に映る自分の姿を確認しておくことが大切です。
もし、画面共有をする場合は、デスクトップの整理やプライバシーに関わる情報の非表示設定なども忘れずに行いましょう。
そして何より、機器トラブルに備えてバックアッププラン(スマートフォンでの接続準備など)を用意しておくことが安心です。

参考記事:「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
服装や身だしなみで気をつけること
プレゼンテーションでは、内容だけでなく見た目の印象も大切です。
清潔感と誠実さを伝える服装を心がけましょう。
【服装のガイドライン】
・基本はシンプルで落ち着いた色合いの服装
・アクセサリーは控えめに、動きを妨げないもの
男子であれば白シャツに紺や黒のスラックス、女子であればブラウスにスカートやパンツスーツなど、フォーマル過ぎず、かといってカジュアル過ぎない服装が適切です。
特に注意したいのは動きやすさです。
窮屈な服装だと姿勢が悪くなったり、自然な動きができなくなったりするため、事前に着用して動きやすさを確認しておきましょう。
髪型は顔が見えやすいようにし、メガネをかける人は反射防止加工されたものが望ましいです。

参考記事:【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
よくある失敗例とその回避策
総合型選抜のプレゼンテーションでは、多くの受験生が同じような失敗を繰り返しています。
失敗例を知り、事前に対策を講じることで、あなたの発表はより完成度の高いものになるでしょう。
時間配分の失敗は最も多いミスの一つです。
準備不足で時間内に終わらなかったり、逆に早く終わりすぎたりするケースが見られます。
これを防ぐには、必ず時間を計りながら複数回練習することが重要です。
本番では予定より1〜2割短く終わるように準備しておくと、緊張で早口になっても適切な時間に収まりやすくなります。
次によくあるのが、スライドへの依存です。
情報を詰め込みすぎたスライドを作成し、それを読み上げるだけのプレゼンになってしまうケースです。
これを避けるには、スライドはあくまで補助ツールと位置づけ、キーワードや図表のみを掲載し、詳細は口頭で説明するスタイルを心がけましょう。
質疑応答での焦りも珍しくありません。
想定外の質問に慌てて的外れな回答をしてしまうことがあります。
対策としては、「少々お時間をいただいてもよろしいでしょうか」と一呼吸置く習慣をつけることです。
5秒程度の沈黙は不自然ではなく、むしろ真剣に考えている印象を与えます。
身体的な失敗としては、視線の固定や不自然な姿勢があります。
緊張すると原稿やスライドばかり見たり、体が硬直したりします。
これを防ぐには、練習の段階で壁に向かって発表したり、友人の前で練習したりする中で、意識的に視線を動かす訓練をしておくことが効果的です。

当日の持ち物チェックリスト
本番当日は緊張で思わぬものを忘れてしまうことがあります。
以下のチェックリストを活用して、万全の準備で臨みましょう。
【必須アイテム】
・受験票・身分証明書
・プレゼンテーション資料(USBメモリ等)のバックアップ
・筆記用具(黒・青のペン、鉛筆、消しゴム)
・時計(スマートフォン不可の場合が多い)
【プレゼン補助アイテム】
・発表用の簡易メモ(A6サイズ程度の小さなカード)
・レーザーポインター(使用許可がある場合のみ)
・ハンカチ(緊張で手が汗ばむ場合に)
【身だしなみ関連】
・リップクリーム(緊張で唇が乾燥しやすい)
・ポケットティッシュ
・ヘアブラシや櫛(身だしなみ最終確認用)
【その他の安心アイテム】
・飲み物(のどの渇きに備えて)
・常備薬(必要な人のみ)
・マスク(予備も含めて)
特に重要なのは資料のバックアップです。
USBメモリだけでなく、クラウドストレージにアップロードしておく、メールで自分に送信しておくなど、複数の方法でデータを保管しておくと安心です。
プレゼンテーション会場のアクセス方法や所要時間も必ず確認し、余裕を持って行動できるようにしましょう。
当日は想定外のことが起こる可能性も考慮し、30分前には会場に到着することを目標にしましょう。
参考記事:【総合型選抜対策】成績が悪い受験生必見|今の評定平均は関係ない
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜のプレゼンテーションに関するよくある質問(FAQ)

総合型選抜でアピールすべきことは何ですか?
総合型選抜で落ちることはありますか?
総合型選抜で受かる確率は?
プレゼンテーション型入試とはどんな入試ですか?
総合型選抜(AO入試)の選考方法の一つで、自分の考えや高校生活で頑張ってきたこと、大学で何を学びたいかを、面接官や教授たちの前で発表する入試のことです。
「話す力」や「伝える力」を通して、書類だけでは伝わりにくいあなたの個性や熱意を大学に見てもらうチャンスです。
例えるなら、大学の先生たちに「私にはこんな魅力があって、この大学でこんなことを学びたいんです!」と直接プレゼンテーションするイメージ。
パワーポイントなどの資料を使うことも多いです。

総合型選抜でアピールすべきことは何ですか?
総合型選抜では、単に成績が良いだけではなく、あなたがどんな人なのか、どんなことに興味があって、大学で何をしたいのかを総合的に見られます。
特にプレゼンテーションでは、以下の点を意識してアピールすると良いでしょう。
・あなたの個性や強み:他の誰にも負けないあなたの特別な経験や能力。
・大学・学部への強い興味と入学後の学びへの意欲:なぜこの大学でこの分野を学びたいのか、具体的な計画や熱意を伝えよう。
・高校生活での頑張り:部活動、委員会活動、ボランティア、探究学習など、主体的に取り組んだ経験とその学び。
・論理的な思考力と表現力:自分の考えを分かりやすく、筋道立てて説明する力。
・将来の目標:大学での学びを活かして、将来どんなことを成し遂げたいか。
「私は○○が好きで、高校では△△に力を入れてきました。大学では□□を学び、将来は××になりたいです!」というように、あなた自身のストーリーを熱意を持って語ることが大切だよ。

総合型選抜で落ちることはありますか?
はい、総合型選抜でも残念ながら落ちてしまうことはあります。
書類選考や面接、小論文など、いくつかの選考方法がある中で、プレゼンテーションも合否を左右する重要な要素の一つです。
主な理由としては、
・準備不足: プレゼンテーションの内容が薄かったり、練習不足でうまく伝えられなかったりする場合。
・大学の求める人物像とのミスマッチ:大学の理念やアドミッションポリシーと、あなたの考えや興味が合わないと判断された場合。
・熱意や意欲が伝わらない:なぜその大学で学びたいのかという熱意や、入学後の具体的な計画が伝わらない場合。
・基本的なコミュニケーション能力の不足:面接官の質問に適切に答えられなかったり、話す態度が悪かったりする場合。
しっかりと準備をして、自分の熱意や考えを誠実に伝えることが大切です。

総合型選抜で受かる確率は?
総合型選抜の合格率は、大学や学部、年度によって大きく異なります。
一般選抜のように明確な合格基準があるわけではなく、あなたの個性や能力、大学とのマッチングなどが総合的に評価されるため、一概に「〇〇%」と言うことは難しいです。
しっかりと準備を行い、自分の魅力を最大限にアピールできれば、合格の可能性は十分にあります。
大切なのは、倍率を気にするよりも、自分自身を深く理解し、志望する大学についてインターネット等で調べ、万全の準備をすることです。
合格保証制度で総合型選抜対策!ホワイトアカデミー高等部

社会人のプロ講師が現役合格を導いてくれる、ホワイトアカデミー高等部の特徴について紹介。
【合格保証と返金制度】
ホワイトアカデミーは、他の塾ではマネのできない、安心サポートが用意されています。その1つ目は、生徒の志望大学群への合格を保証するというものです。ホワイトアカデミー高等部では、生徒一人ひとりの成績向上と合格を真剣に考えています。2つ目は、カリキュラムを消化し、現役で受験校に1校も受からなかった場合、授業料を全額返金する制度です。適切な指導法とプログラムで生徒を合格に導く自信があるからこそできるサポートと言えます。
※合格保証・返金制度には適用条件があります。詳細についてはお問い合わせください。
【講師は全員社会人のプロ講師】
他の塾はアルバイトの大学生が指導することが多いのに対し、ホワイトアカデミー高等部の講師は全員社会人。この違いが何を意味するかというと、受験の世界や社会の厳しさを熟知し、専門知識と実務経験を持つプロが生徒たちを指導する安心感です。ホワイトアカデミー高等部の講師陣は、志望校への合格を高い確率で導くために、実践的なアドバイスを行い、その結果、高い合格率を実現しています。
【一般選抜入試に切り替えて対応】
ホワイトアカデミー高等部は、総合型選抜へのサポートがメインですが、もし万が一、総合型選抜で合格できなかった場合でも、一般入試に向けて切り替えてサポートします。ホワイトアカデミー高等部では、生徒たちが志望する大学への現役合格を実現するために、総合型選抜と一般入試の両方の試験対策を重視しています。
ホワイトアカデミー高等部は、予備校オンラインドットコムがおすすめする総合型選抜専門塾です。
【ホワイトアカデミー高等部の基本情報】
| ホワイトアカデミー高等部の基本情報 | |
| ホワイトアカデミー高等部公式ホームページ | https://whiteacademy-ao.com/ |
| 指導教科 | 総合型選抜・学校推薦選抜対策専門 |
| 指導形式 | オンライン個別指導 |
| 授業料 | 要問い合わせ |
| 講師 | 社会人のプロ講師 |
| 使用端末・アプリ | スマホ・タブレット・PC・Zoom |
| サポート体制 | 合格保証・返金制度あり |
| 無料体験授業 | 無料相談会実施中 |
合格保証と返金制度で万全のサポート体制
※講師は全員社会人のプロ講師!高い合格率!
※総合型選抜・学校推薦型選抜に特化した授業
ホワイトアカデミー高等部の公式ホームページをチェックする!
プレゼンテーション対策!総合型選抜専門塾AOI

総合型選抜専門塾AOIの特徴を紹介。
一人ひとりの生徒に向き合ったフルオーダーメイド授業
総合型選抜専門塾AOIの一人ひとりの生徒に向き合ったフルオーダーメイド授業とは、生徒一人ひとりの学力や学習状況、興味・関心に合わせて、授業内容や指導方法をカスタマイズした授業です。フルオーダーメイド授業では、生徒一人ひとりの特性やニーズに合わせて、授業内容や指導方法をカスタマイズすることで、より効果的な学習が実現できます。
総合型選抜の合格者がメンターとしてサポート
総合型選抜専門塾AOIは、総合型選抜の合格者がメンターとしてサポート。総合型選抜を受験する受験生にとって、大きなメリット。なぜなら、総合型選抜の合格者の経験やノウハウを活かして、合格するために必要な力が身につき、受験に関するさまざまな悩みや不安を、メンターに相談できるからです。
最新の入試情報や受験ノウハウを提供
入試制度や出題傾向は、年々変化しています。そのため、最新の情報を把握しておくことで、より効果的な受験対策ができます。受験ノウハウは、勉強法やメンタルコントロールなど、受験に役立つさまざまな方法をまとめたものです。総合型選抜専門塾AOIの受験ノウハウを活用することで、効率的に学習を進めたり、不安を解消できます。
【総合型選抜専門塾AOIの基本情報】
| 総合型選抜専門塾AOIの基本情報 | |
| 総合型選抜専門塾AOIの公式ホームページ | https://aoaoi.jp/ |
| 指導教科 | 総合型選抜に特化 |
| 指導形式 | オンライン個別指導、全国に校舎あり |
| 授業料 | 44,000円〜 |
| 講師 | 社会人のプロ講師、 |
| 使用端末・アプリ | スマホ、タブレット、PC |
| サポート体制 | オンライン授業対応 |
| 無料体験授業 | 無料体験授業実施中! |
【総合型選抜専門塾AOIの料金】
【高校2年生】
月額:44,000円〜
【高校3年生】
年間:39万円〜
まとめ:総合型選抜(ao入試)プレゼンテーション対策【効果抜群】5つのコツ

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「総合型選抜(ao入試)プレゼンテーション対策【効果抜群】5つのコツ」参考になりましたでしょうか?
まとめ:総合型選抜(ao入試)プレゼンテーション対策【効果抜群】5つのコツ
この記事では、総合型選抜のプレゼンテーション対策として、効果的な5つのコツを中心に解説してきました。
最後にポイントを振り返りましょう。
プレゼンテーション成功の鍵は、入念な準備と繰り返しの練習にあります。
テーマ設定から資料作成、話し方、質疑応答の対策まで、一つひとつのステップを丁寧に準備することで、自信を持って本番に臨むことができます。
特に重要なのは、あなたらしさを表現することです。
総合型選抜では、単なる学力だけでなく、あなたの個性や熱意、将来性が評価されます。
「なぜこの分野に興味を持ったのか」「大学でどのように学びを深めたいのか」といった点を、具体的なエピソードや経験と結びつけて伝えることが効果的です。
プレゼンテーションはコミュニケーションの一形態であることを忘れないでください。
聞き手を意識し、分かりやすく伝えることを最優先に考えましょう。華麗な言葉や複雑な理論よりも、誠実さと熱意が伝わる発表の方が、はるかに印象に残ります。
最後に、緊張は誰にでもあるものです。
適度な緊張は集中力を高める効果もあります。
この記事で紹介した対策を実践し、十分な準備をすることで、緊張を前向きなエネルギーに変えることができるでしょう。
総合型選抜のプレゼンテーションは、あなたの可能性を示す絶好のチャンスです。
自信を持って臨み、あなたならではの魅力を存分に発揮してください。
きっと素晴らしい結果につながるはずです。皆さんの合格を心より応援しています!
総合型選抜対策:おすすめ記事
大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
【総合型選抜】受かる確率を上げる!受験生なら知っておきたい7つのポイント!
【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
【現役高校生】総合型選抜で大学に受かる人はみんなやっている総合型選抜対策!
総合型選抜!面接対策7つのコツとは?服装やマナーについて徹底解説
【必見】大学受験:総合型選抜とは?総合型選抜に向いている人!向いてない人
【総合型選抜】落ちる確率が高い理由と突破の秘策!大学受験を推薦で合格
評定平均とは?計算方法とは?大学推薦入試で差をつける評定対策をアドバイス
総合型選抜(AO入試)対策!いつ始める?時期と学年別戦略を徹底解説
【総合型選抜】自己PR文の書き方完全ガイド|必見!例文付きで解説
総合型選抜のエントリーシートの書き方&例文で夢の大学合格を掴む!
総合型選抜(ao入試)のメリットとデメリット!学校推薦型選抜の違いを解説
総合型選抜に落ちたら!次は何の対策をすべきか?落ちる人の特徴も紹介
総合型選抜おすすめ塾
ホワイトアカデミー高等部の料金・口コミ・評判を担当者に直接取材!
ホワイトアカデミー高等部の合格実績は?メリット・デメリットは?
ルークス志塾の料金はリーズナブル?塾経験者が他塾と料金比較した結果
【ルークス志塾】の評判・口コミ10選!塾経験者が徹底調査
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
AOI塾の料金は高い!他の総合型選抜専門塾と比較した結果は?
【注目】総合型選抜おすすめ塾ランキング!専門家が選んだ11社紹介
小論文対策に強い塾おすすめ10選!短期間で成績アップも夢じゃない
総合型選抜(旧AO入試)対策塾【安い!おすすめ15選】受験生必見!料金相場とは?
【総合型選抜に強い塾】塾に行くべき?塾経験者がおすすめする!【総合型選抜対策塾の紹介】
総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
浪人生が総合型選抜で合格する方法とは?実績豊富なおすすめ塾10選
総合型選抜専門塾【KOSKOS】ってどうなの?口コミ・評判・料金を調査した結果は?
自己推薦書の書き方を例文付きで解説!大学に合格できる「書き出し」


