大学の指定校推薦で落ちる確率は?落ちる理由と合格率を高める対策を解説!
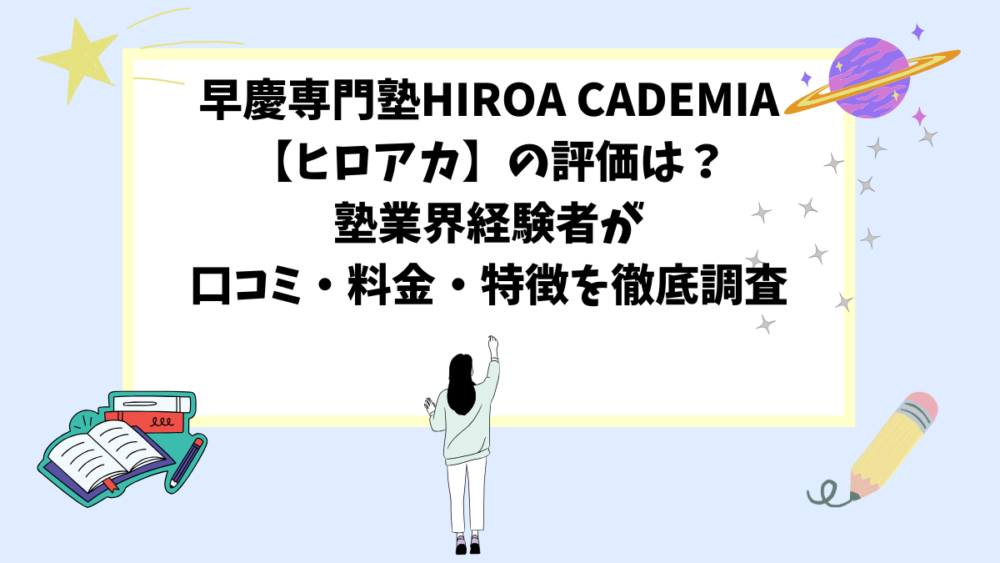
「※この記事には一部PRが含まれます」
大学の指定校推薦を目指す皆さん、不安に感じていることはありませんか?
「ほぼ受かる」と聞いてはいるものの、万が一のことを考えると心配になりますよね。
特に、小論文や面接といった大学での選考で、「もし落ちてしまったらどうしよう…」と考えることもあるのではないでしょうか。
私自身、27年間学習塾で多くの高校生と向き合う中で、この時期の生徒さんや保護者の方々が抱える、こうした『ほぼ受かるはずなのに、万が一が怖い』という切実な声を幾度となく耳にしてきました。
特に、小論文や面接が課される場合は、一般入試とは異なる種類のプレッシャーを感じるものです。
この記事では、そんな高校生の不安を解消するために、指定校推薦で落ちる確率や、不合格になる具体的な原因、そして合格を確実にするための対策を、専門家の視点、そして長年現場で生徒たちを指導してきた経験から分かりやすく解説します。
・指定校推薦で落ちる確率は極めて低いが、ゼロではない
・不合格になるのは「よほどのこと」があった場合に限られる
・「ほぼ受かる」という油断が不合格の大きな原因
・小論文対策、模擬面接、書類確認で合格は確実になる
【小論文対策に強い人気の塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
Contents
指定校推薦の小論文で落ちる確率はほぼゼロ?

結論から言うと、指定校推薦で不合格になる確率は極めて低いです。
私自身、学習塾で何人もの受験生を指導してきましたが、指定校推薦で最終的に不合格になったケースは、経験がありません。
しかし、確率がゼロではないことも事実です。
なぜ落ちにくいのか、そしてなぜゼロではないのか、その理由を詳しく見ていきましょう。
合格率が高いからこそ知っておきたい「ゼロではない」理由
基本的に「よほどのことがない限り」落ちない理由
指定校推薦が「ほぼ受かる」と言われる最大の理由は、大学と高校との間の強い信頼関係に基づいた制度だからです。
大学は、長年の実績から「この高校から推薦される生徒なら、入学後も真面目に学んでくれるだろう」と信頼して、推薦枠を設けています。
一方、高校側もその信頼を裏切らないよう、学業成績や生活態度が優秀で、その大学にふさわしいと判断した生徒だけを責任を持って推薦します。
つまり、あなたが校内選考を通過した時点で、「高校のお墨付きをもらった、大学が求める基準を満たす生徒」であると評価されているのです。
大学側の選考は、その最終確認という意味合いが強いのです。

合格率が高いからこそ知っておきたい「ゼロではない」理由
「ほぼ落ちない」とは言え、不合格になる可能性は残念ながら存在します。
明確な統計はありませんが、不合格になるのはごく稀なケースです。
しかし、毎年全国のどこかでは、指定校推薦で不合格になる生徒が少数ながら存在します。
大学側は、推薦された生徒が大学で学ぶにふさわしい最低限の基準を満たしているかを、小論文や面接を通して確認しています。
この基準に達していないと判断された場合、不合格となる可能性があるのです。
「自分は大丈夫」と油断せず、最低限の準備をしっかり行うことが、合格を確実にする鍵となります。
指定校推薦の小論文で落ちる・不合格になる主な原因

では、具体的にどのようなことが「よほどのこと」と判断され、不合格につながってしまうのでしょうか。
あなたの努力が無駄にならないよう、ここでは特に注意すべき小論文、面接、そしてその他の「落とし穴」について、詳しく見ていきましょう。
面接での不合格ケース
その他(書類不備や問題行動)
小論文での不合格ケース – テーマから著しく逸脱した内容
出題された小論文のテーマや問いに対して、全く関係のないことを書いてしまうケースです。
例えば、『グローバル化社会における日本の役割』というテーマなのに、自分の部活動の思い出ばかりを書いてしまうなど、課題を正しく理解できていないと判断されると、評価は大きく下がります。
私は生徒たちに、『書く前に必ず、何について書くべきか、30秒でいいから立ち止まって考えなさい』と繰り返し伝えてきました。
焦って書き始めると、往々にしてテーマから逸れてしまうものです。
白紙・極端な文字数不足
小論文を白紙で提出するのは論外です。
これは試験を放棄したと見なされます。
指定文字数に対して極端に少ない場合(例えば、800字指定で300字程度しか書けていないなど)も、意欲や能力がないと判断される可能性が非常に高いです。
最低でも指定文字数の8割以上は埋めるようにしましょう。
テーマから著しく逸脱した内容
小論文の出題されたテーマや問いに対して、全く関係のないことを書いてしまうケースです。
例えば、「グローバル化社会における日本の役割」というテーマなのに、自分の部活動の思い出ばかりを書いてしまうなど、出題者の意図を理解できていない、あるいは論理的に考える力が不足していると判断され、評価は大きく下がります。
基本的な構成や日本語のルール無視
小論文には「序論・本論・結論」という基本的な構成があります。
この構成を完全に無視して、思いつくままに書き連ねた文章は評価されません。
誤字脱字が多すぎる、主語と述語がねじれているなど、日本語の文章として成立していない場合も、大学での学びに支障があると見なされる可能性があります。

参考記事:小論文の段落分け完全ガイド|600字・800字・1000字の構成例と段落数の目安
面接での不合格ケース
面接は、あなたの人柄やコミュニケーション能力、そして入学意欲を直接伝える場です。
学力試験では測れない部分を評価されます。
無断欠席や大幅な遅刻
試験の無断欠席は、それだけで不合格です。
やむを得ない事情がない限り、遅刻も絶対に避けなければなりません。
社会人としての基本的なルールを守れないと判断され、信頼を大きく損ないます。
これは当たり前のことですが、緊張のあまり集合場所を間違えたり、時間を勘違いしたりといったうっかりミスで、合格を棒に振る生徒の話を聞いたことがあるため、事前の確認を徹底するよう、強く指導していました。
著しく不適切な態度や服装
面接官に対して横柄な態度をとる、質問を無視する、足を組む、貧乏ゆすりをするなど、著しく不適切な態度は一発で不合格になる可能性があります。
制服の着こなしが乱れていたり、頭髪が華美であったりするなど、場にふさわしくない身だしなみもマイナス評価につながります。
志望理由書との明らかな矛盾
提出した志望理由書の内容と、面接での回答が全く違う場合、「どちらかが嘘なのでは?」と信憑性を疑われます。
例えば、志望理由書で「貴学の〇〇教授のゼミで学びたい」と書いたのに、面接でその教授の名前を答えられない、といったケースです。

参考記事:大学受験面接マナーの教科書!入退室・服装・言葉遣いを完全網羅
その他(書類不備や問題行動)
小論文や面接以外にも、以下のような点で不合格となることがあります。
・提出書類の不備
調査書や志望理由書など、大学に提出する書類に不備(記入漏れ、印鑑の押し忘れなど)があると、受理されない場合があります。
・犯罪行為や重大な問題行動
校内選考後から入学までの間に、万が一、犯罪行為やそれに準ずる重大な問題行動を起こした場合、合格が取り消されることがあります。高校の代表として推薦されていることを自覚し、責任ある行動を心がけましょう。
【小論文対策に強い人気の塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
指定校推薦で落ちる人に共通する特徴

指定校推薦で不合格になってしまう人には、いくつかの共通点が見られます。
自分に当てはまっていないか、確認してみましょう。
最低限の準備や対策を怠っている
大学への入学意欲が感じられない
「ほぼ受かる」と油断している
最も多いのがこのケースです。
『指定校推薦は楽勝』という言葉を鵜呑みにし、何の準備もせずに本番に臨んでしまう人は非常に危険です。
私が勤務していた他の教室の例ですが、指定校推薦で不合格になった生徒は、ほぼ例外なくこの『油断』が原因でした。
小論文の過去問を一度も見ない、面接の練習も一切しない…そうした生徒ほど、想定外の事態に直面した時に対応できなくなってしまうのです。

参考記事:総合型選抜「受かる確率」の真実と合格者だけが知る7つの対策で合格率アップ
最低限の準備や対策を怠っている
油断から、小論文の練習や面接の準備を全くしないパターンです。
・小論文のテーマを一度も確認しない
・面接で何を聞かれるか想定していない
・志望理由書の内容を覚えていない
このような状態では、いざ本番で少し難しい質問をされただけで頭が真っ白になり、何も答えられなくなってしまいます。

大学への入学意欲が感じられない
面接や小論文の内容から、「本当にこの大学で学びたいのか?」という熱意が伝わってこない場合も、評価は低くなります。
「なぜ他の大学ではなく、うちの大学なのですか?」という質問に、「家から近いからです」「親に勧められたからです」といった回答しかできないと、入学意欲が低いと判断されても仕方ありません。
参考記事:翔励学院の口コミ・評判・料金は?小論文対策におすすめできる塾?
指定校推薦で合格を確実にするための対策チェックリスト
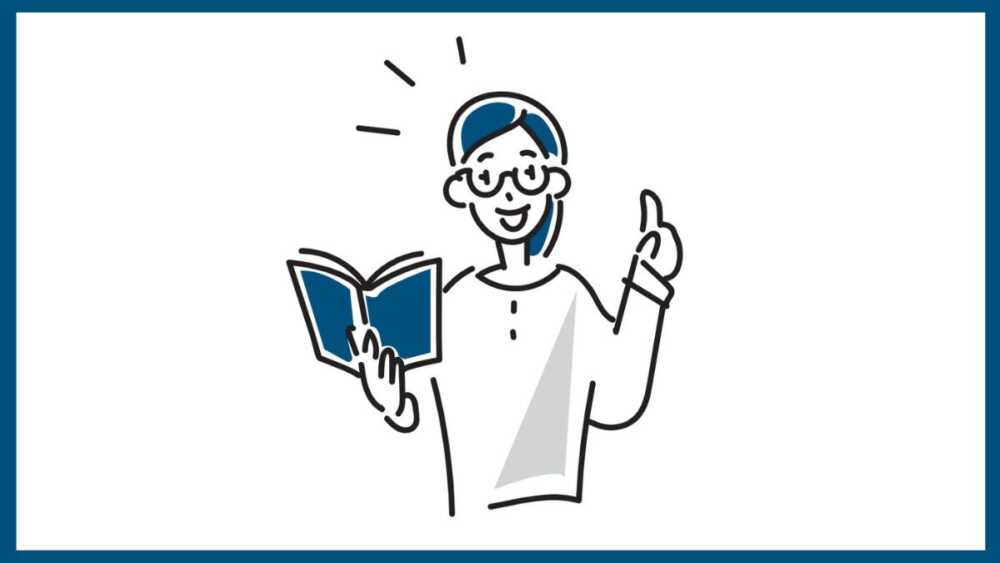
ここまでの内容を読んで、少し不安になったかもしれません。
でも、大丈夫です。
今から紹介する対策をしっかり行えば、合格は確実なものになります。
面接で評価されるポイントと練習方法
志望理由書・提出書類の最終確認
小論文の準備と書き方の基本
小論文は、付け焼き刃ではなかなか上達しません。
以下の点を意識して、計画的に準備を進めましょう。
・過去問や類似テーマで練習する
まずは、志望大学の過去問や、似たテーマの小論文を実際に書いてみましょう。時間を計って書くことで、本番の感覚を掴めます。
・学校の先生に添削してもらう
書いた小論文は、必ず国語科や進路指導の先生に添削してもらいましょう。客観的な視点から、構成の改善点や表現の誤りを指摘してもらえます。塾でも添削指導は行いますが、高校の先生はあなたの学力や人物を最もよく知っています。 大学側も高校との連携を重視していますから、先生に積極的に頼る姿勢は、それ自体が評価されることもありますよ。
・「序論・本論・結論」の型を覚える
序論:問題提起(テーマに対する自分の立場や意見を明確にする)
本論:根拠・具体例(なぜそう思うのか、具体的な事例を挙げて説明する)
結論:まとめ(本論の内容を要約し、改めて自分の意見を述べる)
この型に沿って書くだけで、論理的な文章になります。
・志望学部に関連するニュースに関心を持つ
経済学部なら最近の経済ニュース、国際関係学部なら国際情勢など、自分の志望分野に関連する時事問題に関心を持っておくと、小論文のネタに困りません。

参考記事:「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
面接で評価されるポイントと練習方法
面接は「慣れ」が重要です。
自信を持って話せるように、繰り返し練習しましょう。
・入退室のマナーを覚える
「失礼します」の一礼から始まり、着席、受け答え、退室までの一連の流れを体に覚えさせましょう。YouTubeなどで動画を見て確認するのもおすすめです。
・高校の先生と模擬面接を行う
最低でも3回以上は、先生に面接官役をお願いして練習しましょう。本番さながらの緊張感の中で話す練習をすることで、自分の弱点が見えてきます。
・よく聞かれる質問への回答を準備する
「志望動機を教えてください」
「高校生活で最も力を入れたことは何ですか?」
「大学で何を学びたいですか?」
「あなたの長所と短所を教えてください」
これらの定番の質問には、自分の言葉でスラスラ答えられるように準備しておきましょう。
・ハキハキと明るく話すことを意識する
緊張して言葉に詰まっても構いません。大切なのは、一生懸命伝えようとする姿勢です。少し口角を上げて、明るい表情で話すことを心がけるだけで、印象は大きく変わります。

参考記事:【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
志望理由書・提出書類の最終確認
提出した書類は、あなたの分身です。
面接前に必ず最終確認をしましょう。
・提出前に必ずコピーを取っておく
面接は、提出した書類に基づいて行われます。自分が何を書いたか忘れてしまわないよう、コピーを読み込んで内容を完璧に頭に入れておきましょう。
・誤字脱字がないか複数人でチェックする
自分では気づかないミスがあるかもしれません。提出前に、先生や家族など、複数の人に見てもらいましょう。

参考記事:【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
指定校推薦で落とす大学はある?

「〇〇大学は指定校推薦でも落とすらしい」といった噂を聞いて、不安になる人もいるかもしれません。
しかし、特定の大学が意図的に厳しく審査している、ということは基本的にありません。
医学部など一部の学部での注意点
大学が求める最低基準に達しない場合
どの大学であっても、大学が設定している「学生として最低限クリアしてほしい基準」というものが存在します。
先述したような、白紙の小論文や面接での無断欠席、著しく不適切な態度などは、どの大学であってもこの基準に達していないと判断されます。
つまり、「〇〇大学だから落ちる」のではなく、「どの大学でも通用しないことをしてしまったから落ちる」と考えるのが正しい理解です。

医学部など一部の学部での注意点
ただし、医学部や薬学部、看護学部といった医療系の学部では、他の学部よりも厳しい目で評価される傾向があります。
これらの学部は、人の命に関わる専門職を養成する場であるため、学力だけでなく、高い倫理観やコミュニケーション能力、ストレス耐性などが求められます。
そのため、面接や小論文での評価がよりシビアになる可能性があることは、心に留めておくとよいでしょう。
総合型選抜で逆転合格するなら!
「逆転コーチング総合型選抜」
プロのコーチが生徒をサポート
リーズナブルな料金設定
自分の可能性に挑戦しよう!
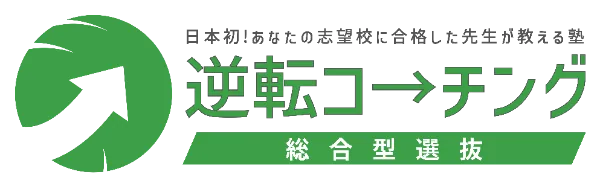
「友だち追加」で未来が変わる
↓↓↓
参考記事:逆転コーチング総合型選抜はやばい?口コミ・評判・料金を徹底取材!
指定校推薦の小論文・面接に関するQ&A
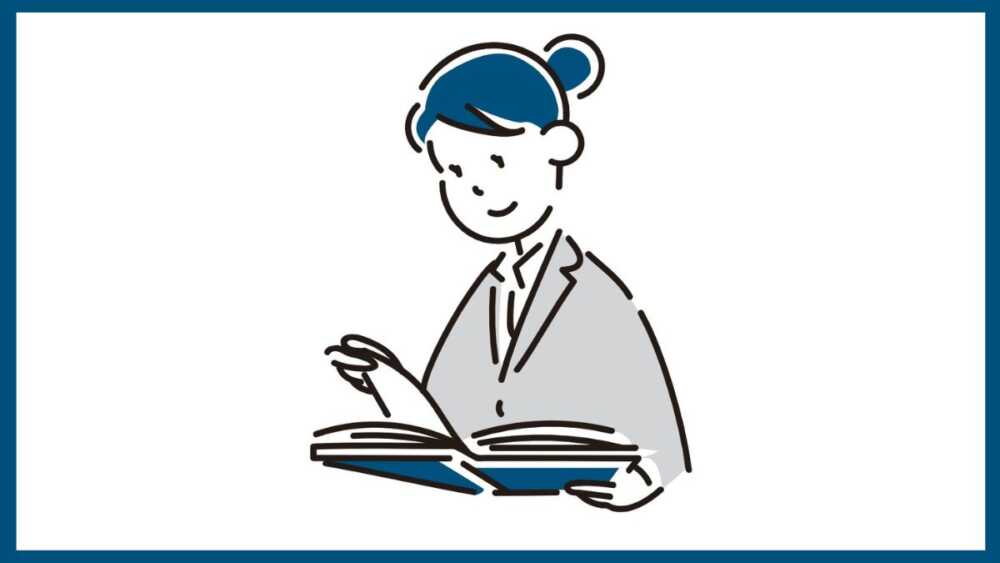
最後に、多くの受験生が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。
Q. 面接でうまく話せなくても不合格になりますか?
Q. 万が一、指定校推薦に落ちたらどうなりますか?
Q. 小論文がうまく書けなかったら落ちますか?
A. 完璧な内容でなくても、それだけで不合格になる可能性は低いです。
大切なのは、与えられたテーマに対して、自分なりに真剣に考えて書いたことが伝わるかどうかです。
多少文章が拙くても、構成が少し甘くても、一生懸命書いた答案であれば、面接官もその努力を汲み取ってくれます。
ただし、前述した「白紙」「テーマからの著しい逸脱」「極端な文字数不足」といったケースは別です。
これらは意欲がないと見なされ、不合格に直結する可能性があります。

Q. 面接でうまく話せなくても不合格になりますか?
A. 言葉に詰まったり、緊張で声が震えたりしても、すぐに不合格にはなりません。
面接官も、高校生が緊張するのは当たり前だと理解しています。大切なのは、うまく話すことよりも、誠実に伝えようとする姿勢です。
もし、質問の意図が分からなければ、「申し訳ありません、もう一度質問をお願いできますでしょうか」と聞き返しても問題ありません。
黙り込んだり、投げやりな態度をとったりする方が、よほどマイナスの印象を与えてしまいます。

Q. 万が一、指定校推薦に落ちたらどうなりますか?
A. すぐに気持ちを切り替えて、一般選抜などの次の入試に備えることになります。
万が一不合格だった場合は、すぐに高校の先生に報告し、今後の受験プランについて相談しましょう。
指定校推薦で不合格になったからといって、その後の一般選抜などで不利になることは一切ありません。
私自身、過去に『指定校推薦に落ちて、そこから一般受験に猛勉強して、もっと上位の大学に合格した生徒』を何人も聞いています。
気持ちを切り替えるのは大変ですが、まだチャンスは残されていることを忘れないでください。
この経験が、あなたの成長につながることもあります。」
指定校推薦!小論文で落ちる確率を減らす塾

合格保証制度あり!総合型選抜におすすめ!ホワイトアカデミー高等部

社会人のプロ講師が現役合格を導いてくれる、総合型選抜専門塾:ホワイトアカデミー高等部の特徴について紹介。
当サイト人気NO.1の総合型選抜専門塾です!
【ホワイトアカデミー高等部の基本情報】
| ホワイトアカデミー高等部の基本情報 | |
| ホワイトアカデミー高等部公式ホームページ | https://whiteacademy-ao.com/ |
| 指導教科 | 総合型選抜・学校推薦選抜対策専門 |
| 指導形式 | オンライン個別指導 |
| 授業料 | 要問い合わせ |
| 講師 | 社会人のプロ講師 |
| 使用端末・アプリ | スマホ・タブレット・PC・Zoom |
| サポート体制 | 合格保証・返金制度あり |
| 無料体験授業 | 無料相談会実施中 |
専門家による小論文専門個別指導塾:翔励学院

小論文専門:翔励学院の基本情報
| 翔励学院の基本情報 | |
| 翔励学院の公式ホームページ | https://www.syorei-gakuin.com/ |
| 指導教科 | 小論文対策に特化 |
| 指導形式 | 個別指導 |
| 授業料 | 34,800円〜 |
| 講師 | 社会人のプロ講師、 |
| 使用端末・アプリ | 対面指導、渋谷校舎のみ |
| サポート体制 | 面接・志望理由書の指導もあり |
| 無料体験授業 | 無料体験授業実施中! |
小論文対策で総合型選抜を突破!
↓↓↓
翔励学院の公式HPをチェック!
おすすめオンライン予備校!総合型選抜専門塾AOI

総合型選抜専門塾AOIの特徴を紹介。
【総合型選抜専門塾AOIの基本情報】
| 総合型選抜専門塾AOIの基本情報 | |
| 総合型選抜専門塾AOIの公式ホームページ | https://aoaoi.jp/ |
| 指導教科 | 総合型選抜に特化 |
| 指導形式 | オンライン個別指導、全国に校舎あり |
| 授業料 | 44,000円〜 |
| 講師 | 社会人のプロ講師、 |
| 使用端末・アプリ | スマホ、タブレット、PC |
| サポート体制 | オンライン授業対応 |
| 無料体験授業 | 無料体験授業実施中! |
総合型選抜「逆転コーチング」の基本情報

逆転コーチングの基本情報
| 逆転コーチングの基本情報 | |
| 逆転コーチングの公式サイト | https://gyakuten-coaching.com/sogo |
| 対象学年 | 高校生、既卒生 |
| 指導教科 | 総合型選抜対策 |
| 指導形式 | オンラインコーチングとリアルタイム授業 |
| 授業料 | 48,000円〜 |
| 講師 | プロコーチ、難関大学に在籍している講師 |
| 使用端末・アプリ | パソコン・タブレット・スマホ |
| サポート体制 | オンライン自習室、全国80ヶ所に対面式の自習室を完備 |
| 無料体験授業 | 無料体験実施中 |
「友だち追加」で未来が変わる
↓↓↓
逆転コーチングの公式LINE
まとめ:大学の指定校推薦で落ちる確率は?落ちる理由と合格率を高める対策を解説!

最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今回の記事、「大学の指定校推薦で落ちる確率は?落ちる理由と合格率を高める対策を解説!」は参考になりましたか?
指定校推薦!小論文で落ちる確率とは?
これまで、指定校推薦の不安を解消し、合格を確実にするための具体的なポイントを解説してきました。
あなたの不安は少しは軽くなりましたか?今回は、指定校推薦で落ちる確率や原因、そして合格を確実にするための対策について解説しました。
最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
・指定校推薦で落ちる確率は極めて低いが、ゼロではない。
・不合格になるのは、小論文や面接で最低限の基準を満たせなかったなど、「よほどのこと」があった場合に限られる。
・落ちる人の多くは、「ほぼ受かる」という油断から、準備を怠っている。
・小論文の練習、模擬面接、書類の再確認といった基本的な対策をしっかり行えば、合格は確実なものになる。
校内選考を突破したあなたは、すでに高校から「この大学にふさわしい」と認められた優秀な生徒です。
そのことに自信と誇りを持ち、やるべき準備を一つひとつ丁寧に行えば、何も心配することはありません。
この記事で得た知識を武器に、万全の態勢で試験に臨んでください。
あなたの合格を心から応援しています!
推薦関連のおすすめ記事
「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
総合型選抜「受かる確率」の真実と合格者だけが知る7つの対策で合格率アップ
【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは
大学面接で聞かれることランキング【質問と回答例】入試対策にもすぐに使える
総合型選抜(AO入試)に向いている人・向いてない人・落ちる人の特徴を解説
総合型選抜の落ちる確率とは?書類審査や面接で受かる気がしない人【必見】
評定平均とは?計算方法とは?大学推薦入試で差をつける評定対策をアドバイス
総合型選抜(AO入試)の対策はいつから準備する?学年別ロードマップで解説
【総合型選抜】自己アピール文の書き方&合格した自己PR例文テンプレ集
総合型選抜のエントリーシートの書き方&例文で夢の大学合格を掴む!
総合型選抜(AO入試)の合格基準とは?評定平均の目安と対策を大公開
総合型選抜(ao入試)に落ちたら?不合格から逆転合格する次の一手はこれだ!
【総合型選抜対策】成績が悪い受験生必見|今の評定平均は関係ない
総合型選抜面接を突破する自己PR作成術と例文!大学受験攻略ガイド
総合型選抜(ao入試)プレゼンテーション対策【効果抜群】5つのコツ
総合型選抜でオープンキャンパスに行っていない場合の対策法とは?
総合型選抜おすすめ塾
ホワイトアカデミー高等部の口コミ・評判は?取材で判明!良い・悪い声の真相
「Loohcs志塾・AOI・ホワイトアカデミー高等部」総合型選抜専門塾の特徴・合格実績を徹底比較!
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
AOI塾の料金(入会金・月謝)を調査!他の総合型選抜塾との年間費用を比較
総合型選抜に強い塾おすすめランキング11選|費用・コスパ・実績で比較
小論文対策に強い塾おすすめ10選!短期間で伸ばせるオンライン塾で逆転合格
【総合型選抜】料金が安い塾おすすめ12選|料金相場とコスパ徹底比較
【総合型選抜に強い塾】塾に行くべき?塾経験者がおすすめする!【総合型選抜対策塾の紹介
総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
浪人生が総合型選抜で合格する方法とは?実績豊富なおすすめ塾10選
総合型選抜専門塾【KOSKOS】ってどうなの?口コミ・評判・料金を調査した結果は?
自己推薦書の書き方を例文付きで解説!大学に合格できる「書き出し」


