総合型選抜(AO入試)の合格基準とは?評定平均の目安と対策を大公開
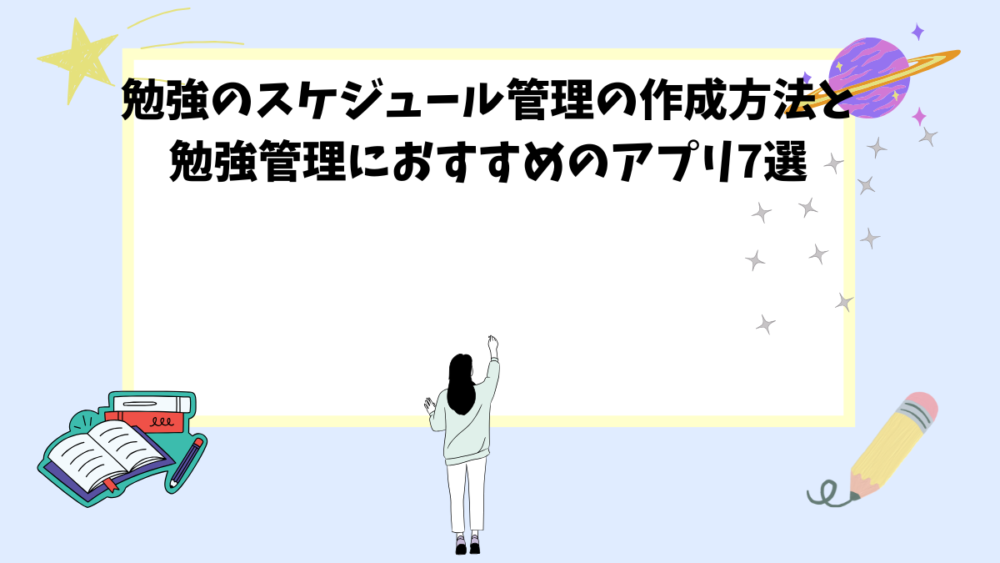
「※この記事には一部PRが含まれます」
監修:進路アドバイザー資格保有者
本記事は、高校生の進路指導において豊富な経験と専門知識を有する、進路アドバイザー資格保有者の監修のもと作成されています。
学習塾業界に27年間従事。多くの生徒を志望校合格に導いてきた受験指導のプロフェッショナルが解説します。
皆さんが自信を持って総合型選抜に取り組めるよう、具体的かつ分かりやすい情報をお届けします。安心して読み進めてください。
「総合型選抜(AO入試)って、具体的に何を見られるの?」「学校の成績(評定)が良くないと、合格は難しいのかな?」
大学受験の方法を調べる中で「AO入試」という言葉を知り、このような疑問をお持ちではないでしょうか。
特に、学力試験だけでなく、自分の個性や経験を活かしたいと考えている方にとって、AO入試(現在の総合型選抜)は非常に魅力的な選択肢です。
この記事では、AO入試(総合型選抜)の基本的な仕組みから、合否を分ける具体的な合格基準、そして多くの人が気になる評定平均の重要性まで、専門家が分かりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたが総合型選抜で合格するために何をすべきかが明確になり、自信を持って準備を始められるようになります。
・総合型選抜(AO入試)は大学とのマッチング入試である
・合格基準はアドミッションポリシーとの一致度が最重要
・評定平均は出願資格として重要だが、他の要素でカバー可能
・志望理由書・面接・活動実績の完成度が合否を左右する
Contents
AO入試で合格!現在の総合型選抜との関係
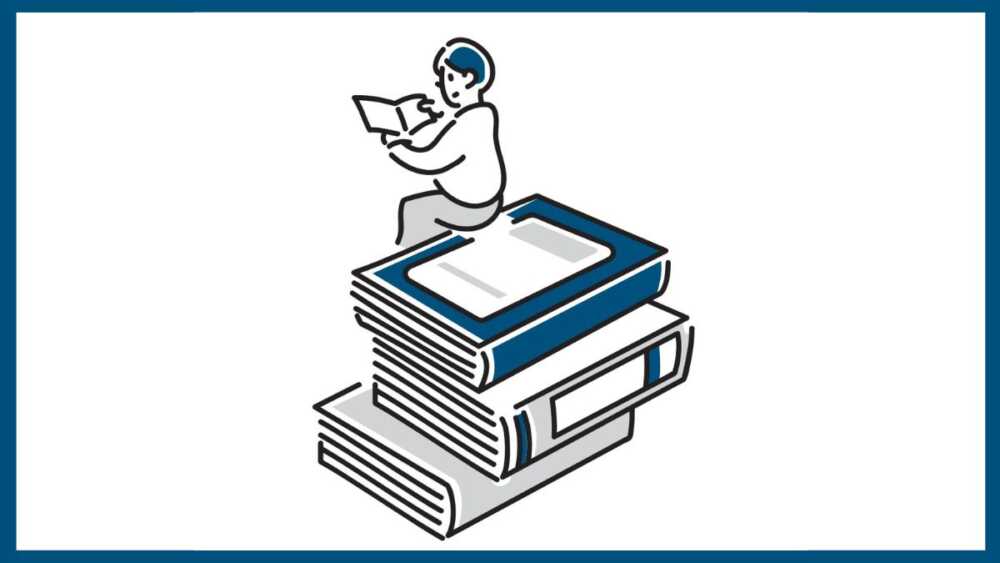
まず、AO入試とは何か、そしてなぜ今「総合型選抜」と呼ばれているのかを理解しましょう。
この基本的な知識が、合格への第一歩です。
アドミッション・オフィス入試の略称と意味
2021年度からの「総合型選抜」への名称変更
大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)
アドミッション・オフィス入試の略称と意味
AO入試とは、「Admissions Office(アドミッション・オフィス)入試」の略称です。
アドミッション・オフィスとは大学の入学者選抜を行う専門部署のことで、学力試験だけでは測れない受験生の個性や意欲、将来性などを多角的に評価し、入学者を選抜する方式を指します。
つまり、知識の量だけでなく、あなたがどんな人物で、大学で何を学びたいのかを重視する入試と考えると分かりやすいでしょう。

2021年度からの「総合型選抜」への名称変更
2021年度の大学入試から、AO入試は「総合型選抜」という名称に変更されました。
これは、単なる名称変更ではありません。
これまでのAO入試以上に、受験生の能力や意欲、活動経験などを「総合的に」評価する姿勢を明確にするための変更です。
知識・技能だけでなく、思考力・判断力・表現力、そして主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度(これらをまとめて「学力の3要素」と呼びます)を、より丁寧に評価する入試へと進化しています。
現在では「AO入試」という言葉も広く使われていますが、正式名称は「総合型選抜」であると覚えておきましょう。

大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)
総合型選抜を理解する上で最も重要なキーワードが「アドミッション・ポリシー」です。
アドミッション・ポリシーとは、大学や学部が「どのような学生に入学してほしいか」を具体的に示した受け入れ方針のことです。
総合型選抜では、受験生がこのアドミッション・ポリシーにどれだけ合致しているかが、合否を判断する最大の基準となります。
例として、早稲田大学のアドミッションポリシーには以下のように記されています。
政治学科は、学問の独立と自律的な市民社会の確立という建学の精神を今に受け継いでいます。その精神は、経済学との密接な連携により、生きた政治現象を分析し、日本から世界に発信できる学問をめざすという高い理想に反映されています。
制度や理論・歴史や思想・地域や国際関係など多くの領域にまたがる複合的な学問領域としての政治学にふさわしい段階的・体系的カリキュラムを準備し、セミナー等の少人数教育を組み合わせることで、政治現象を専門的かつ主体的に考えることのできる人材を育成します。
建設的な批判精神をそなえ、国際・政治・経済・言論・公務など多様な分野で冷静に、献身的にそしてグローバルに活躍できるリーダーの養成をめざします。
専任教員は豊富な海外経験を生かしつつ、多岐にわたる政治学研究の最先端に参画し、経済学をはじめとする隣接諸科学との学際的協働を実践します。
【進路アドバイザーのプロとしての視点】
大学は「ただ優秀な生徒」を求めているのではありません。「うちの大学の教育方針を理解し、卒業後も活躍してくれそうな生徒」を探しているのです。この認識がなければ、どんなに素晴らしい実績や評定があっても、合格は遠ざかってしまいます。私は指導の際、まずこのアドミッション・ポリシーの徹底的な分析から始めます。

AO入試(総合型選抜)の合格基準で評価される5つの要素

では、大学は具体的に何を見て、アドミッション・ポリシーとの適合性を判断するのでしょうか。
ここでは、合否に直結する5つの評価要素を解説します。
1. 志望理由書・エントリーシート
2. 調査書の内容(学習成績・活動記録)
3. 小論文やレポートなどの課題
4. 面接やプレゼンテーションでの対話力
5. 活動報告書(部活動、資格、課外活動)
1. 志望理由書・エントリーシート
志望理由書やエントリーシートは、あなたが大学に送る最初のアピールです。
なぜこの大学・学部で学びたいのか、自分の経験や強みをどう活かせるのかを、あなた自身の言葉で伝える最も重要な書類です。
・これまでの経験(部活動、課外活動、探究学習など)と志望動機がどう結びついているか
・大学のアドミッション・ポリシーを理解し、自分がそれにどう合致するか
・入学後に何を学び、将来どう社会に貢献したいか
これらの点を論理的に、そして情熱を持って記述することが求められます。
【プロの視点】
多くの高校生は「なぜこの大学か」をうまく書けません。ただ「〇〇大学の〇〇学部で学びたい」と書くだけでは不十分です。私が指導する際は、「なぜ他の大学ではダメなのか」「なぜこの教授の元で学びたいのか」というところまで深く掘り下げさせます。ここまで突き詰めることで、他の受験生とは一線を画す、説得力のある志望理由書に仕上がります。

参考記事:総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
2. 調査書の内容(学習成績・活動記録)
調査書とは、高校でのあなたの学びや活動の記録をまとめた公式な書類で、高校の先生が作成します。
調査書には、各教科の成績を数値化した「評定平均」だけでなく、以下のような情報も含まれます。
・各教科の学習における特徴
・部活動、生徒会活動、ボランティア活動などの特別活動の記録
・資格・検定の取得状況
・出欠の記録
大学側はこれらの情報から、あなたの学業への取り組み姿勢や、高校生活における主体性、継続性などを総合的に評価します。

参考記事:大学面接で聞かれることランキング【質問と回答例】入試対策にもすぐに使える
3. 小論文やレポートなどの課題
多くの大学では、出願時に小論文やレポートの提出を課します。
小論文は、あなたの思考力、判断力、表現力を評価するための重要な選考です。
与えられたテーマについて、自分の意見を論理的に述べたり、課題について深く考察したりする力が試されます。
単に知識を問うのではなく、物事を多角的に捉え、自分なりの考えを構築できるかが重視されます。
【プロの視点】
多くの塾が小論文の「型」を教えがちですが、私が大切にしているのは「なぜそのテーマについて考える必要があるのか」という背景を理解させることです。ニュースや社会問題に関心を持ち、自分なりの意見を形成する練習を日頃から行っていれば、どんなテーマが出ても慌てず対応できます。これは、付け焼き刃の対策では決して身につかない力です。

4. 面接やプレゼンテーションでの対話力
書類選考を通過すると、多くの場合、面接やプレゼンテーションが実施されます。
面接やプレゼンテーションは、書類だけでは分からないあなたの人柄やコミュニケーション能力、学習意欲を直接確認する場です。
・志望理由書に書いた内容を、自分の言葉で深く説明できるか
・質問の意図を正確に理解し、的確に答えられるか
・大学で学びたいという熱意が伝わるか
自信を持ってハキハキと話すことはもちろん、大学側との「対話」を楽しむ姿勢が大切です。
【成功事例の紹介】
私の指導した生徒に、評定平均は決して高くなかったものの、見事に難関大学に合格した生徒がいます。その生徒は、面接で「なぜこの大学を選んだのか」という問いに対し、志望理由書には書かれていない、オープンキャンパスでの個人的な感動体験を熱意をもって語りました。面接官は受験生の「誰にも負けない熱意」を高く評価したのです。重要なのは、暗記した内容を話すことではなく、自分の言葉で大学への強い思いを伝えることだと私は常に教えています。
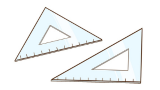
参考記事:総合型選抜(ao入試)プレゼンテーション対策【効果抜群】5つのコツ
5. 活動報告書(部活動、資格、課外活動)
学業以外でのあなたの実績や経験をアピールするのが活動報告書です。
・部活動での実績(全国大会出場、部長としての経験など)
・英語検定や漢字検定、情報処理などの資格
・ボランティア活動や地域での活動経験
・コンテストやコンクールでの入賞歴
これらの活動を通じて何を学び、どのように成長したのかを具体的に示すことが、評価を高めるポイントになります。

参考記事:【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
評定平均(内申点)は合否にどう影響する?
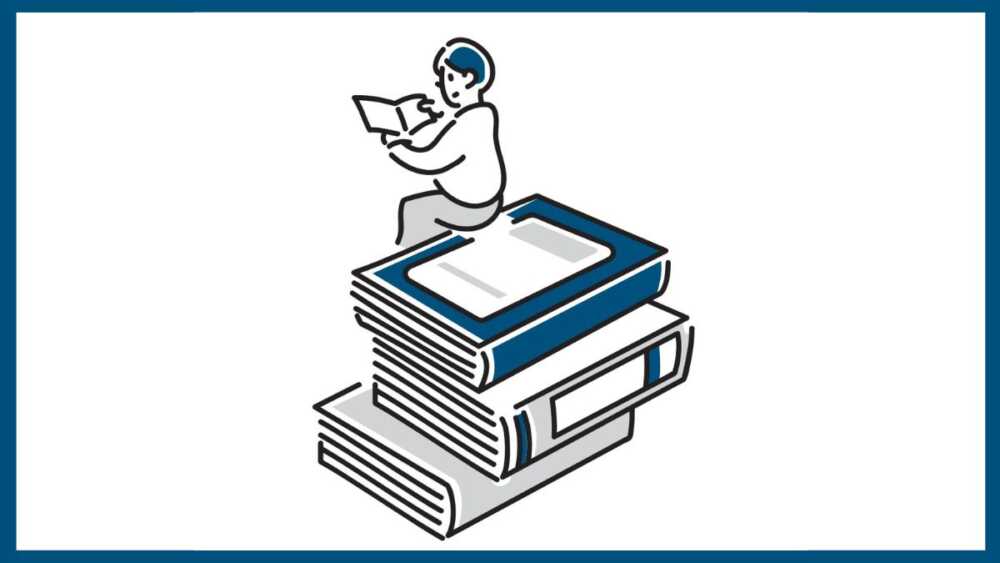
「評定平均が低いと、総合型選抜は無理なのでは?」と心配する人は少なくありません。
ここでは、評定平均が合否に与える影響について詳しく解説します。
評定は出願資格として重要
大学・学部別の評定平均の目安
成績が悪い・評定が低くても合格できる可能性
評定は出願資格として重要
まず知っておくべきなのは、多くの大学で評定平均が出願資格として定められているという事実です。
例えば、「全体の評定平均値が3.5以上であること」や「特定の教科(英語など)の評定が4.0以上であること」といった基準が募集要項に明記されています。
出願基準を満たしていなければ、そもそも出願することができません。
総合型選抜を考えるなら、まず志望大学の募集要項で出願資格を確認することが不可欠です。

大学・学部別の評定平均の目安
求められる評定平均のレベルは、大学や学部によって大きく異なります。
・国公立大学や難関私立大学
一般的に高い評定が求められる傾向にあり、4.0以上を基準とする大学も少なくありません。
・中堅私立大学
3.0~3.8あたりを基準とすることが多いですが、学部によって差があります。
・評定の基準を設けていない大学
一部の大学では、評定の基準を設けず、他の要素をより重視するケースもあります。
ただし、これらはあくまで一般的な目安です。
※これはあくまで一般的な目安です。実際には、評定基準を設けていない大学から4.5以上を求める大学まで様々です。必ず個別の大学の最新の募集要項で正確な出願資格を確認してください。

成績が悪い・評定が低くても合格できる可能性
「出願資格はギリギリ満たしているけど、評定に自信がない…」という場合でも、諦める必要はありません。
総合型選抜は、その名の通り「総合的な評価」を行う入試です。
評定以外の要素、例えば卓越した活動実績や、熱意のこもった志望理由書、面接での的確な応答などで高い評価を得られれば、評定の低さをカバーして合格を勝ち取ることは十分に可能です。
【プロからのアドバイス】
私がこれまで指導してきた経験上、多くの高校生は「特別な実績」がないと悩みがちです。しかし、大学側は誰もが驚くような実績ばかりを求めているわけではありません。「なぜその活動を始めたのか」「活動を通じて何を学び、どう成長したのか」というプロセスを、自分の言葉で語れることが何よりも重要です。部活動でレギュラーになれなくても、その中でチームを支えるために工夫したことや、困難を乗り越えた経験は立派なアピールポイントになります。

参考記事:【総合型選抜】料金が安い塾おすすめ12選|料金相場とコスパ徹底比較
総合型選抜と他の入試制度との違い

総合型選抜の特徴をより深く理解するために、他の入試制度である「学校推薦型選抜」や「一般選抜」との違いを見ていきましょう。
学校推薦型選抜(旧推薦入試)との違い
一般選抜との違い
3つの入試制度の違いがひとめでわかる比較表
学校推薦型選抜(旧推薦入試)との違い
総合型選抜と最も混同されやすいのが、学校推薦型選抜(旧:推薦入試)です。
両者の最大の違いは「学校長の推薦」が必要かどうかです。
・総合型選抜(旧AO入試)
自己推薦が基本です。大学が求める人物像に合致すると自分で判断すれば、誰でも出願のチャンスがあります。
・学校推薦型選抜(旧推薦入試)
出身高校の学校長からの推薦が必要です。学業成績や生活態度が優秀であることが前提となり、校内選考を通過しなければ出願できません。

一般選抜との違い
一般選抜(旧:一般入試)は、主に学力試験の結果で合否が決まる、最も受験者数が多い入試方式です。
・総合型選抜
評価の軸は「大学とのマッチング」です。志望理由書や面接などを通じて、人物や意欲を多面的・総合的に評価します。
・一般選抜
評価の軸は「学力」です。大学入学共通テストや大学独自の学力試験の点数によって、客観的に合否が判定されます。

3つの入試制度の違いがひとめでわかる比較表
| 比較項目 | 総合型選抜(AO入試) | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 |
|---|---|---|---|
| 主な評価方法 | 書類・小論文・面接 | 学校推薦+書類・面接 | 学力試験 |
| 評価の軸 | 大学とのマッチング | 学業成績・人物評価 | 学力 |
| 学校長推薦 | 不要 | 必須 | 不要 |
| 選考時期 | 9月以降〜年内 | 11月以降〜年内 | 1月以降 |
| 併願 | 制限あり | 制限あり | 自由 |

【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
AO入試(総合型選抜)のメリット・デメリット
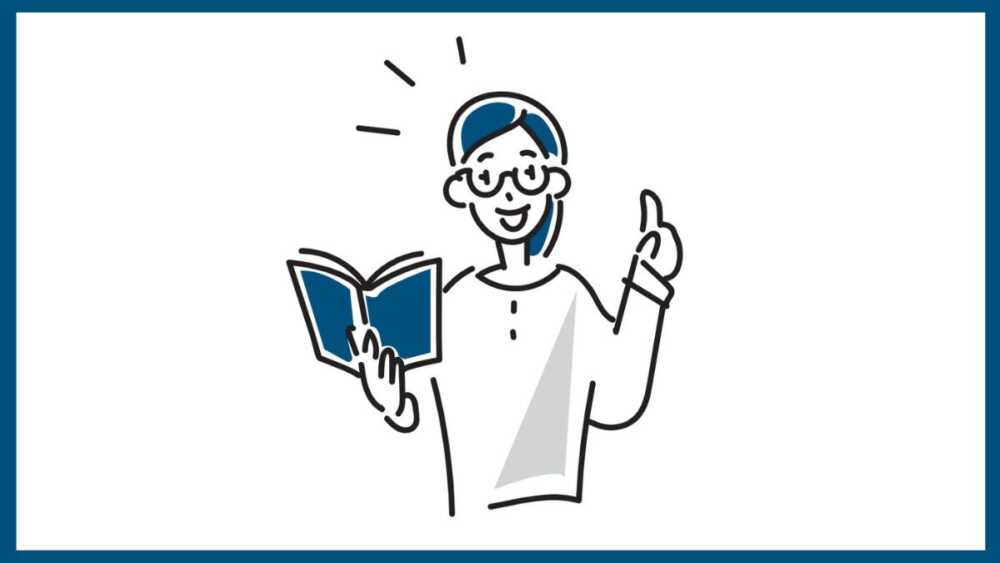
総合型選抜には、他の入試にはない魅力がある一方で、注意すべき点もあります。
メリットとデメリットを正しく理解し、自分に合った入試方法かを見極めましょう。
メリット:学力試験以外の強みを活かせる
メリット:早期に進路が決定する
デメリット:準備に時間がかかり、十分な対策が必須
デメリット:専願が多く併願が難しい場合がある
メリット:学力試験以外の強みを活かせる
総合型選抜の最大の魅力は、ペーパーテストの点数だけでは表せない「あなた自身の強み」を評価してもらえる点です。
例えば、部活動で培ったリーダーシップやチームワーク、探究学習を通じて深めた専門的な知識や研究姿勢、さらにはボランティア活動や地域貢献を通して得た社会への関心や実行力など。
こうした一人ひとりの経験や個性は、一般入試の学力試験では測れません。
総合型選抜では、こうした背景やプロセスそのものが評価の対象となるため、学力試験が苦手な人でも自分の得意分野を武器に合格を勝ち取れる可能性が大きく広がります。

参考記事:総合型選抜「受かる確率」の真実と合格者だけが知る7つの対策で合格率アップ
メリット:早期に進路が決定する
総合型選抜では、多くの大学が秋から冬にかけて合否を発表するため、年内に進学先が決まるケースが多くあります。
一般選抜に比べて数か月も早く進路が確定するので、精神的な余裕が生まれるのも大きなメリットです。
残りの高校生活を受験勉強に追われるのではなく、大学入学後に役立つ学習を先取りしたり、資格取得や語学学習に挑戦したりと、将来につながる準備期間として有効に活用できます。
進路が決まった安心感から、自分のやりたい活動に思い切り打ち込める点も総合型選抜ならではの魅力です。

参考記事:受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは
デメリット:準備に時間がかかり、十分な対策が必須
総合型選抜では、志望理由書の作成、小論文の練習、面接対策など、準備すべきことが数多くあります。
どれも一朝一夕で仕上げられるものではなく、付け焼き刃の対策では通用しません。
例えば志望理由書ひとつを取っても、大学のアドミッションポリシーを理解し、自分の経験や将来像とどう結び付けるかを何度も推敲する必要があります。
小論文では日頃から社会問題や時事ニュースに触れ、自分なりの意見を持つトレーニングが不可欠です。
面接に関しても、練習を重ねなければ本番で熱意や自分らしさを伝えるのは難しいでしょう。
そのため、高校3年生になってから焦って準備するのでは遅く、1・2年生のうちから自己分析や活動実績づくり、情報収集を計画的に始めることが成功の鍵となります。

デメリット:専願が多く併願が難しい場合がある
総合型選抜では、合格した場合に入学を確約する「専願」を条件としている大学が少なくありません。
このため、複数の大学を同時に受験して比べることが難しくなるケースが多いです。
専願での出願は「合格=進学」が前提となるため、志望度が高くない大学に出願してしまうと、後から後悔する可能性もあります。
特に「本当に行きたい大学かどうか」を早い段階で見極めておくことが重要です。
併願が可能な大学であっても、選考スケジュールが重なりやすく、複数校の対策を同時に進めるのは現実的に大きな負担となります。
こうした特徴を踏まえ、出願先を選ぶ際には、志望度の高さや学部の相性を慎重に検討することが欠かせません。
出願から合格発表までのスケジュール

総合型選抜のスケジュールは大学によって異なりますが、一般的な流れを把握しておきましょう。
9月~10月:エントリーと出願書類の提出
10月~11月:選考(面接・小論文など)の実施
11月以降:合格発表
6月~8月:情報収集とオープンキャンパス参加
この時期に多くの大学が募集要項を公開し始めます。
まずは志望大学のウェブサイトで アドミッション・ポリシーや出願資格(評定平均の基準など) を確認しましょう。
同時に、オープンキャンパスに参加して大学の雰囲気を肌で感じることも大切です。
実際にキャンパスを訪れ、授業を担当する教員や在学生の声に触れることで、「自分に合っているかどうか」を具体的に判断できます。
オンライン開催の場合もあるので、積極的に活用しましょう。

9月~10月:エントリーと出願書類の提出
多くの大学ではこの時期にエントリーが始まり、志望理由書や調査書、活動報告書などの提出が求められます。
書類の完成度は合否に直結するため、夏休みの段階から準備を進めておくことが重要です。
特に志望理由書は「大学のポリシーと自分の経験をどう結び付けるか」がポイント。
何度も書き直し、先生や塾の先生に添削してもらいながらブラッシュアップしましょう。

10月~11月:選考(面接・小論文など)の実施
書類選考を通過すると、一次選考や二次選考として面接・小論文・プレゼンテーションなどが行われます。
大学によってはグループディスカッションや独自の課題を課す場合もあります。
複数回の選考が行われることもあるため、スケジュール管理が大切です。
模擬面接や小論文の練習を重ね、当日は自分の言葉で熱意を伝えられるように準備しておきましょう。

11月以降:合格発表
最終選考を経て、合格者が発表されます。
早い大学では11月上旬に結果が出ることもあり、年内に進学先が決まるのは大きな安心材料です。
合格した場合は速やかに入学手続きを進め、大学生活に向けた準備を始めましょう。
残りの高校生活を有意義に使うために、語学学習や資格取得、大学での専攻につながる基礎知識の習得を始めておくのもおすすめです。
総合型選抜の準備で押さえておきたいこと

総合型選抜に臨むには、早めの準備と計画的な対策が欠かせません。
ここでは、効果的な準備のためのポイントを解説します。
適切な準備を進めることで、あなたの個性や強みを最大限にアピールし、志望校合格への道を切り開きましょう。
魅力的な志望理由書・活動報告書を作成するコツ
面接・小論文・プレゼンテーション対策のポイント
募集要項を読み込み、スケジュール管理を徹底する
情報収集と自己分析は早めにスタート
総合型選抜の準備は、高校2年生の冬頃から始めるのが理想的です。
まずは以下の点に取り組みましょう。
・志望大学・学部の選考方法や評価基準を調査する
・過去の出題傾向や合格者の傾向を分析する
・自分の強み、興味関心、将来の目標を言語化する
特に重要なのは、「なぜその大学・学部で学びたいのか」「大学での学びをどう将来に活かしたいのか」という点を掘り下げて考えることです。
表面的な理由ではなく、自分の経験や価値観に基づいた独自の志望理由を見つけましょう。

魅力的な志望理由書・活動報告書を作成するコツ
志望理由書や活動報告書は、あなたという人間を大学に伝える重要な書類です。
・具体的なエピソードを交えて説得力のある内容にする
・「何を学びたいか」だけでなく「なぜ学びたいか」「どう活かしたいか」まで言及する
・学部の特色や教育理念との接点を明示する
例えば、「国際関係学を学びたい」という志望理由なら、「高校時代の海外研修で感じた文化の違いから国際問題に興味を持ち、将来は〇〇の分野で活躍したい」といった具体的なストーリーを描くことが効果的です。

参考記事:【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
面接・小論文・プレゼンテーション対策のポイント
選考方法別の対策ポイントを押さえましょう。
・面接:想定質問への回答を準備し、練習を重ねる。姿勢や話し方にも注意
・小論文:時事問題に関心を持ち、論理的な文章構成力を養う
・プレゼンテーション:わかりやすく簡潔に伝える工夫と、質疑応答の準備
特に面接では、「志望理由」「学びたいこと」「高校時代に力を入れたこと」「入学後にやりたいこと」などについて、具体的に答えられるよう準備しておくことが大切です。
模擬面接を繰り返し行い、自信を持って受け答えできるようにしましょう。

募集要項を読み込み、スケジュール管理を徹底する
総合型選抜は大学ごとに出願時期や選考プロセスが異なります。
・募集要項は隅々まで読み込む
・出願期間、必要書類、選考日程などをカレンダーに記入
・書類作成や対策のスケジュールを逆算して計画する
特に注意すべきは、出願書類の提出期限です。
必要書類を揃えるのに時間がかかることも多いため、余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
複数の大学・学部を受験する場合は、それぞれの選考日程が重ならないかも確認することが重要です。

総合型選抜(AO入試)の合格基準に関するよくある質問

最後に、受験生や保護者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
AO入試と学校推薦型選抜は併願できますか?
高校の先生には何を相談すべきですか?
総合型選抜と一般入試、難易度はどっちが高い?
総合型選抜(AO推薦)の合格率はどのくらい?落ちる可能性は?
高校の成績(評定平均)はどれくらい重要?
総合型選抜がいい理由は何ですか?
総合型選抜は学力重視ですか?
評定が低くても合格できますか?
可能性は十分にあります。
ただし、2つの条件があります。
1つ目は「大学が定める出願資格(評定基準)を満たしていること」、2つ目は「評定の低さをカバーできるだけの、他の強力なアピールポイントがあること」です。
卓越した活動実績や、誰にも負けない熱意と論理性を備えた志望理由があれば、逆転合格も夢ではありません。
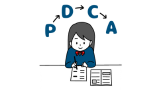
AO入試と学校推薦型選抜は併願できますか?
大学の規定によりますが、難しい場合が多いです。
総合型選抜も学校推薦型選抜も「専願(合格したら必ず入学すること)」を条件としている大学が多いため、事実上併願できないケースがほとんどです。
選考スケジュールが重なることも多く、両方の対策を並行して進めるのは現実的ではありません。
どちらの入試方式で挑戦するか、早い段階で決めることが大切です。

高校の先生には何を相談すべきですか?
積極的に先生を頼りましょう。先生はあなたの強力なサポーターです。
以下のようなことを相談するのがおすすめです。
・志望理由書の添削
客観的な視点で、分かりにくい部分やアピールが弱い部分を指摘してもらえます。
・面接の練習
本番さながらの雰囲気で練習することで、受け答えの仕方や立ち居振る舞いを改善できます。
・調査書の内容確認
自分の活動がどのように記載されるかを確認し、先生にアピールしたい点を伝えておくことも有効です。
・進路相談
あなたの個性や成績をよく知る先生から、あなたに合った大学や学部を提案してもらえるかもしれません。

総合型選抜と一般入試、難易度はどっちが高い?
一概にどちらが難しいとは言えませんが、評価される能力が異なることを理解しておきましょう。
総合型選抜は「あなた自身の個性や意欲」が問われますが、一般入試は「試験当日の学力」が問われます。
【総合型選抜が有利になるケース】
・特定の分野での活動実績や特技がある人
・学力テストより面接や小論文が得意な人
・志望理由が明確で、その学部との相性が良い人
【一般入試が有利になるケース】
・学力テストで高得点を取れる人
・自己PRや面接が苦手な人
・複数の大学を併願したい人
自分の強みがどちらの入試方式で活かせるかを考えて選択するのが最適です。

参考記事:浪人生が総合型選抜で合格する方法とは?実績豊富なおすすめ塾10選
総合型選抜(AO推薦)の合格率はどのくらい?落ちる可能性は?
総合型選抜の合格率は大学・学部によって大きく異なります。
一般的には一般入試より合格率が高い傾向にありますが、人気の高い国公立大学や難関私立大学では狭き門となっています。
【大学の種類別の傾向】
・国公立大学:10〜30%程度(一般入試より高いケースが多い)
・私立難関大学:20〜40%程度
・中堅〜その他私立大学:40〜80%程度
総合型選抜が「合格しやすい」と安易に考えるのは危険です。
総合型選抜では、その大学・学部にふさわしい学生かどうかを厳しく評価されます。
特に、志望理由が浅い、学部とのミスマッチがある、準備不足で面接での受け答えが不十分、といった理由で不合格になるケースが多いため、十分な準備が必要です。
※これらの数値はあくまで大まかな傾向を示すものであり、実際の合格率は大学・学部によって大きく異なります。人気の高い大学・学部では倍率が10倍を超えることもあります。安易に『合格しやすい』と判断せず、必ず志望校の過去の入試データを確認しましょう。

高校の成績(評定平均)はどれくらい重要?
総合型選抜における評定平均の重要度は大学によって異なります。
・明確な基準を設けている大学:「評定平均3.5以上」など出願条件として明示
・参考程度に見る大学:評定は選考の一要素として考慮
・特に重視しない大学:活動実績や面接、提出書類などを重視
総合型選抜では学校推薦型選抜ほど評定平均を重視しないケースが多いですが、基礎学力の証明として見られることは確かです。
特に国公立大学では、一定以上の学力が求められることが一般的です。
評定平均が低い場合は、他の面(活動実績や志望理由の明確さなど)で挽回できるよう、準備を工夫しましょう。

総合型選抜がいい理由は何ですか?
総合型選抜(AO入試)の主な利点は、学力以外の要素も重視される点です。
例えば、部活動の成果やボランティア活動、独自のプロジェクトなど、学業以外の実績や人間性が評価されます。
これにより、単なる試験の点数だけではなく、自分の個性や興味をアピールできるチャンスが広がります。
また、自己推薦やプレゼンテーションを通じて、自分の強みを直接伝える機会があるため、自分に合った大学や学部を見つけやすくなります。

総合型選抜は学力重視ですか?
総合型選抜(AO入試)は、学力だけでなく、その他の要素も重視されます。
もちろん学力も評価の一部ですが、総合型選抜では、それ以外の活動や経験、意欲なども評価されます。
例えば、部活動での成果や地域活動、自己PRや面接での表現力など、学力以外の面が重視されるため、学業だけではなく、幅広い経験や個性をアピールするチャンスがあります。
そのため、学力重視の一般選抜とは異なり、多角的に自分をアピールできるのが特徴です。

参考記事:総合型選抜で塾に行くべきか?診断テストでチェック!塾が必要な人の特徴
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
まとめ:総合型選抜(AO入試)の合格基準とは?評定平均の目安と対策を大公開

今回は、AO入試(総合型選抜)の合格基準について、評価される要素や評定の重要性、対策のポイントを詳しく解説しました。
最後に、この記事の要点を振り返りましょう。
総合型選抜(AO入試)の合格基準とは?
・AO入試は現在「総合型選抜」と呼ばれ、大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)とのマッチングが最も重要。
・合格基準は、志望理由書、調査書、小論文、面接、活動実績などから総合的に評価される。
・評定平均は出願資格として重要だが、それだけで合否が決まるわけではない。
・評定に自信がなくても、他の要素で熱意や個性をアピールできれば合格のチャンスは十分にある。
総合型選抜は、学力だけでなく「あなたという人間」そのものが評価される入試です。
これまでの高校生活を振り返り、自分の強みは何か、大学で何を成し遂げたいのかを深く考えることが、合格への一番の近道です。
まずは、気になる大学のウェブサイトを訪れ、「アドミッション・ポリシー」をじっくり読んでみることから始めてみませんか。
そこから、あなたの新しい挑戦が始まります。
総合型選抜とは?おすすめの記事
大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
総合型選抜「受かる確率」の真実と合格者だけが知る7つの対策で合格率アップ
【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは
大学面接で聞かれることランキング【質問と回答例】入試対策にもすぐに使える
総合型選抜(AO入試)に向いている人・向いてない人・落ちる人の特徴を解説
総合型選抜の落ちる確率とは?書類審査や面接で受かる気がしない人【必見】
評定平均とは?計算方法とは?大学推薦入試で差をつける評定対策をアドバイス
総合型選抜(AO入試)の対策はいつから準備する?学年別ロードマップで解説
【総合型選抜】自己アピール文の書き方&合格した自己PR例文テンプレ集
総合型選抜のエントリーシートの書き方&例文で夢の大学合格を掴む!
総合型選抜(AO入試)の合格基準とは?評定平均の目安と対策を大公開
総合型選抜(ao入試)に落ちたら?不合格から逆転合格する次の一手はこれだ!
総合型選抜おすすめ塾
ホワイトアカデミー高等部の口コミ・評判は?取材で判明!良い・悪い声の真相
「Loohcs志塾・AOI・ホワイトアカデミー高等部」総合型選抜専門塾の特徴・合格実績を徹底比較!
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
AOI塾の料金(入会金・月謝)を調査!他の総合型選抜塾との年間費用を比較
総合型選抜に強い塾おすすめランキング11選|費用・コスパ・実績で比較
【総合型選抜】料金が安い塾おすすめ12選|料金相場とコスパ徹底比較
総合型選抜で塾に行くべきか?診断テストでチェック!塾が必要な人の特徴
総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
浪人生が総合型選抜で合格する方法とは?実績豊富なおすすめ塾10選
総合型選抜専門塾【KOSKOS】ってどうなの?口コミ・評判・料金を調査した結果は?
自己推薦書の書き方を例文付きで解説!大学に合格できる「書き出し」
翔励学院の口コミ・評判・料金は?小論文対策におすすめできる塾?

