小論文の書き出し例文7選!序論のテンプレートとNG例・改善法で得点アップ
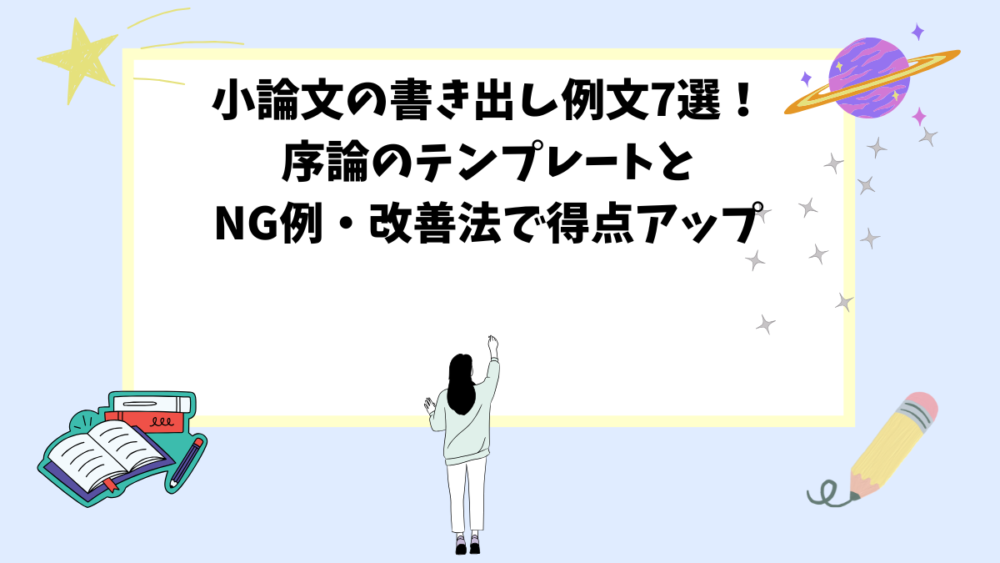
「※この記事には一部PRが含まれます」
小論文を書こうとしたとき、最初の一文で手が止まってしまう――。
これは受験生から最も多く寄せられる悩みのひとつです。
特に序論の「書き出し」は、その後の展開全体を左右するため、どんなテーマでも安定して書ける力が必要です。
私は27年間、全国展開する大手学習塾で高校生・浪人生を指導し、「どうすれば合格につながる文章を書けるか」を徹底的に研究してきました。
その経験から断言できるのは――小論文の序論には「型」と「例文」を丸暗記しておくことが合格への近道だということです。
・小論文の序論をスムーズに書き始められる7つのテンプレート
・実際に使える例文集
・NGな書き出しとその改善ポイントを、私自身の指導現場での経験を交えて紹介します。
「小論文の書き出しは何を書く?」「ダメな例は?」「接続語『だから』の言い換えは?」といったよくある疑問にも答えながら、今すぐ使える“得点UPの書き出し術”をお伝えします。
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
Contents
- 1 最速回答:小論文の書き出しは何を書く?「結論・論点・根拠の予告」を一文で示す
- 2 序論の基本「小論文」書き方の全体像(序論・本論・結論の役割)
- 3 得点が伸びる「書き出し」の原則3つ(明確・簡潔・一貫)
- 4 小論文の書き出しテンプレート7パターン(例文つき)
- 5 テーマ別「小論文」例文集
- 6 「はじめに」の例文は?──レポート調の導入と小論文の違い
- 7 小論文でダメな例は?──NG書き出しと改善ポイント
- 8 「だから」の言い換えは?──接続語の使い分け一覧
- 9 序論 書き方の型:一文目→二文目→三文目の並べ方
- 10 本論 書き方:主張→根拠→具体例→まとめの順序
- 11 小論文 書き方 高校生向け:時間配分と下書きのコツ
- 12 小論文 例文 800字:構成サンプルと段落配分
- 13 高校生 小論文 書き方:評価基準に合わせたチェックポイント
- 14 小論文 テーマ型 例文:賛成・反対・中立の書き分け
- 15 書き出しから本論へのスムーズなつなぎ方フレーズ集
- 16 大学入試小論文の書き出しに関するよくある質問
- 17 仕上げチェックリスト:論点の明確さ・一貫性・語彙の適切さ
- 18 練習用テンプレート配布:序論テンプレ7パターンの穴埋めワーク
- 19 まとめ:小論文の書き出し例7選|序論のテンプレートとNG例・改善法で得点アップ!
最速回答:小論文の書き出しは何を書く?「結論・論点・根拠の予告」を一文で示す

小論文の書き出しは、採点者への最初のメッセージです。
何から書けばいいか分からないという方は、まず「結論→その結論に至る論点→論点の根拠の予告」という順序で、一文にまとめることを意識しましょう。
例えば、「私はSNSの実名制導入に賛成である。この問題は、倫理的側面と社会的影響の観点から考察すべきであり、以下にその理由を3点述べる」のように、冒頭で文章全体の骨子を示すことが重要です。
これにより、読み手はあなたの主張を正確に把握でき、スムーズに読み進められます。
序論の基本「小論文」書き方の全体像(序論・本論・結論の役割)

序論は、これから何を論じるかを明確にする部分で、いわば「文章の設計図」です。
本論では、序論で提示した主張の理由や根拠を具体例やデータを用いて説得力を持たせます。
最後に結論で、序論の内容を再確認し、本論の内容を要約して締めくくります。
この三段階を踏むことで、論理的で分かりやすい文章が完成します。
小論文は芸術作品ではないので、この型を忠実に守ることが高得点への近道です。
得点が伸びる「書き出し」の原則3つ(明確・簡潔・一貫)

小論文の序論で得点を伸ばすには、以下の3つの原則を意識しましょう。
1.明確性: 自分の主張や立場を曖昧にせず、はっきりと示すこと。「〜かもしれない」のような表現は避け、断定的に書くことが重要です。
2.簡潔性: 序論は長々と書く必要はありません。必要な情報を凝縮して、簡潔にまとめることで、読みやすさが向上します。
3.一貫性: 序論で提示した主張と本論・結論で述べる内容に矛盾がないこと。途中で意見がブレると、論理的思考力が欠けていると判断されます。
例えば、環境問題について論じる場合、「地球温暖化は深刻な問題だ」と明確に述べ、その解決策を一貫して提示する必要があります。
これらの原則を守ることで、あなたの文章は論理的で説得力のあるものになります。
小論文の書き出しテンプレート7パターン(例文つき)

小論文の書き出しには、どんなテーマにも応用できる7つのテンプレートがあります。
それぞれのテンプレートの特徴と、SNSの実名制をテーマにした具体的な例文を交えながら、詳しく解説していきます。
2.結論先出し型:主張→理由の順で流れを作る
3.対比型:一般的見方と自分の立場を並べる
4.体験→一般化型:短い体験談から論点へ橋渡し
5.データ提示型:数値・事実で説得力を出す
6.引用→論点提示型:ことばを借りて争点を立てる
7.質問投げかけ型:読者の関心を引いて主張へつなぐ
1.問題提起型:現状の課題を一文で示す
このテンプレートは、テーマに対する現状の課題や問題を提示することから始める方法です。
読者の関心を引きつけ、これから論じる内容の重要性をアピールできます。
例えば、テーマが「SNSの実名制の導入」なら、「近年、SNS上の誹謗中傷が社会問題となっている。」のように、読者が共感できる社会的な課題を冒頭に示します。
これにより、採点者は「この文章は現代の課題を論じるのだな」と理解し、読み進めてくれます。

参考記事:大学の指定校推薦で落ちる確率は?落ちる理由と合格率を高める対策を解説!
2.結論先出し型:主張→理由の順で流れを作る
最もオーソドックスで、ほぼすべてのテーマに応用できる万能なテンプレートです。
最初に自分の結論を明確に述べ、その後に続く理由を予告します。
例えば、「私はSNSの実名制導入に反対である。なぜなら、表現の自由が侵害される危険性があるからだ。」のように、冒頭で自分の立場と最も重要な理由を簡潔に述べます。
採点者はあなたの主張をすぐに理解できるため、論理的で分かりやすい文章だと評価されるでしょう。

3.対比型:一般的見方と自分の立場を並べる
このテンプレートは、世間の一般的な考え方を提示した後に、それに対する自分の意見を対比させることで、独自の視点をアピールする方法です。
例えば、「一般的にSNSの実名制は誹謗中傷対策として有効だと考えられている。しかし、私はこの考え方に問題があると思う。」のように、大衆の意見と自分の意見のギャップを提示します。
これにより、論点の独自性が際立ち、採点者の興味を引くことができます。

4.体験→一般化型:短い体験談から論点へ橋渡し
自分の個人的な体験談を導入とし、そこから社会全体の問題へと論点を広げる方法です。
個人的なエピソードを起点にすることで、説得力が増します。
例えば、「私自身、匿名アカウントからの誹謗中傷を経験し、SNSの匿名性がもたらす弊害を痛感した。この経験から、SNSの実名制は社会全体の課題だと考える。」のように、読者も共感しやすい具体例を提示し、論点へとつなげます。
ただし、体験談は簡潔にまとめ、主張から逸れないように注意しましょう。

5.データ提示型:数値・事実で説得力を出す
信頼性の高いデータや事実を冒頭に提示することで、文章の説得力を一気に高める方法です。
例えば、「警察庁の発表によれば、SNSに起因する犯罪件数は年々増加している。この事実から、SNSの実名制は検討すべき課題であると考える。」のように、客観的な数値を冒頭に示します。
ただし、データは正確なものを使用し、出所を明確にすることが重要です。

6.引用→論点提示型:ことばを借りて争点を立てる
課題文読解型の小論文で特に有効なテンプレートです。
課題文中の筆者の主張や重要な一文を引用し、それに対する自分の意見を述べます。
例えば、「課題文の筆者は「匿名性がコミュニケーションを円滑にする」と述べている。しかし、私はこの考えに異論を唱える。」のように、引用箇所を明確にし、その上で自分の意見を提示します。
「」や二重引用符「”」を使い、引用部分をはっきりとさせることがポイントです。

7.質問投げかけ型:読者の関心を引いて主張へつなぐ
読者に対して質問を投げかけることで、テーマへの関心を喚起し、文章へと引き込む方法です。
例えば、「あなたはSNSの実名制に賛成ですか?反対ですか?」のように、読者自身に問いかける形で文章を始めます。この後、「この問いは単純に答えられるものではない。なぜなら…」と続けることで、より深い議論へと誘うことができます。
テーマ別「小論文」例文集
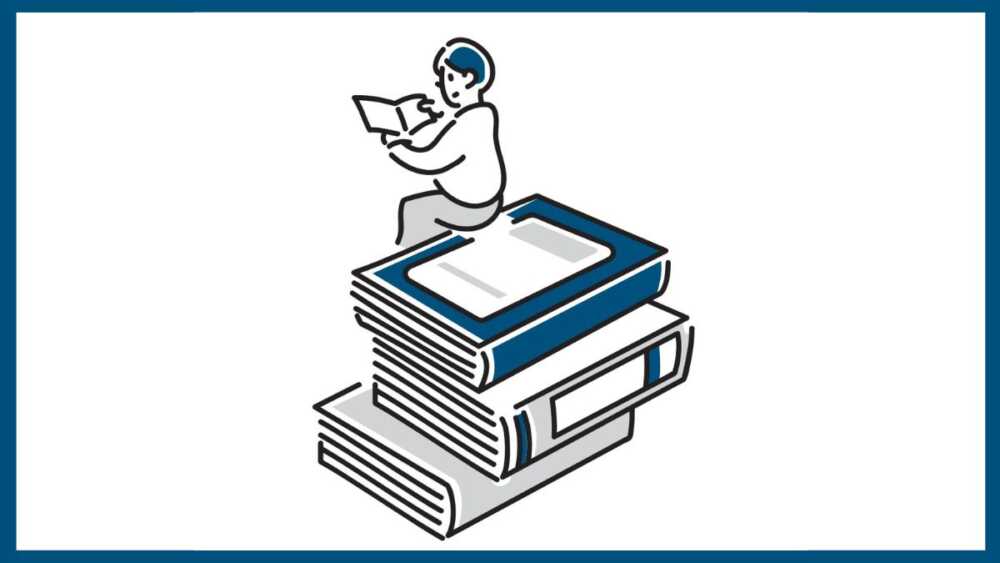
ここでは、よく出題されるテーマを7つ取り上げ、それぞれのテーマに合わせた序論の書き出しの具体例を簡潔に紹介します。
少子化と教育
SNSと表現の自由
環境問題と個人の行動
部活動の意義
医療と倫理
地方創生と若者
AIと仕事
「AI技術の発展は、私たちの働き方を大きく変えつつある。しかし、AIが人間に取って代わることへの懸念も広がっている。私は、AIは仕事を奪うのではなく、人間との協業で新たな価値を生み出すと考える。」
・パターン:対比型
・解説:「働き方を変えつつある」という肯定的な側面と、「懸念も広がっている」という否定的な側面を対比させ、最後に「私は〜と考える」と自身の結論を述べています。

少子化と教育
「日本の少子化は、教育現場にも深刻な影響を与えている。この問題は、単なる生徒数の減少に留まらず、教育の質の低下にもつながる。私は、少子化時代における教育のあり方について論じる。」
・パターン:問題提起型
・解説:「教育現場に深刻な影響を与えている」と現状の問題点を提示し、その問題が「質の低下にもつながる」と続けています。最後に「〜について論じる」と、これから議論するテーマを明確にしています。

SNSと表現の自由
「SNSの普及は、誰もが自由に意見を発信できる社会をもたらした。しかし、その一方で誹謗中傷やフェイクニュースといった問題も生まれている。表現の自由と責任の関係を考察する。」
・パターン:対比型
・解説:「自由に意見を発信できる」という利点と、「誹謗中傷やフェイクニュース」という欠点を対比させ、両側面を考慮しながら論じる姿勢を示しています。

環境問題と個人の行動
「地球温暖化や海洋プラスチック問題など、環境問題はもはや無視できない。しかし、個人の行動がどこまで影響するのか疑問に思う人も多いだろう。私は、個人が環境問題に貢献する方法を論じる。」
・パターン:対比型
・解説:「環境問題は無視できない」という事実と、「個人の行動がどこまで影響するのか疑問」という一般的な考えを対比させ、自身の主張へつなげています。

部活動の意義
「部活動は、多くの高校生にとって学校生活の重要な一部である。しかし、部活動の在り方については、学業との両立や指導者の負担など、様々な議論がある。私は、部活動が持つ教育的意義について再考する。」
・パターン:対比型
・解説:「重要な一部である」という一般的な見方と、「様々な議論がある」という対立する側面を提示し、多角的な視点で論じることを示しています。

医療と倫理
「iPS細胞やゲノム編集といった最先端の医療技術は、私たちの生命観に新たな問いを投げかけている。この技術がもたらす恩恵と、倫理的な課題について考える必要がある。」
・パターン:問題提起型
・解説:「新たな問いを投げかけている」という形で、最先端技術がもたらす課題を提起し、これから「考える必要がある」と論点を明確にしています。

地方創生と若者
「若者の都市部への流出が続く地方において、地域活性化は喫緊の課題である。私は、若者が地元に戻ってきたいと思えるような、地方創生のための具体的な提案を述べる。」
・パターン:問題提起型
・解説:「地域活性化は喫緊の課題」と、解決すべき問題点を提示し、最後に「具体的な提案を述べる」と、これから論じる内容を予告しています。
「はじめに」の例文は?──レポート調の導入と小論文の違い

レポートと小論文では、書き出しの目的が異なります。
「はじめに」の例文を通じて、それぞれの違いを明確に理解し、混同しないようにしましょう。
レポートの「はじめに」は、「このレポートの目的は〜である」のように、客観的な研究の目的や範囲を説明するものです。
小論文の書き出しは、自分の主張や立場を明確に提示することが目的です。
| レポートの「はじめに」 | 小論文の「書き出し」 | |
|---|---|---|
| 目的 | 研究の目的や方法を客観的に示す | 自分の主張や論点を明確に提示する |
| スタイル | 客観的・説明的 | 主観的・論理的 |
| 例文 | 本稿は〇〇を目的とし、〜について考察する。 | 私は〇〇に賛成である。その理由は〜。 |

小論文でダメな例は?──NG書き出しと改善ポイント

小論文の書き出しには、知らず知らずのうちに減点されるNGパターンが存在します。
ここでは、よくある失敗例を挙げ、どうすれば改善できるのかを解説します。
長すぎて主張が見えない
体験談が主張につながらない
根拠のない断定・感情的表現
テーマから逸れる一般論
抽象語の連発で中身がない
例:「現代社会は複雑で、様々な問題が山積している。」
このような書き方は、具体的な内容がなく「結局、何を論じたいのか」が伝わりません。
採点者から見ると、中身の薄い序論だと判断されてしまいます。
解決策としては、抽象的な表現の後に「どの問題について書くのか」をすぐに示すことが大切です。
例えば、「少子化に伴う労働力不足」や「AI技術の進歩による雇用問題」など、焦点を絞って論点を提示しましょう。

長すぎて主張が見えない
例:「私は昔から〇〇について深く考えており、この問題には〜という意見を持っている。なぜなら〜」
このように、序論から自分の体験や感情を長々と書いてしまうと、主張がぼやけてしまいます。
序論は「これから自分がどの立場で何を論じるのか」を簡潔に示す場所です。
詳細な理由や体験談は、本論でしっかり展開すれば十分です。
序論はシンプルに、採点者に「この小論文は何について書かれているのか」が一目で伝わるようにしましょう。

体験談が主張につながらない
体験談は読者にリアリティを与えられるため有効ですが、単なるエピソード紹介で終わってしまうと減点対象になります。
例えば「私はボランティアをした経験がある」と書くだけでは不十分です。
その経験から「人と協力する大切さを学んだ→だから地域社会における助け合いの仕組みが重要だ」というように、必ず主張や論点に結びつけることが必要です。

根拠のない断定・感情的表現
例:「〇〇は絶対に正しい!」
このような書き方は、感情的で説得力に欠けます。
小論文は論理的な文章が求められるため、「絶対に」「必ず」といった断定は避けるべきです。
代わりに「〜というデータがあるため」「〜という調査結果から」など、客観的な根拠を示しながら主張を展開すると、論理性が高まり採点者の評価も上がります。

テーマから逸れる一般論
テーマと直接関係のない話から始めると、「何を論じる小論文なのか」が伝わらなくなります。
例えば、テーマが「AIと仕事の未来」なのに「情報技術は昔から人類を進歩させてきた」という大枠の話から始めるのはNGです。
序論の最初の一文は、必ず与えられたテーマに直結させましょう。
そうすることで、採点者に「この受験生はテーマを正しく理解している」と伝えることができます。
「だから」の言い換えは?──接続語の使い分け一覧

「だから」という接続語は、小論文では稚拙な印象を与えがちです。
ここでは、論理的な文章にふさわしい接続語の使い分けを紹介します。
このため/その結果/以上より
[一方で/しかし/つまり(論理関係の注意点)
したがって/ゆえに/よって
これらの接続語は、「前の文で示した理由や根拠から、当然導かれる結論」を表すときに使います。
論理的な流れを強調するため、最もよく使われる重要な接続語です。
例
「日本の労働人口は年々減少している。したがって、外国人労働者の受け入れを拡大することが必要である。」
「AIの活用は作業効率を大幅に高める。ゆえに、企業は積極的にAI導入を進めるべきだ。」
このように、「理由 → 結論」の流れを明確にし、説得力を高めることができます。

このため/その結果/以上より
これらの接続語は、「前の文の出来事や事実が原因となり、その結果が後に続く」という因果関係を示すときに使います。
特に、複数の要因を整理してから結論に結びつけたいときに効果的です。
例
「交通網の発達や通信技術の向上によって、人々の生活は大きく変化した。その結果、地方と都市の格差は縮小しつつある。」
「近年、若者の読書離れが進んでいる。このため、出版社は電子書籍やSNSを活用した宣伝に力を入れている。」
このように「原因と結果の流れ」を示すことで、論旨の展開がよりわかりやすくなります。

一方で/しかし/つまり(論理関係の注意点)
・「一方で」は、別の視点や対照的な内容を出すときに使います。
・「しかし」は、前の文を受けて逆の立場を述べたいときに使います。
・「つまり」は、前の説明を短くまとめたり、別の言葉で言い換えたりするときに便利です。
例
「AIは業務効率を高めることができる。一方で、雇用を奪うのではないかという懸念もある。」
「環境保護は重要である。しかし、経済成長を妨げるという意見も存在する。」
「少子化が進めば、労働人口が減る。つまり、経済活動全体に悪影響を及ぼす可能性がある。」
これらを適切に使うことで、文章の流れにメリハリがつき、論理がより明確に伝わります。
序論 書き方の型:一文目→二文目→三文目の並べ方

小論文の序論は、一文目から三文目までを型に当てはめることで、誰でも簡単に書けるようになります。
小論文の序論は、以下の3つのステップで構成すると論理的で分かりやすくなります。
一文目:テーマに対する自分の主張を明確に述べる
例:「私はSNSの実名制導入に賛成である。」
二文目:その主張に至る理由や背景を簡潔に説明する
例:「なぜなら、匿名性が誹謗中傷や虚偽情報の拡散を助長していると考えるからだ。」
三文目:本論で論じる内容を予告する
例:「本稿では、SNSの匿名性がもたらす問題点を指摘し、実名制が社会に与える影響について論じる。」
この3ステップを意識するだけで、論理の破綻がない序論が完成します。
本論 書き方:主張→根拠→具体例→まとめの順序
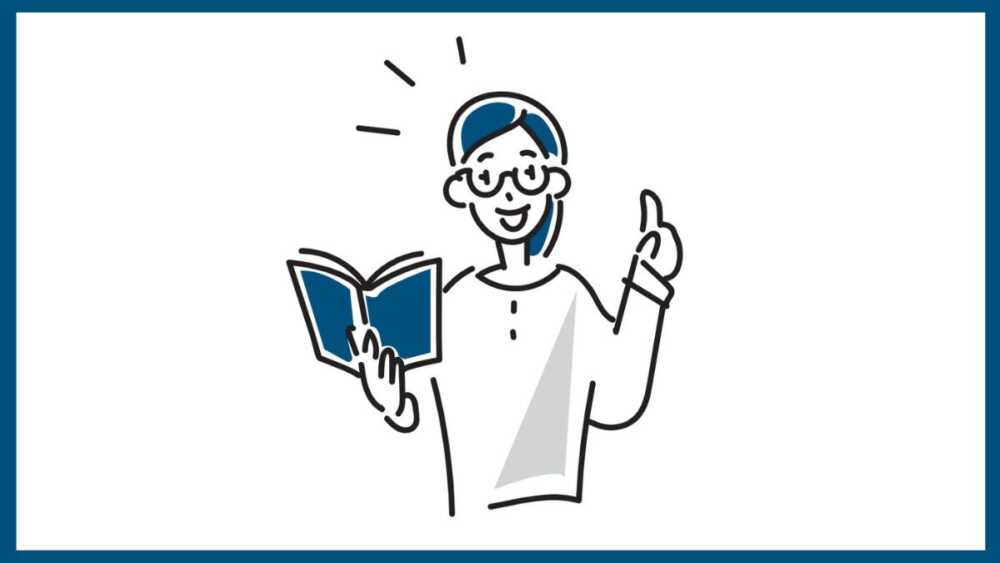
本論は、序論で提示した主張を具体的に補強する役割を持ちます。
本論の各段落は「主張→根拠→具体例→まとめ」の順序で書くことが基本です。
本論では、序論で述べた主張の説得力を高めることが目的です。
各段落を以下の流れで書くことで、採点者にあなたの考えが正確に伝わります。
主張: その段落で最も言いたいことを最初に書きます。
根拠: 主張を裏付ける理由やデータを提示します。
具体例: 根拠をさらに分かりやすくするために、具体的な事例や統計データ、自らの体験談などを加えます。
まとめ: 段落の内容を簡潔にまとめ、次の段落へとつなげます。
この構成で本論を構築すると、一つの段落で一つの主張が完結するため、非常に読みやすくなります。
「800字」の小論文であれば、この構成で2〜3段落書くのが一般的です。
小論文 書き方 高校生向け:時間配分と下書きのコツ

高校生が小論文を書く際には、限られた時間内で効率的に執筆する工夫が必要です。
ここでは、時間配分と下書きのコツについて解説します。
小論文の試験は時間との戦いです。
特に高校生は、時間配分を誤って最後まで書ききれないという事態に陥りがちです。
| ステップ | 目安時間 | 内容 |
|---|---|---|
| 課題文読解・テーマ分析 | 10分 | 何が問われているかを正確に把握する |
| 構成メモ作成 | 10分 | 序論・本論・結論の骨子を作る |
| 執筆 | 50分 | 構成メモに沿って一気に書く |
| 見直し | 10分 | 誤字脱字、論理の矛盾をチェック |
最も重要なのは構成メモの作成です。
ここに時間をかけることで、本番の執筆がスムーズに進みます。
下書きはキーワードや簡単な文章で十分です。
いきなり本文を書き始めず、必ず構成を練る時間を取りましょう。
小論文 例文 800字:構成サンプルと段落配分

800字の小論文は、論理的な構成を意識することで高得点が狙えます。
ここでは、3つのテーマに沿った800字の構成サンプルを具体的に紹介します。
800字例②(課題解決型)
800字例③(提案型)
800字例①(賛否型)
この型は、あるテーマについて「賛成」か「反対」の立場を明確にするものです。
・序論(100字): 賛成の立場を明確に示し、論点を予告する。
・本論1(300字): 賛成の理由(メリット)を具体的に述べる。
・本論2(200字): 反対意見を提示し、それに対して反論する。
・結論(200字): 序論の主張を再確認し、本論の内容を要約する。

800字例②(課題解決型)
この型は、ある社会的な課題を解決するための提案を述べるものです。
・序論(100字): 解決すべき課題を明確に示し、解決策を予告する。
・本論1(250字): 課題の原因や背景を分析する。
・本論2(250字): 提案する解決策を具体的に説明する。
・結論(200字): 提案の有効性を再確認し、将来の展望を述べる。

800字例③(提案型)
この型は、あるテーマについて、自分の考えや新しいアイデアを提示するものです。
・序論(100字): テーマに対する自分の考え(アイデア)を提示する。
・本論1(300字): そのアイデアのメリットや実現可能性を論じる。
・本論2(200字): 予想される反論や課題に対する対策を述べる。
・結論(200字): アイデアの重要性を再確認し、締めくくる。
高校生 小論文 書き方:評価基準に合わせたチェックポイント

小論文の採点者は、いくつかの評価基準に基づいてあなたの文章を判断します。
高校生が特に意識すべきチェックポイントを解説します。
小論文は、単なる作文とは異なり、以下の3つの観点から評価されます。
・論理構成: 序論・本論・結論の繋がりが明確で、一貫性があるか。
・内容: 提示されたテーマに対する深い考察や独自性があるか。
・表現力: 正確な語彙や文法、句読点が適切に使われているか。
特に高校生は、 論理構成が不十分であったり、「〜と思う」「〜じゃないかな」のような曖昧な表現を使いがちです。
断定的な表現を使い、根拠を明確に示すことで、論理的な思考力が評価されます。
小論文 テーマ型 例文:賛成・反対・中立の書き分け

テーマ型小論文では、賛成、反対、中立といった立場を明確にすることが重要です。
それぞれの立場でどう書けば良いかを例文とともに解説します。
テーマ型小論文では、最初に自分の立場をはっきりと示しましょう。
・賛成: 「私は○○に賛成である。その理由は〜」のように、最初に結論を述べ、その理由を説明します。
・反対: 「私は○○に反対の立場である。なぜなら〜」と、明確に反対意見を表明します。
・中立:「○○にはメリットとデメリットの両面がある。私は、〜という観点から論じる。」のように、中立的な立場をとりつつも、論じる視点を明確にします。
どの立場を選ぶかによって、論理構成も変わってきますので、自分の主張を一番伝えやすい立場を選びましょう。
書き出しから本論へのスムーズなつなぎ方フレーズ集

序論と本論の間に適切なつなぎのフレーズを入れることで、文章の流れがスムーズになります。
ここでは、すぐに使えるフレーズをいくつか紹介します。
「本稿では、この問題について以下3つの観点から論じる。」
「この主張の根拠は、主に二つある。第一に〜、第二に〜。」
「この問題の背景には、主に〇〇という要因が考えられる。以下にその詳細を述べる。」
これらのフレーズをうまく使うことで、採点者は文章の全体像を把握しやすくなります。
総合型選抜で逆転合格するなら!
「逆転コーチング総合型選抜」
プロのコーチが生徒をサポート
リーズナブルな料金設定
自分の可能性に挑戦しよう!
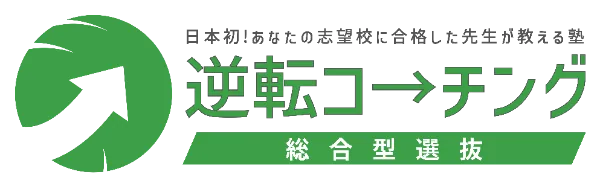
「逆転合格」で未来が変わる
総合型選抜に強い!逆転コーチング
↓↓↓
参考記事:逆転コーチング総合型選抜はやばい?口コミ・評判・料金を徹底取材!
大学入試小論文の書き出しに関するよくある質問
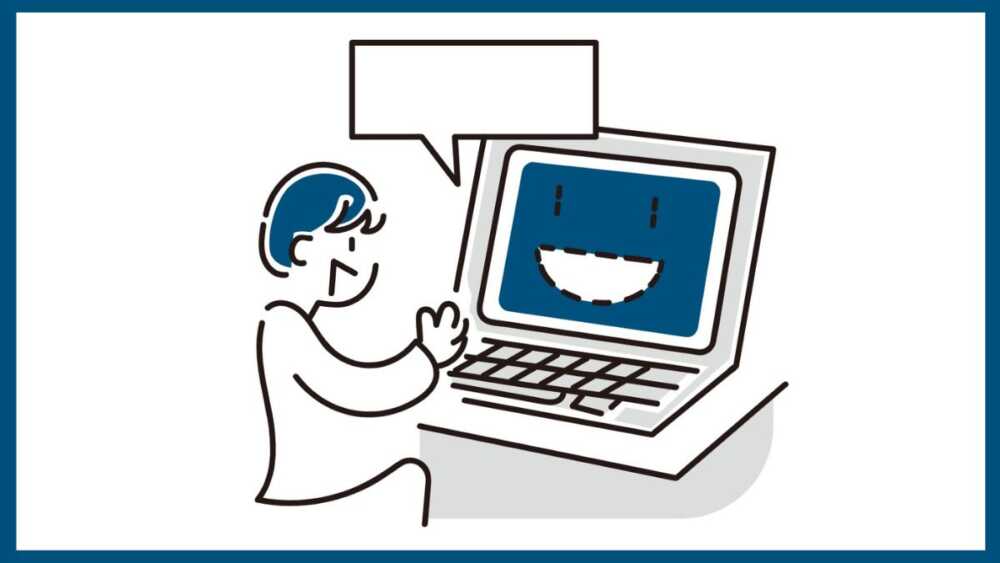
ここでは、小論文の書き出しに関して、多くの受験生から寄せられる質問にお答えします。
小論文でダメな例は?
「だから」の言い換えは?
「はじめに」の例文は?
小論文の書き始めは何を書く?
序論の最初の一文では、自分の結論・主張、論点、そしてその根拠につながるヒントを簡潔に示すのが効果的です。
例えば、「私はAIの導入に賛成である。その理由は労働効率の向上と新しい産業の発展につながるからだ。」のように、最初に立場を明確に示すことで、採点者に「この小論文は何を論じるのか」がすぐに伝わります。
序論は「論点の地図」を示す部分なので、この型を身につけておくことが大切です。

小論文でダメな例は?
避けるべきパターンはいくつかあります。
・抽象的すぎる表現:「現代社会は複雑で様々な問題がある」のように、具体性がなく中身が伝わらない。
・長すぎる序論:体験談や前置きが長く、主張が見えなくなる。
・論理の飛躍:理由を示さず結論だけ書く、根拠が弱い。
・感情的な表現:「絶対に正しい!」「必ず〜すべきだ!」などは説得力を欠く。
小論文では、冷静で論理的に、自分の立場と理由を筋道立てて書くことが大切です。

「だから」の言い換えは?
小論文では、日常的な「だから」よりも、論理的な接続語を使う方が好印象です。
・「したがって」
・「ゆえに」
・「よって」
これらを使うと、前の文の理由から自然に結論が導かれていることが伝わり、文章全体が論理的に見えます。

「はじめに」の例文は?
レポートや研究論文では「本稿では〜について述べる」という「はじめに」で始めることが多いですが、小論文では避けたほうがよいです。
入試の小論文では、自分の立場や意見を明確に示すことが第一だからです。
例えば、「私は少子化対策として教育費の無償化を進めるべきだと考える。」のように、最初から主張を打ち出すことで、採点者に「この文章の方向性」がすぐに伝わります。
仕上げチェックリスト:論点の明確さ・一貫性・語彙の適切さ
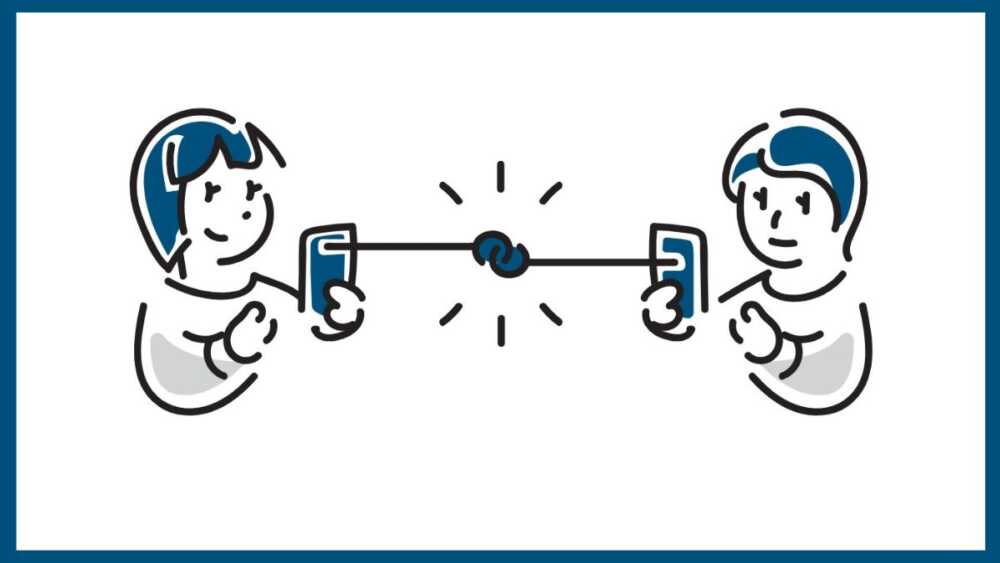
小論文を書き終えたら、提出前に必ず以下のチェックリストで最終確認を行いましょう。
・論点の明確さ: 序論で述べた主張は、本論全体を通して一貫していますか?
・構成の論理: 序論・本論・結論が論理的に繋がっていますか?
・根拠の説得力: 主張を裏付ける根拠や具体例は十分ですか?
・語彙の適切さ: 誤字脱字、不適切な表現はありませんか?
・文字数: 指定された文字数内に収まっていますか?
このチェックリストを実践することで、採点者に良い印象を与え、高得点に繋がります。
練習用テンプレート配布:序論テンプレ7パターンの穴埋めワーク

ここでは、記事で紹介した7つのテンプレートを実際に練習するための穴埋めテストです。
このテストを使って、様々なテーマで書き出しの練習をしてみてください。
(例:「少子高齢化」をテーマに)
問題提起型: 近年、日本の( )が深刻な社会問題となっている。
結論先出し型: 私は日本の( )には、( )という解決策が有効だと考える。
このようなテストで練習すれば、 どんなテーマにも対応できるようになるでしょう。
【解答】
・問題提起型
少子高齢化、貧困格差、長時間労働など
・結論先出し型
少子化には、子育て支援の拡充という解決策が有効だと考える。
長時間労働には、働き方改革の推進という解決策が有効だと考える。
まとめ:小論文の書き出し例7選|序論のテンプレートとNG例・改善法で得点アップ!

小論文の序論の書き方について、7つのテンプレートと実践的なコツを解説しました。
小論文は、「才能」や「センス」ではなく、「型」を学ぶことで誰でも上達できます。
大学入試小論文の書き出しとは?
・テンプレートを丸暗記する
・3題以上練習する
・信頼できる人に添削してもらう
この3つのステップを実践すれば、 あなたの小論文は確実に得点アップします。
独学で難しいと感じる場合は、 小論文に定評のある塾の講師に相談することも有効な手段です。
大学入試の小論文は、一朝一夕に上達するものではありません。
正しい書き方の基本を理解し、適切な手順で練習を重ねれば、必ず合格レベルの小論文を書けるようになります。
この記事で解説した、小論文の基本と評価基準、書き方の7ステップ、基本構成と型、印象的な書き出しと説得力のある結論のコツ、そしてテーマ別の例文や対策のポイントを、ぜひあなたの小論文対策に役立ててください。
特に重要なのは、以下の3点です。
1. 設問を正確に理解し、自分の主張を明確に持つこと。
2. 序論・本論・結論という論理的な構成を意識すること。
3. 主張を支える具体的な根拠や事例を示すこと。
そして、書いた小論文は必ず誰かに読んでもらい、フィードバックをもらうようにしましょう。
客観的な視点からのアドバイスは、あなたの成長を大きく助けてくれます。
大学入試の小論文は、あなたの思考力、表現力、そして社会への関心の深さをアピールする絶好の機会です。
この記事を参考に、自信を持って小論文対策に取り組み、志望校合格を勝ち取ってください!
応援しています。
総合型選抜とは?おすすめの記事
「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
総合型選抜「受かる確率」の真実と合格者だけが知る7つの対策で合格率アップ
【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは
大学面接で聞かれることランキング【質問と回答例】入試対策にもすぐに使える
総合型選抜(AO入試)に向いている人・向いてない人・落ちる人の特徴を解説
総合型選抜の落ちる確率とは?書類審査や面接で受かる気がしない人【必見】
評定平均とは?計算方法とは?大学推薦入試で差をつける評定対策をアドバイス
総合型選抜(AO入試)の対策はいつから準備する?学年別ロードマップで解説
【総合型選抜】自己アピール文の書き方&合格した自己PR例文テンプレ集
総合型選抜のエントリーシートの書き方&例文で夢の大学合格を掴む!
総合型選抜(AO入試)の合格基準とは?評定平均の目安と対策を大公開
総合型選抜(ao入試)に落ちたら?不合格から逆転合格する次の一手はこれだ!
【総合型選抜対策】成績が悪い受験生必見|今の評定平均は関係ない
総合型選抜面接を突破する自己PR作成術と例文!大学受験攻略ガイド
総合型選抜おすすめ塾
ホワイトアカデミー高等部の口コミ・評判は?取材で判明!良い・悪い声の真相
「Loohcs志塾・AOI・ホワイトアカデミー高等部」総合型選抜専門塾の特徴・合格実績を徹底比較!
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
AOI塾の料金(入会金・月謝)を調査!他の総合型選抜塾との年間費用を比較
総合型選抜に強い塾おすすめランキング11選|費用・コスパ・実績で比較
小論文対策に強い塾おすすめ10選!短期間で伸ばせるオンライン塾で逆転合格
【総合型選抜】料金が安い塾おすすめ12選|料金相場とコスパ徹底比較
総合型選抜で塾に行くべきか?診断テストでチェック!塾が必要な人の特徴
総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
浪人生が総合型選抜で合格する方法とは?実績豊富なおすすめ塾10選
総合型選抜専門塾【KOSKOS】ってどうなの?口コミ・評判・料金を調査した結果は?
自己推薦書の書き方を例文付きで解説!大学に合格できる「書き出し」


