受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは
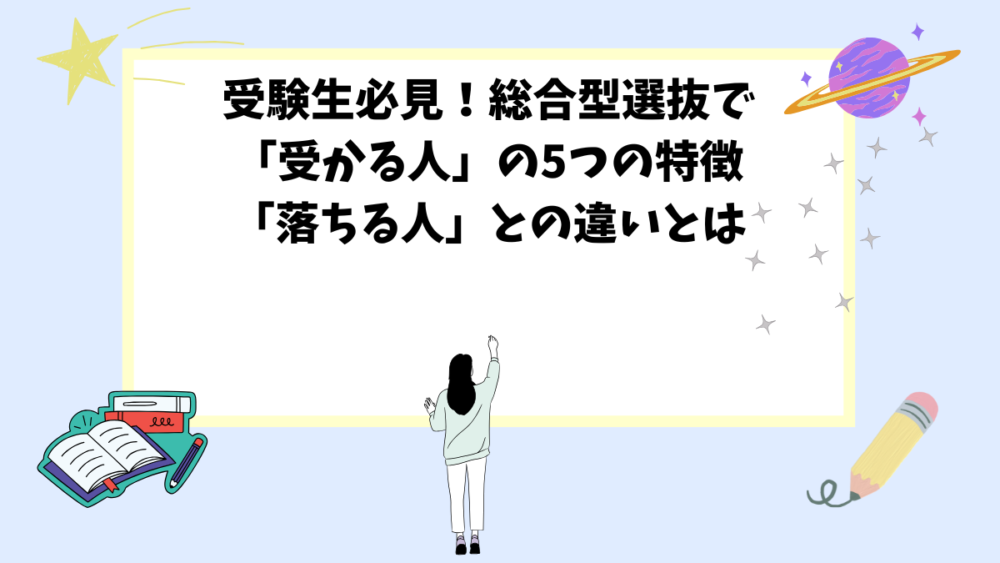
総合型選抜での大学進学を考えている皆さん、どんな人が合格しているのか、そして自分は「受かる人」になれるのか、漠然とした不安を感じていませんか?
総合型選抜の入試方式は、一般選抜とは異なる基準で評価されるため、対策に戸惑う方も少なくありません。
本記事では、長年の個別指導経験を持つ筆者が、総合型選抜で合格を掴む人の共通点と、残念ながら不合格になってしまう人の違いを徹底的に解説します。
具体的な対策方法や、よくある疑問にもお答えしますので、ぜひ最後まで読んで、あなたの合格への道を切り開いてくださいね。
残念ながら不合格になる人に共通する傾向
合格へ導く実践的な対策方法とロードマップ
総合型選抜に関するよくある疑問とその解消法
【オンライン総合型選抜専門塾】
なぜなら、
社会人のプロ講師が徹底指導で
現役合格に導きます!
しかも、
合格保証・返金制度あり!

総合型選抜と公募推薦対策ガイド
無料でプレゼント
↓↓↓
Contents
- 1 はじめに:総合型選抜で「受かる人」と「落ちる人」の決定的な違いとは?
- 2 総合型選抜とは?受かる人は試験日程と選考方法の基本を知っている
- 3 総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴を徹底解説
- 4 総合型選抜で「落ちる人」の共通点と対策不足のサイン
- 5 合格者のリアルな声:成功体験談から学ぶ「受かる秘訣」
- 6 不合格者の声から学ぶ:なぜ「落ちてしまった」のか?
- 7 総合型選抜合格のために今すぐやるべき対策ロードマップ
- 8 総合型選抜に関するよくある疑問と不安を解消
- 9 総合型選抜で受かる人になる!合格を掴むための最終アドバイス
- 10 まとめ:受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは
はじめに:総合型選抜で「受かる人」と「落ちる人」の決定的な違いとは?

総合型選抜の合格を勝ち取る人には共通の特徴があり、一方で不合格になる人にも、その理由となる傾向が見られます。
このセクションでは、私が個別指導の現場で受験生と向き合ってきた経験から、合格者の本質的な強みと、惜しくも涙をのむ原因を明らかにし、あなたの不安を解消するためのヒントを解説します。
本記事でわかること:合格者の特徴と具体的な対策
元学習塾経験者が受験生を見てきたからこそ語れる「総合型選抜、受かる気がしない」を解消するヒント
「総合型選抜は運なのでは?」「自分には特別な実績がないから受かる気がしない…」。
学習塾の現場では、多くの生徒さんがこのような不安や疑問を抱えていました。
しかし、合格する生徒さんには、例外なく共通の思考パターンや行動様式があることを私は知っています。
具体的な指導経験に基づいた成功のヒントをお伝えし、あなたの「受かる気がしない」という気持ちを希望に変えるための道筋を示していきます。
一見平凡に見える活動でも、「なぜそれに取り組んだのか」「そこから何を学んだのか」を深く掘り下げて言語化する力が、合否を分ける大きな要因になることを多くの合格者が証明しています。

参考記事:総合型選抜(AO入試)に向いている人・向いてない人・落ちる人の特徴を解説
本記事でわかること:合格者の特徴と具体的な対策
この記事では、総合型選抜で「受かる人」に共通する5つの明確な特徴を詳しく解説します。
残念ながら「落ちてしまう人」にありがちなポイントも具体的に示し、その違いを明確にします。
あなたの「総合型選抜で受かる確率」を最大化するための、実践的な対策ロードマップもご紹介。
具体的な事例や、長年の指導経験で培ったアドバイスを通して、あなたが自信を持って総合型選抜に挑めるよう、合格へ直結する情報を提供します。

参考記事:大学面接で聞かれることランキング【質問と回答例】入試対策にもすぐに使える
総合型選抜とは?受かる人は試験日程と選考方法の基本を知っている
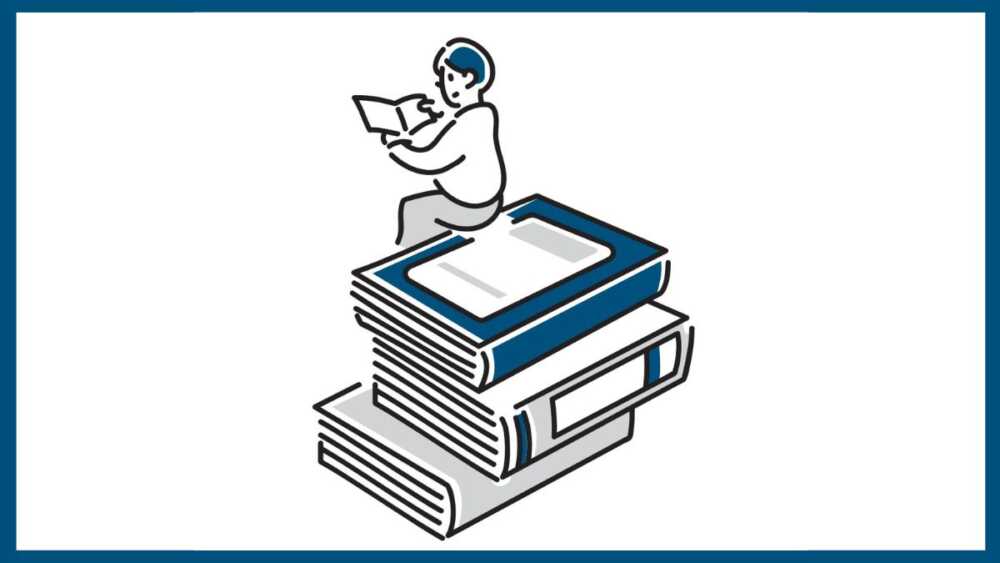
総合型選抜に受かる人は、まずこの入試方式の基本的な仕組みやスケジュールを正確に把握しています。
ここでは、総合型選抜の概要から、一般的な試験日程、そして多様な選考方法について、受験生が知っておくべきポイントを解説します。
総合型選抜の主な試験項目と選考プロセス
総合型選抜の出願から合格までのスケジュール
総合型選抜(旧AO入試)の概要と目的
総合型選抜は、学力試験だけでなく、出願書類、面接、小論文、プレゼンテーションなどを通じて、受験生の「個性」や「人間性」、そして「学びへの意欲」を多角的に評価する入試方式です。
以前は「AO入試」と呼ばれていましたが、2021年度入試から「総合型選抜」に名称が変更され、学力も含めた総合的な評価がより重視されるようになりました。
大学側は、アドミッション・ポリシー(求める学生像)に合致する、主体的に学ぶ意欲のある学生を発見し、育成することを目的としています。
たとえば、高校での探求活動や部活動、ボランティア活動など、これまでの学びや経験を「なぜその大学でさらに深めたいのか」を明確に語れることが求められます。

参考記事:【必見】総合型選抜・AO入試の志望理由書で高評価を得るための書き方【例文付き】
総合型選抜の主な試験項目と選考プロセス
総合型選抜では、大学によって試験内容が多岐にわたりますが、一般的には以下の項目が選考プロセスに含まれます。
これらの項目を通じて、受験生の思考力、判断力、表現力、主体性、多様性などが評価されます。
・書類選考:志望理由書、活動報告書、調査書、自己推薦書など。高校3年間の学びや活動をまとめる重要な書類です。
・小論文:課題に対する思考力や論理的構成力、表現力が問われます。社会課題に関するものや、資料読解型など形式は多様です。
・面接:個人面接、集団面接、グループディスカッション、プレゼンテーションなどがあります。コミュニケーション能力や、大学で学びたいことへの情熱が評価されます。
・学力試験:一部の大学では、共通テストや独自の学力試験を課す場合もあります。
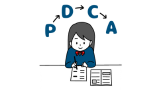
総合型選抜の出願から合格までのスケジュール
総合型選抜は、一般選抜に比べて早い時期に実施されるのが特徴です。
文部科学省の規定では、出願期間は9月1日から、合格発表は11月1日以降とされています。
学力検査を課す場合は、2月1日以降に試験、2〜3月頃に合格発表となることもあります。
たとえば、高校3年生の夏休みには志望理由書の作成など、本格的な準備を始める必要があります。
早ければ年内に合格が決まるため、受験生の負担を軽減できる一方で、早期からの計画的な準備が不可欠です。
| 選抜方式 | 出願期間(目安) | 合格発表(目安) | 併願の可否 |
|---|---|---|---|
| 総合型選抜 | 9月1日〜 | 11月1日〜 | 大学による |
| 学校推薦型選抜 | 11月1日〜 | 12月1日〜 | 不可が多い |
| 一般選抜 | 1月中旬〜 | 3月上旬〜 | 可 |
総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴を徹底解説

総合型選抜で合格を勝ち取る人には、共通した明確な特徴があります。
総合型選抜で受かる人の特徴は、単に学力が高いだけでなく、「学びに向かう姿勢」や「人間性」といった多面的な評価軸に基づいています。
このセクションでは、私が指導経験から「受かる人」の5つの特徴を具体的に解説し、あなたが「受かる人」になるためのヒントを解説します。
特徴2:学びたいことや将来のビジョンが明確に言語化できる
特徴3:自分の強みや個性を具体的なエピソードで表現できる
特徴4:高校内外の活動や資格取得で学びを深めている
特徴5:日々の学習で十分な評定平均を維持している
特徴1:大学のアドミッション・ポリシーに深く合致している
総合型選抜で受かる人は、志望大学のアドミッション・ポリシー(大学が求める学生像)を深く理解し、自身の学びたいことや経験が、その大学・学部でどのように活かせるかを明確に語れます。
単に大学の求める人物像をなぞるのではなく、自分の言葉で「なぜ私はこの大学にふさわしいのか」を説明できるのです。
たとえば、「地域創生」を掲げる学部に志望するなら、高校時代に地域ボランティアに参加し、そこで感じた課題と、大学でその課題をどのように解決したいか、具体的な学びの計画まで落とし込めているかが重要です。
大学側は、入学後に意欲的に学び、大学の教育理念に貢献してくれる学生を求めています。
【大学のアドミッション・ポリシーに深く合致している人】
・「地域貢献」に力を入れている大学に対し、地元のボランティア活動を通じた経験をアピールできる人
・「グローバル人材の育成」を掲げる学部に、海外留学や国際交流の経験をもとに志望理由を組み立てられる人
・「探究心」や「主体性」を重視する大学で、課題研究や探究学習を自ら立ち上げて取り組んだ経験を語れる人

特徴2:学びたいことや将来のビジョンが明確に言語化できる
総合型選抜で受かる受験生は、「なぜこの大学で学びたいのか」「大学で何を学び、将来どうなりたいのか」が明確です。
これは、深い自己分析と大学研究の賜物です。
総合型選抜で受かる人は、自分の興味や関心が単なる「好き」で終わらず、学問分野と結びつき、具体的なキャリアプランまで見据えています。
たとえば、漠然と「心理学に興味がある」だけでなく、「なぜ人間の心に興味を持ったのか」「具体的な心理学のどの分野を深く学びたいのか」「将来、その知識をどのように社会に役立てたいのか」を具体的に言語化できる人が強いです。
【学びたいことや将来のビジョンが明確に言語化できる人】
・「医療職に就きたい」という目標に対して、看護体験や家族の介護経験を通じた思いを具体的に語れる人
・「教育分野で子どもに関わりたい」という夢を、教育実習の参加や子ども食堂の支援活動を交えて話せる人
・「心理学を学びたい」理由を、いじめや不登校の課題をきっかけに自分で調べたり支援策を考えた経験と結びつけている人

特徴3:自分の強みや個性を具体的なエピソードで表現できる
総合型選抜では、受験生の個性や人間性も重要な評価対象です。
受かる人は、自分の強みや個性を単なる抽象的な言葉で終わらせず、具体的なエピソードを交えて説得力を持って表現できます。
たとえば、「私は協調性があります」と言うだけでなく、「〇〇部の部長として、意見の対立があった際に、どのようにチームをまとめ、目標達成に導いたか」という具体的な経験を話すことで、その強みが実際にどのように機能したかをアピールできるのです。
【自分の強みや個性を具体的なエピソードで表現できる人】
・クラス委員長としてクラスをまとめ、文化祭の成功に導いた経験を「リーダーシップ」として語れる人
・チームでの意見対立を調整し、目標達成に貢献した体験を「協調性」として具体的に伝えられる人
・苦手だった科目を努力して克服したエピソードを通じて、「粘り強さ」や「成長意欲」をアピールできる人

特徴4:高校内外の活動や資格取得で学びを深めている
部活動、委員会活動、ボランティア、資格取得など、高校生活における様々な活動を通して、何を学び、どう成長したのかを明確に語れる人も、総合型選抜で有利です。
重要なのは、活動の実績そのものよりも、「その経験から何を得て、大学でどう活かしたいか」という学びの深さです。
たとえば、英検準1級を持っていること自体も素晴らしいですが、「英語学習を通して、異文化理解の重要性を知り、将来は国際協力の分野で活躍したい」といった形で、経験と将来のビジョンを結びつけられると、さらに評価が高まります。
【高校内外の活動や資格取得で学びを深めている人】
・地域の図書館でボランティア活動を行い、「子どもと本」をテーマに進路を深めている人
・英検・数検・漢検などの資格を継続的に取得し、学びに対する姿勢を示している人
・探究学習や高校独自のゼミで、自分のテーマを設定してプレゼンや論文発表を経験している人

特徴5:日々の学習で十分な評定平均を維持している
総合型選抜では、必ずしも高い学力が必要とされないと思われがちですが、実際には評定平均が出願条件となったり、評価対象になったりする大学も少なくありません。
受かる人は、日々の授業や定期テストに真摯に取り組み、地道な努力で高い評定平均を維持しています。
「学びに対する真摯な姿勢」や「継続力」を示す重要な指標となるため、総合型選抜を検討しているなら、高校1年生の頃から日々の授業を大切にし、定期テストで高得点を狙うことがとても大切です。
【日々の学習で十分な評定平均を維持している人】
・毎回の定期テストで90点以上を目標に学習を続け、評定平均4.5以上をキープしている人
・学習習慣を毎日確立し、学校の授業だけでなく家庭学習も計画的にこなしている人
・得意・不得意に関係なく、全科目バランスよく努力し、先生からの信頼も厚い人

参考記事:評定平均とは?計算方法とは?大学推薦入試で差をつける評定対策をアドバイス
総合型選抜で「落ちる人」の共通点と対策不足のサイン
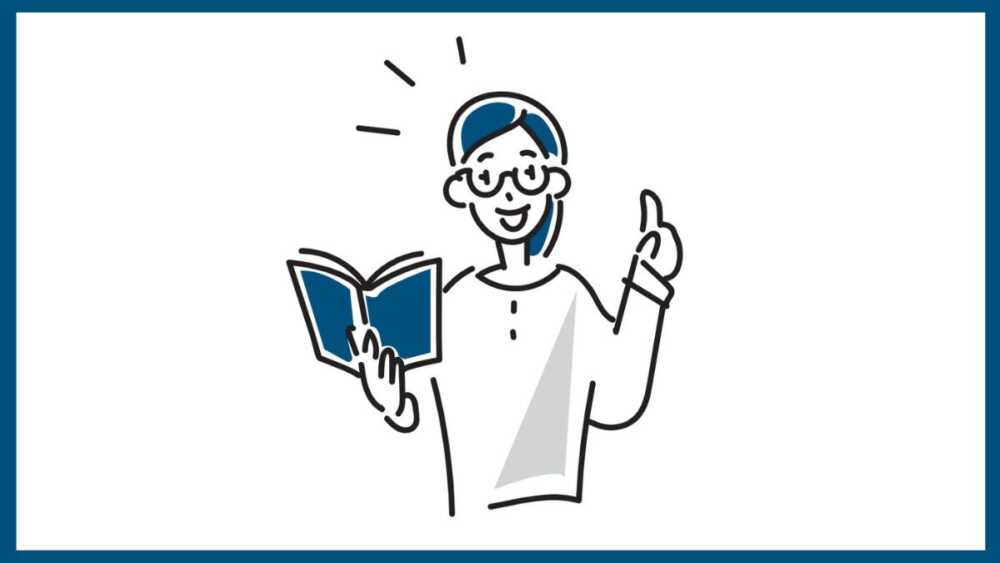
総合型選抜で残念ながら合格に至らない受験生には、共通の傾向が見られます。
これらのサインに気づき、早めに対策を講じることで、「落ちる人」の特徴から抜け出し、合格へ近づくことができます。
面接や小論文など、各選考対策が不十分な人
出願条件(評定平均や活動実績)を軽視している
自ら「問い」を立て、行動に移すことが苦手な人(総合型選抜 向いてない人)
自己分析・大学研究が甘く、志望動機が曖昧な人
総合型選抜で「落ちる人」の典型的な特徴の一つは、自己分析や大学研究が不十分で、志望動機が曖昧な点です。
「なぜこの大学なのか」「なぜこの学部なのか」という問いに対して、誰もが書けるような表面的な理由しか述べられず、「その大学でなければならない理由」を説得力を持って語れないのです。
たとえば、「将来は人の役に立ちたいから心理学部」という漠然とした理由では、「なぜ心理学なのか」「具体的にどのように人の役に立ちたいのか」まで踏み込めていないため、大学側には入学後の意欲が低いと見なされてしまう可能性があります。

面接や小論文など、各選考対策が不十分な人
総合型選抜は多角的な評価が魅力ですが、その分、面接や小論文といった対策に時間がかかる選考方法が多いです。
「落ちる人」は、これらの対策を「なんとなく」進めたり、「十分な練習をせずに本番に臨んでしまう」傾向があります。
たとえば、小論文では論理的な思考力と構成力が問われるにも関わらず、過去問演習や添削を十分にこなしていないと、本番で「何を書けばいいかわからない」「時間内に書ききれない」といった事態に陥ってしまいます。
面接でも、想定される質問への準備が甘く、一貫性のある回答ができないことが不合格に繋がります。

参考記事:大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
出願条件(評定平均や活動実績)を軽視している
総合型選抜は人物重視の入試とはいえ、評定平均や活動実績といった出願条件を軽視してしまうと、不合格の原因になりかねません。
中には「書類や面接で挽回できる」と考え、評定平均の低さや活動記録の不足をそのままにしてしまう受験生もいます。
大学側は、学習への姿勢や継続力を、評定や実績を通じてしっかりと見ています。
出願条件を満たしていなければ、書類選考で足切りされることもあるため、まずは「土台を整える」ことが大前提です。

自ら「問い」を立て、行動に移すことが苦手な人(総合型選抜 向いてない人)
総合型選抜で求めるのは、自ら問題を発見し、解決のために行動できる主体性です。
そのため、「腰が重い人」や「人から指示されないと動けない人」は、この入試方式には「向いていない」と評価されがちです。
たとえば、探求活動に取り組んだ経験があったとしても、「与えられたテーマをこなしただけ」で、「自分から疑問を見つけ、その解決のために試行錯誤した経験」が語れないと、「学びに向かう姿勢」が不足していると判断されてしまう可能性があります。
合格保証がある!総合型選抜専門塾!ホワイトアカデミー高等部←おすすめ!
※安心できる社会人のプロ講師がマンツーマンで指導!
フルオーダーメイドの授業で合格に導く!総合型選抜専門塾AOI
※小論文、志望理由書など総合型選抜のことならお任せください!
小論文対策に絶対の自信がある!小論文専門:翔励学院
※合格できる小論文の書き方を丁寧に指導!合格率94%
難関大学に逆転合格!逆転コーチング総合型選抜←当サイトで人気
難関私立大学の総合型選抜に特化したオンライン塾
合格者のリアルな声:成功体験談から学ぶ「受かる秘訣」

ここからは、実際に総合型選抜で合格を掴んだ先輩たちのリアルな声をご紹介します。
総合型選抜に受かる人がどのような戦略を立て、どのような努力をして合格を勝ち取ったのか、具体的なエピソードから「受かる秘訣」を探っていきましょう。
【ケース2】高3からの短期集中で合格を掴んだ先輩の事例
塾経験者が教える!実際に指導した合格者の共通点や裏話
【ケース1】課外活動の経験を活かして合格した先輩の戦略
公立高校に通っていたA君は、高校の異文化交流プロジェクトに積極的に参加し、そこで得た経験を志望理由書に深く落とし込みました。
面接では、プロジェクトでの具体的な課題解決経験を話し、リーダーシップと行動力をアピール。事前に課された経済学の試験と英語の筆記試験対策を徹底したことが、合格の大きな要因だったと語っていました。
「早めに英検(準2級)を受けておいたことも、いま振り返ると良かった」と、早期対策の重要性を強調していました。

【ケース2】高3からの短期集中で合格を掴んだ先輩の事例
私立高校に通っていたB君は、高校3年生の夏に専門学校から大学へと進路を変更。
小論文対策は夏から、面接練習は10月頃からと、短期間での集中対策を敢行しました。
志望理由書では、まだ明確でない将来の夢を正直に伝えつつも、「大学で社会で役立つ知識やスキルを幅広く身につけたい」という意欲を具体的に示しました。
B君は、「自己理解が深まったこと」が合格の秘訣だと語っています。
面接で聞かれそうな質問への回答を準備する中で、自分の好きなことや得意なこと、大学でどう学びたいかが明確になり、本番で自信を持ってアピールできたそうです。

塾経験者が教える!実際に指導した合格者の共通点や裏話
長年の個別指導経験から、合格した生徒たちの最大の共通点は、「自分と大学の深い対話」ができていたことです。
総合型選抜で受かる人は、「なぜその大学・学部でなければならないのか」を論理的に、そして情熱的に語れる準備をしていました。
たとえば、一見目立つ実績がなくても、日々の小さな疑問を深掘りし、それが大学での学びにどう繋がるかをストーリーとして構築できる生徒は、高い評価を得ていました。
これは、「単なる活動報告」ではなく「学びのプロセスと成果」を重視する総合型選抜の本質を理解していたからに他なりません。
不合格者の声から学ぶ:なぜ「落ちてしまった」のか?

総合型選抜は、対策を誤ると不合格につながることもあります。
ここでは、残念ながら不合格となってしまった先輩たちの声から、その原因と具体的な対策を学び、あなたの受験に活かしましょう。
準備不足が招いた不合格の落とし穴
塾経験者が教える!指導で見てきた不合格の原因と具体的な改善策
【ケース1】緊張しすぎて頭が真っ白に…失敗から見えた課題(総合型選抜 落ちた 知恵袋)
Cさんは、第一志望の総合型選抜の面接で「緊張しすぎて頭が真っ白に」なってしまい、準備したことが話せなかったと語っていました。
質問は想定内だったものの、「この学校にどうしても入りたい」という気持ちが強すぎた結果、本番で本来の力が発揮できなかったそうです。
Cさんは、「いつも同じ先生としか練習していなかったため、異なる相手との練習や、複数の先生対自分という形での練習をしておけばよかった」と反省していました。
志望動機をほぼ丸暗記していたことで、「自分の言葉ではない表現があったため、緊張時に言葉が出てこなくなった」という気づきも得ていました。
これは、「総合型選抜 落ちた 知恵袋」などでもよく見られる失敗例の一つです。

準備不足が招いた不合格の落とし穴
不合格となってしまう多くのケースでは、自己分析や大学研究の甘さ、そして面接や小論文といった個別対策の不足が主な原因として挙げられます。
たとえば、「なんとなく良さそう」という理由で大学を選んでしまい、アドミッション・ポリシーとのミスマッチに気づかないまま受験したり、小論文対策を「ぶっつけ本番」で臨んでしまったりするケースが見られます。
総合型選抜対策の準備不足は、書類や面接での説得力の欠如に繋がり、結果として不合格という形で現れてしまうのです。

塾経験者が教える! 指導で見てきた不合格の原因と具体的な改善策
長年の学習塾経験から、数多くの不合格も見てきました。
総合型選抜で不合格になる人の多くは、「自己流の限界」にあります。
特に、「自分を客観的に見つめ直す自己分析の不足」や、「志望大学が本当に求めている人物像の誤解」が致命的な原因となることが多かったです。
具体的な改善策としては、まず第三者の目(学校の先生、予備校の講師、経験者など)を借りて、自分の強みや弱み、志望動機を客観的に評価してもらうこと。
模擬面接や小論文の添削を繰り返し行い、本番に近い環境で実践的な練習を積むことが不可欠です。
「緊張で頭が真っ白」になることを防ぐには、想定外の質問にも対応できる柔軟な思考力を養うことが重要です。
総合型選抜合格のために今すぐやるべき対策ロードマップ

総合型選抜で「受かる人」になるためには、計画的で体系的な対策が不可欠です。
ここでは、合格を掴むために、あなたが今すぐ始めるべき具体的なステップをロードマップ形式でご紹介します。
対策2:徹底的な自己分析で「自分だけの強み」を言語化する
対策3:志望校の傾向に合わせた面接・小論文対策を徹底する
対策4:説得力のある提出書類を作成する
塾経験者が教える! 各対策で陥りやすい落とし穴と効果的な練習法
対策1:志望大学のアドミッション・ポリシーを深く理解し、自分を重ねる
まず何よりも重要なのは、志望大学・学部のアドミッション・ポリシーを徹底的に読み込み、理解することです。
ただ読むだけでなく、「この大学はどんな学生を求めているのか?」「自分のどんな経験や学びが、ここに合致するのか?」と、自分ごととして深く考えることが重要です。
たとえば、アドミッション・ポリシーに「主体性」が求められているなら、高校生活であなたが主体性を発揮した具体的なエピソードを複数洗い出し、それらをどのように結びつけるかを検討しましょう。

対策2:徹底的な自己分析で「自分だけの強み」を言語化する
総合型選抜では、あなたの個性や強みが問われます。
「なぜそれをやったのか?」「そこから何を学んだのか?」「それが将来どう繋がるのか?」といった「問い」を自分に投げかけ、これまでの経験を深掘りしてください。
たとえば、部活動や委員会、ボランティア活動、あるいは個人的な探求活動など、「何をして、何を感じ、何を考え、どう行動し、何を得たか」を具体的に書き出すことで、自分だけの強みが明確になり、説得力のある志望理由書や面接でのアピールに繋がります。

参考記事:総合型選抜(AO入試)の対策はいつから準備する?学年別ロードマップで解説
対策3:志望校の傾向に合わせた面接・小論文対策を徹底する
書類審査を通過したら、次には面接や小論文といった実践的な試験が待っています。
これらの対策は、「数をこなす」ことが重要です。
志望校の過去問を徹底的に分析し、出題傾向を把握しましょう。
・小論文対策:課題解決型、資料読解型など、形式に応じた論理的な文章構成を身につけること。信頼できる先生や塾の講師に繰り返し添削してもらうことが不可欠です。
・面接対策:志望理由や自己PR、大学で学びたいことなど、想定される質問に対する回答を準備し、模擬面接を何度も実施すること。話す内容だけでなく、話し方や表情、姿勢なども意識しましょう。

対策4:説得力のある提出書類を作成する
志望理由書や活動報告書、自己推薦書などは、あなたの熱意と個性を伝える最初の機会です。
総合型選抜の書類は、大学のアドミッション・ポリシーとあなたの強みがどのように重なるかを明確に示すストーリー性を持たせるように意識してください。
具体的には、「なぜその大学、その学部なのか」を具体的なエピソードを交えて論理的に説明し、「入学後に何を学び、どう貢献したいのか」まで具体的に記述することで、説得力が増します。
何度も推敲し、第三者にも読んでもらい、分かりやすく、誤字脱字のない完璧な状態で提出しましょう。

塾経験者が教える! 各対策で陥りやすい落とし穴と効果的な練習法
私自身の学習塾での指導経験から、多くの受験生が陥りがちな落とし穴は、「表面的な対策で終わってしまうこと」です。
たとえば、面接練習で用意した回答を丸暗記してしまうと、想定外の質問に対応できなくなり、「頭が真っ白に」なる原因になります。
効果的な練習法としては、用意した回答を自分の言葉で再構築する練習をすること。
小論文では、テーマに関する知識を深めるだけでなく、その知識を「自分の意見」として論理的に展開する練習が重要です。
「なぜ?」「どうすれば?」という問いを常に持ち、多角的な視点で物事を考える訓練を積むことで、深い思考力が養われます。
総合型選抜に関するよくある疑問と不安を解消

総合型選抜に関して、受験生や保護者の皆さんからよく聞かれる疑問や不安の声があります。
ここでは、それらの疑問に一つずつお答えし、皆さんの「受かる確率」を高めるための情報を解説します。
国公立・私立大学の総合型選抜に「受かる人」の違いとは?
総合型選抜に落ちたらどうする?その後の選択肢
総合型選抜は併願できる?学校推薦型選抜との違い
総合型選抜の合格率・落ちる確率は?(総合型選抜 受かる確率)
「総合型選抜は受かりやすい」と思われがちですが、実際には大学・学部によって倍率や難易度が大きく異なります。
国公立大学や難関私立大学では、総合型選抜でも非常に高い倍率になることが珍しくありません。
「総合型選抜 受かる確率」は一概には言えませんが、重要なのは、「何となくの挑戦」ではなく、「戦略的な準備」を行うことです。
募集要項をよく確認し、過去の合格者数や倍率を調べておくことが推奨されます。

参考記事:総合型選抜の落ちる確率とは?書類審査や面接で受かる気がしない人【必見】
国公立・私立大学の総合型選抜に「受かる人」の違いとは?
国公立大学と私立大学の総合型選抜では、合格者の特徴や評価されるポイントに違いが見られることがあります。
関連記事
ホワイトアカデミー高等部の口コミ・評判は?取材で判明!良い・悪い声の真相
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
まとめ:受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは

最後までご覧いただき、ありがとうございました。
今回の記事、「受験生必見!総合型選抜で「受かる人」の5つの特徴「落ちる人」との違いとは」は参考になりましたか?
まとめ:【現役高校生】総合型選抜で受かる人はみんなやっている総合型選抜対策!
総合型選抜は、あなたの高校生活における学びや経験、そして将来への意欲を大学に伝える素晴らしいチャンスです。
「受かる人」になるためには、大学のアドミッション・ポリシーを深く理解し、自己分析を徹底し、具体的な対策を早期から始めることが不可欠です。
総合型選抜の入試は、単なるテストの点数では測れないあなたの「個性」や「人間性」を評価してくれます。
今回ご紹介した「受かる人」の5つの特徴を参考に、あなた自身の強みを磨き、合格を掴み取ってください。
そして、もし「総合型選抜、受かる気がしない」と感じたら、一人で抱え込まず、学校の先生や塾の専門家など、信頼できる大人に相談することも大切な一歩です。
あなたの受験を心から応援しています。
総合型選抜とは?おすすめの記事
大学面接で聞かれることランキング【質問と回答例】入試対策にもすぐに使える
総合型選抜(AO入試)に向いている人・向いてない人・落ちる人の特徴を解説
【総合型選抜】自己アピール文の書き方&合格した自己PR例文テンプレ集
総合型選抜のエントリーシートの書き方&例文で夢の大学合格を掴む!
総合型選抜(AO入試)の合格基準とは?評定平均の目安と対策を大公開
総合型選抜(ao入試)に落ちたら?不合格から逆転合格する次の一手はこれだ!
「小論文の書き方」高校生が知っておきたい5つのポイント(例文あり)
大学入試の小論文│テーマ型の書き方とポイント!例文付きで解説
【必見】総合型選抜の面接14の質問!良い回答例と悪い回答例
総合型選抜「受かる確率」の真実と合格者だけが知る7つの対策で合格率アップ
【学校推薦型選抜対策】受かる人・落ちる人の特徴とは?合格の鍵を探る
総合型選抜おすすめ塾
ホワイトアカデミー高等部の口コミ・評判は?取材で判明!良い・悪い声の真相
「Loohcs志塾・AOI・ホワイトアカデミー高等部」総合型選抜専門塾の特徴・合格実績を徹底比較!
総合型選抜専門塾AOIの評判・口コミ10選!気になる点を塾経験者が徹底調査
AOI塾の料金(入会金・月謝)を調査!他の総合型選抜塾との年間費用を比較
総合型選抜に強い塾おすすめランキング11選|費用・コスパ・実績で比較
小論文対策に強い塾おすすめ10選!短期間で伸ばせるオンライン塾で逆転合格
【総合型選抜】料金が安い塾おすすめ12選|料金相場とコスパ徹底比較
総合型選抜で塾に行くべきか?診断テストでチェック!塾が必要な人の特徴
総合型選抜おすすめオンライン塾厳選11社!塾経験者が徹底調査
浪人生が総合型選抜で合格する方法とは?実績豊富なおすすめ塾10選
総合型選抜専門塾【KOSKOS】ってどうなの?口コミ・評判・料金を調査した結果は?
自己推薦書の書き方を例文付きで解説!大学に合格できる「書き出し」







