受験生必見!英語の勉強法【ゼロから始める】短期間で偏差値の爆上げを目指す

※この記事には一部PRが含まれます。
大学受験を控えた受験生の皆さん、英語の成績が伸びずに悩んでいませんか?
「何から手をつけて良いか分からない」「頑張っているのに結果が出ない」と不安を感じている方もいるかもしれません。
この記事では、ゼロからでも短期間で英語の偏差値を大幅にアップさせるための具体的な勉強法と、実践的な戦略を分かりやすく解説します。
効率的な学習で、志望校合格を掴み取りましょう!
英語の成績が伸びない原因と解決策
短期間で偏差値を上げるための学習戦略
各分野(文法、単語、長文、リスニング、英作文)の具体的な勉強法
受験勉強のモチベーションを維持するヒント
Contents
受験生の英語の勉強法で悩むのはなぜ?

「英語が苦手」「勉強しても伸びない」と感じている受験生は少なくありません。
このセクションでは、受験生が陥りやすい英語の勉強法の落とし穴と、頑張っているのに結果が出ない本当の理由を深掘りし、あなたの勉強法がなぜ「ゼロから」やり直す価値があるのかを明らかにします。
英語が苦手な受験生が陥りがちな落とし穴
頑張っているのに結果が出ない本当の理由
あなたの勉強法は「ゼロから」やり直す価値がある
英語が苦手な受験生が陥りがちな落とし穴
多くの受験生は、自分に合わない勉強法を続けていたり、基礎が固まっていないのに難しい問題に手を出してしまったりする落とし穴にはまっています。
たとえば、単語だけをひたすら暗記したり、長文読解をいきなり解き始めたりしても、文法や構文の理解が不足していると、思ったように成績は伸びません。
この状態では、努力が報われず、モチベーションも低下しがちです。

頑張っているのに結果が出ない本当の理由
一生懸命勉強しているのに成績が上がらないのは、努力が足りないからではありません。
多くの場合、勉強の質に問題があるためです。具体的には、インプットばかりでアウトプットの練習が不足していたり、復習が不十分だったりするケースが考えられます。
たとえば、参考書を読み込むだけでなく、実際に問題を解き、間違えた箇所を徹底的に分析することが重要です。
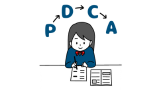
あなたの勉強法は「ゼロから」やり直す価値がある
もし今の英語の勉強法に不安を感じているなら、一度「ゼロから」見直す価値があります。
基礎の基礎から着実に学び直すことで、今まで見落としていた苦手分野を克服し、効率的な学習へと繋げられます。
これは一見遠回りのように見えて、実は短期間で偏差値を爆上げするための確実な方法なのです。
難関大学にあなたも逆転合格できる
圧倒的な合格率が本物の証
難関私大に合格する完璧なノウハウ
志望大学の先生があなたをサポート
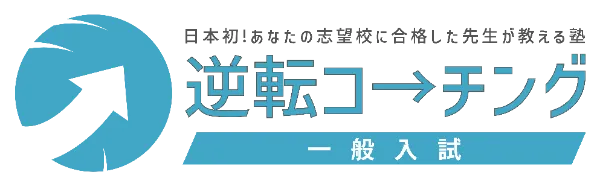
「友だち追加」で無料コーチング
勉強計画を無料で作成
↓↓↓
参考記事:高校2年生におすすめ塾24選【コーチング×東大生×AI】いつから通う?費用は?
短期間で受験生の英語の偏差値を爆上げするための勉強法

英語の偏差値を短期間で効率的に爆上げするには、闇雲に勉強するのではなく、明確な戦略が必要です。
ここでは、現状把握から基礎固め、そして実践的なアウトプットまで、合格へと導くための3つのステップを解説します。
ステップ1:現状把握と目標設定で勉強計画を立てる
ステップ2:基礎を徹底的に固める「ゼロから」の英語学習
ステップ3:アウトプット重視で実践力を磨く
ステップ1:現状把握と目標設定で勉強計画を立てる
まず、自分の現在の英語力と志望校合格に必要なレベルを把握しましょう。
模試の結果や過去問を分析し、どの分野が弱点なのか、何点足りないのかを明確にすることが重要です。
具体的な目標を設定し、それを達成するための長期・短期の勉強計画を立てます。
たとえば、「3ヶ月後に偏差値10アップ」といった具体的な目標を立てると、モチベーションを維持しやすくなります。

参考記事:【日東駒専対策】合格までの勉強時間と最初にやる参考書について
ステップ2:基礎を徹底的に固める「ゼロから」の英語学習
英語の偏差値を上げるためには、基礎の徹底が不可欠です。
特に、英語が苦手な受験生は、まず単語、文法、構文といった基本を「ゼロから」丁寧に学び直すことに時間をかけましょう。
焦って難しい問題に挑戦するのではなく、基礎固めに集中することで、後々応用問題にもスムーズに取り組めるようになります。

ステップ3:アウトプット重視で実践力を磨く
基礎が固まったら、次に重要なのはアウトプットです。
実際に問題を解くことで、知識が使えるスキルへと変わります。
たとえば、長文読解や英作文、リスニングなど、実際の入試形式に近い演習を積極的に行いましょう。
間違えた問題は必ず復習し、なぜ間違えたのか、どうすれば正解できたのかを徹底的に分析することで、実践力が飛躍的に向上します。
【基礎固め編】「ゼロから始める」受験英語の土台作り
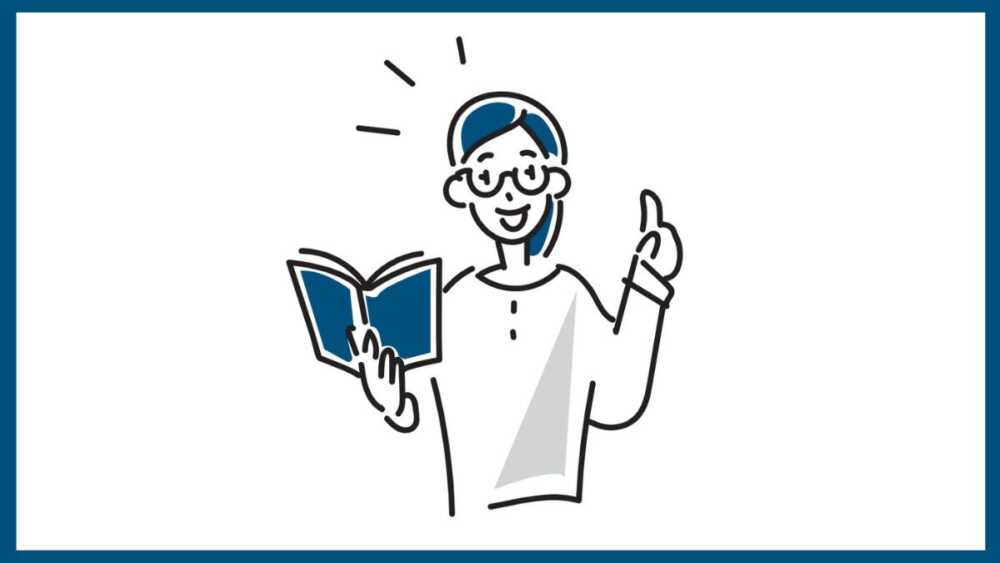
英語の偏差値を短期間で爆上げするためには、揺るぎない土台を築くことが最も重要です。
このセクションでは、英文法、英単語・熟語、英文解釈という英語学習の基本中の基本を、「ゼロから始める」受験生が効率的にマスターするための具体的な方法を詳しくご紹介します。
英文法をマスターする最短ルート
英単語・熟語を定着させる暗記術
英文解釈力を高める読み込み方
英文法をマスターする最短ルート
英文法は、英語の文章を正確に理解し、表現するための骨格です。
苦手意識を持つ受験生が多いですが、文法を体系的に学ぶことで、英語の構造がクリアに見えてきます。
受験生のための効率的な文法学習法
効率的な文法学習は、まず全体像を把握することから始まります。
たとえば、分厚い参考書を最初から最後まで読むのではなく、各章の要点をまず掴み、その後で演習問題に取り組むのがおすすめです。
「なぜそうなるのか」という理由を理解しながら、類題を繰り返し解くことで、知識が定着しやすくなります。
おすすめの英文法参考書と使い方
英文法参考書は、自分のレベルに合ったものを選ぶことが重要です。
使い方のポイントは、一冊を完璧にすることです。
複数の参考書に手を出すよりも、繰り返して読み込み、問題演習を重ねることで、知識がより深く定着します。

英単語・熟語を定着させる暗記術
英単語・熟語は、英語長文読解や英作文の必須アイテムです。
効率的な暗記法を身につけることで、短期間で語彙力を大幅に向上させることができます。
「短期間で」覚える!効率的な単語帳の使い方
「短期間で」単語を覚えるためには、視覚と聴覚を同時に使うことが有効です。
たとえば、単語帳の日本語訳だけでなく、例文と一緒に音声を聴きながら覚えると、記憶に残りやすくなります。
一度に大量に覚えようとするのではなく、毎日決まった数の単語を繰り返し確認する「回転学習」が非常に効果的です。
受験生が使うべき英語単語アプリ
スマートフォンの単語アプリも、効率的な学習ツールになります。
・Anki:忘却曲線に基づいて復習のタイミングを教えてくれるため、効率的に定着できます。
・mikan:ゲーム感覚で学べるため、継続しやすいのが特徴です。
隙間時間を使って、手軽に単語学習を進められるのがアプリの大きなメリットです。

英文解釈力を高める読み込み方
英文解釈とは、複雑な英文を正確に構造分解し、意味を理解する力です。
これができると、どんな長文も読みこなせるようになります。
一文一文を正確に読むための勉強法
英文解釈の練習では、一文一文を丁寧に分析することが重要です。
たとえば、SVOC(主語、動詞、目的語、補語)を意識しながら、動詞の形、修飾語句の範囲、接続詞や関係詞の働きなどを正確に把握する練習をしましょう。
最初は時間がかかりますが、この練習を繰り返すことで、複雑な英文も迷わず読めるようになります。
【実践力UP編】「短期間で」英語の偏差値を伸ばす応用学習
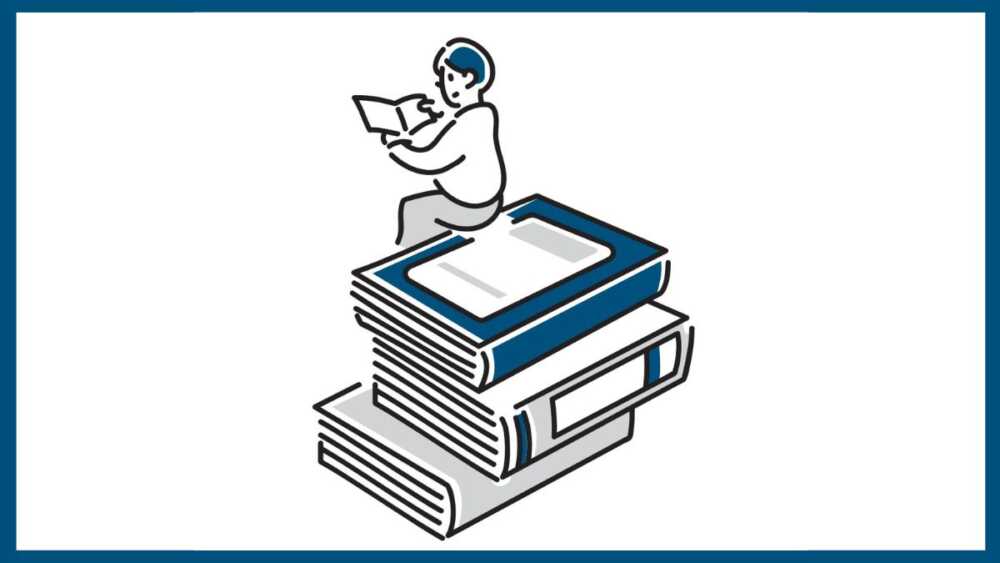
基礎が固まったら、いよいよ応用力を高める段階です。
このセクションでは、長文読解、リスニング、英作文という入試で差がつく3つの分野で、「短期間で」英語の偏差値を伸ばすための実践的な学習法をご紹介します。
これらのスキルを磨くことで、本番で高得点を狙えるようになります。
長文読解のスピードと精度を上げる秘訣
リスニング力を劇的に向上させる方法
英作文・自由英作で高得点を狙うには
長文読解のスピードと精度を上げる秘訣
長文読解は、多くの受験生が苦手意識を持つ分野です。
しかし、正しい方法で取り組めば、短期間で飛躍的に改善させることができます。
限られた時間で長文を攻略する勉強法
長文読解では、時間内に正確に読み解くことが求められます。
効果的な方法は、まず設問に目を通し、何が問われているかを把握することです。
文章全体をざっと読み、大意を掴みます。
必要な情報を探しながら精読していくと、限られた時間で効率的に解答できます。
例えば、段落ごとに要点をまとめる練習も有効です。
多読と精読のバランス
長文読解力を高めるには、多読と精読のバランスが重要です。
・多読:興味のある洋書や英語ニュースなどを気軽にたくさん読むことで、英語に慣れ、読むスピードを上げます。完璧に理解できなくても構いません。
・精読:入試レベルの英文を一文一文丁寧に分析し、構文や文法事項を正確に理解する練習です。この両輪を回すことで、総合的な読解力が向上します。
リスニング力を劇的に向上させる方法
リスニングは、英語の音に慣れることが何よりも大切です。
「短期間で」リスニング力を上げるには、毎日継続して英語の音声に触れることが不可欠です。
受験生のための効果的なリスニングトレーニング
効果的なリスニングトレーニングには、「シャドーイング」や「ディクテーション」があります。
・シャドーイング:英語の音声を聞きながら、影(シャドー)のように少し遅れて発音する練習です。発音やイントネーションが身につき、聞き取れない原因となる発音の認識不足を解消します。
・ディクテーション:聞こえた英語の音声を書き取る練習です。聞き取れない単語やフレーズを特定し、弱点を明確にできます。
音源活用で「短期間で」耳を鍛える
参考書付属のCDだけでなく、英語ニュースアプリやポッドキャストなど、多様な音源を活用しましょう。
特に、BBCやCNNのニュースは、受験英語のリスニング対策にも有効です。
通学時間などの隙間時間に積極的に聞き流すことで、「短期間で」英語耳を鍛えることができます。

英作文・自由英作で高得点を狙うには
英作文は、知識をアウトプットする力が問われる分野です。
基礎的な文法や語彙力を基に、論理的な文章を構成する能力が求められます。
受験英語で使える表現のストック術
英作文で高得点を取るためには、頻出テーマに合わせた「使える表現」をストックすることが重要です。
たとえば、「賛成」「反対」の意見を述べる際に使えるフレーズや、グラフ説明で用いる表現など、テンプレートとなる表現を暗記しておくと便利です。
例文を丸ごと覚えることで、自然な英語表現が身につきます。
添削を活用した実践的な英作文対策
書いた英作文は、必ず添削してもらうことが大切です。
学校の先生や予備校の講師、オンライン添削サービスなどを活用し、文法ミスや不自然な表現を指摘してもらいましょう。
客観的なフィードバックを受けることで、自分の弱点を明確にし、短期間で効率的に修正できます。
添削された箇所を何度も書き直すことで、表現力が向上します。
自分にピッタリの参考書がわかる塾
パーソナルトレーナーがサポート!
コーチング塾【STRUX】
毎日の計画があるから、
「あとは、勉強するだけ」

\当サイト限定のキャンペーン/
【参考書2冊+52,800円分】
なんと!どちらもプレゼント!
↓↓↓
受験生を支える!英語学習を継続するためのモチベーション維持術

受験勉強は長期戦です。特に英語はすぐに成果が見えにくく、モチベーションが下がりやすいと感じる受験生もいるかもしれません。
このセクションでは、勉強に行き詰まった時にどう乗り越えるか、そして受験生を励ますメッセージや勉強時間を効率的に確保するコツについて解説します。
挫折しそうな時の乗り越え方
受験生を励ます英語の名言やメッセージ
勉強時間を効率的に確保するコツ
挫折しそうな時の乗り越え方
英語の勉強で挫折しそうになったら、まずは休息を取ることも重要です。
無理に頑張り続けると、かえって効率が落ちてしまいます。
気分転換に好きな音楽を聴いたり、短い散歩に出かけたりするのも良いでしょう。
小さな目標を設定し、それを達成する喜びを積み重ねることも有効です。
たとえば、「今日は単語を10個完璧にする」など、具体的な目標を設定してみてください。

受験生を励ます英語の名言やメッセージ
モチベーションが下がった時は、心に響く言葉が力になります。
たとえば、
“The only way to do great work is to love what you do.”
(素晴らしい仕事をする唯一の方法は、自分がしていることを愛することだ。)というスティーブ・ジョブズの言葉や、
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”
(成功は最終的なものではなく、失敗は致命的なものではない。大切なのは、続ける勇気である。)というウィンストン・チャーチルの言葉などは、受験生の皆さんを勇気づけてくれるでしょう。
これらのメッセージを読み、前向きな気持ちを保ちましょう。

参考記事:総合型選抜(AO入試)に向いている人・向いてない人・落ちる人の特徴を解説
勉強時間を効率的に確保するコツ
受験生にとって、時間は最も貴重な資源です。
効率的に勉強時間を確保するには、「隙間時間」の活用が鍵となります。
たとえば、通学中の電車の中や、食事の待ち時間など、たった5分でも英語の単語帳を開く習慣をつけましょう。
「ポモドーロ・テクニック」(25分集中+5分休憩を繰り返す)のような時間管理術を取り入れることで、集中力を維持し、効率的に学習を進めることができます。
【Q&A】受験生の英語勉強法に関する疑問を解決!
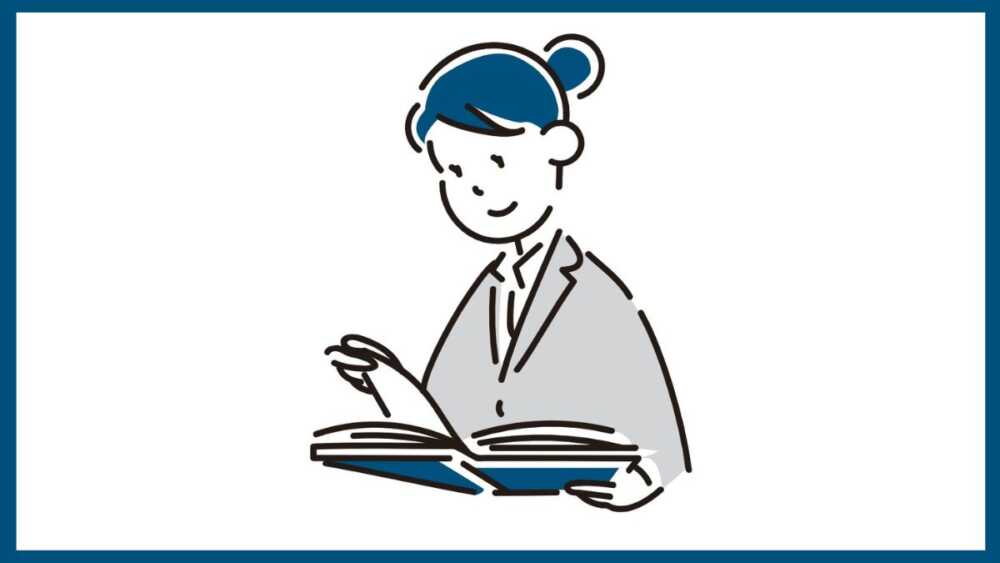
受験生の皆さんからよく寄せられる英語の勉強法の疑問にお答えします。
「何から手をつけて良いか分からない」「この時期から間に合うのか」といった共通の悩みを解決し、短期間で偏差値を爆上げするためのヒントを解説します。
受験英語の勉強の順番は?
定期テストで英語で100点を取る方法はありますか?
英語をペラペラに話すには何年かかる?
英語を勉強するにはまず何から?
受験英語の勉強時間はどれくらいが目安?
英語の勉強法は中学生と高校生でどう違う?
10月からの追い上げで英語は間に合う?
受験英語の勉強の順番は?
受験英語の勉強は、一般的に「単語・熟語」→「文法」→「英文解釈」→「長文読解・リスニング・英作文」の順に進めるのが効率的です。
完全に分けるのではなく、ある程度基礎が固まったら、並行して進めることで、総合的な英語力がバランス良く伸びていきます。

定期テストで英語で100点を取る方法はありますか?
定期テストで100点を取るためには、教科書と授業内容の完璧な理解が不可欠です。
・教科書本文の暗記:音読を繰り返して、スラスラ言えるようにしましょう。
・文法の徹底理解:授業で習った文法事項は、問題集で繰り返し演習し、使いこなせるようにします。
・ワーク・問題集の繰り返し:学校で配布されたワークは、完璧に解けるまで何度も繰り返しましょう。

英語をペラペラに話すには何年かかる?
「英語をペラペラに話す」という目標は、人それぞれですが、日常会話レベルであれば、集中的に学習すれば1〜2年で到達可能です。
ただし、ビジネスレベルや専門的な内容となると、さらに数年単位の継続的な学習が必要になります。
受験英語の勉強は、その基礎固めとして非常に役立ちます。

英語を勉強するにはまず何から?
英語を勉強する上でまず最初に取り組むべきは、英単語と英文法です。
この二つは英語の基礎の基礎であり、家を建てる際の土台のようなものです。
単語を覚え、文法のルールを理解することで、英文が少しずつ読めるようになり、英語学習の面白さを感じられるようになります。

受験英語の勉強時間はどれくらいが目安?
受験英語の勉強時間は、現在の英語力や志望校によって異なりますが、一般的には毎日2〜3時間を目標にすると良いでしょう。
たとえば、単語30分、文法1時間、長文読解1時間のように、分野ごとに時間を割り振るのがおすすめです。
特に「短期間で」偏差値を爆上げしたい場合は、集中して時間を確保することが重要です。

英語の勉強法は中学生と高校生でどう違う?
中学生の英語学習は、主に基礎的な文法と単語の習得が中心です。
高校生、特に受験生は、より複雑な構文の理解、長文読解の速読力、リスニング、英作文など、応用的なスキルが求められます。
中学生のうちに基礎をしっかり固めておくことが、高校生になってからのスムーズな学習につながります。

10月からの追い上げで英語は間に合う?
10月からの追い上げでも、英語は十分に間に合います!
諦める必要は全くありません。
重要なのは、残された時間を最大限に活用し、効率的な勉強法に切り替えることです。
具体的には、基礎の総復習を最優先し、頻出分野に絞って集中的に学習することで、「短期間で」偏差値を爆上げさせることは可能です。
まとめ:受験生必見!英語の勉強法【ゼロから始める】短期間で偏差値の爆上げを目指す

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「受験生必見!英語の勉強法【ゼロから始める】短期間で偏差値を爆上げ」は参考になりましたでしょうか?
まとめ:今日から実践!「短期間で」英語の偏差値を爆上げする勉強法
受験生必見!英語の勉強法【ゼロから始める】短期間で偏差値を爆上げ
この記事では、受験生が英語の偏差値を「ゼロから」短期間で爆上げするための具体的な勉強法と戦略を徹底的に解説してきました。
英語学習における多くの受験生が抱える悩みを解決するために、以下のロードマップに沿って実践的なアドバイスをお届けしましたね。
英語の成績が伸び悩む原因を明らかにし、あなたの勉強法がなぜ「ゼロから」やり直す価値があるのかを理解していただきました。
短期間で効果を出すための全体戦略として、現状把握と目標設定、基礎の徹底、アウトプット重視という3つのステップをご紹介。
「ゼロから始める」受験生のために、英文法、英単語・熟語、英文解釈の効率的な学習法を具体的に解説しました。
「短期間で」偏差値を伸ばすための応用学習として、長文読解、リスニング、英作文の各分野における実践的なスキルアップ術を惜しみなく公開。
限られた時間で成果を出すための具体的なヒントが満載です。
受験勉強でモチベーションが下がりそうな時のために、挫折しそうな時の乗り越え方や受験生を励ます英語の名言、そして効率的な勉強時間の確保術もお伝えしました。
最後に、受験生が抱える英語学習のよくある疑問にもQ&A形式で丁寧にお答えしました。
受験生におすすめ!オンライン塾の紹介
【オンライン塾】
高校生の英語に強いオンライン塾【OUTCOME】の料金・口コミ・特徴を徹底調査
オンライン自習室が無料で使える!高校生におすすめできる塾8選
【大学受験】オンラインコーチング塾徹底比較!高校生・浪人生の選び方・費用
コーチング塾とは?高校生におすすめ!オンラインコーチング塾20選
キミノスクールに興味のある方必見!【口コミ・評判・料金】を徹底調査!おすすめできるオンライン塾?
【武田塾みたいな塾】塾経験者がおすすめする塾10選!優れた指導で効果抜群
浪人生向けオンラインコーチング塾14選!逆転合格を叶える選び方と完全比較
AOI塾の料金は高い!他の総合型選抜専門塾と比較した結果は?
青チャートの正しい使い方!数学のレベル別に徹底解説【受験生必見】
【必見】オンライン家庭教師e-Liveの口コミ・評判・料金を徹底調査してみた!
AOI塾の料金は高い!他の総合型選抜専門塾と比較した結果は?
浪人生におすすめオンライン家庭教師26選!ランキング形式で徹底比較
浪人生の皆さん予備校はオンライン塾がおすすめな理由知ってます?

