大学受験日本史!おすすめ参考書&問題集17選!レベル別×合格への最強ルート
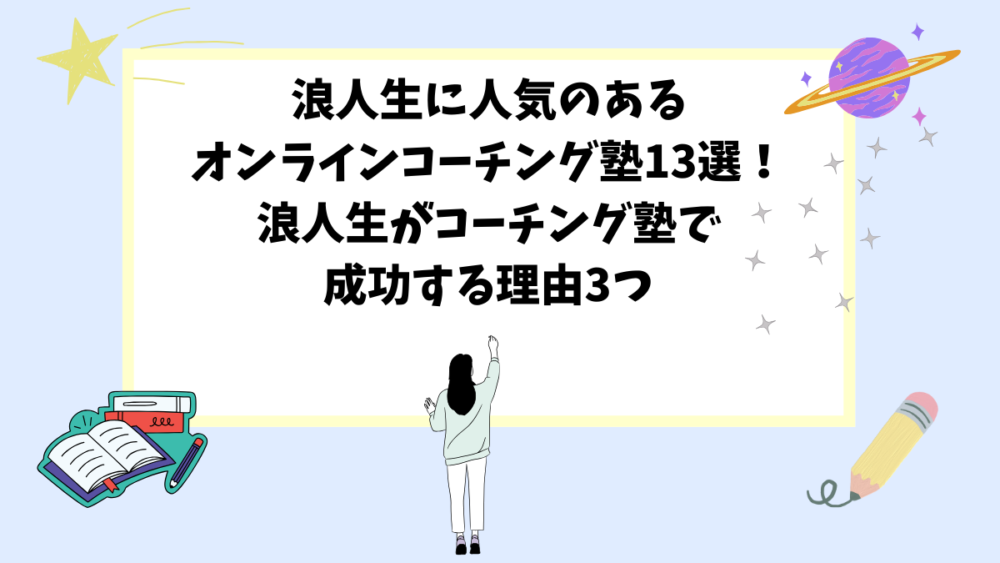
※この記事には一部PRが含まれます。
「大学受験の日本史、何から手をつければいいんだろう…」「新課程の『日本史探究』になって、参考書選びも変わったのでは?」
こんな悩みを抱えている皆さん、私も27年間学習塾で受験生を指導してきた経験から、その不安な気持ちはよく分かります。
志望校合格という大きな目標に向かう中で、自分にぴったりの参考書・問題集を選ぶことは、合格への最短ルートを見つけることと同じくらい重要です。
この記事では、長年の指導経験を持つ私が、数ある教材の中から本当に効果のあった日本史の参考書・問題集を厳選しました。
レベル別・目的別の選び方から、志望校合格まで導く「最強の日本史の参考書ルート」まで、あなたの疑問や不安にすべてお答えします。
塾経験者が語る!「失敗しない日本史の参考書選び」の鉄則
新課程「日本史探究」対応!レベル・目的別のおすすめ参考書15選
成績を爆上げする具体的な勉強法と参考書活用テクニック
受験生のよくある疑問に答えるQ&A
Contents
大学受験日本史、おすすめ参考書選びの「失敗談」から学ぼう!
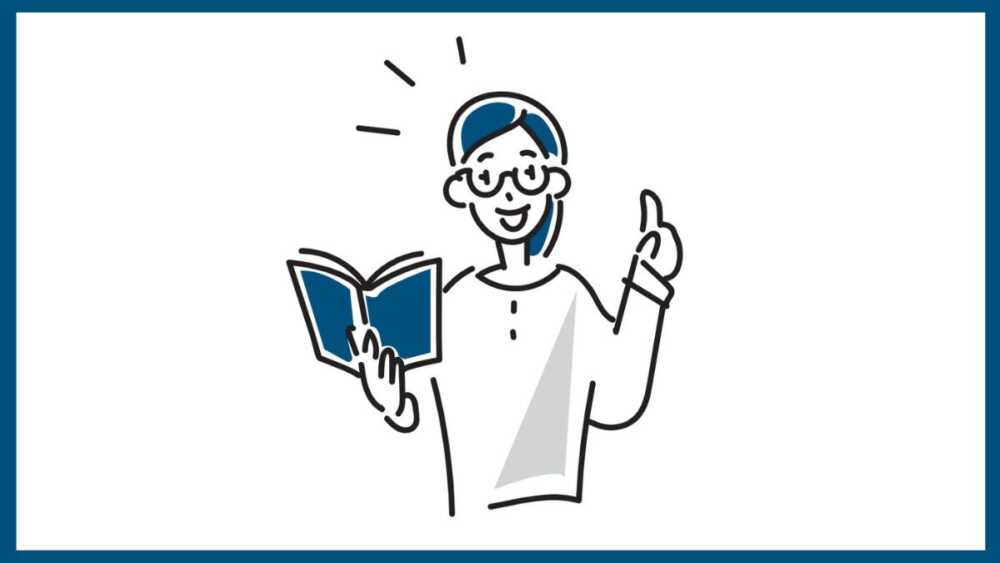
多くの受験生が日本史の参考書選びでつまづいてしまうのはなぜでしょうか?
ここでは、長年指導に携わってきた私が目にしてきた、よくある失敗例とその原因、そして失敗を避けるための鉄則をお伝えします。
新課程を履修中の皆さんも、自分に合った一冊を見つけるための第一歩として、ぜひ参考にしてください。
よくある失敗例:自分に合わない参考書を選んでしまうワケ
失敗しないための3つの鉄則!あなたの最強参考書を見つけるポイント
よくある失敗例:自分に合わない参考書を選んでしまうワケ
日本史の参考書選びで最も多い失敗は、自分の学力や学習スタイルに合わないものを選んでしまうことです。
例えば、書店で「これ良さそう!」と直感的に購入したり、友人が使っているからと安易に真似したりして、結局使わずに終わってしまうケースは少なくありません。
理由1:レベルが合っていない「背伸び」買い
難関大学を目指すからといって、いきなり難しい参考書に手を出すのは非常に危険です。
例えば、基礎が固まっていないのに分厚い論述対策の参考書を買ってしまうと、内容が理解できず、挫折の原因になってしまいます。
塾の現場でも、難易度の高い参考書を買ったものの、結局ほとんど手つかずで質問に来る生徒さんをよく見かけました。
まずは自分のレベルを正確に把握することが合格への第一歩です。
理由2:目的に合わない「とりあえず」買い
「とりあえず日本史の参考書を買っておこう」という曖昧な目的で購入すると、学習計画が立てられず、非効率な勉強につながります。
例えば、共通テスト対策が必要なのに、二次試験の論述問題集ばかりに取り組んでも、点数には繋がりません。
「みんな持っているから」という理由で有名な参考書を買っても、それが自分の学習目標に合っていなければ、時間の無駄になってしまうこともあります。
新課程「日本史探究」では思考力が問われるため、特に目的意識が重要です。
理由3:情報が古くて「非効率」な買い方
大学入試の傾向や出題形式は、毎年少しずつ変化しています。
特に共通テスト導入や新課程「日本史探究」への移行で、日本史の出題形式も進化しています。
古い情報や、最新の入試傾向に対応していない参考書を選んでしまうと、せっかく勉強しても本番で力を発揮できない可能性があります。
常に最新の情報にアンテナを張り、適切な参考書を選ぶようにしましょう。
特に新課程の皆さんは、教材の対応状況も確認してください。

参考記事:【日本史】年号を語呂合わせで暗記する【大学受験】語呂合わせ一覧
失敗しないための3つの鉄則!あなたの最強参考書を見つけるポイント
それでは、どうすれば失敗せずに自分にぴったりの参考書を見つけられるのでしょうか?
私が27年間、数多くの生徒を指導してきた中で見出した、確実に成功へと導くための3つの鉄則をお伝えします。
これらを意識して選べば、後悔しない一冊に出会えるはずです。
鉄則1:自分の実力を正しく知ろう
まずは、自分が今どれくらい日本史を理解できているのかを、正しく把握することが大切です。
・模試や学校のテストでの点数を確認
・どの時代・テーマが苦手かをチェック
・新課程の範囲で抜けがないかも要確認
私が務めていた学習塾では、最初にレベルチェックテストを行い、その結果に基づいて生徒さんに最適な参考書やカリキュラムを提案していました。
「知っているつもり」は禁物です。
新課程で学ぶ内容の理解度も確認してください。
鉄則2:ゴールから逆算して参考書を選ぶ
目標がはっきりしていないと、参考書選びもブレてしまいます。
・志望校や受験方式(共通テスト・記述試験など)を確認
・目標点数から「今やるべきこと」を逆算
・必要な対策に合わせて参考書を選ぶ
例えば、「共通テストで高得点を取りたい人」と「難関大の記述問題に強くなりたい人」では、選ぶべき参考書が違います。
具体的なゴールを決めておくと、自分にぴったりの参考書が見つかりやすくなります。
鉄則3:参考書は実際に手に取って選ぶ
ネットの評判だけで選ぶのではなく、自分の目で見て選ぶことが大切です。
・解説のわかりやすさ
・文字の見やすさ、大きさ
・図やグラフの使われ方、レイアウト
・自分が「読みやすい」と感じるかどうか
書店で参考書を開いて、「これなら続けられそう!」と感じるかを確かめましょう。
新課程に対応しているかも、忘れずにチェックしてください。
直感的な「これだ!」という感覚も、実はとても大切です。
必要な参考書を見つけるには、「実力を知る → ゴールを決める → 実際に選ぶ」の順番を意識しましょう。
日本史参考書の種類と役割:あなたの学習計画を明確にしよう!

日本史の参考書と一口に言っても、その種類は様々です。
それぞれが異なる役割を持っているので、闇雲に手を出すのではなく、自分の学習段階や目的に合わせて使い分けることが効率的な学習の鍵となります。
ここでは、主要な参考書の種類とその役割を解説します。
新課程の「日本史探究」を学ぶ皆さんにも共通する基本的な考え方です。
歴史の流れを掴む「講義系参考書」:日本史の土台作り
知識を定着させる「一問一答・用語集」:暗記の質を高める
実力アップの鍵!「問題集」:アウトプットで定着
視覚で覚える「資料集・図録」:イメージ記憶を強化
合格へ導く「過去問」:出題傾向と弱点把握
歴史の流れを掴む「講義系参考書」:日本史の土台作り
講義系参考書は、歴史の出来事を単なる暗記ではなく、「なぜそうなったのか」「どのような背景があったのか」といった因果関係や流れを理解するためのものです。
教科書よりも砕けた表現で書かれており、まるで授業を受けているかのように読み進められます。
例えば、「金谷の日本史『なぜ』と『流れ』がわかる本」や「石川晶康 日本史講義の実況中継シリーズ」などが代表的です。
講義系の参考書は日本史学習の土台をしっかりと築くために欠かせません。
新課程の思考力重視の学習にも役立ちます。

参考記事:【日本史の覚え方】3ステップで主要人物・年号・流れを暗記する最強術!
知識を定着させる「一問一答・用語集」:暗記の質を高める
一問一答や用語集は、主に知識のインプットと定着を目的とした参考書です。
短い質問と答えで構成されており、移動時間やスキマ時間にも手軽に利用できます。
「日本史一問一答」や「日本史用語集」などが有名です。
一問一答や用語集の参考書は、覚えた知識を「引き出す」練習をすることで、暗記の質を高め、忘れにくくする効果があります。
私は生徒に、「本当に覚えているかどうか」を確かめるために、こまめに一問一答でチェックするように伝えていました。
なぜなら。ただ覚えた“つもり”で終わらせず、自分の記憶をしっかり確認することが大切だからです。

実力アップの鍵!「問題集」:アウトプットで定着
問題集は、インプットした知識が本当に身についているかを確認し、実践力を養うためのものです。
様々な形式の問題を解くことで、自分の弱点を発見し、知識の抜け漏れを補強することができます。
例えば、共通テスト形式の問題集や、志望校のレベルに合わせた記述・論述問題集などがあります。
「問題を解く」というアウトプットの作業は、新課程「日本史探究」で求められる思考力や判断力を養うためにも不可欠なステップです。

参考記事:日本史の勉強法は教科書をよく読む!【これならできる日本史の勉強】
視覚で覚える「資料集・図録」:イメージ記憶を強化
資料集や図録は、写真や図、グラフ、地図などの視覚情報が豊富に掲載されている参考書です。
文字情報だけではイメージしにくい歴史の場面や文化、経済状況などを具体的に理解するのに役立ちます。
「山川詳説日本史図録」などは、多くの受験生が活用しています。
視覚情報は記憶に残りやすく、特に文化史や外交史などで大きな効果を発揮します。
新課程の資料読解問題にも対応するためにも、講義系参考書や教科書と併用して活用しましょう。

参考記事:「歴史総合」と「日本史探究」の違いとは?科目選択で後悔しない完全ガイド
合格へ導く「過去問」:出題傾向と弱点把握
過去問は、志望校の出題傾向を把握し、時間配分の練習、そして自分の弱点を洗い出すための最も重要な参考書です。
ただ解くだけでなく、なぜ間違えたのか、どうすれば正解できたのかを徹底的に分析することが大切です。
私は生徒たちに、過去問は「宝の山」だと常に伝えていました。
共通テストの過去問はもちろん、志望校の二次試験の過去問は、必ず数年分は解いて分析するようにしましょう。
新課程の入試形式にも対応できるよう、最新版の過去問を入手してください。
【個別指導が定額で受け放題】
\偏差値40から難関大学合格/
受験勉強のストレスから解放される
合格までの最短ルートがわかる
偏差値がグングン上がる!
資料請求は成功への第一歩
【基礎固め・日本史が苦手なあなたへ】おすすめの参考書

ここからは、私が27年間塾で教えてきた経験をふまえて、大学受験の日本史に本当に役立つ参考書を、皆さんの今のレベルや勉強の目的に合わせて、わかりやすく紹介していきます。
「日本史って、何から始めればいいの?」「歴史の流れが全然つかめない…」と悩んでいる人も多いと思います。
そんな不安や苦手意識をなくして、自信を持って日本史の勉強を始められるような、オススメの参考書を紹介します。
詳説日本史探求
詳説日本史ノート
日本史用語集
日本史一問一答
図説 日本史通覧
『詳説日本史探究』(山川出版社)
■『詳説日本史探究』(山川出版社)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年1月1日 |
| 対応レベル | 高校標準〜MARCH・難関大レベル(教科書) |
| 特徴・メリット | ・全国の高校で広く使用されている日本史教科書の定番 ・新課程に完全対応、最新の研究成果や一次史料も収録 ・MARCH〜早慶レベル入試では、この教科書の知識が基礎になる |
| 向いている人 | ・学校で使用しており、予習・復習のベースにしたい人 ・正確かつ網羅的に知識を身につけたい人・論述・史料問題の背景を深く理解したい人 |
| 勉強時間の目安 | 焼く40時間 |
| 分類 | インプット用の参考書 |
『日本史探究 詳説日本史ノート』(山川出版社)
■『日本史探究 詳説日本史ノート』(山川出版社)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年3月28日(新課程対応版) |
| 対応レベル | 高校標準〜MARCH基礎レベル(教科書準拠) |
| 特徴・メリット | ・『詳説日本史探究』に完全準拠した穴埋め式ノート ・重要語句や通史の流れを効率よく復習、定着できる ・書き込み式で能動的に学習しやすく、記憶の定着に効果的 |
| 向いている人 | ・『詳説日本史探究』を使っている高校生 ・教科書の重要事項を効率的に定着させたい人 ・スキマ時間に復習や確認学習を進めたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約40時間 |
| 分類 | ノート系の参考書 |
山川出版社の「詳説日本史ノート」は、インプット系とアウトプット系の両方を兼ね備えたノート系の参考書。
詳説日本史ノートを読みすすめることで、インプットの学習ができ、空欄を埋めることでアウトプットの学習もできる参考書。
インプットした日本史の知識を書き込んで、自分専用の参考書が作れます。
『日本史用語集(山川出版)』
■『日本史用語集(山川出版)』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年12月22日 |
| 対応レベル | 全レベル(高校基礎〜難関大) |
| 特徴・メリット | ・日本史全範囲の用語を網羅し、辞書的に使える ・各用語に詳細な解説、関連語、補足情報を掲載 ・新課程「探究」に対応し、最新の歴史用語や解釈も反映 |
| 向いている人 | ・学習中に知らない用語をすぐ調べたい人 ・論述問題や記述式対策で正確な語句を確認したい人 ・知識の深掘りや背景理解を重視したい人 |
| 分類 | 用語集 |
山川出版社の「日本史用語集」は、多くの高校で教科書や資料集と一緒に配布されています。
この日本史用語集は、日本史の知識を補完するためのとても有効な参考書です。
「日本史用語集」は簡単に言えば、日本史の用語がたくさん掲載されている辞書のようなものであり、わからない単語や細かいことまで知りたいときに、日本史用語集で調べて解決します。
『山川一問一答 日本史探究』
■『山川一問一答 日本史探究』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年1月24日 |
| 対応レベル | 共通テスト〜MARCHレベル(一問一答) |
| 特徴・メリット | ・日本史の重要用語を網羅的に収録し、暗記・確認に最適・新課程「日本史探究」に完全対応、最新用語や概念もカバー ・頻出度が★の数で明示されており、優先順位をつけて効率学習できる |
| 向いている人 | ・用語を徹底的に覚えたい人 ・知識の抜けや曖昧さをチェックしたい人 ・スキマ時間で効率よく復習したい人 |
| 勉強時間の目安 | 約60時間 |
| 分類 | アウトプット系の参考書 |
必要な部分から確実に、日本史の知識を身につけるには、山川出版社の「日本史一問一答」形式の問題集を使うとよいでしょう。
「日本史一問一答」問題集は、日本史の勉強を進める上での第一段階ともいえる知識の定着に大きな効果があります。
短期間で最も効率よく頻出用語を暗記できるのが「日本史一問一答」の特徴です。
日本史のおすすめ参考書:図説 日本史通覧
■図説日本史通覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年2月20日(印刷) |
| 対応レベル | 共通テスト~MARCH・国公立2次レベル(資料問題・論述力養成) |
| 特徴・メリット | ・大学入試対策に最適な資料集で、視覚資料と文章資料を多数掲載 ・資料読解を通して論述力・思考力が身につく・「ヒストリースコープ」「考察」など、資料から読み解く力を育てる仕組みが豊富 ・世界史との関連も学べる「東アジア全図」「そのころの世界」などの特集付き |
| 向いている人 | ・共通テストや国公立の資料問題、論述問題対策をしたい人 ・資料集を使って深い理解を得たい人・日本史の背景や関連性をビジュアルで把握したい人 |
| 勉強時間の目安 | 約60〜80時間(通読+資料確認+演習) |
| 分類 | インプット+資料読解系参考書(資料集+演習) |
インプット系:おすすめ日本史の参考書6冊

インプット系:おすすめ日本史の参考書5冊についてまとめてみました。
以下のおすすめ参考書について紹介しています。
時代と流れで覚える!日本史用語
きめる!共通テスト 歴史総合+日本史探究
大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本
『金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本』シリーズ
『金谷の歴史総合「なぜ」と「流れ」がわかる本』
日本史実況中継
『時代と流れで覚える!日本史用語 』
■『時代と流れで覚える!日本史用語(文英堂)』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年7月3日 |
| 対応レベル | 高校入門〜共通テスト、日大レベル(用語暗記・通史理解) |
| 特徴・メリット | ・用語を「時代の流れ」に沿って整理し、因果関係と背景理解を促進・新課程「日本史探究」に対応した構成で、思考力重視の学習ができる ・図やイラストが多く、視覚的に理解しやすい作り |
| 向いている人 | ・一問一答が苦手で、流れの中で覚えたい人 ・用語の背景や意味を大事にしたい人 ・新課程の出題形式(資料読解・考察)に慣れたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約40時間 |
| 分類 | インプット系の参考書 |
「時代と流れで覚える」は日本史に苦手意識がある人でもすらすらと読めて、受験勉強の基礎固めが1冊でできる、講義形式の参考書。
最短距離で日本史の流れがわかるように、日本史の軸となる政治史を中心に、丁寧に解説されています。
これから日本史を勉強する人も「日本史教室」から、取り組むと良いでしょう。
『きめる!共通テスト 歴史総合+日本史探究』
■『きめる!共通テスト 歴史総合+日本史探究』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年7月4日 |
| 対応レベル | 共通テストレベル(標準) |
| 特徴・メリット | ・共通テストの出題傾向に特化した構成で、効率的に得点力アップ ・図表・グラフ・史料の読み取り方をわかりやすく解説 ・歴史総合と日本史探究の融合型問題への対応力を養成 ・短期間でも成果が出やすいコンパクトな講義形式 |
| 向いている人 | ・共通テスト対策に集中したい人 ・限られた時間で効率よく得点力を上げたい人 ・史料や図表を使った実践的な問題形式に慣れたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約40時間 |
| 分類 | インプット系の理解本 |
『大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本』
■『大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年11月14日 |
| 対応レベル | 高校基礎〜共通テスト満点狙い(標準〜応用) |
| 特徴・メリット | ・20年以上愛され続けた定番の共通テスト対策本、改訂版で新課程に対応・「タテのつながり(時系列)」と「ヨコのひろがり(他分野・世界史との関連)」を視覚的に整理できる年表付き ・史料・図版・写真の読解に強く、共通テスト特有の出題に対応 ・歴史総合の視点から近世・近代以降の世界史的背景も補強 ・基礎の基礎から丁寧に解説しており、0から100までを目指せる構成 |
| 向いている人 | ・共通テストで高得点(80〜100点)を目指す人 ・単なる暗記ではなく、つながりや背景も理解したい人 ・資料・史料読解問題に苦手意識がある人 ・歴史総合と日本史探究をまとめて対策したい人 |
| 勉強時間の目安 | 約50時間 |
| 分類 | インプット系の理解本 |
『金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本』シリーズ
■『金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本』(原始・古代史)(中世・近世史)(近現代史)全3冊
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年3月12日(近現代史) |
| 対応レベル | 高校入門〜共通テスト、日大レベルの基礎固め |
| 特徴・メリット | ・「なぜ」「どのように」という視点で歴史の流れを解説 ・会話形式の講義スタイルで読みやすく、臨場感がある・因果関係や背景を深く理解できる構成。新課程に対応 |
| 向いている人 | ・通史を体系的に理解したい人 ・歴史の流れがつかみにくいと感じている人 ・暗記中心の勉強に限界を感じている人、楽しく学びたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約40時間 |
| 分類 | インプット系の理解本 |
『金谷の歴史総合「なぜ」と「流れ」がわかる本』
■『金谷の歴史総合「なぜ」と「流れ」がわかる本』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年3月19日 |
| 著者 | 金谷 俊一郎 |
| 対応レベル | 高校入門〜共通テストレベル(歴史総合の理解・定着) |
| 特徴・メリット | ・「なぜ」と「流れ」に着目して歴史総合をわかりやすく解説 ・近現代のグローバルな動きや日本との関係性を通して学べる ・会話形式の講義スタイルで初学者にも読みやすい ・新課程「歴史総合」の教科書内容を体系的にカバー |
| 向いている人 | ・新課程の歴史総合を基礎から理解したい人 ・通史の大まかな流れと因果関係を把握したい人 ・講義形式でテンポよく学びたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約40時間 |
| 分類 | インプット系の理解本 |
『日本史探究授業の実況中継(実況中継シリーズ)』
■日本史探究授業の実況中継(実況中継シリーズ)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2023年10月24日(新課程対応版 全4冊) |
| 対応レベル | 日大レベル〜MARCHレベル |
| 特徴・メリット | ・石川晶康先生の人気講義を再現した講義形式の参考書・要点が整理されており、理解しやすく学習のペースがつかみやすい ・新課程に対応し、入試頻出テーマや出題傾向に沿った構成 |
| 向いている人 | ・講義形式でテンポよく学習したい人 ・独学でも理解しやすい教材を求める人 ・MARCH対策で差がつくポイントを効率よく学びたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約80時間 |
| 分類 | インプット系の理解本 |
「日本史実況シリーズ」は、全4冊のシリーズ本。
この4冊で日本史の文化史も含めて大学受験に必要な日本史の知識がこの4冊に網羅されています。
以上、インプット系の参考書について紹介しました。
アウトプット系:日本史のおすすめ問題集5冊

アウトプット系:日本史のおすすめ問題集5冊についてまとめてみました。
以下のおすすめ問題集について紹介しています。
高校 とってもやさしい歴史総合
時代と流れで覚える! 日本史用語
実力をつける日本史100題
HISTORIA[ヒストリア] 日本史探究精選問題集
大学入学共通テスト実戦問題集 歴史総合、日本史探究
高校 とってもやさしい歴史総合
■高校 とってもやさしい歴史総合
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2022年4月19日 |
| 対応レベル | 高校基礎レベル(新課程「歴史総合」初学者向け) |
| 特徴・メリット | ・基礎の基礎に絞った内容で、短期間でやり切れる構成 ・図版ややさしい文章で理解しやすく、流れをつかみやすい ・「ここだけ!」で最重要点を素早く確認できる ・空欄補充→文章読解で、因果関係を自然に理解できる |
| 向いている人 | ・歴史が苦手な高校1・2年生 ・とにかくやさしい入門書を探している人 ・定期テストや共通テスト対策の基礎固めをしたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約10〜15時間(全160ページを軽く読み進めるペース) |
| 分類 | インプット+簡易アウトプット系(入門~基礎確認レベル) |
時代と流れで覚える! 日本史用語
■時代と流れで覚える!日本史用語
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年7月3日 |
| 対応レベル | 共通テスト〜MARCH・国公立二次(論述対策にも対応) |
| 特徴・メリット | ・新課程「日本史探究」に対応し、現代史を増補 ・入試頻出の重要用語を厳選し、共通テスト・私大・国公立対策に活用可能 ・見開き構成で視覚的に理解しやすく、表・地図・文章の流れで知識を整理できる ・3ステップ学習(まとめ→穴埋め→文章)+赤シート対応で効率的な暗記が可能 |
| 向いている人 | ・短時間でインプットを一気に進めたい人 ・流れの中で用語を理解し記憶に残したい人 ・視覚的に歴史の全体像をつかみたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約20〜30時間(通史+用語確認を繰り返しながら学ぶスタイル) |
| 分類 | インプット+アウトプット補助型(まとめ・チェック・流れ理解の総合参考書) |
実力をつける日本史100題
■日本史おすすめ問題集:実力をつける日本史100題
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2013年3月8日 |
| 対応レベル | 共通テスト〜国公立二次・私大中〜上位(MARCH〜旧帝大・早慶レベルまで対応) |
| 特徴・メリット | ・Z会オリジナルの良問を厳選し、時代別・テーマ別・論述問題まで網羅 ・見開きで問題+目標時間+配点が一目でわかる構成 ・解説編は参考書レベルの詳しさで、理解を深める構成 ・論述問題には要素ごとの配点も明示され、実戦力アップに最適 |
| 向いている人 | ・共通テストから国公立・難関私大の記述・論述対策を行いたい人 ・一問一答や用語暗記だけでなく、実践的なアウトプットをしたい人 ・過去問に入る前の演習素材として最適な問題集を探している人 |
| 勉強時間の目安 | 約40〜60時間(1日2題ペースで約50日) |
| 分類 | アウトプット系問題集(時代別・テーマ史・論述問題を含む総合演習書) |
HISTORIA[ヒストリア] 日本史探究精選問題集
■HISTORIA[ヒストリア] 日本史探究精選問題集
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2025年6月26日 |
| 対応レベル | 共通テスト〜難関国公立・私立大(MARCH〜早慶・旧帝大レベル) |
| 特徴・メリット | ・全100題で通史・文化史・テーマ史を網羅する構成 ・入試の良問+オリジナル問題で重要用語カバー率を最大化 ・問題ごとに「単元を限定」し、効率よく復習できる ・解説は問題編と同じ厚さで丁寧・詳細・実戦的な演習を通じて、本番対応力を高められる |
| 向いている人 | ・共通テスト〜二次試験レベルの総合演習に取り組みたい人 ・単元ごとに演習と復習を効率的に進めたい人 ・通史だけでなく文化史・テーマ史もバランスよく演習したい人 ・詳しい解説で理解を深めたい人 |
| 勉強時間の目安 | 約60〜80時間(1日2〜3題ペースで約1〜1.5ヶ月) |
| 分類 | アウトプット系問題集(総合演習/通史・文化史・テーマ史・論述問題の総合演習書) |
大学入学共通テスト実戦問題集 歴史総合、日本史探究
■大学入学共通テスト実戦問題集 歴史総合、日本史探究
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発売日 | 2024年8月26日 |
| 対応レベル | 共通テストレベル(基礎〜標準) |
| 特徴・メリット | ・代々木ゼミナールが作成した共通テスト形式のオリジナル予想問題を3回分収録 ・2024年度共通テスト本試験、2022年試作問題、模試問題なども収録・マークシート形式で本番さながらの演習が可能 ・出題傾向分析と学習アドバイス付き |
| 向いている人 | ・共通テストの実戦演習を行いたい人 ・過去問だけでなく、新傾向の予想問題で慣れておきたい人 ・マーク式の演習に不安がある人 |
| 勉強時間の目安 | 約15〜20時間(1回分×3〜5セットを実施・復習まで含めて) |
| 分類 | アウトプット系問題集(共通テスト予想問題集/実戦演習) |
【独学でも安心】塾なしで日本史を極めるためのおすすめの参考書セット

「塾に通っていないけれど、日本史でしっかり点数を取りたい!」という方も安心してください。
適切な参考書を組み合わせれば、独学でも十分高得点を目指せます。
ここでは、私が塾で教えていた生徒の中にも、独学で難関大に合格した例を参考に、独学におすすめの参考書セットをご紹介します。
| タイプ | おすすめ参考書 | 使い方(独学のポイント) |
|---|---|---|
| 講義系 | 金谷の日本史『なぜ』と『流れ』がわかる本(新課程対応版) | まずは全体の流れを理解する。繰り返し読み、内容を自分の言葉で説明できるようにする。 |
| 用語集 | 日本史一問一答、日本史用語集 | 講義系と並行して使い、知識の抜け漏れがないか確認。赤シートを活用し、知らない用語は教科書や講義系の参考書で確認する。 |
| 問題集 | 大学入試 全レベル問題集 日本史(日本史探究) 1 基礎レベル 、共通テスト過去問:日本史 | インプット後のアウトプット用として使用。解きっぱなしにせず、解説をしっかり読み、なぜ間違えたのかを分析する。間違えた問題は必ず復習する。 |
| 補助教材 | 山川詳説日本史図録(最新版) | 講義系や用語集で学ぶ際に、関連する図や写真を一緒に見て、視覚的に記憶する。資料読解の練習にもなり、新課程対策にも効果的。 |
■大学入試 全レベル問題集 日本史(日本史探究) 1 基礎レベル
| 項目 | 詳細情報 |
|---|---|
| 書名 | 大学入試 全レベル問題集 日本史(日本史探究) 1 基礎レベル 新装新版 |
| 著者 / 出版社 | 太田尾智之 / 旺文社 |
| 対象レベル | 初級者向け~中級者向け:日本史が苦手な人、受験対策の第一歩におすすめ |
| 種類 / 目的 | 問題集:基礎から入試対策までの幅広いレベルに対応 |
| 特徴・強み | 高校基礎~入試対策レベルまで対応。過去問から厳選された問題を収録し、時系列順に25テーマ構成。丁寧でわかりやすい解説により、日本史が苦手な人でも理解しやすい。重要事項の「流れ」がつかみやすく、初学者にも使いやすい構成。 |
| 注意点・弱み | 基礎レベル中心の内容のため、難関大を目指す場合は上級レベルの問題集が必要。使用法の詳細なガイドが少なく、自己管理が求められる。 |
| 効果的な使い方 | 通史学習と並行し、問題演習を進めながら基礎知識を定着させる。解説を読み込み、「なぜその答えになるのか」を理解することが重要。苦手な時代・テーマを重点的に演習することで効率的な弱点克服が可能。 |
独学のポイントは、「自習の質」を徹底的に高めることです。
参考書を使ってインプットした知識を、問題集でアウトプットし、間違えたらすぐに復習するというサイクルを徹底しましょう。
一人で勉強しているとモチベーションが下がることがあるかもしれませんが、定期的に模擬試験を受けて自分の成長を確認したり、SNSなどで同じ目標を持つ仲間と情報交換したりするのもおすすめです。
日本史の成績を爆上げ!参考書を最大限に活用する勉強法

どんなに良い参考書を持っていても、その使い方を間違えてしまうと成績は伸びません。
ここでは、私が27年間、数多くの生徒を指導してきた経験に基づき、日本史の成績を劇的に伸ばすための具体的な勉強法と、参考書を最大限に活用するテクニックを惜しみなくお伝えします。
新課程「日本史探究」を学ぶ皆さんにも、必ず役立つ情報です。
日本史は「流れ」が命!年号暗記に頼らない学習法
覚えた知識を定着させる!効果的な暗記術
参考書を「読んで終わり」にしない!活用テクニック
いつから始める?日本史の理想的な年間スケジュールと学習時間
日本史は「流れ」が命!年号暗記に頼らない学習法
「日本史は年号をひたすら暗記する科目」と思っていませんか?
実は、それは大きな誤解です。
年号を丸暗記するだけでは、入試で問われる「なぜ?」「どうして?」といった本質的な理解には繋がりません。
日本史の学習で最も大切なのは、歴史の「流れ」を掴むことです。
特に新課程では、単なる知識だけでなく、歴史的思考力や判断力が問われます。
時代ごとの特徴を掴む「縦のつながり」
まずは、原始・古代から近現代まで、それぞれの時代ごとの特徴や主要な出来事を掴みましょう。
例えば、鎌倉時代は武士の台頭、室町時代は文化の成熟と地方の勢力争い、といった大まかな流れを理解します。
私は生徒に、各時代の始まりと終わり、そしてその時代を特徴づけるキーワードをノートに書き出すよう指導していました。
これが、日本史を深く理解する縦軸になります。
同時期の出来事を比較する「横のつながり」
次に重要なのが、同じ時期に日本各地や世界で何が起こっていたのかという「横のつながり」を意識することです。
例えば、織田信長が活躍していた戦国時代には、京都ではどんな文化が栄えていたのか、同じ時代に他の大名はどんな動きをしていたのか?
こうした事柄を関連付けて考えることで、歴史の流れがつながり、知識が定着しやすくなります。
特に、外交史や文化史、経済史でこの「横のつながり」を意識すると、理解度が格段に深まります。
新課程の多角的視点で歴史を捉えるためにも重要です。

覚えた知識を定着させる!効果的な暗記術
日本史は知識量が多いため、効率的な暗記術が不可欠です。
ただ黙々と暗記するのではなく、脳の特性を活かした工夫をすることで、記憶の定着率を格段に上げることができます。
新課程でも、やはり知識の定着は基本です。
「アウトプット中心」の反復練習サイクル
人間の脳は、「思い出す」作業を繰り返すことで記憶が強化されます。
ただ講義系参考書を読むだけでなく、一問一答や問題集を使ってアウトプットを繰り返すことを意識しましょう。
例えば、「参考書を読む→一問一答で確認→間違えたところをもう一度参考書で確認」というサイクルを回します。
私は生徒に、「とにかく声に出して答えを言ってみてごらん」と勧めていました。
この方法は新課程の学習にも有効です。
「寝る前5分」で暗記効率アップ!
寝る前の時間は、記憶の定着に非常に効果的です。
日中に学習した内容を、寝る前にわずか5分でもいいので復習してみてください。
例えば、一問一答を数ページめくるだけでも、脳はその情報を整理し、長期記憶として定着させようとします。
この「寝る前5分」の習慣は、多くの難関大学合格者が実践していたテクニックの一つです。
新課程の複雑な知識も、これで効率的に記憶できます。
苦手な時代・分野は「集中特訓」する
すべての時代・分野を均等に学習するのではなく、自分の苦手な時代や出題頻度の高い分野に特化して、集中的に取り組む時間を作りましょう。
例えば、文化史が苦手なら文化史に特化した問題集を解いたり、特定の時代の流れが掴めないならその部分の講義系参考書を何度も読み込んだりします。
弱点を克服することが、全体の点数アップに繋がります。
新課程で特に強化された近現代史も、必要に応じて集中特訓しましょう。

参考書を「読んで終わり」にしない!活用テクニック
せっかく購入した参考書を最大限に活かすためには、「読んで終わり」にしてはいけません。
参考書を「自分だけの最高の教材」に変えるための具体的な活用テクニックをご紹介します。
新課程の学習にもそのまま応用できます。
付箋やマーカーで「自分だけの参考書」にカスタマイズ
参考書に積極的に書き込みをしたり、付箋やマーカーで印をつけたりしましょう。
例えば、重要語句にはマーカー、関連情報には付箋でメモ、疑問点には疑問符をつけるなど、自分なりのルールを決めてカスタマイズします。
これは、「この参考書は自分が一生懸命勉強した証拠だ」というモチベーションにも繋がり、復習の際にも「どこが重要か」「どこが苦手だったか」が一目で分かります。
間違えた問題は「〇〇ノート」で徹底管理
問題集で間違えた問題は、必ず「間違い直しノート」(や、ルーズリーフ、単語カードでもOK)に記録しましょう。
問題と正解だけでなく、「なぜ間違えたのか」という原因(知識不足、読み間違いなど)と、「どうすれば正解できたのか」という改善策を具体的に書き込みます。
このノートには、自分の苦手がまとめられているため、成績アップのヒントがつまった「伸びしろノート」と言えます。
定期的に見直すことで、同じ間違いを繰り返さなくなります。
参考書と問題集の「完璧な連携」方法
講義系参考書でインプットした知識を、問題集でアウトプットする際は、常に両方を連携させて学習しましょう。
例えば、問題集で間違えた部分があれば、すぐに講義系参考書や用語集に戻って関連箇所を確認します。
私は生徒たちに、「参考書は辞書のように使うんだよ」と教えていました。
この連携作業を繰り返すことで、知識はより深く、正確に定着します。
新課程の多角的な学びにも繋がります。

いつから始める?日本史の理想的な年間スケジュールと学習時間
「日本史の勉強、いつから始めるのがベストなんだろう?」という疑問は、多くの受験生が抱くものです。
ここでは、皆さんの学年や状況に合わせた、日本史学習の理想的な年間スケジュールと勉強時間の目安をご紹介します。
高校2年生:基礎を固め、興味を深める時期
高校2年生は、日本史の基礎をじっくりと固めるのに最適な時期です。
高校2年生の間に無理に全範囲を終わらせる必要はありません。
講義系参考書で歴史の流れを掴むこと、そして興味を持った時代や人物について深く調べてみるなど、日本史に親しむことを意識しましょう。
週に3~5時間程度、継続して学習する習慣をつけることが大切です。
塾では、この時期に日本史の面白さを伝えることに注力していました。
高校3年生:共通テスト・二次対策に集中する時期
高校3年生になると、いよいよ本格的な受験勉強がスタートします。
高校3年生は、共通テスト対策と志望校の二次試験対策に集中しましょう。
夏までに全範囲のインプットを終え、夏以降は問題演習と過去問対策に時間を割くのが理想的です。
週に8~10時間程度を目安に、計画的に学習を進めましょう。
模試の結果を分析し、苦手分野を徹底的に潰すことが合格へのカギです。
新課程の出題傾向にも注意してください。
浪人生:弱点克服と総仕上げの時期
浪人生は、前年の反省を踏まえ、自分の弱点を徹底的に克服するチャンスです。
特に日本史は、知識の抜け漏れがないか、論述対策は十分かなど、より深い理解と応用力が求められます。
年間を通して計画を立て、週に10時間以上を目安に、質の高い学習を継続しましょう。
私は浪人生の生徒に、「同じ間違いは二度としない」という強い気持ちで臨むよう指導していました。
新課程の思考力を問う問題にも対応できるよう、深く掘り下げた学習が重要です。
大学受験:日本史のおすすめ参考書に関するよくある質問Q&A
長年、多くの受験生と接してきた中で、日本史の学習に関してよく聞かれる質問があります。
ここでは、皆さんが抱えるであろう疑問や不安に、私の経験を交えながらお答えしていきます。
もちろん、「日本史探究」を学ぶ皆さんの疑問にもお答えします。
Q1:日本史は暗記科目って本当ですか?
Q2:独学でも日本史で高得点は狙えますか?
Q3:共通テストでしか日本史を使わない場合も、二次対策の参考書は必要ですか?
Q4:日本史の勉強でモチベーションが下がってしまったらどうすればいいですか?”
Q1:日本史は暗記科目って本当ですか?
A1:半分は本当で、半分は違います。
確かに、日本史は年号や人名、出来事の名前など、覚えるべき知識がたくさんあります。
ただ丸暗記するだけでは、入試で高得点を取るのは難しいでしょう。
なぜなら、大学入試の日本史は、知識だけでなく「なぜそれが起こったのか」「その出来事が社会にどう影響したのか」といった因果関係や背景理解を問う問題が増えているからです。
新課程の「日本史探究」では、この「なぜ」や「どうして」を考察する力がさらに重視されます。
私が教えていた生徒の中には、最初はひたすら年号を覚えようとしていた生徒もいましたが、歴史の「流れ」を意識して学習するようにアドバイスすると、驚くほど成績が伸びました。
【重要ポイント】
・流れの理解:「なぜ」が分かれば「何」も覚えやすくなります。
・アウトプット:覚えた知識を使って問題を解くことで、使える知識になります。
表面的な暗記だけでなく、深い理解を伴う学習を心がけてください。

Q2:独学でも日本史で高得点は狙えますか?
A2:はい、独学でも十分に高得点を狙うことは可能です。
実際に、私の塾の生徒の中にも、塾に通わず独学で日本史で高得点を叩き出し、難関大学に合格した生徒はたくさんいました。
独学で成功するための鍵は、「計画性」と「情報収集」、そして「正しい参考書の選び方と使い方」です。
塾では個別の進捗管理や質問対応ができましたが、独学の場合はそれらを自分で補う必要があります。
【独学成功のヒント】
・年間計画を立てる:いつまでにどの範囲を終わらせるか、具体的に計画を立てましょう。
・定期的に模試を受ける:自分の実力と弱点を客観的に把握するために、模試は欠かさずに受験しましょう。新課程対応の模試も積極的に活用してください。
・質問できる環境を作る:学校の先生や、信頼できる先輩など、困った時に質問できる人を見つけておくと安心です。
この記事の「【独学でも安心】塾なしで日本史を極めるための参考書セット」も参考にしてください。

Q3:共通テストでしか日本史を使わない場合も、二次対策の参考書は必要ですか?
A3:基本的には必要ありませんが、一部例外もあります。
共通テストのみで日本史を使うのであれば、共通テストに特化した対策で十分です。
二次試験対策用の参考書は、記述・論述問題や、共通テストよりもはるかに深い知識が問われるため、非効率になってしまいます。
特に新課程の共通テストは、史料やグラフを用いた思考問題が増える傾向にあるため、そこに特化した対策が重要です。
ただし、例外として以下のケースでは検討の余地があります。
・共通テストで満点に近い高得点を目指す場合:より網羅的な知識を身につけるために、一部の難関大向け講義系参考書を補助的に使うことも考えられます。
・日本史が心から好きで、もっと深く学びたい場合:学問的な興味から、より専門的な参考書に手を出すのは素晴らしいことです。
効率を最優先するなら、共通テストの過去問や予想問題集、共通テストレベルの問題集を徹底的にやりこむのが最善策です。

Q4:日本史の勉強でモチベーションが下がってしまったらどうすればいいですか?
A4:モチベーションの波は誰にでもあります。
そんな時は、一旦立ち止まって「リフレッシュ」と「目標の再確認」をしてみましょう。
私も塾で、多くの生徒が日本史の暗記量に圧倒されて、途中でやる気をなくしてしまう姿を見てきました。
そんな時に私がアドバイスしていたのは、以下のことです。
・休息を取る:無理に続けても効率は上がりません。短時間の休憩や、好きなことをする時間を設けて気分転換しましょう。
・目標を再確認する:なぜ日本史を勉強しているのか、志望校に合格したいという最初の気持ちを思い出してください。合格後の自分を想像するのも良いモチベーションになります。
・成功体験を積み重ねる:簡単な問題集から始めて、「できた!」という喜びを感じることで、自信を取り戻せます。
・歴史の面白さに触れる:たまには歴史ドラマや漫画、ドキュメンタリーなどを見て、歴史そのものの面白さに触れてみましょう。知識が点ではなく、生き生きとしたストーリーとして感じられるはずです。新課程の「探究」の視点で歴史番組を見るのも面白いです。
一人で抱え込まず、友人や先生、家族に相談するのも良い方法です。
あなたの努力は必ず報われます。応援しています!
参考記事:キミノスクールに興味のある方必見!【口コミ・評判・料金】を徹底調査!おすすめできるオンライン塾?
まとめ:日本史の参考書・問題集おすすめ17選!レベル別×志望校合格への最強ルート

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「日本史の参考書・問題集おすすめ17選!レベル別×志望校合格への最強ルート」は参考になりましたでしょうか?
日本史のおすすめ参考書と問題集!
大学受験日本史で成功を掴むためには、自分のレベルと目標に合った参考書・問題集を選び、それを信じて徹底的にやり込むことが何よりも大切ですし、新課程「日本史探究」を履修している皆さんもこの原則は変わりません。
この記事で紹介した選び方や参考書ルートを参考に、あなただけの最強の一冊を見つけてください。
・まずは自分の現在地を知る:自分のレベルに合った参考書から始める。特に新課程で学んでいる内容との関連も意識しましょう。
・目的を明確にする:「流れを掴む」「用語を覚える」「問題を解く」など、目的に合った教材を選ぶ。
・志望校の傾向を分析する:過去問を見て、必要な対策(論述、史料、文化史など)を把握する。新課程入試への移行にも注意を払いましょう。
・決めた一冊を信じてやり抜く:浮気せず、一冊を完璧に仕上げる。
参考書選びは、長い受験勉強の第一歩です。
この記事が、あなたの志望校合格への確かな一歩となることを心から願っています。頑張ってください!
日本史に関するおすすめ記事
【2025年】歴史総合・日本史探求おすすめ参考書20選!レベル別に紹介
社会の選択は日本史で決まり!大学受験│日本史の勉強はいつから始めるべき?
理系受験生の社会の選択を表にまとめて分かりやすく解説します!
【歴史総合の勉強法】これで完璧!定期テストも大学受験も怖くない!
詳説日本史ノート「最強の使い方&勉強法」で成績UP!高校生・受験生必見の完全ガイド
山川の日本史用語集の使い方!【ポイント3つ】日本史の暗記が効率的に!
日本史の勉強法!定期テストで高得点を取る方法【日本史の勉強の基本】
日本史の勉強法は教科書をよく読む!【これならできる日本史の勉強】
【日本史の覚え方】3ステップで主要人物・年号・流れを暗記する最強術!
【日本史】年号を語呂合わせで暗記する【大学受験】語呂合わせ一覧
大学受験日本史!おすすめ参考書&問題集17選!レベル別×合格への最強ルート
【大学受験】日本史VS世界史の選択!社会の受験科目の選び方完全ガイド

