社会の選択は日本史で決まり!大学受験│日本史の勉強はいつから始めるべき?
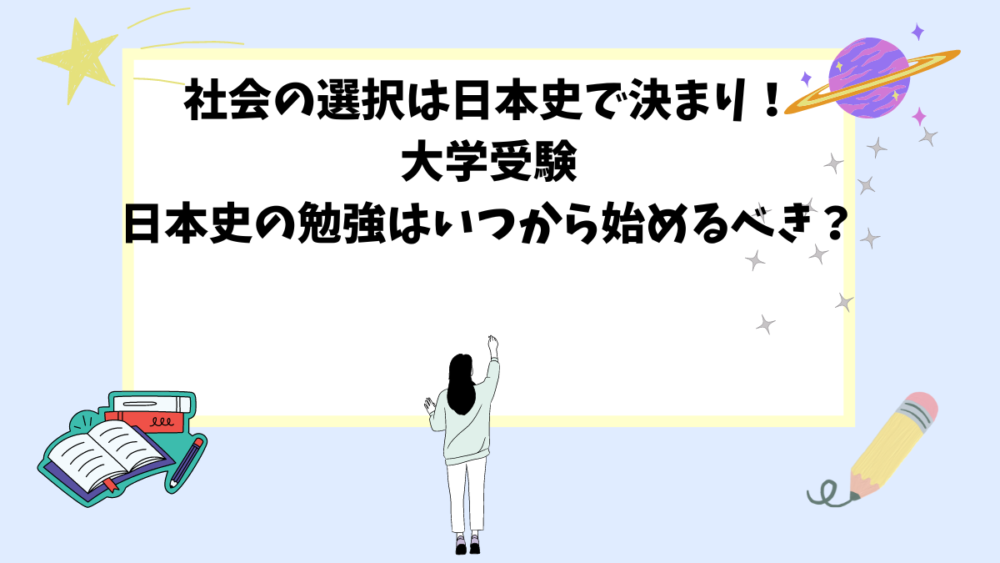
「※この記事には一部PRが含まれます」
こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。
受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。
記事の終わりには、日本史の成績がアップする勉強情報を掲載しています。参考にしてください。
今回のお悩みはこちら。
日本史の勉強方法は?
どのようなスケジュールで勉強するの?
大学受験において、社会の選択って迷いますよね?
今回紹介する「社会の選択は日本史で決まり!大学受験│日本史の勉強はいつから始めるべき?」を読めば、社会の選択の参考になります。
なぜなら、社会の選択で迷った生徒に指導していた内容だからです。
この記事では、大学受験における社会の選択方法や日本史の勉強を始める時期について具体的に紹介しています。
この記事を読み終わると、日本史の勉強の参考になるはずです。
日本史対策、何から始めるべき?
日本史の勉強はいつから
日本史の年間学習スケジュール
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ
※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
Contents
社会の選択は日本史で決まり!大学受験│日本史の勉強はいつから始めるべき?

受験生なら誰もが気になる、社会の選択!
何から始めるかについて、以下のポイントを解説いたします。
日本史の勉強は出来事の暗記だけではない!
とにかく現代史を頑張ろう!
大学受験は日本史を選択?
文系受験を検討されている大学受験生のみなさん、社会の科目は何を利用するか決まりましたか?
もし、まだどれにしようか決めかねている方がいらっしゃいましたら、ぜひ日本史を選択することを検討してみてください。
その理由は2つあります。
1. どの話も「日本が中心」であるため
2. 国語の文学史範囲もカバーできるため
1については、例えば大学受験の世界史と比較をしてみましょう。
世界史ではその名の通り、世界さまざま、かつ長い歴史をもつ国々の歴史や文化について学ぶこと、またその国々が姿を変えていく様子を学ぶ必要があります。
暗記が得意な人にとっても全範囲を網羅することは容易ではありません。
しかし、日本史は「日本の歴史」です。
海外と日本の関係についての理解が必要な場面は多少あり100%が日本国内の出来事におさまるとは言えません。
それでも様々な国々の変遷を学ぶよりは通史の学習に対するハードルは下がるはずです。
2については、国語の文学史が個別入試の試験問題に出題される大学があります。
文学や美術史における流派や思想・主義は歴史的事実と強いかかわりを持つため、日本史における学びが文学史の対策にもなり一石二鳥です。
このような理由から、大学受験では日本史を選択することを検討してみてください。

参考記事:【歴史総合の勉強法】これで完璧!定期テストも大学受験も怖くない!
日本史の勉強は出来事の暗記だけではない!
ここまで日本史を受験に利用することをおすすめしました。
次に、すでに日本史受験を考えている方に質問です。
日本史の試験には、いったい何が出題されるでしょうか?
「日本史というくらいなのだから、ひたすら歴史上の出来事だけ覚えていればいいでしょう!」という声も聞こえてきそうですが、大学受験はそれだけでは乗り切れません。
どんな出来事がいつどこで起こったのか、またその背景やそれに関係する人々、外国との関係、その当時、定められていた法、そこから派生して生まれた書物や美術作品の名前と内容など、一つのものごとについて深い知識が求められる場面がほとんどです。
これをはるか昔日本のはじまりの頃から今日のことまで覚えなければならないなんて、考えただけでも気が遠くなりそうですね。

日本史はとにかく現代史を頑張ろう!
前に述べた説明ですでに「日本史のほうが覚える量が少なそうなのに、それでも暗記量が多いなんて!」
と思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、諦めてはいけません。
日本史はしっかり勉強すれば勉強した分だけあなたの味方になってくれます。
日本史はどのように勉強を始めるべきでしょうか?
個人的におすすめは「開国以降の歴史を攻略しよう」ということです。
みなさんも日常的に、ニュースを目にしていて思われるかもしれませんが、現代のわたしたちの生活は一日一日めまぐるしい変化の中にあります。
毎日のように情勢に変化がある、新しい事件が起こる、昨日までなかったものが今日は存在する。
その一つひとつが歴史になります。
1854年にアメリカからペリーが来日し、それまで鎖国状態にあった日本はいわゆる「開国」をしました。
その後の日本は欧米諸国との関係を深めながら、だんだんと国際的な地位を築きました。
当然国が大きくなればなるほど、良くも悪くも「事件」が起こります。
日本史の話に戻りますが、この開国以降の出来事が今日の日本を作っており、出来事の数もそれまでとは桁違いであるためにこの範囲をしっかりと暗記することが大学受験日本史攻略につながります。
歴史の勉強となるとどうしても最も古い旧石器時代から現代に向かって歴史を網羅したいという気持ちになるとは思いますが、受験の攻略のためには重要な範囲の学習を最優先すべきです。
難関大学にあなたも逆転合格できる
圧倒的な合格率が本物の証
難関私大に合格する完璧なノウハウ
志望大学の先生があなたをサポート
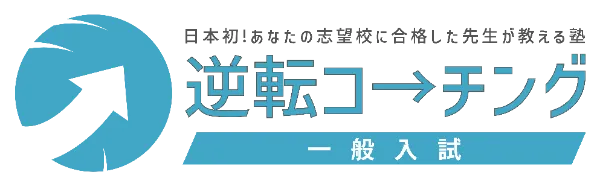
「友だち追加」で無料コーチング
勉強計画を無料で作成
↓↓↓
大学受験│日本史の勉強はいつから

次に、日本史の勉強の進め方を見てみましょう。
以下のポイントを解説します。
日本史の教科書はあなどれない!
副教材をフル活用しよう
日本史の一問一答は受験生の味方に
日本史の大学受験勉強はいつから
日本史の勉強をいつから始めれば良いのか?高校生からよく質問される内容です。
一番理想的なのが、高校2年生の冬休みから始めるのがおすすめです。
理由は、多くの受験生が高校3年生から日本史の勉強を始めるため、高校2年生の冬休みから日本史の勉強を始めることでアドバンテージができるからです。
他の受験生より、日本史の勉強を早くスタートさせることで余裕を持って、勉強に取り組むこともできます。
高校3年生になるまでには、日本史の復習として教科書を1周するのが理想的です。
たまに、高校3年生の生徒から同じ質問を受けますが、その時は、「今すぐ」と答えています。

日本史の教科書はあなどれない!
日本史を学習する際、まずは教科書太字レベルをしっかりと暗記することに専念しましょう。
教科書を読み出来事の前後関係の把握をして、特に太字で書かれている用語や出来事は読み流さず自分の言葉で説明できるようになることが大切です。
それができたら次に教科書に取り上げられている年表や写真、本文より小さな字で書かれている説明書きまで逃さず読みましょう。
特に教科書に掲載される美術作品や建物の写真は試験問題にも図付きで掲載されることが予想されますので、説明なしでその図を見た際にどの出来事に関連するものであったか識別ができると完璧です。

参考記事:【日本史の覚え方】3ステップで主要人物・年号・流れを暗記する最強術!
副教材をフル活用しよう
ほとんどのみなさんは教科書とともに日本史資料集もお持ちだと思います。
資料集は教科書よりも詳細な出来事の説明や年表、家系図などが掲載されているため、日本史の学習の際には必ず手元においておきましょう。
活用方法としてはわからない用語が登場したときにそれを調べることがメインとなります。
これに加え資料集の年表をコピーしてノートに貼り、年号や出来事の名前に暗記マーカーを引いてまるごと暗記する方法もおすすめします。
さらに学校によっては「史料集」も購入されている方がいらっしゃるはずです。
史料問題は合否の明暗を分けると言っても過言ではないほど、必ずおさえるべきものです。
例えば天皇が詠んだ和歌や法律の制定を示す文章、現代史においては条約締結の声明文など、その史料がどのような出来事と関連するのか、誰が出した文章であるのか、さらには史料中の語句の穴埋めまでもが出題されます。
通史の学習をする際には時代や節の区切りごとに重要な史料はどのようなものがあるか確認しましょう。

参考記事:日本史の勉強法は教科書をよく読む!【これならできる日本史の勉強】
日本史の一問一答は受験生の味方に
学校で使用する教材の他になにか新しく参考書を購入するのであれば、まずは一問一答を購入することを推奨します。
一問一答はその名の通り短答形式の問題集になっており、自分が確認したい問題のみをピックアップすることも可能ですし、移動時間や模擬試験、本番前などどのような場面においても勉強に最適な教材です。
歴史上の事実に重点をおいたベーシックな一問一答のみならず、前にも述べた史料問題に特化した一問一答も販売されています。
暗記は反復学習が大切ですので、これらの参考書を活用して学習・復習をすすめましょう。
難関大学にあなたも逆転合格できる
圧倒的な合格率が本物の証
難関私大に合格する完璧なノウハウ
志望大学の先生があなたをサポート
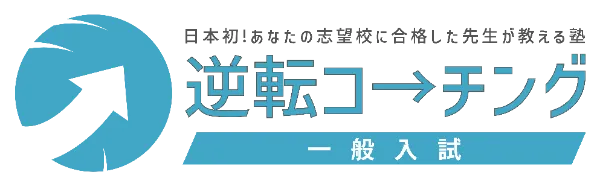
「友だち追加」で無料コーチング
勉強計画を無料で作成
↓↓↓
日本史の勉強:年間学習スケジュール

最後に日本史の年間の学習スケジュールを見てみましょう。
ポイントは以下になります。
文学史・美術史・経済史は夏休み終了までに完璧に!
日本史の過去問題演習は早く始めよう!
日本史は時間にゆとりを持って
この項目では大学受験生の日本史学習スケジュールについてお話しします。
受験勉強する際には国語や英語など、問題演習にまとまった時間を要する科目についつい時間を費やしがちになってしまうことも多いかと思います。
その点日本史はスキマ時間を効率よく利用した学習が可能であるため、通学時間や休み時間、他科目の勉強の合間にリフレッシュとしても演習ができます。
しかしながら何度もお伝えしているように、通史を学ぶこと、またそれに関連した項目についてまでインプットするには国語や英語と同等の時間がかかります。
最も理想的な学習スケジュールとしては、高校3年生進級前までに通史の確認を終えることが目標です。
それが叶わずとも、5月までには大まかで構わないので一連の流れの把握は終えられるようにしましょう。
日本史は一度にその範囲を完璧にして次の単元に進むより、何周も通史を繰り返すことにより深い暗記を実現するイメージで勉強することをおすすめします。
※通史とは:古代から現代まで通して叙述した歴史。

参考記事:【2025年】MARCH日本史おすすめ参考書25選!基礎から合格まで完全網羅
文学史・美術史・経済史は夏休み終了までに完璧に!
すでに述べたように、日本史は通史のみならずその出来事により生まれた芸術作品や法律など、派生して生まれたものに焦点を当てて暗記することも求められます。
特に文学史・美術史・経済史は長期休みを利用し、ひとまとめに確認しましょう。
またその際には資料集の特集ページや専用の問題集を用いた演習を同時に行うと効果的です。
山川出版社「分野別問題集」やZ会出版「攻略日本史 テーマ・文化史」などは分野ごとに特化した問題集であるため、おすすめです。

参考記事:理系受験生の社会の選択を表にまとめて分かりやすく解説します!
日本史の過去問題演習は早く始めよう!
過去問題演習はためらわず、早めの時期から始めることをおすすめします。
試験においては一つの大問につき一つの時代や出来事を扱うということが殆どです。
そのため既習分野については学習が一段落した時点から過去問題を解けるようになります。
早い時期から過去問題を用いて問題演習することにより、どの程度の学力が備わっているのかを把握するのみならず、どの程度の深さの知識が求められるのか知ることにも繋がり、その後の対策を練り直すことも可能になります。
「まだ夏だから過去問題は解かなくてもいいや」「冬になったら過去問題を解こう」とは思わず、早め早めの対策を講じることが日本史攻略のカギになることでしょう。
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ
※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
まとめ:社会の選択は日本史で決まり!大学受験│日本史の勉強はいつから始めるべき?

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「社会の選択は日本史で決まり!大学受験│日本史の勉強はいつから始めるべき?」は参考になりましたでしょうか?
まとめ:社会の選択は日本史で決まり!大学受験│日本史の勉強はいつから始めるべき?
社会に限らず、大学受験勉強は、長期間、継続して勉強が必要。
つまり、勉強していく上で、自分の興味がある科目について勉強するのが効率的。
なぜなら、興味がある科目については、モチベーションを保って勉強できるからです。
また、どの科目を選択したとしても、受験において有利不利はないのです。
どの科目も興味がないという受験生もいるかも知れませんが、興味が持てそうな分野を見つけて、選択してください。
勉強するうちに、意外に楽しく思えてくる可能性もあるのです。
社会の選択は、自分が勉強しやすい科目を選択して取り組むのがベストと言えるでしょう。
大学受験の日本史の勉強は、高校2年生の冬休みから始めるのが理想的です。
理由は、以下のとおりです。
早めに始めることで、基礎固めをしっかりできる
日本史は、膨大な量の知識を必要とする科目です。早めに始めることで、基礎固めをしっかりとでき、後々苦手分野が残りにくくなります。
志望校のレベルに応じた対策を立てられる
日本史は、大学によって出題傾向が異なります。早めに始めることで、志望校のレベルに応じた対策が立てられます。
もちろん、高校1年生から始めるのも良いでしょう。高校1年生のうちに、日本史の全体像を把握しておくことで、高校2年生以降の学習がスムーズになります。
ただし、高校1年生のうちに日本史の勉強をあまり深く進めすぎると、高校2年生以降にモチベーションが低下する可能性があります。まずは、日本史の全体像を把握し、高校2年生以降に重点的に学習する分野を決めておくと良いでしょう。
日本史の勉強を効率的に進めるためには、以下の点に注意しましょう。
教科書や参考書をしっかりと読み込む
日本史の勉強の基本は、教科書や参考書をしっかりと読み込むこと。教科書や参考書をしっかりと理解することで、日本史の基礎知識を身につけます。
過去問を解く
過去問を解くことで、大学受験でどのような問題が出題されるのかを把握できます。また、過去問を解くことで、自分の実力を把握し、弱点を克服するための対策が立てられます。
定期的に復習する
日本史は、膨大な量の知識を必要とする科目です。定期的に復習することで、忘れた知識を思い出し、記憶を定着できます。
日本史の勉強は、地道な努力が必要です。しかし、しっかりとした計画と努力を継続することで、必ず合格を勝ち取れるでしょう。
成績アップ!日本史おすすめ勉強情報
大学受験日本史!おすすめ参考書&問題集17選!レベル別×合格への最強ルート
【日本史】年号を語呂合わせで暗記する【大学受験】語呂合わせ一覧
日本史の勉強法は教科書をよく読む!【これならできる日本史の勉強】
【日本史の覚え方】3ステップで主要人物・年号・流れを暗記する最強術!
「歴史総合」と「日本史探究」の違いとは?科目選択で後悔しない完全ガイド
山川の日本史用語集の使い方!【ポイント3つ】日本史の暗記が効率的に!
詳説日本史ノート「最強の使い方&勉強法」で成績UP!高校生・受験生必見の完全ガイド
日本史探求の最強勉強法!歴史総合もこれで完璧【おすすめ参考書8選】
【2025年】MARCH日本史おすすめ参考書25選!基礎から合格まで完全網羅
予備校オンラインドットコムおすすめ塾の紹介
【鬼管理専門塾とは】口コミ・評判を塾経験者が徹底解説!怪しい塾なの?
【必見】スタディコーチの口コミ・評判が気になる方!塾経験者が調査しました!

