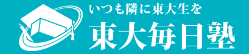【歴史総合の勉強法】これで完璧!定期テストも大学受験も怖くない!
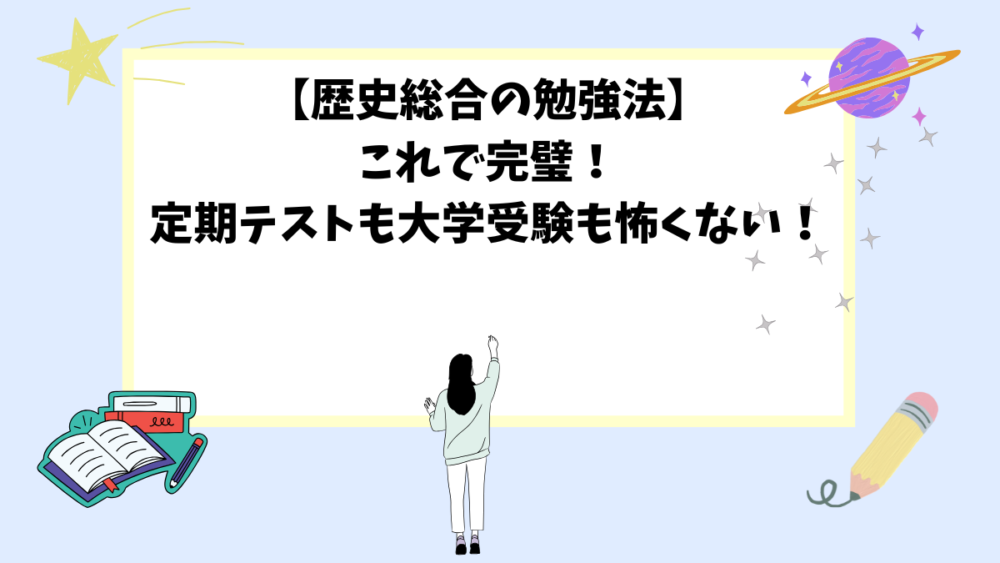
「※この記事には一部PRが含まれます」
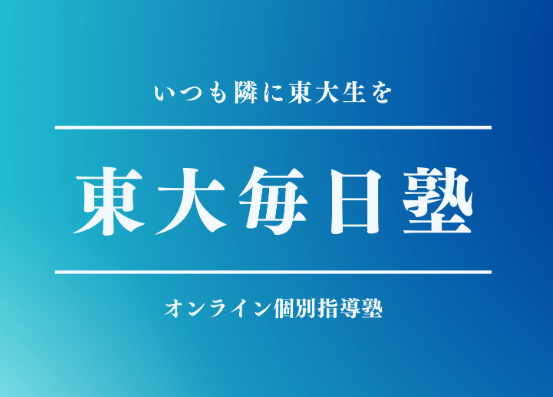 本記事の監修者:東大毎日塾
本記事の監修者:東大毎日塾
本記事の内容は、難関大学合格を目指す受験生を応援する「東大毎日塾」が監修しています。東大毎日塾は、個別指導と学習管理を通じて多くの生徒の学力向上をサポートしており、最適な学習法についての知見を基に記事を作成しました。
「歴史総合の勉強法」や自分にあった参考書をお探しの方は、東大毎日塾にお問い合わせください。
こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。
受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。
今回のお悩みはこちら。
定期テストや大学受験の対策も教えてください。
歴史総合は従来の日本史・世界史と異なる新しい科目のため、多くの高校生が勉強法に迷っています。
でも大丈夫!
歴史総合の特徴をつかめば、効率的に学習を進められます。
この記事では、日々の学習の基本から定期テスト対策、さらには大学受験を見据えた勉強法まで段階的に解説します。
教科書の読み方、ノートのまとめ方、暗記のコツなど、すぐに実践できる方法ばかりなので、ぜひ参考にしてください。
歴史総合という科目の特徴と、従来の日本史・世界史との違い
歴史総合の学習で求められる能力
歴史総合の学習でつまずきやすいポイントとその対策の方向性
定期テストで高得点を取るための対策と勉強計画の立て方
大学受験(共通テスト)における歴史総合の位置づけと対策
Contents
なぜ難しい?「歴史総合」の特徴と勉強を始める前に知っておくべきこと
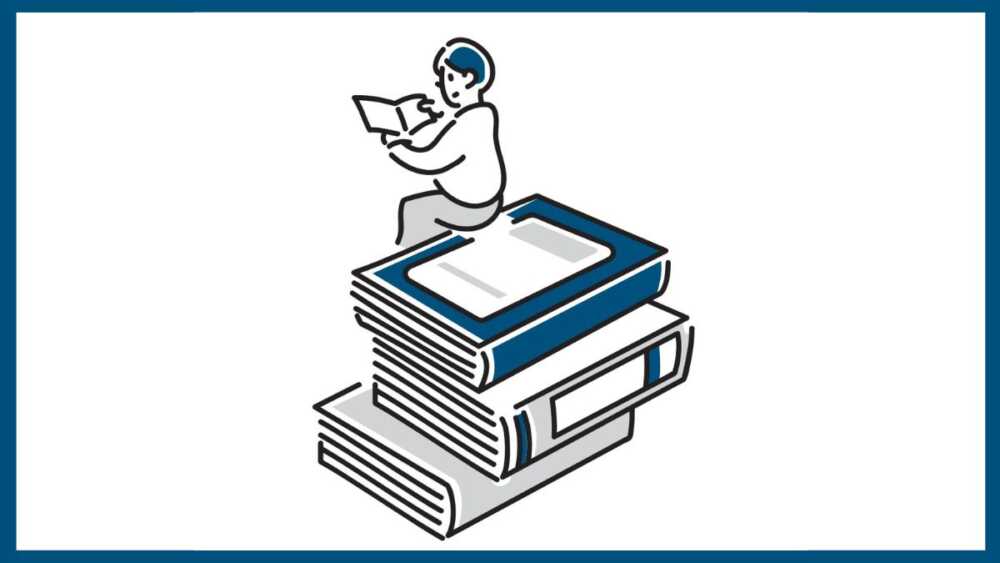
「歴史総合」という科目がなぜ存在するのか、どんな特徴があるのかを理解することが、効果的な勉強の第一歩です。
歴史総合の性質を知ることで、学習のアプローチが変わり、成績アップにつながります。
まずは歴史総合の全体像をしっかり把握していきましょう。
歴史総合で問われる力:単なる暗記だけでは通用しない理由
高校生が歴史総合でつまずきやすいポイントと対策の方向性
新科目「歴史総合」とは? 日本史と世界史を”合わせて”学ぶ意味
歴史総合は、2022年度から必修化された新科目で、日本史Aと世界史Aを統合し、主に近現代史(18世紀以降)を学びます。
歴史総合の最大の特徴は、世界の出来事と日本の歴史を関連付けて理解することです。
たとえば、明治維新を学ぶ際には、同時期の世界情勢(産業革命や欧米の帝国主義など)とのつながりを見ることで、なぜ日本が近代化を急いだのかが理解しやすくなります。
こうした多角的な視点で歴史を学ぶことで、現代社会の諸問題についても深く考察できるようになるのです。

歴史総合で問われる力:単なる暗記だけでは通用しない理由
歴史総合では、従来の「年号や出来事の暗記」だけでなく、以下の力が求められます。
・資料活用能力:史料や図表から情報を読み取り、解釈する力
・多角的思考力:日本と世界の歴史を関連付けて考える力
・因果関係の理解:出来事の背景や影響を構造的に把握する力
特に共通テストでは、資料を読み解いて考察する問題が多く出題されます。
2025年の共通テストでも、地図や統計データから情報を読み取る問題が出題されました。
暗記一辺倒の学習では対応できないため、歴史的思考力を鍛える学習が不可欠です。

参考記事:「歴史総合」と「日本史探究」の違いとは?科目選択で後悔しない完全ガイド
高校生が歴史総合でつまずきやすいポイントと対策の方向性
高校生が歴史総合で特につまずきやすいポイントは主に3つあります。
・時代の流れが掴みにくい:年表を活用し、大きな流れを最初につかむ
・日本史と世界史の関連付けが難しい:同時代の出来事をセットで覚える
・用語が多すぎて覚えられない:重要度に応じた学習で効率化する
対策としては、まず教科書の全体像を把握することから始め、時系列に沿って「ストーリー」として歴史を理解することをおすすめします。
関連するトピックをまとめて学ぶことで、記憶の定着率も高まります。
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
東大生・早慶生からのコーチング|スタディコーチ
※偏差値が短期間で急上昇する理由は?東大式学習メソッド!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
【基本のキ】毎日の学習で差をつける!歴史総合の基礎固め勉強法
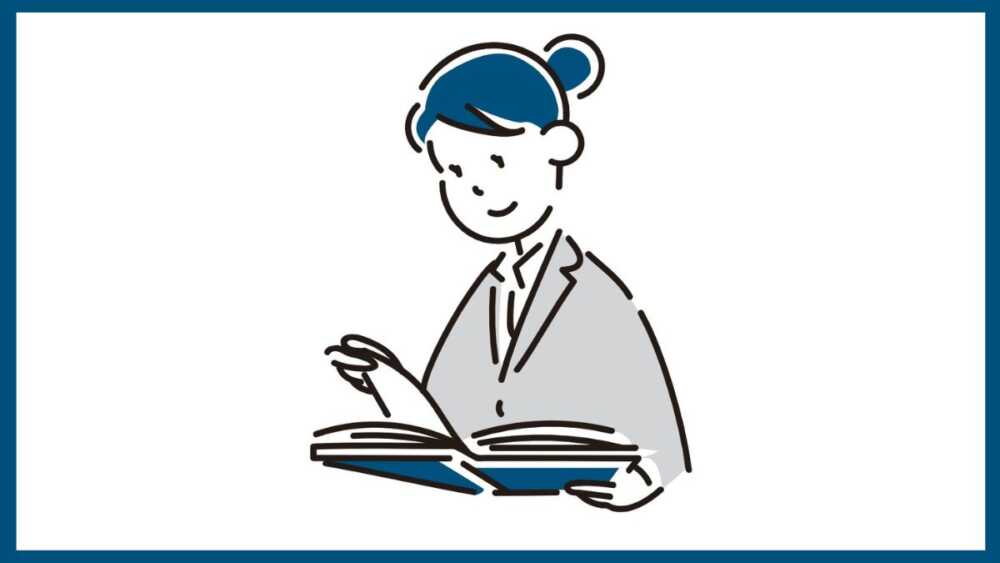
歴史総合の成績を上げるためには、日々の学習習慣がとても重要です。
特に高校1年生のうちに基礎をしっかり固めておくことで、後々の学習がスムーズになります。
ここでは、授業の受け方から教科書の読み方、効果的なノート作りまで、日常的な学習方法について解説していきます。
教科書を使い倒す!歴史の流れと重要事項を掴む読み込み術
「歴史総合のノートはこう作る!」成績アップにつながるまとめ方
授業の受け方一つで変わる!予習・復習の効果的なサイクル
歴史総合の授業を最大限に活かすためには、「予習→授業→復習」のサイクルを確立することが大切です。
特に復習は記憶の定着に不可欠です。
【効果的な予習・復習のポイント】
・予習:教科書の該当範囲を読み、重要用語に線を引いておく(15分程度)
・授業:先生の説明で重視されているポイントをノートに記録する
・復習:授業当日・翌日・週末の3回復習することで記憶の定着率が格段に上がる
たとえば、「明治維新」を学ぶ場合、予習で教科書から「薩長同盟」「大政奉還」などの重要語句をチェックしておき、授業で先生が強調する「幕末の国際情勢」などの背景知識を書き留め、復習で全体の流れを確認するというサイクルが効果的です。

教科書を使い倒す!歴史の流れと重要事項を掴む読み込み術
歴史総合の学習において、教科書は最も信頼できる教材です。
効果的な教科書の活用法は以下の通りです。
・授業後の読み直し:授業で理解したことを教科書で再確認する
・「背景・経過・結果/影響」の視点で読む:出来事をこの3段階で整理する
・自分なりのマーキング:重要度に応じて色分けしたり、記号を付けたりする
たとえば、ソ連のアフガニスタン侵攻について学ぶ際は、背景(アフガニスタンでの社会主義政権成立と内紛)、経過(ソ連軍のゲリラ戦での苦戦)、結果/影響(西側諸国との関係悪化)と整理すると理解しやすくなります。

「歴史総合のノートはこう作る!」成績アップにつながるまとめ方
効果的なノート作りは学習効率を大きく左右します。
歴史総合に適したノート作りのポイントをレベル別に紹介します。
授業内容を整理する基本のノート術
基本となるノート術は、「テスト化」できる形式です。
以下の手順で作成しましょう。
・重要用語をオレンジペンで記入する
・赤シートで隠せるようにレイアウトする
・各回の復習時に自己テストとして活用する
このようにすることで、ノートが単なる記録ではなく、学習ツールとして機能します。
復習時に答えられなかった用語にはチェックマークをつけ、繰り返し確認することで記憶の定着を図りましょう。
日本史と世界史の繋がりが見えるノート術
歴史総合の特徴を活かしたノート作りには、日本と世界の出来事を関連付けて記録する工夫が有効です。
・ノートを縦に二分割し、左側に世界史、右側に日本史を書く
・同時期の出来事を同じ高さに配置する
・関連する出来事を矢印などで結ぶ
たとえば、1929年の世界恐慌と、その影響を受けた日本の昭和恐慌を同じ高さに配置し、関連を示すことで、経済危機の世界的な連鎖を視覚的に理解できます。
資料や図解を活用した視覚的なノート術
より高度なノート術として、資料や図解を取り入れる方法があります。
・資料集から関連する地図や統計をコピーして貼り付ける
・自分で簡単な図や表を作成して理解を深める
・色分けを活用して時代や地域ごとの特徴を視覚化する
視覚的な情報は記憶に残りやすく、また資料読解力の向上にも役立ちます。
たとえば、第一次世界大戦前のヨーロッパの同盟関係を図示すると、複雑な国際関係が理解しやすくなります。
【効率化テクニック】歴史総合の暗記と理解を深める実践的な勉強方法

歴史総合では多くの用語や出来事を覚える必要がありますが、闇雲に暗記するのではなく、効率的な方法で記憶と理解を深めることが大切です。
ここでは、暗記を効率化し、歴史の本質的な理解を深めるための実践的なテクニックを紹介します。
ストーリーで理解する!歴史の流れを楽しく記憶するコツ
資料読解問題を得点源に!読み取りと思考力を鍛える練習法
「問い」を立てる学習で、考察力・表現力を伸ばす
年号・人名・出来事を関連付けて覚える!効果的な暗記術
単語や年号をバラバラに覚えるよりも、関連付けて覚えることで記憶の定着率が高まります。
効果的な暗記のポイントは、
・時代区分で整理する:たとえば、「戦間期(1918-1939)」という大枠で出来事をまとめる
・語呂合わせを活用する:「いい国作ろう鎌倉幕府(1192)」など
・関連する出来事をセットで覚える:「ワシントン会議(1921-22)→海軍軍縮→四カ国条約・九カ国条約・五カ国条約」
特に効果的なのは、年表作成です。
A4用紙を横向きにして時代ごとに区切り、日本史と世界史の出来事を並行して書き込むと、同時代の出来事が一目でわかります。
これを週末に見直すことで、時代感覚が養われます。

ストーリーで理解する!歴史の流れを楽しく記憶するコツ
歴史は「物語(ストーリー)」として捉えると理解も記憶も深まります。
以下の方法を試してみましょう。
・因果関係を意識する:「なぜそれが起きたのか」「何につながったのか」を考える
・当時の人々の立場で考える:「自分がその立場ならどう判断するか」と想像する
・現代との関連を見つける:過去の出来事が現在にどうつながっているかを考える
たとえば、「日露戦争」を学ぶ際、単に「1904-05年に起きた」と暗記するのではなく、「なぜ日本はロシアと戦うことになったのか」「勝利の背景には何があったのか」「戦後の国際情勢にどう影響したのか」と考えることで、立体的な理解が得られます。

資料読解問題を得点源に!読み取りと思考力を鍛える練習法
共通テストや二次試験で重視される資料読解問題。
これを得点源にするためには日頃からの練習が欠かせません。
・教科書の資料や図説を積極的に活用する:普段から様々な資料に触れる習慣をつける
・「何が書かれているか」だけでなく「何を意味するか」を考える:資料の背景や意図を読み取る
・表やグラフの変化の理由を考察する:数値の変化には必ず歴史的背景がある
具体的な練習法としては、教科書や資料集の図表を見て「この変化は何を意味するか」「なぜこの時期にこの変化が起きたのか」などの問いを自分で立てて答えてみることが効果的です。

「問い」を立てる学習で、考察力・表現力を伸ばす
歴史的思考力を養うには、自ら「問い」を立てる学習法が効果的です。
・「なぜ」から始まる問いを立てる:「なぜ日本は明治維新後に急速に近代化できたのか」など
・複数の出来事を比較する問いを考える:「フランス革命とロシア革命の共通点と相違点は?」
・自分なりの仮説を立てて検証する:「もし第一次世界大戦が起きていなかったら世界はどう変わっていたか」
このような思考訓練は、論述問題への対応力を高めるだけでなく、歴史を深く理解することにもつながります。
週に1回でも、こうした「問い」について考える時間を設けるとよいでしょう。
【高校生向け】歴史総合の定期テスト対策!高得点を取るための戦略

定期テストは歴史総合の理解度を測る重要な機会であり、普段の学習の成果を発揮する場です。
しかし、範囲が広く、何をどう勉強すればいいか悩む高校生も多いでしょう。
ここでは、効率的に準備して高得点を取るための具体的な戦略を解説します。
効率的なテスト勉強計画の立て方(範囲別・時期別)
教科書・ノート・ワーク(なしの場合も)の効果的な活用法
テスト前日でも諦めない!短時間でできる最終チェックポイント
定期テストの出題傾向を知る:先生が重視するポイントは?
定期テストで高得点を取るためには、自分の学校や担当教員の出題傾向を把握することが第一歩です。
【チェックすべきポイント】
・前回までのテスト内容を分析する:過去の問題を見直し、どの部分から多く出題されているかを把握する
・授業中の強調点に注目する:先生が「ここ重要!」と言ったポイントや板書で強調した部分は出題される可能性が高い
・プリントの内容を確認する:配布プリントの内容は基本的にテスト範囲に含まれる
たとえば、「板書をそのままテスト問題にする先生」「教科書の太字をよく出題する先生」「授業中の補足説明から出題する先生」など、先生によって出題パターンは異なります。
先輩や同級生からの情報も参考にしながら、効率的な対策を立てましょう。

効率的なテスト勉強計画の立て方(範囲別・時期別)
計画的なテスト勉強は、限られた時間で最大の効果を得るために不可欠です。
以下は、テスト2週間前からの効果的な計画例です。
| 時期 | 学習内容 |
|---|---|
| 2週間前〜1週間前 | ・教科書を通読し、全体像を把握する ・重要用語をチェックし、意味を確認する ・ノートや配布プリントを整理する |
| 1週間前〜3日前 | ・用語の暗記に集中する ・ワークや問題集を解いて理解度をチェックする ・苦手分野を重点的に復習する |
| テスト前日 | ・最重要ポイントの最終確認 ・年表で時代の流れを再確認する ・資料問題の解き方を復習する |
勉強時間の配分は、苦手な部分に多めに時間をかけつつも、得意な部分も忘れないよう万遍なく復習することが大切です。

教科書・ノート・ワーク(なしの場合も)の効果的な活用法
定期テスト対策で最も重要なのは、手元の教材を効果的に活用することです。
| 教材区分 | 活用法のポイント |
|---|---|
| 教科書の活用法 | ・太字や重要語句をマーカーでチェックする ・各章のまとめや図版の説明文も確認する ・脚注や補足情報にも目を通す |
| ノートの活用法 | ・授業中の重要ポイントや先生の口頭説明を確認する ・赤シートで用語をテスト形式で復習する ・不明点は教科書で確認・補足を書く |
| ワークがない場合 | ・市販の問題集を購入 or 図書館で借りる ・教科書から自作問題を作って解く ・オンラインの無料問題を活用する |
特に教科書は定期テストの出題源になるため、教科書の内容を確実に理解することが高得点への近道です。

テスト前日でも諦めない!短時間でできる最終チェックポイント
テスト前日になってしまっても、効果的な対策はあります。
限られた時間で最大の効果を得るための方法を紹介します。
【最優先でチェックすべきポイント】
・重要用語の最終確認:赤シートを使って重要語句の意味をチェック(できない用語に印をつける)
・時代の流れの確認:年表で主要な出来事の順序を確認する
・先生が強調したポイント:授業中に「ここは出る」と言われた内容を重点的に復習
【短時間で効果的な復習方法】
・20分勉強して5分休憩のサイクルで集中力を維持する
・声に出して重要事項を読み上げる(聴覚的記憶の活用)
・図や表を書いて視覚的に整理する
たとえば、「第一次世界大戦の原因→経過→結果」といった形で、主要テーマごとに流れを整理してまとめるのが効果的です。
睡眠時間を確保することも重要なので、遅くとも23時までには勉強を切り上げましょう。
東進は現役合格実績No.1の大学受験予備校
圧倒的No.1、日本一の【現役合格実績】
資料請求はスマホで1分!無理な営業も一切なし!
【大学受験を見据えて】共通テスト「歴史総合」の対策と勉強法

共通テストでは歴史総合が出題され、多くの受験生が対策に頭を悩ませています。
特に資料を読み解く力が問われる傾向にある共通テストでは、日頃からの準備が合否を分けます。
ここでは、最新の出題傾向を踏まえた効果的な対策方法について解説します。
共通テスト対策はいつから?何から始めるべき?
共通テスト特有の問題形式(資料問題・思考力問題)へのアプローチ
「歴史総合、日本史探究/世界史探究」選択の考え方と比較
高卒認定試験における歴史総合の勉強法
共通テストにおける歴史総合の位置づけと
共通テストでは、歴史総合は「歴史総合・世界史探究」または「歴史総合・日本史探究」の中で出題されています。
2025年度からは各科目とも歴史総合分野から25点程度、出題されるようになりました。
【共通テスト歴史総合の特徴】
・資料読解型問題が中心:地図、グラフ、史料などを読み解く問題が多い
・思考力・判断力を問う問題:単なる知識だけでなく、情報を分析する力が必要
・世界と日本の関連を問う問題:両者の関係性を理解することが重要
たとえば、2025年度の共通テストでは、ミシシッピ号の寄港地とコレラ流行の関係性を地図から読み取る問題や、カストロ政権誕生やプラハの春などの時系列を問う問題が出題されました。
単なる暗記では太刀打ちできない、資料を活用した思考力問題への対応が必要です。

大学入学共通テストに関する情報は、大学入試センターをご確認願います。
共通テスト対策はいつから?何から始めるべき?
共通テスト対策は計画的に進めることが大切です。
時期別の対策方法を紹介します。
| 時期 | 対策内容 |
|---|---|
| 高2〜高3夏休み前 | ・探究科目(日本史探究・世界史探究)の基礎固め ・教科書の内容を理解し、定期テストで高得点を狙う |
| 高3夏休み〜10月 | ・歴史総合の復習を本格的に開始 ・教科書・参考書で知識を整理し、不足分野を補強 ・夏期講習などを活用する |
| 高3 11月〜受験直前期 | ・実戦問題演習を中心に取り組む ・過去問や実戦問題集を繰り返し解く ・模試の復習で弱点を強化 |
早めの対策開始が理想ですが、受験直前期からでも効果的な学習は可能です。
まずは教科書内容の確認から始め、段階的に演習量を増やしていきましょう。

共通テスト特有の問題形式(資料問題・思考力問題)へのアプローチ
共通テストでは資料を読み解く問題が多く出題されます。
効果的な対策方法を紹介します。
【資料問題への対応力を高める練習】
・日頃から教科書や資料集の図表を「読む」習慣をつける
・「何が書かれているか」だけでなく「何を意味するか」を考える
・資料から読み取れる情報と、既知の歴史的知識を結びつける
【思考力問題への対応法】
・問題文をしっかり読み、何を問われているかを正確に把握する
・選択肢を吟味し、消去法も活用する
・時代背景や因果関係を常に意識する
たとえば、グラフから情報を読み取る問題では、「この時期になぜ数値が変化したのか」を歴史的背景と結びつけて考察する練習が効果的です。
日頃から資料を「歴史の文脈で解釈する」習慣をつけましょう。

歴史総合、日本史探究/世界史探究」選択の考え方と比較
共通テストでは「歴史総合、日本史探究」か「歴史総合、世界史探究」のどちらかを選択することになります。
自分に合った科目選択のポイントを解説します。
日本史探究・世界史探究とは?歴史総合との違い
歴史総合と探究科目の主な違いは以下の通りです。
| 項目 | 歴史総合 | 日本史探究・世界史探究 |
|---|---|---|
| 扱う時代 | 主に近現代(18世紀以降) | 古代から現代まで |
| 学習内容 | 世界と日本の関連性を重視 | それぞれ日本史・世界史を詳細に学ぶ |
| 学習量 | 比較的少ない | かなり多い(用語約5000語) |
| 必修 / 選択 | 必修 | 選択 |
歴史総合が近現代史を中心に世界と日本の関連性を重視するのに対し、探究科目ではより専門的に、古代から現代までの歴史を学びます。
共通テストでの科目選択:自分に合った選び方のヒント
科目選択では以下のポイントを考慮しましょう。
・得意・不得意:日本史と世界史、どちらに親しみを感じるか
・学習の進度:どちらの科目をより深く学んでいるか
・志望大学の傾向:二次試験でどちらの科目が必要か
たとえば、世界史が得意で二次試験でも世界史が必要な場合は「歴史総合、世界史探究」を選択するのが合理的です。
逆に日本史が得意であれば「歴史総合、日本史探究」がおすすめです。迷った場合は、模試で両方を受験してみて比較するのも一つの方法です。
高卒認定試験における歴史総合の勉強法
高卒認定試験でも歴史総合が出題されます。
効率的な学習方法は、
・市販の高卒認定試験対策教材を活用する
・過去問を繰り返し解く(出題傾向が安定しているため効果的)
・重要用語を中心に効率よく学習する
高卒認定試験は基礎的な内容が中心となるため、教科書の内容をしっかり理解していれば十分に対応可能です。
特に基本用語の理解と、時代の流れの把握を重視しましょう。
【教材選びの決定版】歴史総合の学習効果を高める参考書・問題集ガイド

効率的に歴史総合を学ぶためには、自分に合った教材選びが重要です。
しかし、歴史総合は比較的新しい科目のため、どの教材を選べばよいか迷うことも多いでしょう。
ここでは目的別におすすめの教材と、それらの効果的な活用法を紹介します。
資料集・地図帳の効果的な使い方:もっと深く歴史を理解する
独学をサポートするWebサイト・アプリ・動画活用術
自分に合った参考書・問題集の選び方:レベルと目的で選ぶ
参考書・問題集選びで最も大切なのは、自分のレベルと目的に合ったものを選ぶことです。
以下の基準で教材を選びましょう。
【レベル別の選び方】
・基礎レベル:カラーイラストが多く、平易な文章で解説されているもの
・標準レベル:教科書準拠で、やや詳しい解説があるもの
・発展レベル:入試問題レベルの内容で、深い解説があるもの
【目的別の選び方】
・授業理解用:教科書の内容をわかりやすく解説したもの
・定期テスト対策用:要点整理と基本問題が充実したもの
・受験対策用:思考力問題や資料問題が豊富なもの
実際に書店で手に取り、レイアウトや文体、問題の難易度などを確認してから購入するのがおすすめです。
自分が継続して使える教材を選ぶことが、学習効果を高める鍵となります。
基礎固め・授業理解におすすめの参考書
歴史総合の土台となる基礎知識をしっかりと身につけ、日々の授業内容を深く理解するためには、わかりやすさを重視した参考書が心強い味方となります。
| 書名 | 特徴 | 使い方 |
|---|---|---|
| 『歴史総合 近代から現代へ ノート』 | 教科書の内容に沿って、重要事項が整理 | 授業前後に通読し流れを把握 |
| 『共通テスト対応 スピードマスター歴史総合』 | 用語チェック欄付きで暗記に強い | 赤シート合わせで用語確認 |
短い説明文と図で概要をつかめるので、授業理解がスムーズになります。
定期テスト対策に役立つ問題集・ワーク
定期テストでしっかりと結果を出すためには、教科書や参考書で学んだ知識を実際にアウトプットする練習が不可欠です。
・『よくわかる高校歴史総合問題集』:教科書準拠、範囲別演習で直前チェックに最適。
・『山川 定期テスト対策ワーク』:一問一答+記述で点数に直結する形式。
時間がないときは○付け後に誤答だけ解き直すと復習効率が上がります。
共通テスト対策向けの実践的な参考書・問題集
共通テストで高得点を獲得するためには、広い範囲の知識を整理し、論理的な思考力や読解力を養う必要があります。
・大学入学共通テスト 歴史総合、日本史探究の点数が面白いほどとれる本(KADOKAWA)
共通テストの範囲に特化しており、図やイラストが豊富で視覚的に理解しやすいのが特徴です。初学者の方や、短期間で効率よく学習したい方におすすめです。
・共通テスト過去問研究 歴史総合,日本史探究
過去問は対策の基本です。共通テストの出題傾向や形式を把握するために必ず取り組みましょう。時間を計って解くことで、本番の練習にもなります。
資料集・地図帳の効果的な使い方:もっと深く歴史を理解する
歴史総合の学習をより深く、そして面白くするためには、資料集や地図帳の活用が欠かせません。
教科書や参考書で学んだ出来事や文化を、当時の絵画や写真、古文書などの一次資料を通して見ることで、文字だけでは伝わらない臨場感や背景にある人々の息遣いを感じることができます。
地図帳を活用することで、歴史的な出来事が起こった場所の位置関係や地理的な条件を把握し、なぜそのような出来事が起こったのかという理解を深めることができます。

独学をサポートするWebサイト・アプリ・動画活用術
【NHKラーニング】
「NHK高校講座 歴史総合」という番組が放送されています。
放送スケジュールはNHKの番組表で確認できます。
過去の放送はNHKラーニングのウェブサイトで視聴できる場合があります。
【YouTubeチャンネル】
・歴史総合・世界史探究のミカタ:近現代史を中心に、1分で学べるショート動画や解説動画を配信しています。
・ただよび文系チャンネル:「歴史総合」のプレイリストで、各時代の解説授業動画が公開されています。
・共通テスト社会科・理科チャンネル:「歴史総合 解説授業」というプレイリストで、共通テスト対策にも役立つ解説動画が配信されています。
【アプリ】
・TimeLine-歴史年表をつくろう: 自分で年表を作成できるシンプルなアプリです。
・パラレル年表:複数の出来事を並べて表示できる年表アプリです。
・日本史の王様 / 一問一答形式で手軽に学習できるアプリです。
これらの番組やアプリは、歴史総合の学習をより深く、そして楽しくしてくれるはずです。
ぜひ、色々と試して、自分に合ったものを見つけてください。
【疑問を解消】歴史総合の勉強法に関するQ&A(知恵袋で見かける質問も)

歴史総合の勉強法に関するよくある質問を紹介します。
Q2.歴史の勉強は何から始めればいいですか?
Q3.日本史と世界史どっちが難しいですか?
Q4.世界史の歴史総合はいつから必修になるの?
Q5.高一で歴史総合が苦手…どうすれば克服できる?
Q6.勉強時間はどれくらい必要?部活との両立は?
Q7.モチベーションが続かない時の対処法は?
Q8.模試の復習はどうやるのが効果的?
Q9.ワークがない学校だけど、どうやって演習すればいい?
Q1.歴史総合は何から始めればよいですか?
まず、歴史総合の全体像を掴むことから始めましょう。
教科書をざっと読み、どんな時代やテーマを学ぶのか把握します。
次に、興味のある時代や人物から深く掘り下げてみてください。
好きな戦国武将や世界の出来事を入り口に、周辺の知識を広げていくと学習がスムーズに進みます。
授業で扱った範囲をその日のうちに復習する習慣も重要です。
キーワードや年号をノートにまとめ、教科書の重要箇所に線を引くだけでも効果があります。
焦らず、自分のペースで歴史の世界を探求しましょう。

Q2.歴史の勉強は何から始めればいいですか?
歴史の勉強は、「なぜ?」という疑問を持つことから始めましょう。
年号や出来事を暗記するだけでなく、「なぜ起こったのか」「どんな影響を与えたのか」という背景や繋がりを意識することが大切です。
具体的には、教科書を読む際に重要なキーワードに線を引いたり、メモを書き込んだりします。
歴史年表を活用し、出来事の前後関係や同時代の世界情勢を意識することも有効です。
歴史漫画やドラマなどを楽しむのも、歴史への興味を持つ良いきっかけになります。

Q3.日本史と世界史どっちが難しいですか?
日本史と世界史の難易度は、人それぞれです。
日本史は、自国の歴史で親しみやすい反面、時代が長く専門用語も多いです。
世界史は多様な文化を扱いますが、繋がりを理解できた時の面白さは格別です。
どちらを選ぶにしても、興味を持つことが大切です。好きな時代や地域から始めるのがおすすめです。
得意な学習スタイルで選ぶのも良いでしょう。物語が好きなら日本史の人物伝、多様な文化に興味があるなら世界史の地域史から入るのも良いかもしれません。

Q4.世界史の歴史総合はいつから必修になるの?
歴史に関する科目は、2022年度から「歴史総合」「日本史探究」「世界史探究」の3科目になりました。
「歴史総合」は原則として全ての高校生が必修科目です。
これは、日本史と世界史の内容を近現代史を中心に統合的に扱う科目です。
「世界史の歴史総合」という言葉に疑問を感じるかもしれませんが、「歴史総合」自体が日本と世界の近現代史を繋げて学ぶ科目だと理解してください。
現代社会の課題やグローバルな視点を養うことが目標です。

Q5.高一で歴史総合が苦手…どうすれば克服できる?
高1で歴史総合が苦手な場合、まず「どこが苦手なのか」を具体的に把握しましょう。
年号暗記、背景理解、用語の混乱など、原因によって対策が変わります。
対策としては、授業ノートを丁寧に復習し、教科書や参考書と照らし合わせます。
歴史年表や地図を活用して、時間的・地理的な関係性を意識するのも効果的です。
積極的に質問することも重要です。それでも難しい場合は、学習塾やオンライン教材の活用も検討しましょう。
焦らず、自分に合った勉強法を見つけることが大切です。

Q6.勉強時間はどれくらい必要?部活との両立は?
歴史総合の勉強時間は、理解度や目標によります。
授業の予習・復習に加え、定期テスト前には集中的な学習が必要です。
部活動と両立するためには、スキマ時間の活用が鍵となります。
通学時間や休憩時間に単語帳や一問一答を活用したり、週末にまとめて復習時間を確保したりしましょう。
毎日少しでも歴史に触れる習慣をつけることが大切です。
タイマーで集中できる時間を区切ったり、To Doリストで計画的に学習を進めたりするのも有効です。

Q7.モチベーションが続かない時の対処法は?
モチベーションが続かない時は、「なぜ歴史を学ぶのか」という目的を再確認しましょう。
目標を細かく設定し、達成感を積み重ねるのも効果的です。
友達と一緒に勉強したり、教え合ったりするのも良い刺激になります。
時には思い切って休憩し、気分転換することも大切です。
好きな音楽を聴いたり、軽い運動をしたりしてリフレッシュしましょう。

Q8.模試の復習はどうやるのが効果的?
模試の復習は、まず自己採点を丁寧に行い、間違えた問題を分析することから始めます。
「なぜ間違えたのか」原因を特定することが重要です。
正解した問題も必ず見直し、解説を読み込み、関連知識も確認しましょう。
間違えた問題や理解不十分な箇所はノートにまとめ、参考書で再度確認します。
模試の解き直しも効果的です。時間を置いてから再度挑戦することで、理解度を確認できます。
模試の結果を今後の学習に活かしましょう。

Q9.ワークがない学校だけど、どうやって演習すればいい?
学校でワークがない場合は、教科書付属の練習問題や章末問題を積極的に解きましょう。
問題数が少ないと感じる場合は、市販の問題集や参考書を活用するのがおすすめです。
書店で自分に合ったものを選びましょう。
過去の定期テストの問題を入手して解いてみるのも有効です。
先生に相談すれば、過去問を提供してくれる場合もあります。
オンラインの学習プラットフォームやアプリにも豊富な演習問題があります。
積極的に問題に取り組み、間違えた箇所は必ず復習しましょう。
まとめ:【歴史総合の勉強法】これで完璧!定期テストも大学受験も怖くない!

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「【歴史総合の勉強法】これで完璧!定期テストも大学受験も怖くない!」は参考になりましたでしょうか?
まとめ:【歴史総合の勉強法】これで完璧!定期テストも大学受験も怖くない!
この記事では、歴史総合の勉強法について、基礎固めから定期テスト対策、そして大学受験を見据えた学習法まで、幅広く解説してきました。
歴史総合は、単なる暗記科目ではなく、歴史の流れを理解し、現代社会との繋がりを考察する力を養うための科目です。
今回ご紹介した教科書の読み方、ノートのまとめ方、効率的な暗記術、資料問題へのアプローチ、そして自分に合った教材の選び方を実践することで、皆さんは必ず歴史総合を得意科目にすることができます。
大切なのは、日々の授業を大切にし、予習・復習を習慣にすること。
今回紹介したWebサイトやアプリなどのデジタルツールも積極的に活用し、多角的な視点から歴史を学ぶことです。
定期テスト前には、出題傾向を把握し、計画的に対策を進めることで、高得点も夢ではありません。
大学受験においては、共通テストで問われる資料読解力や思考力を磨くことが重要になります。
過去問や模試を活用し、実践的な演習を積み重ねることで、本番でも自信を持って臨めるはずです。
歴史総合の学習を通して培われる、過去から学び未来を考える力は、皆さんの人生においてかけがえのない財産となります。
この記事を参考に、今日から一歩踏み出し、歴史総合の学習を楽しみながら、定期テストも大学受験も自信を持って突破してください!応援しています!
成績アップ!日本史おすすめ勉強情報
大学受験日本史!おすすめ参考書&問題集17選!レベル別×合格への最強ルート
【日本史】年号を語呂合わせで暗記する【大学受験】語呂合わせ一覧
日本史の勉強法は教科書をよく読む!【これならできる日本史の勉強】
【日本史の覚え方】3ステップで主要人物・年号・流れを暗記する最強術!
「歴史総合」と「日本史探究」の違いとは?科目選択で後悔しない完全ガイド
山川の日本史用語集の使い方!【ポイント3つ】日本史の暗記が効率的に!
詳説日本史ノート「最強の使い方&勉強法」で成績UP!高校生・受験生必見の完全ガイド
日本史探求の最強勉強法!歴史総合もこれで完璧【おすすめ参考書8選】
【2025年】MARCH日本史おすすめ参考書25選!基礎から合格まで完全網羅
【歴史総合の勉強法】これで完璧!定期テストも大学受験も怖くない!
社会の選択は日本史で決まり!大学受験│日本史の勉強はいつから始めるべき?