日本史Aと日本史Bの違いを徹底比較!大学受験で後悔しない選び方と勉強法
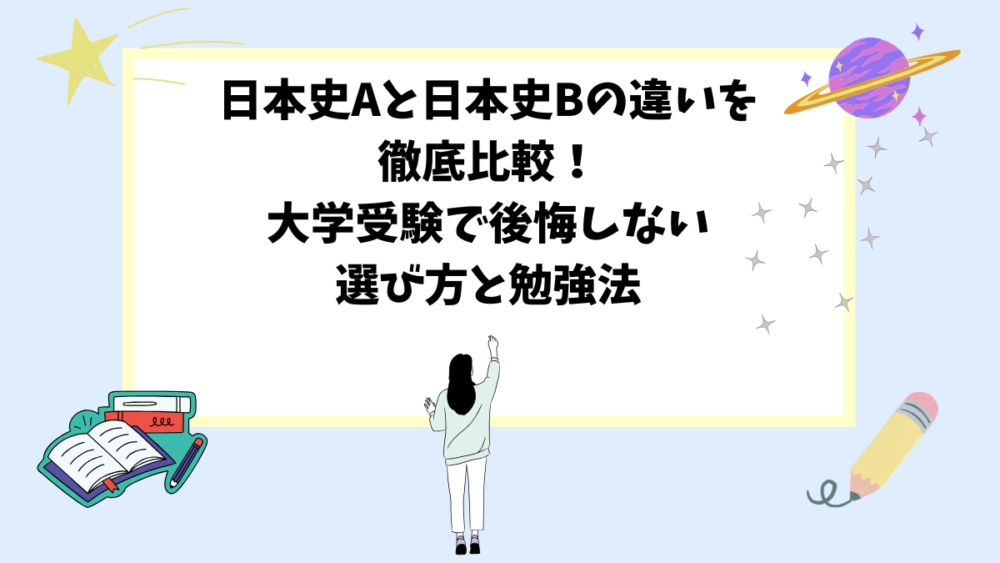
「※この記事には一部PRが含まれます」
「高校で日本史Aや日本史Bを学んだけど、大学受験でどう扱われるの?」 「新課程の『歴史総合』や『日本史探究』と、昔の日本史って何が違うんだろう?」
もしかしたら、あなたは今、そんな疑問を抱えていませんか?
特に、旧課程で学んだ方(浪人生や社会人、学び直しの方)は、あの頃の科目選択が正しかったのか、改めて確認したいと思っているかもしれませんね。
この記事では、長年学習塾で日本史指導に携わり、数々の生徒を合格に導いてきた私が、旧課程の「日本史A」と「日本史B」の決定的な違いを徹底的に解説します。
その上で、新課程の「歴史総合」や「日本史探究」との関連性も踏まえ、あなたの疑問を解消し、後悔しない科目選択と効果的な勉強法をアドバイスします。
【おすすめオンライン塾】
現役東大生のノウハウが凝縮
受験の勝ち方を熟知した!
東大生・早慶生が徹底サポート
旧課程と新課程(歴史総合・日本史探究)の関連性を明確化
指導経験に基づく、後悔しない科目選択と実践的勉強法
大学受験における日本史の役割とよくある疑問への回答
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
現役の東大・旧帝大・早慶生が指導|スタディコーチ
※東大式「逆授業」で学力を伸ばす!夢の志望校合格へ!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
Contents
【日本史Aと日本史B】知っておくべき決定的な違い5つ
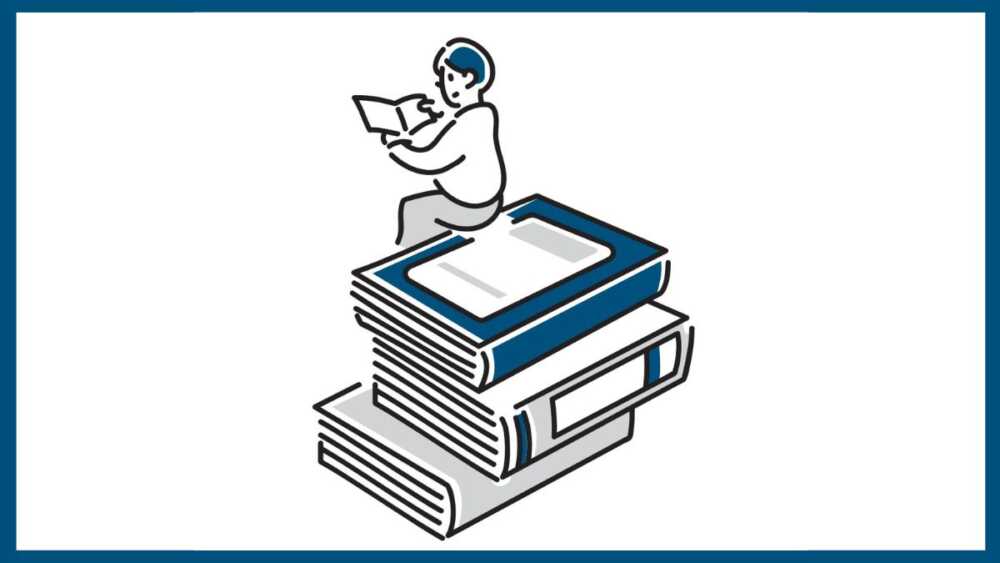
高校で日本史を学ぶ際、多くの生徒さんが直面したのが日本史Aと日本史Bの選択でした。
この二つの科目は、名前は似ていますが、学習する内容、量、そして大学受験での役割において大きな違いがありました。
ここでは、旧課程で学んだ方が理解を深めるため、また新課程の生徒さんが旧課程の日本史科目の特徴を知るために、その決定的な5つの違いを詳しく解説していきます。
違い2:高校での単位数と授業時間
違い3:試験の傾向と難易度
違い4:大学入試での利用可能性と重要度
違い5:2025年からの新課程における位置づけ
違い1:学習範囲と内容の広さ(近現代 vs 通史)
日本史Aと日本史Bの最も大きな違いは、学習する時代の範囲にありました。
この範囲の違いが、その後の学習の難易度や大学入試への影響を大きく左右しました。
・日本史Aの概要(近現代史中心、時代・テーマ別に比較)
日本史Aは、主に近現代史(明治時代以降)に特化した科目でした。特定のテーマに焦点を当てて、深く掘り下げて学びます。たとえば、政治史、経済史、文化史など、それぞれのテーマを時代を追って詳細に学ぶことが多かったです。そのため、原始・古代から学ぶ日本史Bに比べ、学習範囲は狭く設定されていました。
・日本史Bの概要(原始・古代から現代までの通史)
日本史Bは原始・古代から現代までの日本の歴史を網羅する「通史」でした。文字通り、日本のすべての時代を時系列に沿って学習します。たとえば、旧石器時代から始まり、縄文、弥生、飛鳥、奈良…と、現在の日本に至るまでの歴史の流れ全体を学びました。そのため、日本史Aに比べて圧倒的に学習範囲が広く、深い知識が求められていました。私が教えてきた生徒さんの中には、「日本史Aなら楽そう」と思って選んだものの、テーマごとの深掘りに苦戦するケースも時々見られました。

違い2:高校での単位数と授業時間
学習範囲の広さは、高校での単位数や授業時間にも直結していました。
この違いは、他の科目に割ける学習時間にも影響を与えるため、科目選択の際には考慮すべき重要な点でした。
日本史Aは通常、週2単位(年間70時間程度)で履修されることが多かったです。
一方、日本史Bは週4単位(年間140時間程度)が一般的で、日本史Aの約2倍の時間をかけて学習することになっていました。
この授業時間の差は、学習内容の密度と深さにそのまま反映されるため、他の科目との兼ね合いを考える上で非常に重要でした。
たとえば、理系の生徒で社会科にあまり時間をかけたくない場合は、日本史Aが選択肢になることもあったでしょう。
実際に、理系の生徒さんで日本史Bを選んで苦戦するケースも見てきましたが、その多くは時間配分の問題でした。

違い3:試験の傾向と難易度
学習範囲の差は、大学入学共通テストを含む、各種試験の傾向と難易度にも大きな影響を与えていました。
どちらの科目を選ぶかで、試験対策の方向性も変わってきたのです。
日本史Aは、出題範囲が狭いため、よりテーマ性や史料読解力を問う問題が多い傾向にありました。
平均点は年によって変動が大きく、日本史AがBを上回る年もあれば、BがAを大幅に上回る年もありました。
一概に難易度を平均点だけで比較することは困難です

違い4:大学入試での利用可能性と重要度
ここが、多くの高校生にとって最も重要な違いとなっていました。科目選択が、志望大学の受験に直接影響したからです。
日本史Bは、国公立大学や難関私立大学の多くで、受験科目として採用されていました。
特に、共通テストで社会科が必須となる国公立大学の場合、日本史Bは主要な選択肢の一つでした。
たとえば、東京大学や京都大学のような国公立大学の文系学部では、日本史Bの知識が必須となるケースがほとんどでした。
日本史Bで受験できる大学は非常に限定的でした。
主に私立大学の一部や専門学校での採用が多く、国公立大学ではほとんど利用できませんでした。
安易に日本史Bを選ぶと、志望校の選択肢が大幅に狭まるという大きなリスクがあることを認識しておくべきでした。
私が長年指導してきた中で、この選択ミスで涙を流す生徒さんを何度も見てきました。

違い5:2025年からの新課程における位置づけ
学習指導要領の変更により、現在の高校生が受ける2025年度からの大学入学共通テストでは、日本史A・日本史Bという名称の科目は出題されません。
これらは新課程の科目に移行しています。
従来の日本史Aと日本史Bは、新課程では「歴史総合」と「日本史探究」という科目に再編されます。
「歴史総合」は近現代の日本史と世界史を総合的に学ぶ必修科目となり、「日本史探究」が旧課程の日本史Bに近い、通史を深く学ぶ選択科目となります。
つまり、より深い日本史の知識を問われる大学受験では、この「日本史探究」の学習が必須となります。
旧課程の日本史A・Bの知識は、新課程の日本史探究の基礎となりますが、最新の入試情報やカリキュラムの動向に常に注目しておくことが重要です。
日本史Aと日本史Bの違いを図や表で一目で比較!
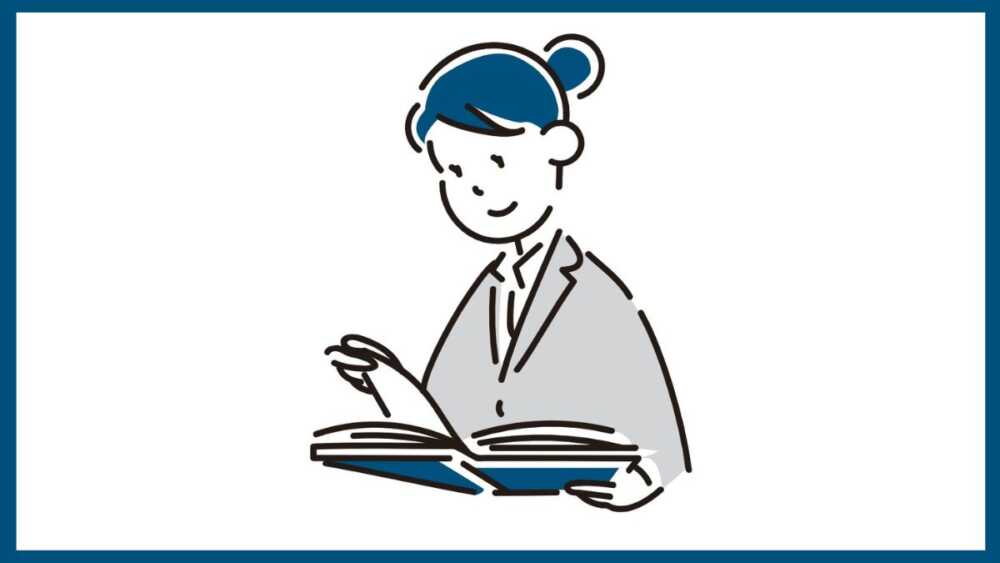
ここまで日本史Aと日本史Bの5つの決定的な違いを解説してきました。
それぞれの特徴を文字で読むだけでなく、一目で理解できるよう、比較表でまとめましたのでご確認ください。
あなたが科目選択を考える際の、また新課程を理解する際の重要な判断材料となるはずです。
| 項目 | 日本史A(旧課程) | 日本史B(旧課程) |
|---|---|---|
| 学習範囲 | 近現代史(明治以降)中心 | 原始・古代~現代までの通史 |
| 学習量 | 比較的少ない | 圧倒的に多い |
| 高校での単位数 | 週2単位程度(年間約70時間) | 週4単位程度(年間約140時間) |
| 試験傾向 | テーマ別、史料読解中心 | 広範囲、歴史の流れと因果関係重視 |
| 難易度(学習) | やや易しい(範囲が狭いため) | 難しい(範囲が広いため) |
| 入試での利用 | 限定的(一部私大、専門学校) | 多数の大学で利用可能(国公立・難関私大) |
| 共通テスト | 選択可能(受験者数はBより少ない) | 選択可能(受験者数が多い) |
| 推奨されるタイプ | 理系で社会科に時間を割けない人、特定の分野に興味がある人 | 文系、国公立・難関私大志望者、歴史好きな人 |
大学受験で後悔しない!日本史Aと日本史B、あなたに最適なのはどっち?

日本史Aと日本史Bの具体的な違いを理解した上で、次に考えるべきは「結局、自分はどちらを選ぶべきなのか?」という最も重要な選択です。
あなたの志望大学や将来の目標によって、最適な選択は異なります。
ここでは、それぞれの科目がどんな生徒さんに適していたか、そして安易な選択がなぜ危険だったのかを解説します。(※この章は主に旧課程の生徒さんの科目選択の判断を想定しています。)
日本史Bが向いている人・おすすめのケース(文系、難関大志望、幅広い大学受験を視野に入れる場合)
【警告】安易な日本史A選択が危険な理由と後悔しないための判断基準
日本史Aが向いている人・おすすめのケース(理系で社会科に時間を割けない、専門学科など)
日本史Aは、特定の状況下で選択肢となり得た科目でした。
主に、社会科に多くの学習時間を割けない生徒さんにおすすめしていました。
たとえば、理系学部を志望していて、数学や理科の学習に重点を置きたい生徒さんは、学習負担の少ない日本史Aを選ぶことで、他の科目に時間を有効活用できる場合がありました。
商業科や工業科といった専門学科の高校で、大学受験よりも専門分野の学習を優先したい場合も、日本史Aが適していることがありました。
この選択は大学の選択肢を狭めることを十分に理解しておく必要がありました。

日本史Bが向いている人・おすすめのケース(文系、難関大志望、幅広い大学受験を視野に入れる場合)
多くの大学受験生、特に文系志望の生徒さんには、日本史Bの選択を強く推奨していました。
日本史Bは、大学受験で最も汎用性が高く、有利な科目だったからです。
具体的には、国公立大学や難関私立大学の文系学部を志望する生徒さんは、迷わず日本史Bを選ぶべきでした。
ほとんどの大学で日本史Bが受験科目として認められており、選択肢が広がるためです。
将来的に幅広い進路の可能性を残しておきたい生徒さんや、純粋に歴史が好きで深く学びたい生徒さんにも日本史Bは最適でした。
日本史Bは学習範囲が広い分、努力次第で大きな得点源にすることも可能でした。

【警告】安易な日本史A選択が危険な理由と後悔しないための判断基準
「日本史Aは範囲が狭いから楽そう」という理由だけで安易に選んでしまうと、将来的に大きな後悔につながる可能性がありました。
日本史を指導してきた経験から言えるのは、安易な日本史A選択は志望校の選択肢を大幅に狭めてしまうということでした。
多くの国公立大学や難関私立大学では、日本史Bを必須、または推奨科目としていました。
高校入学時には漠然としか進路を決めていなかったとしても、学年が上がるにつれて志望校が明確になった際、「日本史Aでは受験できない…」という絶望的な状況に直面する生徒を数多く見てきました。
高校3年生になってからの科目変更は非常に困難です。
科目選択は、あなたの将来を左右する重要な判断であることを忘れないでください。
必ず、現時点での志望校だけでなく、将来的な可能性も視野に入れて慎重に判断するようにしましょう。
【日本史B/日本史探究選択者必見】膨大な範囲を攻略する効率的な勉強法とコツ

用語・年号の効率的な暗記法(一問一答、反復学習、視覚情報活用)
つまずきやすい文化史・外交史の対策法
アウトプット重視!過去問・問題集を使った実践演習サイクル
おすすめの参考書・問題集と活用法
旧課程で日本史Bを選んだ、あるいは新課程で「日本史探究」を学ぶあなた。
確かに範囲は広いですが、正しい勉強法を実践すれば、必ず得意科目にできます。
学習塾で数々の生徒を合格に導いてきた私が、その効率的な学習法とコツを伝授します。
勉強の基本は「歴史の流れ」の理解から
日本史B(または日本史探究)の勉強で最も大切なのは、用語を暗記する前に、まず「歴史の流れ」を掴むことです。
多くの生徒さんがいきなり用語の暗記から入って挫折してしまいます。
たとえば、年号や人物名をただ丸暗記するのではなく、「なぜこの出来事が起きたのか」「この人物は何をしたのか、その背景は何か」といった因果関係を意識しながら学習しましょう。
教科書を読み込む際は、出来事が起きた背景、結果、その後の影響をノートにまとめるなどして、ストーリーとして理解することが重要です。
時代の流れが頭に入っていれば、個別の用語も繋がりやすくなり、忘れにくくなります。
私の塾では、まず年表を使って大まかな流れを掴むことを徹底させていました。

勉強計画を作成してくれるコーチング塾:勉強計画を立ててくれる塾おすすめ17選!大学受験で逆転合格へ!
用語・年号の効率的な暗記法(一問一答、反復学習、視覚情報活用)
歴史の流れを理解したら、次に必要になるのが正確な用語や年号の知識です。
ここでは、効率的な暗記法を具体的にご紹介します。
多くの生徒を指導してきて効果的だったのは、一問一答形式の反復学習です。
例えば、市販の一問一答集を使い、完璧に答えられるようになるまで何度も繰り返すことが重要です。
一度覚えたと思っても、時間を置いて何度も復習することで、長期記憶に定着します。
教科書の図や写真、資料集の絵などを積極的に活用する「視覚情報活用」も有効です。
出来事のイメージと結びつけることで、用語が記憶に残りやすくなります。
年号は語呂合わせを活用するのも良いでしょう。

つまずきやすい文化史・外交史の対策法
日本史B(または日本史探究)の中で、多くの受験生がつまずきやすいのが文化史と外交史です。
これらは独特の知識が求められるため、特別な対策が必要です。
文化史は、時代ごとの特徴や、各文化財の名称、作者などを覚えるのが大変です。
対策としては、文化史に特化した参考書や資料集を繰り返し読み込み、写真とセットで覚えることを意識してください。
たとえば、仏像の名称と制作された時代、特徴などをセットで覚えることが重要ですす。
外交史については、国際情勢と日本国内の動きを連動させて理解すると良いでしょう。
なぜその外交政策が取られたのか、国際的にどのような影響があったのかなど、背景と結果をセットで把握することで、より深く理解できます。
私の指導経験でも、ここを乗り越えれば点数が飛躍的に伸びる生徒が多かったです。

アウトプット重視!過去問・問題集を使った実践演習サイクル
インプットばかりでは、知識は定着しません。
学んだ知識を「使える知識」にするためには、アウトプットが不可欠です。
教科書や参考書で知識をインプットしたら、必ず問題集を使って演習を行いましょう。
特に、共通テストや志望大学の過去問は、出題傾向を知る上で最も重要な教材です。
問題を解いたら、丸付けをして終わりではなく、間違えた問題は必ず解説を読み込み、なぜ間違えたのか、どこが分かっていなかったのかを徹底的に分析してください。
そして、間違えた知識をもう一度インプットし直し、再度問題を解くというサイクルを繰り返すことで、知識がより強固になります。
この「インプット→アウトプット→分析→再インプット」のサイクルを、習慣にしてください。

参考記事:山川【日本史一問一答】の使い方を知って日本史の偏差値アップ
おすすめの参考書・問題集と活用法
適切な参考書や問題集を選ぶことは、日本史B(または日本史探究)の学習効率を大きく左右します。
あなたのレベルや目標に合わせた教材を選びましょう。
まずは、学校で配られる教科書と資料集を徹底的に活用してください。
これが学習の基本です。
その上で、通史を理解するための参考書(例えば、『金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本』のような講義系参考書)と、用語を覚えるための一問一答集(例えば、『日本史一問一答 完全版』)を準備しましょう。
問題集は、共通テスト対策用の問題集から始め、その後、志望大学の過去問へと移行していくのがおすすめです。
それぞれの教材を並行して使い、常にアウトプットを意識しながら学習を進めていくことが合格への近道です。

参考記事:日本史探求の最強勉強法!歴史総合もこれで完璧【おすすめ参考書8選】
日本史A・日本史Bに関するよくある質問(Q&A)

ここでは、旧課程の日本史Aと日本史Bの選択や学習に関して、生徒さんや保護者の方からよくいただく質問にお答えします。
あなたが抱える疑問や不安を解消する手助けになれば幸いです。
日本史Bは本当に難しい?諦めずに取り組むには?
日本史AとBは新課程でどう変わった?(歴史総合・日本史探究との関連)
日本史AとBのどちらが難しいですか?
歴史AとBの違いは何ですか?
日本史Bと日本史の違いは何ですか?
共通テストの日本史AとBの違いは何ですか?
科目選択後に変更は可能?
日本史Aでも難関大学は受験できる?
旧課程で日本史Aを履修すると、難関大学を受験するのは非常に難しいです。
旧課程の国公立大学の多くは、共通テストで「日本史B」を想定した出題範囲であったため、日本史Aの知識だけでは対応できませんでした。
私立大学でも、早稲田大学や慶應義塾大学といった難関大学の主要学部では、日本史B(通史)の知識が求められることがほとんどでした。
例外として、特定の学部(例:芸術系、体育系)や一部の私立大学で日本史Aでも受験可能なケースはありましたが、非常に限定的でした。
私が指導した中でも、日本史Aで難関大を目指した生徒は、最終的に科目変更の壁にぶつかることが多かったです。
もし難関大学を目指すのであれば、基本的には日本史Bを選択すべきだと考えてください。

参考記事:東進日本史一問一答の使い方と特徴!「必修版」「完全版」「3rd」との違い
日本史Bは本当に難しい?諦めずに取り組むには?
日本史B(および新課程の日本史探究)は学習範囲が広いため、確かに「難しい」と感じる生徒さんは多いです。
しかし、諦める必要は全くありません。
私が指導してきた経験上、日本史Bで伸び悩む生徒さんの多くは、基礎が固まっていないか、効率的な勉強法を知らないだけです。
先ほどご紹介した「歴史の流れの理解」「反復学習」「アウトプット重視」といった正しい勉強法を実践すれば、誰でも必ず得意科目にできます。
地道な努力が必ず報われる科目ですので、焦らず、着実に学習を進めていきましょう。
つまづいたときは、参考書を読み直したり、信頼できる先生に質問したりして、疑問をすぐに解消することが重要です。

参考記事:大学受験日本史!おすすめ参考書&問題集17選!レベル別×合格への最強ルート
日本史AとBは新課程でどう変わった?(歴史総合・日本史探究との関連)
2022年度から高校で新しい学習指導要領が施行され、2025年度からの大学入学共通テストにも影響が出ます。
従来の日本史Aと日本史Bは、新課程では「歴史総合」と「日本史探究」という科目に再編されます。
「歴史総合」は近現代の日本史と世界史を総合的に学ぶ必修科目となり、「日本史探究」が旧課程の日本史Bに近い、通史を深く学ぶ選択科目となります。
つまり、より深い日本史の知識を問われる大学受験では、この「日本史探究」の学習が必須となります。
新しい課程への移行に伴い、大学側の入試方針も変化する可能性があるため、常に最新の情報を確認するようにしてください。

日本史AとBのどちらが難しいですか?
一概にどちらが「難しい」とは言えません。
学習する範囲と求められる知識の性質が異なるためです。
・日本史A(旧課程):範囲は狭いですが、その分深い理解やテーマごとの分析力が問われていました。
・日本史B(旧課程):範囲は広大ですが、歴史の流れや因果関係をしっかり理解できれば、多くの大学で対応できました。
多くの大学で必要とされる学習量と汎用性を考えると、日本史Bのほうが大変に感じるかもしれませんが、正しい勉強法で取り組めば必ず成果が出ます。
どちらも奥深く、やり方次第で得意科目になりますよ。

歴史AとBの違いは何ですか?
「歴史AとB」は、多くの場合「日本史Aと日本史B」を指すと考えられます。
その最も大きな違いは、学習する時代の範囲にありました。
・日本史A(旧課程):主に明治時代以降の近現代史に焦点を当て、テーマ別に深く学びました。
・日本史B(旧課程):原始・古代から現代までの日本の歴史全体を、時系列に沿って網羅的に学びました。
この範囲の違いが、高校での単位数、授業時間、そして大学入試での利用可能性に大きな影響を与えていました。
混乱しやすい点ですが、基本的には「日本史」というくくりで理解すると良いでしょう。

日本史Bと日本史の違いは何ですか?
一般的に高校の科目選択や大学受験において「日本史」という場合、多くは「日本史B」を指していることが多かったです。
「日本史」という言葉は、文字通り日本の歴史全般を指しますが、高校の学習指導要領においては「日本史A」と「日本史B」という2つの科目に分かれていました。
したがって、「日本史B」は「日本史」という大きなカテゴリーの中の、原始・古代から現代までの通史を扱う科目の名称だと理解してください。
学校の先生や予備校講師が「日本史」と言ったら、ほとんどの場合、日本史B(通史)の話をしていると考えて大丈夫です。

共通テストの日本史AとBの違いは何ですか?
大学入学共通テストにおける日本史Aと日本史Bの主な違いは、出題される範囲と問題の傾向でした。
・日本史A(旧課程):主に近現代史からの出題が中心となり、史料読解やテーマ別の考察力が問われる問題が多く含まれていました。
・日本史B(旧課程):全時代(原始・古代から現代まで)から幅広く出題されていました。史料読解に加え、年代の並び替えや出来事の因果関係を問う問題など、より広範な知識と歴史的思考力が求められていました。
平均点は年によって変動しましたが、国公立大学や難関私立大学の多くは、日本史Bでの受験を前提としていました。
新課程に移行しても、この通史を重視する傾向は「日本史探究」で引き継がれると予想されます。

科目選択後に変更は可能?
高校入学後の社会科目の選択は、原則として途中で変更することは非常に難しいです。
特に日本史Aから日本史Bへの変更は、学習範囲の差が大きすぎるため、新たに日本史Bの内容を独学で追いつくのは相当な努力が必要になります。
学校によっては特別な対応をしてくれるケースもありますが、それはまれです。
私が学習塾で、科目変更をして成功した生徒はごく一部で、ほとんどの場合は大きな負担や後悔につながっていました。
そのため、科目選択は高校1年生のうちに、将来の進路を十分に考慮して慎重に行うことが何よりも重要です。
もし変更を考える場合は、速やかに学校の先生や進路指導の担当者に相談してください。
現役の東大・旧帝大・早慶生が指導|スタディコーチ
※東大式「逆授業」で学力を伸ばす!夢の志望校合格へ!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
参考記事:逆転コーチングの口コミ・評判は本当?怪しい・やばい噂の真相を取材で徹底検証
まとめ:日本史Aと日本史Bの違いを徹底比較!大学受験で後悔しない選び方と勉強法

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「日本史Aと日本史Bの違いを徹底比較!大学受験で後悔しない選び方と勉強法」は、参考になりましたでしょうか?
まとめ:日本史Aと日本史Bの違いはたったこれだけ!
日本史Aと日本史Bの違いをまとめると以下のようになります。
単位数と選択される高校の特性
日本史A:2単位の科目で、工業高校や商業高校などの専門分野を学ぶ高校で主に選択される。
日本史B:4単位の科目で、普通科の高校で広く選択される。
学習範囲
日本史A:主に近現代史
日本史B:原始時代や古代から現代までの日本の歴史を網羅的に学ぶ。
受験の利用可能性
日本史A:選択できる大学が限定的
日本史B:大学の入試、特に国公立大学の共通テストや個別試験での使用が可能。
総じて、日本史Aは範囲が狭く、受験科目としての利用性が低い一方で、日本史Bは広範囲にわたり、多くの大学入試で必要とされる重要な科目となっています。
日本史Aと日本史Bの選択は、学校や地域、大学の入試要項によって異なる場合があります。具体的な選択肢や出題内容は、受験する学校や志望校の入試要項を確認する必要があります。それぞれの大学の公式ウェブサイトや入試案内を参照し、正確な情報を入手してください。
成績アップ!日本史おすすめ勉強情報
大学受験日本史!おすすめ参考書&問題集17選!レベル別×合格への最強ルート
【日本史の年号】語呂合わせ!大学受験で「覚えるべき50選」と最強の暗記法
日本史の勉強法は教科書が最強!歴史総合・日本史探求の理解を深める6ステップ
【日本史の覚え方】最強の3ステップ!『暗記』と『探究』を両立して点数UP
「歴史総合」と「日本史探究」の違いとは?科目選択で後悔しない完全ガイド
山川の日本史!超鉄板おすすめの参考書6冊と勉強ルート!探究・歴史総合対応
山川の日本史用語集の使い方!【ポイント3つ】日本史の暗記が効率的に!
詳説日本史ノート「最強の使い方&勉強法」で成績UP!高校生・受験生必見の完全ガイド
日本史探求の最強勉強法!歴史総合もこれで完璧【おすすめ参考書8選】
【日東駒専対策】日本史の参考書のおすすめ10冊!8割取れる勉強ルート
【2025年】MARCH日本史おすすめ参考書25選!基礎から合格まで完全網羅

