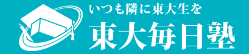【日本史の覚え方】最強の3ステップ!『暗記』と『探究』を両立して点数UP
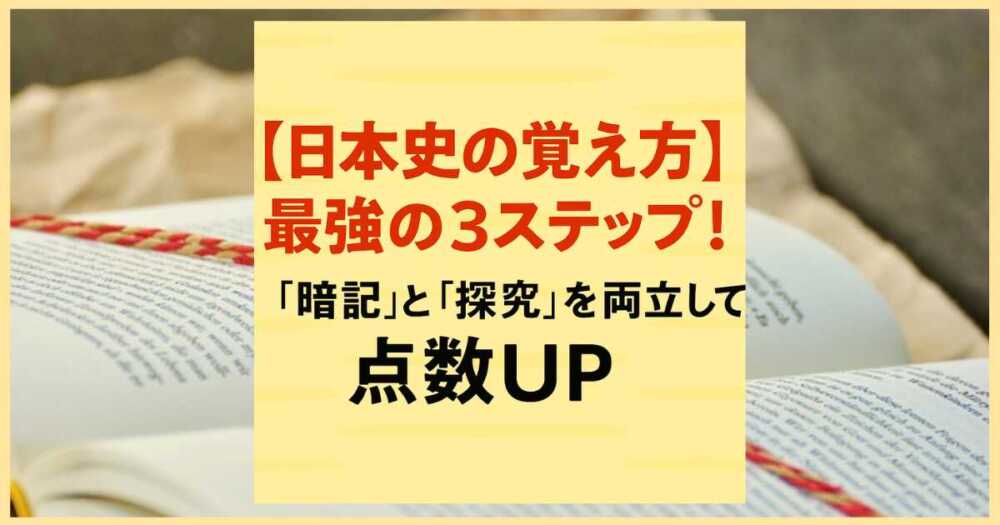
※この記事には一部PRが含まれます。
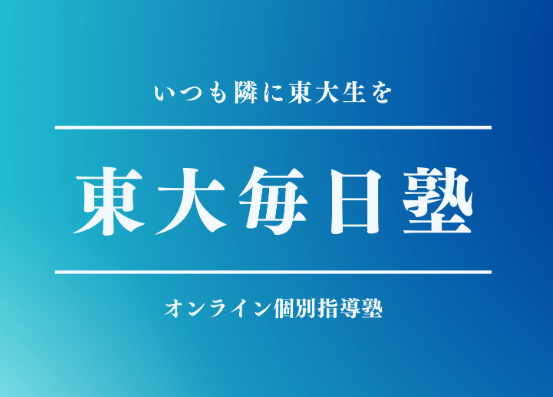 本記事の監修者:東大毎日塾
本記事の監修者:東大毎日塾
本記事の内容は、難関大学合格を目指す受験生を応援する「東大毎日塾」が監修しています。東大毎日塾は、個別指導と学習管理を通じて多くの生徒の学力向上をサポートしており、最適な学習法についての知見を基に記事を作成しました。
「日本史の覚え方」や自分にあった参考書をお探しの方は、東大毎日塾にお問い合わせください。
日本史が覚えられない高校生へ
「書いても覚えられない」「プリントは暗記したのに点数が伸びない」
予備校オンラインドットコム編集部には、この悩みが多く届きます。
27年以上学習塾に携わってきた経験から断言できることがあります。
日本史は“暗記科目”ではなく、“理解して覚える科目”です。
新課程では「探究」や資料読解が重視され、丸暗記では得点できません。
この記事では、知識が自然と頭に入り、テストでも点数に直結する日本史の最強の覚え方3ステップを解説します。
・丸暗記から卒業!暗記と探究を両立する3ステップ
・原因と結果で流れをつかむ最強の覚え方
・点数が伸びる白紙テストのやり方
・定期テスト/共通テスト/大学受験の対策法もわかる
Contents
日本史が覚えられない理由と“正しい覚え方”を知ることの重要性

日本史が覚えられない高校生の多くは、文脈のない暗記や優先順位のない勉強が原因です。
まずは「なぜ覚えられないのか」を知ることが、成績アップへの第一歩です。この章では、日本史の覚え方の基本となる考え方を分かりやすく解説します。
日本史の覚え方の本質は「原因と結果」
書き続けても暗記できないのは“文脈がない”から
覚える量に圧倒される理由は「優先順位がない」から
日本史の覚え方の本質は「原因と結果」
日本史の覚え方で一番大切なのは、出来事を原因と結果でつなぐことです。
例えば、「鎌倉幕府はどうして成立したのか?」と理由を考えるだけで理解が深まります。
用語を単独で覚えるのではなく、出来事の流れをつかむことで記憶が安定し、定期テストでも点が取りやすくなります。

書き続けても暗記できないのは“文脈がない”から
ひたすら書く暗記が失敗しやすいのは、そこにストーリー(文脈)がないからです。
例えば「大化の改新」だけを覚えても、「なぜ起きたのか」「誰が中心なのか」を知らないとすぐ忘れてしまいます。
背景とセットで覚えると、知識がつながりやすくなります。

覚える量に圧倒される理由は「優先順位がない」から
日本史は覚える量が多いですが、すべてを同じ重要度で覚える必要はありません。
まずは太字用語や頻出事項などコア知識を優先しましょう。
例えば、教科書の太字→資料集の重要文化→頻出の人物の順に覚えると効率が上がります。
優先順位をつけることで暗記が楽になります。
日本史の覚え方は3ステップでOK(新課程・探究対応)

日本史は、正しい手順で勉強すれば誰でも点数を伸ばせます。
ここでは、暗記が苦手な高校生でも実践しやすい3つのステップを紹介します。
通史の理解→セット暗記→アウトプットの順に進めることで、新課程の「探究」でも通用する力が身につきます。
このシンプルな手順で、暗記の壁を突破しましょう。▶「歴史総合」と「日本史探究」の違いについて
【ステップ2】重要人物・出来事・年号をセットで覚える
【ステップ3】アウトプットで定着させる:白紙テストの活用
【ステップ1】通史の流れをつかむ:原因と結果で覚える
日本史の勉強でもっとも大切なのは、最初に大きな流れをつかむことです。
細かい知識を覚える前に、まずは次の2つを押さえてみてください。
・何が原因で起きた出来事なのか
・その結果どうなったのか
この“原因と結果”をつなげて読むと、内容がストーリーのようにつながり、忘れにくくなります。
予備校オンラインドットコム編集部の学習塾経験者の経験からも、通史を理解した生徒は定期テストでも大学受験でも点が急に伸びるケースが多いです。
まずは、全体の流れをざっくりつかむことから始めてください。
※今日の勉強で1つだけ、原因→結果を書き出してみてください。それだけで流れの理解が一気に深まります。

【ステップ2】重要人物・出来事・年号をセットで覚える
日本史の覚え方の中でも、年号の暗記は語呂合わせを使うと覚えやすくなります。
語呂合わせは短時間の暗記にも強く、特にテスト直前の見直しに効果的です。
流れがつかめたら、次に覚えるのはその時代の最重要ポイントです。
特におすすめなのが、次の「4点セット」で覚える方法です。
1.人物
2.政策や出来事
3.年号
4.時代背景
例えば「徳川吉宗」と覚えるときは、「享保の改革」や財政難の背景まで一緒に覚えると、問題文から判断しやすくなります。
これは新課程で重視される“探究型の理解”にもつながり、共通テストでも効果を発揮します。
※人物・出来事・年号の中から1セットだけでもいいので、今日のうちにまとめてみてください。セットで覚えると忘れにくさが全然違います。

【ステップ3】アウトプットで定着させる:白紙テストの活用
覚えたことをしっかり定着させるためには、アウトプット(書き出す)が必要です。
日本史の覚え方で特に効果が高いのが、この白紙テストです。
・教科書やノートを閉じる
・白紙に覚えていることを書き出す
・思い出そうとする負荷をかける
この3つだけで、記憶は一気に定着します。
学習塾の現場でも、短時間の白紙テストを続けた生徒は、テスト本番で知識を思い出すスピードが大幅に上がっています。
毎日5分だけでも続けると、大きな力になります。
共通テストでは、日本史の覚え方として“資料から特徴を読み取る力”が求められます。
白紙テストと合わせて、教科書や資料集の図版を見て特徴を言語化する練習を取り入れると得点につながります。
※白紙テストは1分でも効果があります。覚えた範囲を短く書き出す練習を今日ひとつだけやってみてください。
白紙テストとは、教科書やノートを見ずに、白紙の紙に今覚えている知識をすべて書き出す学習法です。
【具体的なやり方】
・学習範囲をインプットした後、何も見ない状態で白紙を用意します。
・その範囲の重要用語、年号、人物、因果関係などを、可能な限り書き出します。
・書き終わったら、すぐに教科書や解答と照らし合わせ、赤ペンで修正・加筆します。
ステップ1:日本史の「流れ」を最速でつかむ方法(新課程)

通史の理解は日本史の土台です。
ここでは、初心者でも最速で流れをつかめる方法を紹介します。
物語として読む、因果関係を可視化する、毎日の短時間ルーティン、動画や資料集の活用など、理解を深めるコツをわかりやすくまとめました。
因果関係を矢印でつなぐ
ゼロからの人向け:1日5分ルーティン
動画・漫画・資料集でイメージをつくる方法
物語で覚えると忘れにくい
通史は「ストーリー」として覚えると頭に入りやすくなります。
例えば、平安から鎌倉への流れを「武士が力をつけ、政治が変わる物語」として読むと、出来事がつながって記憶しやすくなります。
人物の目的や気持ちを考えながら読むと、内容の理解がさらに深まります。

因果関係を矢印でつなぐ
出来事を覚えるときは、原因→結果を矢印で結ぶだけで理解が大きく進みます。
例えば「遣唐使廃止→国風文化の発展」という流れを矢印でまとめると、テストで理由を問われても対応しやすくなります。
自分だけの“流れメモ”を作るのもおすすめです。

ゼロからの人向け:1日5分ルーティン
日本史が苦手な人は、まず1日5分だけ通史に触れる習慣を作りましょう。
例えば、寝る前に教科書の見出しだけ確認したり、昨日覚えた範囲を軽く見直すだけでもOKです。
接触回数が増えることで、脳が情報を「重要」と判断し、自然と暗記が進みます。

動画・漫画・資料集でイメージをつくる方法
難しい時代や文化は、視覚的なツールを使うと理解が早くなります。
歴史漫画で大まかな流れをつかみ、YouTubeの解説動画で補足し、資料集で実際の写真を確認する流れが効果的です。
例えば、鎌倉文化の仏像を写真で見ると、時代背景と結びついて忘れにくくなります。

日本史の勉強法は教科書が最強!歴史総合・日本史探求の理解を深める6ステップとして、通史の進め方を具体的に解説しています。
ステップ2の詳しい覚え方:セット暗記術

日本史は、単語をバラバラに覚えるとすぐに忘れてしまいます。
ここでは、人物・出来事・年号をひとつの流れとして覚える「セット暗記」の方法を紹介します。
セット化することで内容がつながり、そのままテストで使える知識になります。
日本史人物の覚え方:政策・時代背景と合わせて覚える
日本史年号の覚え方:語呂合わせ・歌の活用
文化史の覚え方:視覚で覚える
テーマ史の覚え方:横の流れで理解する
セット暗記が最強な理由
セット暗記とは、用語を「人名」「年号」「出来事」の塊で覚えることです。
例えば、「徳川吉宗」「享保の改革」「目安箱の設置」をセットで覚えます。
一つの用語を思い出すだけで関連情報が一気に引き出され、探究に必要な知識の奥行きが生まれます。
知識がバラバラになるのを防ぐ上で、非常に大きなメリットとなります。

参考記事:山川の日本史用語集の使い方!【ポイント3つ】日本史の暗記が効率的に!
日本史人物の覚え方:政策・時代背景と合わせて覚える
人物を覚える際は、その人物が「なぜ」重要なのかを常に意識しましょう。
以下の4点をセットで覚えることで、定期テストの記述問題や大学受験の論述問題にも対応できる力が身につきます。
1.誰が(人物名)
2.何をしたか(政策・出来事)
3.いつ(年号)
4.その結果(時代背景・影響)
具体的には、ただ「徳川家康」と覚えるのではなく、「安土桃山時代から江戸時代に武家諸法度などを定めた人物」と覚えるのがおすすめです。
日本史年号の覚え方:語呂合わせ・歌の活用
年号を覚えるときは、語呂合わせや歌を使うと記憶に残りやすくなります。
例えば、「645年=大化の改新(むしごよい)」のように、イメージをつけると忘れにくくなります。
ただし、語呂合わせだけに頼らず、その出来事が時代のどんな転換点だったかもセットで理解することが大切です。
短時間で思い出す力を鍛えたいときに特に効果的です。

語呂合わせと最強の暗記法については、【日本史の年号】語呂合わせ!大学受験で「覚えるべき50選」と最強の暗記法でさらに詳しく解説しています。
文化史の覚え方:視覚で覚える
多くの高校生が苦手とする文化史は、視覚的なツールで覚えるのが最も効率的です。
文化史だけ覚えられないとお悩みなら、まず資料集の作品を見て覚えることから始めてみましょう。
視覚情報と、文化が生まれた時代の背景(例えば、貴族文化か武家文化か)をセットで整理することで覚えやすくなります。

テーマ史の覚え方:横の流れで理解する
テーマ史では、外交・税制・政党など「時代をまたぐ変化」を横につなげて理解する必要があります。
例えば、税のしくみなら「庸→租→公事→年貢」のように、仕組みがどう変化したかを表にすると一目で分かります。
共通テストや難関私大ではテーマ史が頻出なので、通史と合わせて整理しておくと得点力が大きく上がります。
ステップ3の詳しい覚え方:アウトプット戦略

覚えた知識を確実に点数につなげるためには、「思い出す練習」が欠かせません。
ここでは、白紙テストや一問一答、ノートの使い方、復習のタイミングなど、知識を長く残すためのアウトプットの方法をまとめて解説します。
一問一答の正しい使い方
ノートまとめの作り方:教科書を“探究ノート”にする
忘却曲線に合わせた復習スケジュール
歌・アプリ・単語帳でスキマ時間を最大化する
白紙テストが最短で伸びる理由
白紙テストは、教科書やノートを閉じて覚えた内容を書き出す方法です。
人は「思い出そうとしたとき」に記憶が強く定着するため、短い時間でも効果があります。
例えば、昨日覚えた人物や出来事を5分だけ白紙に書き出すだけで、復習効率が大きく変わります。
予備校オンラインドットコム編集部の経験上、白紙テストを習慣にした生徒ほど、模試の点数が安定しています。

一問一答の正しい使い方
一問一答は基礎固めに有効ですが、知識がバラバラになるという課題や懸念点があります。
やってはいけない暗記法は、答えを覚えるまでひたすら繰り返すことです。
正しい使い方は、間違えた問題の前後関係や理由をすぐに教科書で確認し、知識をセット化し直すことです。
山川【日本史一問一問】の使い方も参考にしながら、正しいアウトプット法を実践しましょう。

ノートまとめの作り方:教科書を“探究ノート”にする
教科書をただ書き写すだけのノートは、時間の無駄です。
探究ノートにするためには、知識の構造化を意識し、出来事の横に「なぜ起きた?」「影響は?」といった問いを書き込みましょう。
例えば、豊臣秀吉の政策の横に「メリットとデメリット」を書き出すだけで、論述の練習になります。
詳しいノート術の完全ガイド(詳説日本史ノート「最強の使い方&勉強法」)も参考に、自分だけの探究ノートを作りましょう。

忘却曲線に合わせた復習スケジュール
人間の記憶は時間と共に忘れていく(忘却曲線)ため、適切なタイミングで復習することが覚え方のポイントです。
覚えた当日の夜、翌日、そして一週間後、一か月後と間隔を空けて復習しましょう。
分散学習こそが、暗記が苦手な人でも知識を長期記憶として定着させる秘訣です。

歌・アプリ・単語帳でスキマ時間を最大化する
通学中や休憩時間などのスキマ時間は、暗記の反復に最適です。
「日本史 覚え方 歌」やアプリを活用して、無理なく接触頻度を高めましょう。
単語帳を使う場合も、表を見てすぐ答えを出す練習を繰り返すことが、インプットの効率を最大化する鍵となります。
テスト別:最適な日本史の覚え方

日本史は「どのテストを受けるか」によって覚え方が変わります。
定期テスト、共通テスト、大学受験では、それぞれ求められる力が違うため、勉強の優先順位も変わります。
ここでは、テスト別に最適な覚え方を簡潔に整理し、効率よく点数につながる方法を紹介します。
日本史 定期テストの覚え方
日本史 共通テストの覚え方
日本史 大学受験の覚え方
一夜漬けで何をやるべきか
日本史 定期テストの覚え方
定期テストで点を取りたいなら、範囲の流れを正確に押さえることが最重要です。
授業で扱った流れを理解したうえで、漢字ミスがないように見直しましょう。
例えば、「御成敗式目」「延喜式」のような難しい用語は直前に書いて確認します。
先生が授業で強調した部分は出題されやすいので、教科書だけでなく授業ノートのチェックも欠かせません。

日本史 共通テストの覚え方
共通テストでは、用語暗記だけでは解けません。
資料やグラフ、文章を読み取り、時代の特徴や背景をつかむ力が必要です。
例えば、年貢に関する資料が出たら、その背景にある政治や経済の変化を理解することが得点につながります。
普段から資料集を見て、図版の特徴を言葉で説明する練習をすると、本番でも落ち着いて対応できます。

日本史 大学受験の覚え方
国公立・難関私大の個別試験では、記述力や論述力が問われます。
知識を整理して因果関係を説明できるようにしておくことが大切です。
例えば、「元禄文化が栄えた理由」を説明する場合、背景、政策、社会情勢をセットで言えることが求められます。
普段から白紙テストで自分の言葉で説明する練習をしておくと、論述問題にも対応できます。

一夜漬けで何をやるべきか
一夜漬けは基本的におすすめできませんが、どうしても時間がない場合は、範囲を絞って覚えるしかありません。
やるべきは「最重要年号」「漢字間違いしやすい用語」「時代を区切る出来事」の3つだけです。
例えば、「645年 大化の改新」「1868年 明治維新」など、流れをつかむ核となる部分を確認しましょう。
ただし、徹夜は逆効果で、記憶が残らないため必ず睡眠を取りましょう。
レベル別:日本史をゼロから始める人の勉強法

日本史を「どこから始めればいいかわからない」という高校生はとても多いです。
最初は細かい暗記より、全体の流れをつかむことが大切です。
ここでは、初心者が最初にやるべきこと、中学生の先取り、参考書ルート、保護者のサポート方法をまとめています。
ゼロから通史を理解する参考書ルート
中学生の先取り法:高校内容を効率よく覚えるコツ
中学生の先取り
初心者がまずやるべきこと
日本史が苦手な人ほど、通史を一度も最後まで通して読めていません。
最初にやるべきことは、細かい暗記ではなく「通史をざっくり1周」することです。
例えば、歴史漫画や講義系参考書を使って、大きな流れをざっとつかむだけで、その後の暗記が驚くほど楽になります。
「原始→古代→中世→近世→近代→現代」という流れを一度見通すことが、ゼロからの第一歩です。

ゼロから通史を理解する参考書ルート
通史を理解するには、教科書よりも噛み砕いて説明してくれる参考書の方が進めやすいです。
おすすめは次のルートです。
・「漫画・動画」で全体像をつかむ
・「講義系参考書」で流れをもう一度確認
・「一問一答」で重要語をチェック
例えば、漫画でざっくり流れを理解し、その後に講義系参考書で因果関係を補強することで、理解が深まります。

中学生の先取り
中学生で高校日本史を先取りしたい場合は、難しい用語を覚える必要はありません。
まずは「流れ」をつかむことに集中しましょう。
例えば、NHK for Schoolの歴史番組や歴史漫画を活用すると、自然に大きな流れを理解できます。
高校に入ってからの授業が理解しやすくなるため、先取りは大きなアドバンテージになります。

保護者ができるサポート方法
保護者の方は、暗記の量を増やす手伝いではなく、勉強方法の相談相手になることが大切です。
例えば、お子様が「書いても覚えられない」と悩んでいる場合は、この記事で紹介した「原因と結果で覚える方法」や「セット暗記」を提案してみてください。
予備校オンラインドットコム編集部でも多くの生徒を見てきましたが、家庭で声をかけてもらえることは学習継続の大きな力になります。
東大毎日塾のように、専門的な学習サポートを提供する塾の活用も視野に入れましょう。
日本史の「覚え方」よくある質問Q&A

日本史の勉強でつまずいたとき、多くの高校生が同じような疑問を抱えています。
ここでは、予備校オンラインドットコム編集部に届く質問の中から特に多いものを取り上げ、短く分かりやすく答えていきます。
Q2.語呂合わせは本当に効果がある?
Q3.年号が覚えられない理由
Q4.文化史が覚えられないときの対策
Q5.通史とテーマ史はどちらを先に?
Q6.共通テスト対策はいつから始める?
Q7. 日本史は先に暗記?それとも理解?
Q1.日本史は一夜漬けで点が取れる?
一夜漬けは短期的には効果がありますが、長期的な定着には向きません。
どうしても時間がない場合は、語呂合わせやセット暗記を使って最重要ポイントに絞るのが現実的です。
一夜漬けは短期記憶にしかならないため、定期テストで運良く点が取れても、すぐに忘れてしまうという課題や懸念点があります。
大学受験で必要な知識は、忘却曲線に基づいた分散学習でのみ定着します。

Q2.語呂合わせは本当に効果がある?
語呂合わせは年号を短時間で覚えるのにとても効果があります。
リズムや言葉のイメージが記憶に残りやすいため、テスト直前の最終確認に最適です。
例えば「泣くよ(794)うぐいす平安京」のように、語呂がつくと数字が頭に入りやすくなります。
ただし、語呂合わせだけに頼ると背景が理解できないので、流れとセットで覚えることが大切です。
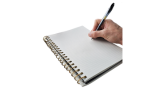
Q3.年号が覚えられない理由
年号だけを単独で覚えようとすると記憶に残りません。
理由は、出来事や人物と結びついていないからです。
年号は「出来事の意味」とセットにすると覚えやすくなります。
例えば「1853年 ペリー来航」だけでなく、「なぜ来たのか」「その後何が変わったのか」まで理解すると記憶に残ります。
数字に意味を与えることがポイントです。

Q4.文化史が覚えられないときの対策
文化史が苦手な理由は、イメージしにくいからです。
対策として、写真やイラストを中心に覚える方法が最も効果的です。
資料集を開いて、作品名→作者→時代背景をセットで確認しましょう。
例えば「平等院鳳凰堂」を見ながら、藤原氏の力が強かった時代とつなげると覚えやすくなります。
視覚を使うだけで理解が一気に進みます。

Q5.通史とテーマ史はどちらを先に?
必ず通史が先です。
通史は歴史の縦の流れで、日本史全体の土台になります。
土台ができていないと、政党史や文化史などのテーマ史を学んでもバラバラになってしまいます。
通史を一度通し、その後にテーマ史で理解を深めるとスムーズに進みます。

Q6.共通テスト対策はいつから始める?
高校3年生の夏休みから本格的に始めるのが一般的です。
ただし、資料読解や因果関係の理解は、日頃の学習から意識してください。
遅くとも高3の夏までには通史を一通り終わらせることがポイントです。

Q7. 日本史は先に暗記?それとも理解?
先に理解→あとで暗記が正解です。
流れがつながっていないと覚えた内容がすぐに抜け落ちてしまうためです。
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
現役の東大・旧帝大・早慶生が指導|スタディコーチ
※東大式「逆授業」で学力を伸ばす!夢の志望校合格へ!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
参考記事:キミノスクールに興味のある方必見!【口コミ・評判・料金】を徹底調査!おすすめできるオンライン塾?
まとめ:日本史の覚え方は“暗記×探究”のハイブリッドで点数UP

日本史は暗記だけでは点が伸びず、理解だけでも得点につながりにくい科目です。
だからこそ、暗記と探究の両立がもっとも効果的な勉強法になります。
この記事で紹介した3ステップを続ければ、試験で安定して点が取れるようになります。
まずは、通史の流れを「原因→結果」でつかみ、次に重要語句を人物・出来事・年号でセットにして覚えます。
最後は白紙テストなどのアウトプットで記憶を定着させることが大切です。
例えば、学んだ範囲を5分だけ白紙に書き出すだけでも大きな効果があります。
正しい勉強法を続ければ必ず実力は伸びます。
あなたの日本史学習を応援しています。
日本史を効率よく進めたい人は、東大生が毎日質問に答えてくれる「東大毎日塾」の無料体験を使うと、勉強の進め方が大きく変わります。
成績アップ!日本史おすすめ勉強情報
新課程・科目選択・全体戦略
・「歴史総合」と「日本史探究」の違いとは?科目選択で後悔しない完全ガイド
・日本史の勉強法は教科書が最強!歴史総合・日本史探求の理解を深める6ステップ
・大学受験の日本史探究・歴史総合はいつから?高1〜高3別スケジュールと勉強法
・【歴史総合の勉強法】これで完璧!定期テストも大学受験も怖くない!
参考書・問題集・学習ルート
・大学受験日本史!おすすめ参考書&問題集17選!レベル別×合格への最強ルート
・山川の日本史!超鉄板おすすめの参考書6冊と勉強ルート!探究・歴史総合対応
・日本史探求の最強勉強法!歴史総合もこれで完璧【おすすめ参考書8選】
・【日東駒専対策】日本史の参考書のおすすめ10冊!8割取れる勉強ルート
・【2025年】MARCH日本史おすすめ参考書25選!基礎から合格まで完全網羅
暗記・知識定着テクニック
・【日本史の年号】語呂合わせ!大学受験で「覚えるべき50選」と最強の暗記法
・山川の日本史用語集の使い方!【ポイント3つ】日本史の暗記が効率的に!
・詳説日本史ノート「最強の使い方&勉強法」で成績UP!高校生・受験生必見の完全ガイド
・山川【日本史一問一答】の使い方を知って日本史の偏差値アップ
執筆者のプロフィール
【執筆者プロフィール】
予備校オンラインドットコム編集部
 【編集部情報】
【編集部情報】
予備校オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営者経験者、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。高校生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。
予備校オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram