高校生の読書感想文の書き方|評価される構成・始め方・NG例まで完全解説
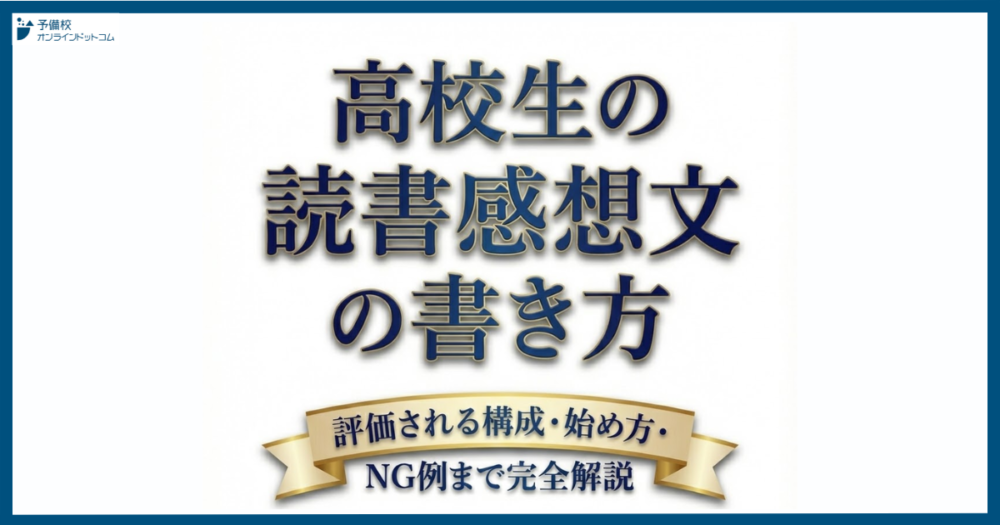
「※この記事には一部PRが含まれます」
「読書感想文がどうしても書けない」「何枚も原稿用紙を埋めるなんて無理」と悩んでいませんか?
正直、夏休みの宿題の中で一番後回しにしている人も多いはずです。白紙の原稿用紙を前に、スマホを見ている時間の方が長くなっていませんか?
実は、高校生の読書感想文には明確な合格パターンが存在します。
27年以上、教育の現場で多くの生徒を見てきた専門家の視点から、最短で終わらせるためのコツや、具体的な例文、さらにはAIとの上手な付き合い方まで徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、あんなに重かった筆がスムーズに動き出しているはずです。
「感想」ではなく「自分の考え」を書く
あらすじは2割、自分の体験を8割にする
迷わず埋まる「4段落構成」を活用する
AIは「代筆」ではなく「相談相手」に使う
Contents
- 1 読書感想文が苦手な高校生へ|この記事どおりにやれば書ける
- 2 30秒でわかる結論|高校生の読書感想文は「感想」ではない
- 3 コピペOK|評価される読書感想文の基本構成メモ
- 4 高校生の読書感想文は小中学生と何が違うのか
- 5 評価される読書感想文の基本構成|この順番で書けばOK
- 6 読書感想文の書き出し|最初の一行で差がつく
- 7 感想が思いつかない高校生でも書ける考え方
- 8 読書感想文の題名はどう付けるべきか
- 9 高校生の読書感想文でよくあるNG例
- 10 読書感想文とコピペの注意点|やってはいけない使い方
- 11 ChatGPTを使うなら知っておきたい正しい使い方
- 12 優秀作品に共通する高校生の読書感想文の特徴
- 13 本選びで迷ったときの考え方
- 14 提出前に必ず確認したいチェックポイント
- 15 高校生の読書感想文の書き方Q&A|よくある疑問を解決
- 16 まとめ:高校生の読書感想文の書き方|評価される構成・始め方・NG例まで完全解説
- 17 執筆者のプロフィール
読書感想文が苦手な高校生へ|この記事どおりにやれば書ける

読書感想文への「面倒くさい」という不安は、実は「正しい書き方を知らない」だけです。
難しい理屈ではなく、今日からすぐに使える具体的な手順をまとめたガイドを読み進めてみてください。
高校生の皆さんが抱える「文章力がなくて評価が下がるのではないか」という心配は、正しい「型」を知るだけで解消できます。
予備校で多くの作文を指導してきた経験から言えるのは、先生に伝わる文章には決まった形があるということです。
・最短で宿題を終わらせて自由になりたい
・先生から「お、しっかり考えて書いているな」と思われたい
このような願いを叶えるために、難しい言葉は一切使わず、誰でも実践できるテクニックだけを凝縮しました。
まずは肩の力を抜いて、リラックスして読み進めてみてください。
▶高校生向けの読書感想文の例文(800字・2000字)を先に見たい人はこちら
30秒でわかる結論|高校生の読書感想文は「感想」ではない

忙しい皆さんのために、まずは結論からお伝えします。先生に良い印象を持たれやすいポイントは、たったこれだけです。
・高校生の読書感想文は「感想」ではなく「考えを書く文章」
・評価されるのは「あらすじ」ではなく「自分の変化」
・迷ったらこの記事の4つの型にあてはめればOK
・正しい順番で書けば、原稿用紙は自然に埋まる
読書感想文において、「あらすじを長々と書くこと」は非常にもったいない書き方になりやすいです。
先生が本当に見たいのは、本の内容そのものではなく、その本を読んだ結果、あなたがどう成長し、何を考えたかという心の動きなのです。
コピペOK|評価される読書感想文の基本構成メモ

白紙の原稿用紙を前にフリーズしないために、そのまま使える「設計図」を紹介します。
この4つの要素を順番に埋めていくだけで、論理的で高校生らしい文章が驚くほど簡単に完成します。
執筆を始める前に、以下の4つの項目について一言ずつメモを書いてみてください。
これがそのまま感想文の骨組みになります。
1. 書き出し:なぜこの本を選んだか、読む前の自分はどうだったか。
2. きっかけ:心が動いた場面やセリフの引用。
3. 深掘り:なぜそこが気になったのか。自分の体験(部活、勉強、友人関係)と重ねる。
4. まとめ:これから自分はどう生きていきたいか。
例えば、「部活でスランプだった自分」という体験を軸にするなら、主人公の挫折シーンを引用して、「自分もこうありたい」と結ぶだけ。これで立派な高校生レベルの感想文になります。
高校生の読書感想文は小中学生と何が違うのか

高校生の感想文は「素直な感動」よりも「自分なりの視点」が大切です。
この違いを理解することが、子供っぽい文章を卒業するための第一歩となります。
先生が見ているポイントはこの3つ
高校生らしい文章とはどういうことか
あらすじ中心だと評価が下がりやすい理由
高校生があらすじばかりを書いてしまうことは、もったいない書き方になりやすいです。
先生は本のあらすじを知りたいわけではありません。あらすじは全体の20%以下に抑え、残りはすべて自分の考えを描写することに使いましょう。

先生が見ているポイントはこの3つ
先生が採点時にチェックするのは、「独自の視点」「論理的な構成」「語彙力」の3点です。
特に、ネットの焼き直しではない、あなた自身のリアルな悩みが反映されているかどうかが、先生に伝わるための大きな選択基準となります。

高校生らしい文章とはどういうことか
高校生らしい文章とは、感情を「すごかった」の一言で済ませず、「〇〇という理由で、私は△△だと考えた」と理由をハッキリさせることです。
例えば、ニュースで見た社会問題と結びつけるなどの視野の広さを見せると、一気に「高校生らしさ」が出ます。
評価される読書感想文の基本構成|この順番で書けばOK
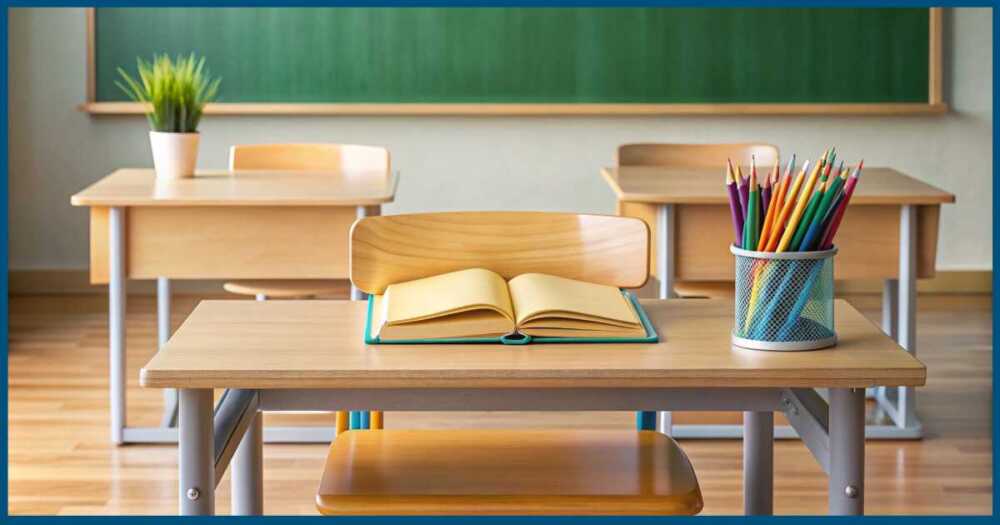
迷わずに書き切るコツは、構成ごとの「目安の量」を意識することです。
ここでは、2000字(原稿用紙5枚)を書き切るための具体的な目安と流れを解説します。
| 構成パート | 内容の目安 | 原稿用紙の枚数目安 |
| 書き出し | 本を選んだ理由・読む前の自分 | 約1枚 |
| 本文(前半) | 心に残った場面・あらすじ | 約1.5枚 |
| 本文(後半) | 自分の体験とのリンク・深い考察 | 約1.5枚 |
| まとめ | 本を読んで変わったこと・将来の決意 | 約1枚 |
※文字数指定がある場合は、必ず学校の指示を優先してください。
本文で感想を深めるコツ
まとめで高校生らしさを出す方法
書き出しで迷わない考え方
書き出しは、読者をあなたの世界へ引き込む扉です。
「なぜ今、この本を手に取ったのか」という個人的な理由から始めると、嘘偽りのない、伝わりやすいオリジナルの導入になります。

本文で感想を深めるコツ
本文では、本の内容を自分の過去や今の状況と「対比」させることが重要です。
例えば、主人公の孤独と、自分が部活で一人悩んだ時の不安を重ねることで、文章に圧倒的なリアリティと説得力が生まれます。

まとめで高校生らしさを出す方法
結論では、読書体験を「これからの行動」に変えてください。
「明日からこう変わる」という決意を述べることで、文章が前向きに締まります。
これは、小論文や志望理由書でも使える高度なテクニックです。
読書感想文の書き出し|最初の一行で差がつく

最初の一行を工夫するだけで、読み手の心はつかめます。
インパクトを与えるための簡単なコツを紹介します。▶書き出しだけを集中的に確認したい人は、高校生向けの書き出し例も参考になります
避けるべき書き出し
評価されやすい書き出しの型
インパクトのある書き出しの考え方
いきなり「核心」から入るのが効果的です。
例えば、「私はこの本を読んで、これまでの自分を恥じた」や、印象に残ったセリフの引用から始めると、読み手は「なぜ?」と興味を持ち、続きを読みたくなります。

避けるべき書き出し
「私は〇〇という本を読みました」という普通すぎる報告は避けましょう。
これは文字数の無駄遣いであり、読み手に「工夫がない」という印象を与えます。
自分の感情や、驚いた事実から入るのが明確な推奨事項です。

評価されやすい書き出しの型
「〇〇という言葉に出会うまで、私は△△だと信じていた」という変化の型が使いやすいです。
自分の常識が覆された瞬間を書くことで、知的で成長意欲のある高校生という良い印象を与えられます。
感想が思いつかない高校生でも書ける考え方

本を読んでも「別に何も感じなかった」というのは、高校生の正直な本音かもしれません。
でも、視点を少し変えるだけで、書くべき材料はいくらでも見つかります。
自分に問いかけると書ける質問例
すぐ使えるメモの取り方
本のどこに注目すればいいか
すべてを理解しようとせず、「一箇所だけ、自分と似ているところ」を探してください。
主人公の癖や、作者のちょっとした一言など、重なる部分が1つあれば、そこを起点に文章を大きく広げることが可能です。

自分に問いかけると書ける質問例
「もし自分がこの場面にいたら、違う選択をしたか?」と自分に質問してみてください。
例えば、「自分なら逃げ出す」と感じたなら、なぜ主人公は逃げなかったのかを考えるだけで、深い分析ができます。

すぐ使えるメモの取り方
読書中に「えっ?」と手が止まったページに付箋を貼るだけでOKです。
その違和感こそが感想の種になります。
付箋の部分を書き出し、自分の日常と結びつける作業が、最も効率的な執筆プロセスです。
読書感想文の題名はどう付けるべきか

題名は感想文の「顔」なので、自分なりの工夫を加えましょう。
内容をパッと伝えつつ、読み手の期待感を高めるタイトルの付け方には、簡単な法則があります。
内容が伝わる題名の付け方
題名で評価を落とさない考え方
「『〇〇』を読んで」という題名だけでは、個性が薄いと判断されがちです。
これにサブタイトルを加えるだけで、印象は劇的に変わります。題名に自分の主張を少しだけ込めるのが、センスを感じさせる選択基準です。

内容が伝わる題名の付け方
「〇〇から学んだ、本当の勇気とは」や「私が〇〇を嫌いになれなかった理由」など、自分の結論をチラ見せする形が理想です。
具体的には、本の中のキーワードと自分の感情を組み合わせたタイトルを意識しましょう。
高校生の読書感想文でよくあるNG例

頑張って書いたつもりでも、「評価が伸びにくいポイント」を知らないと損をしてしまいます。
多くの生徒がやりがちな失敗パターンを知って、上手に回避しましょう。
ネットの感想をなぞったような文章
中学生レベルで終わってしまうまとめ
あらすじばかりになってしまう文章
あらすじが長すぎる文章は、「自分の頭で考えていない」というもったいない印象を与えてしまいます。
あらすじはあくまで「前提」であり、あなたの「意見」を支えるための脇役に徹させるのが正しい構成のルールです。

ネットの感想をなぞったような文章
どこかで聞いたような「綺麗事」ばかりの文章は、すぐにバレます。
先生が求めているのは、あなたの本音です。
例えば、「主人公が嫌いだった」という否定的な感想であっても、理由がハッキリしていれば良い印象を持たれやすいです。

中学生レベルで終わってしまうまとめ
「楽しかったです」「また読みたいです」という終わり方は、評価が伸びにくいです。
その本から得た教訓を、自分の人生や今の社会問題にどう当てはめるかという「応用」の視点を必ず入れるようにしてください。
▶終わり方で評価を落とさないために、まとめの例文も確認しておきましょう
読書感想文とコピペの注意点|やってはいけない使い方

コピペの誘惑に駆られることもあるかもしれませんが、今の不正チェックはとても厳格です。
リスクを理解し、正しく参考にするための境界線を解説します。
参考にするなら注意すべきポイント
コピペがバレやすい理由
先生は毎年、同じ本の感想文を大量に読んでいます。
また、ネットの文章は言葉のリズムが不自然なことが多く、「これ、自分の言葉じゃないな」と直感でわかります。
バレた時のリスクはとても大きいので、絶対に避けましょう。

参考にするなら注意すべきポイント
ネットの文章を「丸写し」するのではなく、「構成の組み方」だけを参考にしましょう。
例えば、ある上手な作品が「引用から始まっている」ことに気づいたら、自分も別のシーンを引用して書き始める、という使い方が賢明です。
ChatGPTを使うなら知っておきたい正しい使い方

生成AI(ChatGPTなど)は「代わりに書いてもらう」のではなく「相談相手」として使いましょう。
自分の実力を高めながら完成度を上げるためのコツを紹介します。
・向いている人:考えはあるが、言葉にするのが苦手な人
・向いていない人:丸投げして楽をしたい人
下書きとして使う考え方
バレにくくするための修正ポイント
そのまま提出すると危険な理由
AIが書く文章は、正しいですが「個人の体験」が欠けています。
そのまま出すと、AI特有の言い回しで即座に見抜かれます。
「AIバレ」を避けるには、自分の血の通ったエピソード(部活の話など)の追加が不可欠です。

下書きとして使う考え方
「この本を読んだ感想の切り口を5つ出して」とAIに頼むのは非常に有効な使い方です。
自分では思いつかなかった視点をもらい、それを元に自分の体験談を肉付けすることで、執筆スピードは劇的に上がります。

バレにくくするための修正ポイント
AIが書いた文章に、あえて「自分らしい話し言葉に近い表現」を混ぜたり、自分にしかわからない具体的な出来事を1文足すだけで、AI感は消えます。
AIはあくまで「下書き・整理」のための道具として使いましょう。
優秀作品に共通する高校生の読書感想文の特徴

優秀な作品には「変化のドラマ」が描かれています。
それらを知ることで、質の高い文章を書くためのヒントが見えてきます。
自分の考えが評価につながる理由
内容よりも大切にされているポイント
伝わりやすい作品は、例外なく「書き手の葛藤(悩み)」が描かれています。
単に「良い本でした」ではなく、「本を読む前は悩んでいた自分が、読み終わる頃にはこう変わっていた」という変化のストーリーが評価されます。

自分の考えが評価につながる理由
自分の考えをハッキリ述べることは、「考える力」の証明です。
著者の意見にすべて賛成するのではなく、「自分はこう思うが、別の見方もあるのではないか」と多角的に考えることで、知性と誠実さをアピールできます。
本選びで迷ったときの考え方

「何を書くか」と同じくらい大事なのが「本選び」です。感想文が書きやすい本には共通点があります。▶どの本を選べばいいか迷う人は、読書感想文本の選び方を参考にしてください
避けたほうがいい本の傾向
読書感想文に向いている本の特徴
主人公が大きな決断をする物語や、今の社会問題を扱った本は、自分の意見を乗せやすく、文字数を稼ぎやすいです。
具体的には、自分と同じ高校生が主人公の青春小説を選ぶのが、失敗しない王道の選択です。

避けたほうがいい本の傾向
物語が複雑すぎるミステリーなどは、あらすじの説明だけで力尽きてしまうためあまりおすすめしません。
あまりにも「完璧すぎる名作」は、自分の感想を付け加える隙がなく、苦労することが多いです。
提出前に必ず確認したいチェックポイント

文章が書けたら、最後は「ルール」の確認をしましょう。
形式が整っているだけで、先生からの第一印象は格段にアップします。▶原稿用紙の枚数・文字数・書き方が不安な人は、高校生向け原稿用紙ガイドを確認してください
最後に見直すべきポイント
名前や形式で減点されないための注意点
学校によって細かい指定がある場合もあるため、必ず先生の指示を優先してください。
一般的には原稿用紙の1行目に題名、2行目に名前を書きます。
「句読点は行頭に置かない」などの基本は、文章の信頼性を左右します。

最後に見直すべきポイント
声に出して読んでみて、リズムがおかしいところはないか確認しましょう。
特に「です・ます」と「だ・である」が混ざっていないかは、最も多いミスの一つです。
文末の表現を統一するだけで、読みやすさは倍増します。
高校生の読書感想文の書き方Q&A|よくある疑問を解決

読書感想文を書く時に、誰もが一度は抱く「具体的な悩み」に一問一答で答えます。
ここを読めば、不安はすべて解消されるはずです。
Q.コピペはどこまでなら大丈夫?やってはいけないライン
Q.書き出しがどうしても思いつかないときはどうする?
Q. 読書感想文の名前の書き方やルールで注意することは?
Q.優秀作品は何が違うの?普通の感想文との決定的な差
上手な作品は、読む人の心を動かす「描写の具体性」が違います。
抽象的な言葉を使わず、「雨の日のグラウンドの匂い」のような五感を刺激する表現を混ぜることで、情景が浮かび、評価がグッと上がります。

Q.コピペはどこまでなら大丈夫?やってはいけないライン
既存の文章を3文以上そのまま写すことは、コピペと判断されるリスクが高いです。
参考にする場合は、考え方のヒントだけをもらって、主語を「自分」に変えて、完全に自分の言葉で作り直す必要があります。

Q.書き出しがどうしても思いつかないときはどうする?
「私は今まで、〇〇について真剣に考えたことがなかった」という「知らなかった自分」から始めてみてください。
そこから「でもこの本を読んで…」と繋げれば、スムーズに進めます。最初から完璧を目指さないことがコツです。
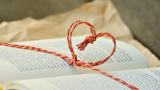
Q. 読書感想文の名前の書き方やルールで注意することは?
基本は「右から2行目に、名字と名前の間に1マス空けて書く」ことです。
ただ、学校ごとのルールが最優先です。原稿用紙の最後の一マスに句読点が来る場合は、欄外に書くか、文字と一緒にマスの隅に書き込みましょう。
ここまで読んで「これなら書けそう」と思えたなら、もう大丈夫です。
まとめ:高校生の読書感想文の書き方|評価される構成・始め方・NG例まで完全解説

読書感想文は、決して怖い課題ではありません。
この記事で紹介した型を守れば、誰でも先生に伝わる文章を書き上げることができます。
大切なのは、本を通じて今の自分と向き合うことです。
あんなに嫌いだった読書感想文が、書き終える頃には自分のことを深く知る良いきっかけになっているはずです。
迷ったら「書き出し→きっかけ→深掘り→まとめ」の4つだけ思い出してください。
まずは今日、10分だけ本を開いて、1か所に付箋を貼ってみてください。
その小さな一歩が、完成への一番の近道です。応援しています!
執筆者のプロフィール
【執筆者プロフィール】
予備校オンラインドットコム編集部
 【編集部情報】
【編集部情報】
予備校オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営経験者、ファイナンシャルプランナー、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。高校生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。
予備校オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram
参考:医学部6年間のロードマップ完全
中学受験や高校受験に向けた塾選び、日々の家庭学習でお悩みの方には、姉妹サイトの「塾オンラインドットコム」がおすすめです。小・中学生向けの効率的な勉強法や、後悔しない塾の選び方など、保護者さまが今知りたい情報を専門家が分かりやすく解説しています。ぜひ、あわせて参考にしてください。
