大学受験の過去問はいつから?スバリ◯月!何年分?国公立・私立対策を解説
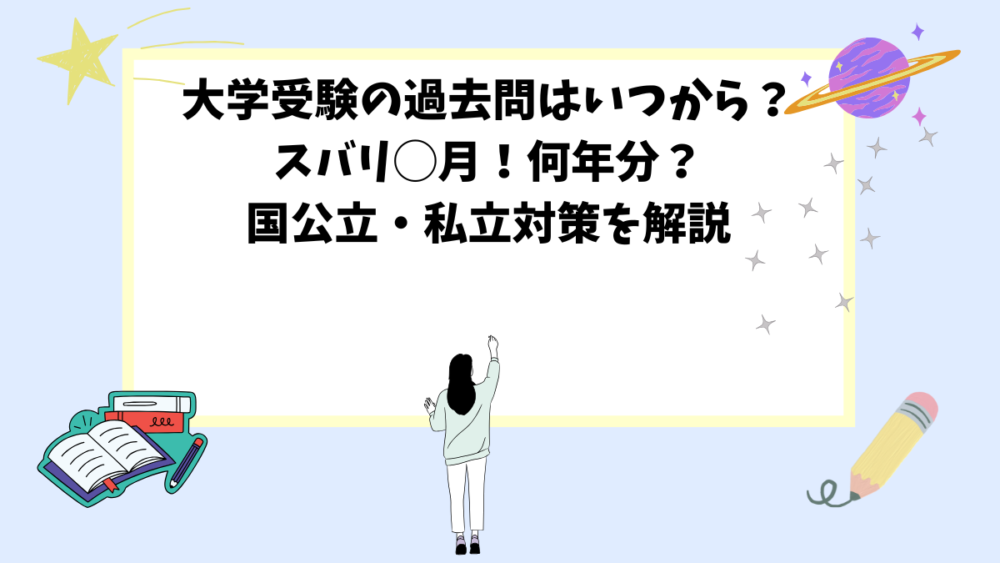
※この記事には一部PRが含まれます。
「大学受験の過去問(赤本)って、いつから手をつければいいんだろう…?」「周りはもう始めてるみたいで焦る…何年分解けば合格できるの?」
私は30年以上、学習塾業界に携わっています。これまでに小学生から浪人生まで送り出し、幅広い合格実績があります。
その中で、過去問演習の開始時期や年数を誤って、実力を出し切れなかった生徒も見てきました。
もちろん、適切なタイミングと方法で着手し、逆転合格を果たした生徒も数多くいます。
この記事では、そうした長年の指導経験をもとに、過去問演習のベストタイミングと必要年数を解説します。
単なる理論ではなく、実際の合格者がたどった道筋を反映しているので、今日からの勉強計画にすぐ活かせます。
過去問演習は基礎固め後の9〜10月開始が効果的
第一志望は5〜10年分、併願校は3〜5年分が目安
国公立・私立・共通テスト別の開始時期と対策法
時期別スケジュールと効果的な復習・分析方法
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
現役の東大・旧帝大・早慶生が指導|スタディコーチ
※東大式「逆授業」で学力を伸ばす!夢の志望校合格へ!
Contents
結論、大学受験の過去問はいつから?9月〜10月から

結論から言うと、大学受験の過去問(赤本)に本格的に取り組むべき最適な時期は高校3年生(または浪人生)の9月〜10月です。
なぜなら、多くの受験生が夏休みまでに主要科目の基礎固めを終えるため、その知識が本当に志望校レベルで通用するのかを試す段階に入るのがこの時期だからです。
ただし、これはあくまで一般的な目安。
あなたの学習状況や志望校によって最適なタイミングは変わります。
大切なのは、「なぜその時期に始めるのか」という目的を理解することです。
大学受験の過去問は9月〜10月から始めるのが王道
基礎固めの完了が過去問開始の合図
基礎が不安な場合の開始時期と対策
夏休み中に一度解いて実力を把握
大学受験の過去問は9月〜10月から始めるのが王道
これまでのの指導経験から断言します。
基礎固めを終えた高校3年生(または浪人生)は、9月〜10月から本格的に過去問演習を始めるのが最も効果的です。
例えば、私が担当した都立高校出身のAさん(早稲田大学合格)は、高3の夏休みで英語・国語の基礎を徹底し、9月から週2年分ペースで過去問を解きました。秋の模試では志望校判定がC判定でしたが、12月時点でA判定にまで伸びています。
逆に、夏前に基礎が固まっていないのに過去問を始めたBくんは、間違いの原因が「基礎不足」なのか「応用力不足」なのか判別できず、秋以降の伸びが鈍化しました。
このように、基礎完成がスタートの合図です。

基礎固めの完了が過去問開始の合図
過去問演習を始める大前提は、志望校の入試で問われる範囲の基礎固めが完了していることです。
基礎が固まっていない状態で過去問を解いても、「全く歯が立たない…」と自信を失うだけ。問題が解けない原因が「基礎知識の不足」なのか「応用力の不足」なのかが分からず、効果的な復習ができません。
「基礎固めが完了した状態」とは、具体的には以下のようなレベルを指します。
| 項目 | チェックの目安 | 補足ポイント |
|---|---|---|
| 英単語・古文単語 | 英単語帳・古文単語帳を1冊最後まで覚えている | 覚えたつもりではなく、テスト形式で8割以上正答できる状態 |
| 英文法 | 基本文法問題集を1冊仕上げている | 文法問題を解くだけでなく、間違えた理由を説明できる |
| 英文解釈 | 基礎的な構文解釈がスムーズにできる | 長文読解で文構造を取れるレベル |
| 数学 | 教科書レベルの基本問題を自力で解ける | 公式の暗記だけでなく、導出や使い方を説明できる |
| 理科(選択科目) | 教科書レベルの典型問題を解ける | 計算問題と知識問題の両方をバランス良く仕上げる |
| 社会 | 主要用語を一通り暗記している | 一問一答形式で8割以上正答できる状態 |
| 苦手単元 | 明確に把握し、対策計画がある | 苦手を放置せず、演習や暗記で克服中 |
これらの基礎が身についていれば、過去問演習を通して「時間配分」「問題のクセ」「頻出分野」といった、より実践的な対策にスムーズに移行できます。

基礎が不安な場合の開始時期と対策
「まだ基礎に不安がある…」という場合、焦って過去問に手を出す必要はありません。
過去問演習の効果を最大化するためにも、まずは基礎の徹底を優先しましょう。
9月以降も、苦手な単元や分野に絞って参考書や問題集に戻り、穴をなくす作業を続けてください。
過去問を始めるのが10月や11月になったとしても、基礎が盤石であれば、その後の伸びは大きく変わってきます。

夏休み中に一度解いて実力を把握
本格的な演習は秋からで問題ありませんが、夏休みの間に一度、第一志望の最新年度の過去問を解いてみることを強くおすすめします。
この目的は、高得点を取ることではありません。
・現状の実力と合格点との差を把握する
・志望校の問題形式、難易度、出題傾向を肌で感じる
・どの分野に課題があるのかを明確にする
ここで見つかった課題を意識しながら夏休み後半や秋以降の学習計画を立てることで、より戦略的に受験勉強を進めることができます。
過去問は何年分解くべき?

「過去問をいつから始めるか」と並んで多くの受験生が悩むのが、「過去問を何年分解くべきか」という量的な問題です。
やみくもに解くのではなく、志望校のレベルに合わせて適切な量をこなすことが合格への近道です。
第一志望校は最低5年、理想は10年分
併願校は3〜5年分を目安に
早慶・MARCHなど難関私大の必要年数
第一志望校は最低5年、理想は10年分
結論として、第一志望校の過去問は最低でも5年分、できれば10年分は解いておきましょう。
・ 最低5年分
最近の出題傾向や形式を掴むために必須の量です。これだけ解けば、時間配分や問題の難易度にも慣れることができます。
・理想は10年分
10年分を解くことで、数年単位での出題傾向の変化や、大学側が受験生に求める能力の「核」となる部分が見えてきます。他の受験生と差をつけるためには、このレベルまでの分析が非常に有効です。
ただし、あまりに古い過去問は現在の学習指導要領と出題範囲が異なる場合があるため、注意が必要です。

併願校は3〜5年分を目安に
併願校については、第一志望ほど時間をかける必要はありません。
合格最低点を確実にクリアする戦略を立てるために、3〜5年分を目安に取り組みましょう。
目的は、その大学特有の問題形式に慣れ、時間内に合格点を取るためのペースを掴むことです。
第一志望の対策が落ち着いた12月頃から着手しても間に合います。

早慶・MARCHなど難関私大の必要年数
早稲田大学やMARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)といった難関私立大学を目指す場合、可能であれば10年分以上の過去問に取り組むことをおすすめします。
難関私大は、学部ごとに問題のクセが強く、出題形式も多様です。
・早慶
特に英語や国語で、独特の長文や難解な問題が出題される学部が多いです。多くの過去問に触れ、その「クセ」に慣れることが直接得点力に繋がります。
・MARCHレベル
学部間の併願も多いため、複数の学部の過去問を解くことで対策の幅が広がります。問題の相性を見極める上でも、多くの年度を解く価値は高いです。
多くの過去問を解き、分析することで、他の受験生より一歩も二歩もリードできるのが難関私大対策の特徴です。
MARCHにあなたも逆転合格できる
圧倒的な合格率が本物の証
難関私大に合格する完璧なノウハウ
志望大学の先生があなたをサポート
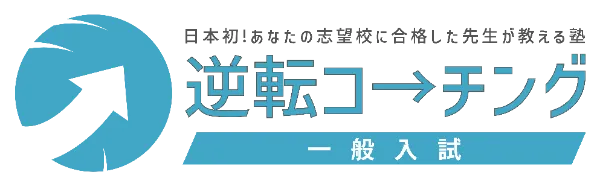
「友だち追加」で無料コーチング
勉強計画を無料で作成
↓↓↓
大学受験志望校別:過去問を始める時期の目安

過去問演習のスケジュールは、国公立志望か私立志望かによっても変わってきます。ここでは、志望校のタイプ別に最適な開始時期を解説します。
共通テスト対策の開始時期
国公立大学(二次試験)の開始時期
私立大学の開始時期
共通テスト対策の開始時期
大学入学共通テストの対策は、専用の問題集(いわゆる黒本や青本など)を使って11月頃から本格的に始めるのが一般的です。
共通テストは、思考力や情報処理能力を問う独特な形式のため、専用の対策が欠かせません。
特に時間配分が非常にシビアなので、本番同様の時間を計って演習を繰り返すことが重要です。
過去問(過去の共通テストやセンター試験の問題)と並行して、各予備校が出版する予想問題集にも取り組み、多様な問題形式に慣れておきましょう。

国公立大学(二次試験)の開始時期
国公立大学の二次試験対策は、共通テストが終わってから本格化させる受験生も多いですが、それでは対策が後手に回る可能性があります。
理想は、共通テスト対策と並行して10月頃から少しずつ手をつけることです。
特に、論述問題や証明問題など、解答を作成するのに時間がかかる問題が出題される大学を志望する場合は、早期からの対策が合格の鍵を握ります。
1年分でも良いので、二次試験の問題に触れる習慣をつけましょう。

私立大学の開始時期
私立大学は、大学・学部ごとに問題の傾向が大きく異なるため、第一志望の対策は9月頃から早めに着手するのがおすすめです。
特に複数の学部や大学を併願する場合、それぞれの対策に相応の時間がかかります。
1. 9月〜11月
第一志望校の過去問に集中し、傾向分析と弱点克服を進める。
2. 12月以降
第一志望の対策に目処が立ったら、併願校の過去問に着手する。
このような流れで計画を立てると、バランス良く対策を進めることができます。
時期別|過去問演習のスケジュール例

ここでは、具体的な時期ごとに、過去問演習をどのように進めていけばよいかのモデルプランを紹介します。
秋(9月〜11月)の過去問の取り組み方
直前期(12月〜1月)の過去問の取り組み方
夏休み(〜8月)の過去問の取り組み方
この時期の目的は、本格的な演習ではなく「力試し」と「現状分析」です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| やること | 第一志望校の最新年度の過去問を1年分だけ解く |
| 目的 |
– 志望校との距離を測る- 難易度や時間配分を体感する – 苦手分野や課題を洗い出す |
| ポイント | 点数に一喜一憂せず、「なぜ解けなかったのか」を分析し、秋以降の学習計画に活かす |
夏休みは本格的な過去問演習ではなく、現状を知るための「力試し」の時期です。
ここで得た課題をもとに、秋以降の対策を計画的に進めることが重要です。

秋(9月〜11月)の過去問の取り組み方
この時期は、過去問演習のメイン期間です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| やること | 第一志望校の過去問を週1〜2年分のペースで解く |
| 目的 |
– 出題傾向を把握する – 時間内に解き切るペースを確立 – 弱点を参考書や問題集で克服 |
| ポイント | 解きっぱなしにせず、1年分ごとに復習・分析を徹底。1周目は傾向把握、2周目で解法を固める |
秋は過去問演習のメイン期間です。
量と質の両方を意識し、解いた後の復習を徹底しましょう。
傾向分析を通して戦略を磨き、得点力を高めることが目的です。

直前期(12月〜1月)の過去問の取り組み方
この時期は、新しい問題に手を広げるのではなく、「完成度」を高めることに集中します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| やること | – 間違えた問題や苦手大問の解き直し- 合格最低点を超える戦略の最終調整- 共通テスト・併願校対策を並行 |
| 目的 |
– 知識の穴をなくす- 時間配分を体に染み込ませる – 本番で動じない精神的余裕を作る |
| ポイント | 本番と同じ時間割で演習を行う。体調管理も含めて万全の準備をする |
直前期は新しい問題に手を広げるよりも、これまでの復習と完成度の向上に集中します。
本番を想定した演習や時間管理の練習で、試験当日に最大の力を発揮できる状態を作ります。
過去問の効果的な使い方と復習法

過去問は、ただ解くだけでは成績は伸びません。その価値を最大限に引き出すための「使い方」と「復習法」を解説します。
2周目以降の目的|弱点克服と得点力向上
解きっぱなしを防ぐ復習と分析のコツ
1周目の目的|傾向把握と時間配分
過去問演習の1周目は、点数を気にしすぎる必要はありません。
まずは敵を知ることに徹しましょう。
・出題形式の把握
マーク式か記述式か、大問は何個あるか、といった全体像を掴みます。
・頻出分野の特定
どの単元がよく出題されるのかを分析し、今後の学習の優先順位をつけます。
・時間配分のシミュレーション
時間を計って解き、どの問題にどれくらい時間がかかるのか、理想的な時間配分はどのくらいかを考えます。

2周目以降の目的|弱点克服と得点力向上
2周目以降は、1周目で見つかった課題を克服し、合格点を取るための「得点力」を磨く段階です。
・弱点分野の徹底演習
間違えた問題や苦手な分野を、なぜ間違えたのか理解できるまで徹底的に復習します。
・時間内に解き切る練習
1周目で立てた時間配分戦略を実践し、時間内に合格点を取る練習を繰り返します。
・合格最低点を超える戦略の構築
「この大問は半分取れればOK」「この問題は捨てる」といった、本番で確実に合格点を取るための現実的な戦略を立てます。

解きっぱなしを防ぐ復習と分析のコツ
過去問演習で最も重要なのは、解いた後の復習と分析です。
以下のステップを必ず実行してください。
1.間違えた原因の分析
なぜ間違えたのかを「知識不足」「時間不足」「ケアレスミス」「勘違い」などに分類し、原因を明確にします。
2.解答・解説の熟読
正解した問題も含め、すべての問題の解説を読み込みます。なぜその答えになるのか、別解はないかなど、深く理解することが重要です。
3.解き直し
間違えた問題は、解説を読んだ後、必ず何も見ずに自力で解き直しましょう。スラスラ解けるようになるまで繰り返すのが理想です。
4.分析ノートの作成
過去問演習専用のノートを作り、年度ごとの点数、間違えた問題の原因、気づいたこと、次回の目標などを記録しておくと、自分の成長と課題が一目で分かり、モチベーション維持にも繋がります。
「大学受験の過去問いつから?」に関するQ&A

最後に、受験生からよく寄せられる過去問に関する質問にお答えします。
併願校の過去問はいつから何年分解く?
赤本とは?黒本や青本との違い
最初に解く過去問は何年分がおすすめ?
11月や1月から過去問を始めるのは遅い?
決して遅すぎるということはありません。
部活などで秋まで忙しかった受験生が、11月から過去問を始めて逆転合格するケースはたくさんあります。
ただし、残された時間は限られています。
重要なのは、焦らずに効率的な計画を立てることです。
・優先順位をつける
すべての範囲を完璧にするのは難しいかもしれません。過去問を分析し、頻出分野や配点の高い分野に絞って集中的に対策しましょう。
・量を絞る
第一志望は5年分、併願校は2〜3年分など、やるべき量を現実的な範囲に絞り、その代わり一問一問を完璧に仕上げることを目指しましょう。

併願校の過去問はいつから何年分解く?
第一志望の対策がある程度進んだ11月下旬〜12月頃から始めるのが一般的です。
解くべき年数は、最低3年分、できれば5年分が目安です。
第一志望の勉強の妨げにならないよう、計画的に進めましょう。
併願校の入試日が近い場合は、直前期に集中して対策するのも一つの手です。

赤本とは?黒本や青本との違い
・「赤本」とは
教学社が出版している大学入試過去問題集の通称です。表紙が赤いことからそう呼ばれています。多くの大学の過去問を網羅しており、掲載年数が多いのが特徴です。
(参考:赤本ウェブサイト)
・黒本
河合塾が出版する共通テストの過去問・実践問題集の通称です。本番に近い形式のオリジナル問題が豊富で、共通テスト対策の定番となっています。
(参考:河合塾の共通テスト総合問題集)
・青本
駿台文庫が出版する大学入試の過去問題集や共通テストの実践問題集の通称です。丁寧で詳しい解説に定評があり、難関大学志望者を中心に人気があります。
(参考:駿台文庫)

最初に解く過去問は何年分がおすすめ?
まずは最新年度の1年分だけを解くのがおすすめです。
理由は、現在の入試傾向に最も近く、自分の実力と志望校との距離を最も正確に測れるからです。
最初に何年分も解いてしまうと、力試しなのか本格的な演習なのか目的が曖昧になってしまいます。
まずは最新年度で課題を把握し、それを元に学習計画を立ててから、古い年度の過去問へと進んでいくのが最も効率的です。
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
現役の東大・旧帝大・早慶生が指導|スタディコーチ
※東大式「逆授業」で学力を伸ばす!夢の志望校合格へ!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
まとめ:過去問をいつからやるのか?何年分?

今回は、大学受験の過去問を始める時期や量、効果的な使い方について詳しく解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。
過去問をいつからやるのか?
・過去問演習の本格的な開始時期は、基礎固めが終わる9月〜10月が最適。
・解くべき量は、第一志望校は最低5年〜理想10年分、併願校は3〜5年分が目安。
・過去問はただ解くだけでなく、「原因分析」「解き直し」といった復習こそが最も重要。
・始める時期が多少遅れても、焦らず、自分に合った効率的な計画を立てれば十分に挽回可能。
過去問は、志望校からの「合格への招待状」であると同時に、あなた自身の弱点を教えてくれる最高の参考書です。
周りと比べて焦る気持ちも分かりますが、大切なのはあなた自身のペースで、着実に一歩ずつ進むことです。
この記事で紹介した方法を参考に、自分だけの合格戦略を立て、自信を持って本番に臨んでください。
あなたの努力が実を結ぶことを心から応援しています。
関連記事
文系高2、受験勉強「何から?」合格への年間計画と先輩の実践ロードマップ
高校1年生の勉強時間と勉強法!現役で合格するために大切なポイントはこれだ!
偏差値50から早稲田大学に合格した講師に勉強時間と勉強法を聞いてみました!
過去問対策におすすめ!コーチング塾の紹介
【学習管理塾】STRUXはおすすめ?評判・料金・特徴を塾経験者が取材してわかったこと
【必見】スタディコーチの口コミ・評判が気になる方!塾経験者が調査しました!
大学受験エンカレッジの口コミ・評判はやばい?真実を直接取材!料金も徹底解説
逆転コーチングの料金は高い?生徒・保護者が知りたい月謝・費用・追加料金の実態
逆転コーチングの口コミ・評判は本当?怪しい・やばい噂の真相を取材で徹底検証
東大先生の料金は高い?入会金・月謝の相場と他社比較を解説【料金の注意点】
東大先生の口コミ・評判だけを集めた本音レビュー【良い・悪いを専門家が分析】
モチベーションアカデミアのリアルな評判・口コミ・料金・デメリットまで解説
アガルート学習コーチングの口コミ・評判はやばいって本当?料金等を徹底検証
勉強計画を立ててくれる塾おすすめ17選!大学受験で逆転合格へ!
オンラインコーチング塾おすすめ15選|自宅学習で成績UP!編集部が徹底解説
スタディコーチの料金表をチェック!入会金・月謝・コース・他塾と徹底比較
オーバーフォーカス塾の口コミ・評判・料金は高い?実際の評価とは?
現論会のリアルな口コミ・評判!「やばい」噂の真相と料金・合格実績を調査
東大毎日塾の口コミ・評判を徹底調査!塾長に取材してわかったこと?
大学受験pispis塾の口コミ・評判はやばい?料金についても調査
【東進ハイスクール・東進衛星予備校】評判・口コミ10選!高校生におすすめ?【塾経験者が徹底調査
プリンターを持っている方なら純正インクを使用するよりも安く印
互換・リサイクルの格安プリンターインクの専門通販サイトインク
現在メーカーでは生産終了してしまっているインク型番まで幅広く

