【現代文の読み方・解き方】劇的に変わる7つのコツと最強の勉強法
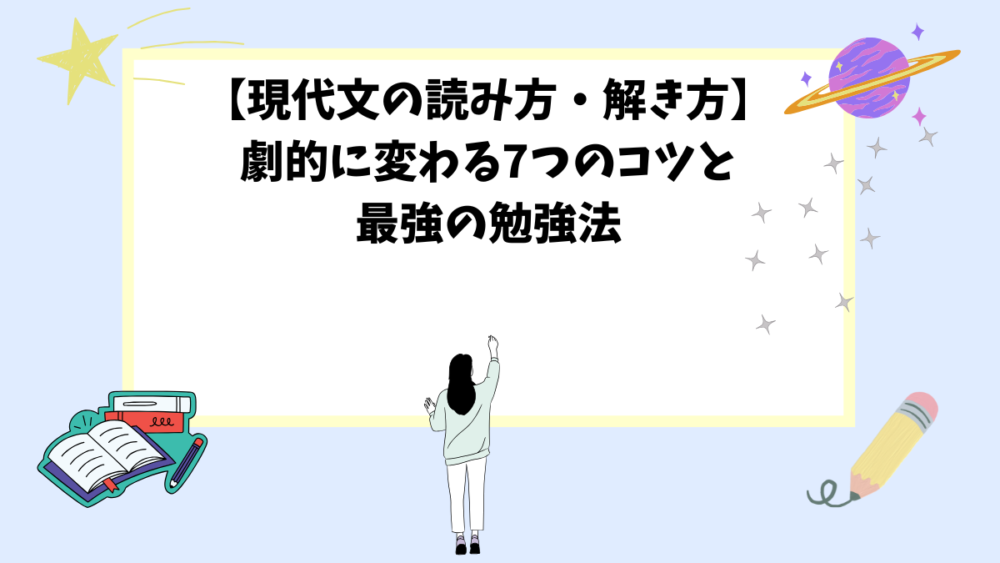
「※この記事には一部PRが含まれます」
こんにちは、受験生応援メディア「予備校オンラインドットコム」編集部です。
「現代文、日本語なのにどうしてこんなに難しいんだろう…」
「どんなに時間をかけても、文章の言いたいことが掴めない…」
もしあなたがそう感じているなら、それは決してあなただけではありません。
多くの受験生が現代文に苦手意識を持っています。
でも、安心してください。現代文は「センス」や「国語力」といった漠然としたものではなく、誰でも身につけられる「正しい読み方のコツ」と「効果的な勉強法」を知っているかで、驚くほど点数が安定し、得意科目に変わる可能性を秘めています。
この記事では、現代文の成績を劇的にアップさせるための【7つの具体的な読み方のコツ】と、学んだコツを自分の力として定着させる【今日からできる効果的な勉強法】を、どこよりも分かりやすく解説します。
これを読めば、現代文のモヤモヤが晴れて、自信を持って問題に取り組めるようになるはずです。
ぜひ最後まで読んで、現代文の苦手を一緒に克服しましょう!
現代文を読む上で最も大切なたった一つの「考え方」
文章の構造や筆者の意図を正確に掴むための、具体的な7つの「読み方のコツ」
学んだ読み方を自分の力にするための、今日からできる「効果的な勉強法」
多くの人がやりがちな「よくある間違い」と、その対策
現代文の学習に役立つ「おすすめの教材やツール」の種類
現代文に関するあなたの素朴な疑問の答え
Contents
なぜ現代文の読み方が難しいと感じるのか?その根本原因

「現代文って、日本語なのにどうして難しいんだろう?」と感じていませんか?
単語や文法だけでは内容が掴めないのには、根本的な理由があります。
ここでは、あなたが現代文を難しいと感じてしまう本当の原因を解説します。
単語や文法を知っているだけでは読めない理由
現代文特有の「論理のルール」とは
感情で読んでしまうことの危険性
単語や文法を知っているだけでは読めない理由
家を建てる時、釘や木材といった材料(単語や文法)だけがあっても、家は完成しませんよね?
どこに何をどう組み合わせるか、という「設計図」や「組み立て方」が必要です。
現代文もこれと同じです。
個々の単語の意味や文法のルールを知っているだけでは、文章全体が持つ「構造」や筆者が伝えたい「メッセージ」を正確に読み取ることは難しいのです。
特に複雑な評論文などでは、単語一つ一つを理解しても、それらがどう組み合わされて筆者の主張が成り立っているのかを掴むには、別のスキルが必要になります。
単語や文法は基本中の基本ですが、それだけでは不十分なのです。

現代文特有の「論理のルール」とは
現代文、特に評論文などには、筆者が自分の考えや情報を読み手に分かりやすく、間違いなく伝えるための「お約束」のようなルールが存在します。
これが「論理のルール」です。
例えば、「つまり」「なぜなら」「しかし」といった接続詞は、文章の流れ(言い換え、理由、逆転など)を示しています。
指示語(「これ」「それ」など)が何を指しているのかを正確に追うことも重要です。
これらのルールは、文章という設計図に書かれた記号のようなもの。
このルールを知らないと、筆者が意図した通りに文章を組み立て直すことができず、表面的な理解で終わってしまったり、誤った解釈をしてしまったりする危険性があります。

感情で読んでしまうことの危険性
小説などを読むとき、登場人物の気持ちに感情移入したり、自分自身の経験と重ね合わせて感動したりすることは、読書本来の楽しみ方です。
しかし、入試やテストの現代文で点数を取るためには、この「感情で読む」読み方が落とし穴になることがあります。
現代文の問題では、あなたの個人的な感想や感情ではなく、文章中に明確に書かれている「客観的な根拠」に基づいて解答することが求められるからです。
筆者が文章という形で提示した情報だけを頼りに、論理的に内容を読み解く訓練ができていないと、「なんとなく」で答えてしまい、正解から遠ざかってしまいます。
テスト対策としては、感情を一旦横に置き、頭を使って論理的に読む練習が必要です。
【結論】現代文の読み方をマスターするための「たった一つの考え方」

現代文が難しいと感じる原因が分かったところで、次に知るべきは、現代文を読む上で最も大切なたった一つの「考え方」です。
これは、これからお伝えする具体的な読み方のコツを実践する上での「土台」となる部分です。
この考え方を身につけるだけで、目の前の文章がまるで違って見えてくるはずです。
現代文を得意にするための、すべての基本となる心構えをお伝えします。
文章の「型」と筆者の「設計図」を意識する重要性
常に「なぜ?」「つまり?」を問いかける姿勢
文章の「型」と筆者の「設計図」を意識する重要性
現代文の文章(特に評論文)には、筆者が読み手に自分の考えを効果的に伝えるための、ある程度決まった「型」や「構造」があります。
例えるなら、家を建てる時の「設計図」のようなものです。
この設計図には、「まずはじめに問題を提起する」「次にその原因を分析する」「そして自分の意見を述べる」「最後にまとめとして繰り返す」といった流れや、「対比を使って違いを強調する」「具体例を挙げて説明を分かりやすくする」といった組み立て方が示されています。
単語や文法といった材料だけでなく、この「設計図」全体を意識しながら読むことで、筆者が一番言いたいことは何か、それぞれの部分がどんな役割を果たしているのかが掴みやすくなり、迷子にならずに文章全体を理解できるようになります。

常に「なぜ?」「つまり?」を問いかける姿勢
現代文を読むとき、ただ目で文字を追うだけでなく、頭の中で筆者に対して「なぜ?」「つまり?」と問いかけながら読むことが非常に大切です。
たとえば、「なぜ筆者はここでこんな話をしているんだろう?」「前の内容を言い換えているのかな?(つまり?)」のように、常に疑問を持ち、文章の繋がりや筆者の意図を確認しようとします。
この能動的な「問いかけ」が、文章の論理的な繋がりを見つけたり、難解な表現を自分の中で整理したりする手助けになります。
まるで筆者と対話するように読むことで、受け身ではなく、文章の核心に積極的に迫ることができるようになり、読解力が飛躍的に向上します。
この姿勢こそが、現代文マスターへの第一歩です。
【実践】現代文の読み方・解き方が劇的に変わる7つのコツ

現代文が難しい原因を理解し、読む上での「たった一つの考え方」を掴んだら、次はそれを日々の読解で活かす具体的なテクニックです!
ここでは、文章を正確かつ効率的に読み解くための、実践的な7つのコツをご紹介します。
これらのコツは、現代文の成績アップに直結するものばかりです。
それぞれのコツを理解し、実際の文章で意識して使うことで、あなたの現代文の読み方は劇的に変わるはずです。
さあ、現代文マスターへの扉を開きましょう!
コツ①:筆者の「主張(結論)」を最速で見つける方法
コツ②:文章の骨格を作る「指示語」「接続詞」の追跡法
コツ③:「対比」「言い換え」を見抜いて内容を正確に把握する
コツ④:「具体例」から「抽象(筆者の言いたいこと)」を読み取る逆算思考
コツ⑤:紛らわしい「比喩」「たとえ」に惑わされない技術
コツ⑥:段落ごとに「役割」と「トピック」を把握する構造読み
コツ⑦:評論と小説で押さえるべき「読み方の違い」
コツ①:筆者の「主張(結論)」を最速で見つける方法
評論文や論説文のゴールは、筆者が「何を一番伝えたいか」、つまり「主張(結論)」を読み取ることです。
これを最初に見つけられると、その後の文章が全て、その主張を説明したり、根拠を示したりしているものだと理解でき、格段に読みやすくなります。
筆者の主張は、特に以下の場所や言葉の近くにあることが多いです。
・文章の最初や最後:導入で問題提起し、最後に結論を述べるパターン。
・特定の接続詞の後ろ:「したがって」「ゆえに」「だから」「つまり」「結局」といった言葉は、結論やまとめのサインです。
・断定的な表現:「~べきである」「~考える」「~が重要だ」など、筆者の強い意見を示す言葉。
これらの目印を意識しながら読むことで、文章全体の「核」を素早く掴むことができます。

コツ②:文章の骨格を作る「指示語」「接続詞」の追跡法
指示語(これ、それ、あれ、どれ)や接続詞(そして、しかし、だから、つまり)は、文章の文と文、段落と段落をつなぎ、論理的な流れを作る「骨組み」のようなものです。
・指示語:「これ」が何を指しているのかを正確に掴むことで、文と文の具体的な繋がりが分かります。直前の語句や文をしっかり確認しましょう。
・接続詞:文や段落の関係性(順接、逆接、並列、補足など)を示します。接続詞に注意することで、筆者の思考の方向性が分かり、文章全体をスムーズに追うことができます。
指示語・接続しの言葉を意識的に追跡することで、文章の表面的な意味だけでなく、筆者がどう情報を組み立てているのか、その「骨格」が見えてくるようになります。

コツ③:「対比」「言い換え」を見抜いて内容を正確に把握する
現代文では、内容を明確にしたり、筆者の主張を際立たせたりするために、「対比」や「言い換え」という表現技法がよく使われます。
・対比とは?
二つの異なるもの(AとB)を並べて比較することで、それぞれの特徴や違いをはっきりさせる方法です。「~に対して」「一方」「これに対し」といった言葉が目印になることがあります。筆者は対比を用いて、自分が支持する側(多くの場合AかBのどちらか)を強調することが多いです。
・言い換えとは?
同じ内容を別の言葉で繰り返したり、難しい表現を分かりやすく説明したりする方法です。「すなわち」「つまり」「換言すれば」といった言葉がサインです。言い換えられている部分は、筆者が重要だと考えているポイントであることが多いので、しっかりチェックしましょう。
これらを見抜くことで、文章の核心部分や筆者が強調したい点を正確に捉えることができます。

コツ④:「具体例」から「抽象(筆者の言いたいこと)」を読み取る逆算思考
現代文では、抽象的な理論や主張(筆者が言いたいこと)を述べた後に、それを分かりやすくするために具体的な例が示される構成がよくあります。
たとえば、「環境問題は深刻だ(抽象)」→「富士山のゴミ問題(具体例)」のように繋がります。
読むときは、具体例そのものに詳しくなることよりも、その具体例が「何を示しているのか」、つまりその前に述べられた抽象的な筆者の言いたいこと(概念や主張)に戻って考える「逆算思考」が重要です。
難しい具体例に出会った時ほど、「この例は何を説明するために使われているんだろう?」と考えて、前後の抽象的な記述を確認することで、筆者の真意を理解しやすくなります。

コツ⑤:紛らわしい「比喩」「たとえ」に惑わされない技術
筆者は、難しい概念を読者にイメージさせやすくするために、身近なものに例える「比喩」や「たとえ」を使います。
たとえば、「人間の記憶はスポンジのようだ」といった表現です。
ここで大切なのは、比喩そのもののイメージに引っ張られすぎないことです。
「スポンジ」という言葉から連想される色々なイメージにこだわりすぎると、筆者が「何のために」その比喩を使ったのか、つまり比喩を通して伝えたい「本来の意味(この場合は『吸収しやすい』や『保持できる』といった記憶の性質)」を見失ってしまうことがあります。
比喩やたとえは、あくまで「例え」です。
それらが指し示している「本体」や、筆者がその比喩で何を強調したいのかを客観的に読み取る技術を磨きましょう。

コツ⑥:段落ごとに「役割」と「トピック」を把握する構造読み
長い文章を読む際は、いきなり全体を理解しようとするのではなく、段落ごとに区切って、それぞれの役割と最も大切な内容(トピック)を把握していくと、文章全体の構造が掴みやすくなります。
各段落は、文章全体の中で特定の「役割」を持っています。
・導入段落:問題提起、テーマの提示
・展開段落:原因分析、具体例、別の意見の紹介
・結論段落:主張のまとめ、将来への展望
それぞれの段落には、そこで最も言いたいこと(「トピックセンテンス」と呼ばれることも)が含まれています。
段落ごとに「この段落は何のためにあるんだろう?」「ここで一番言いたいことは何だろう?」と考えながら読む「構造読み」をすることで、文章全体の「設計図」が頭の中に描けるようになり、内容が整理されて理解が進みます。

コツ⑦:評論と小説で押さえるべき「読み方の違い」
現代文の文章には、主に「評論・論説文」と「小説・随筆」があります。
これらは目的も内容も大きく異なるため、同じ読み方ではいけません。
【評論・論説文】
・目的:筆者の論理的な主張や考えを理解すること。
・注目点:主張、根拠、論理展開、キーワード、接続詞、対比、具体例の役割。
【小説・随筆】
・目的:登場人物の心情、情景描写の意味、出来事の背景などを読み取ること。
・注目点:登場人物の言動・心情の変化、情景描写(五感で感じられるもの)、時間の経過、比喩表現、会話文の裏に隠された意味。
自分が今読んでいるのが評論なのか小説なのかを意識し、それぞれのタイプに合わせて注目すべきポイントを切り替えることが、正確な読解と得点アップの鍵となります。
【今日からできる】現代文の読み方を定着させる効果的な勉強法

現代文を読むための「コツ」を知ることは、地図を手に入れたようなものです。
目的地(問題が解ける、内容が理解できる)にたどり着くには、実際に地図を使って歩く練習が必要ですよね?
このセクションでは、学んだ読み方のコツを自分の力として定着させるための、具体的な勉強法をお伝えします。
どれも今日からすぐに始められるものばかり。
これらの方法を実践して、現代文をあなたの得意科目に変えましょう!
【基本】教科書や問題集を使った「音読」と「黙読」の正しいやり方
【応用】文章構造を理解するための「要約」練習法
【必須】語彙力を爆発的に増やすためのインプット・アウトプット法
【実践】問題演習(過去問・参考書)で「読み方」を鍛えるステップ
【復習法】解けなかった問題から読み方のどこに問題があったかを分析する
【基本】教科書や問題集を使った「音読」と「黙読」の正しいやり方
読む練習の基本は、教科書や問題集に載っている文章を使った「音読」と「黙読」です。
・音読とは?
声に出して文章を読むことで、目で追うだけでは気づきにくい、文章のリズムや句読点の意味、論理の切れ目などが体で感じられるようになります。つっかえずにスムーズに読めるようになるまで繰り返すことで、速く正確に読む力も養われます。ただ読むだけでなく、筆者の主張だと思うところに強弱をつけたり、接続詞で区切ることを意識したりすると効果的です。
・黙読とは?
声に出さずに頭の中で意味を追います。時間制限を設けて集中力を高めたり、読んだ後に文章の構造や筆者の意図を頭の中で整理したりする練習に適しています。タイマーを使って、本番を意識した緊張感の中で読む練習もおすすめです。
どちらの方法も、漫然とこなすのではなく、「文章を理解するぞ!」という意識を持って行うことが大切です。

参考記事:現代文の定期テスト勉強法をアドバイス【現代文の勉強のコツ】
【応用】文章構造を理解するための「要約」練習法
文章の「設計図」を理解する力を高めるのに最適なのが「要約」です。
これは、文章全体の中から筆者の主張と、それを支える最も重要なポイントだけを抜き出し、元の文章より短い言葉でまとめる練習です。
【要約のステップ例】
1.まず文章全体を読み、大まかなテーマを掴む。
2.段落ごとに「ここで筆者が一番言いたいことは何か?」を考える。
3.筆者の主張やキーセンテンスだと思うところに線を引く。
4.接続詞や指示語を手がかりに、文章の論理的な繋がりを確認する。
5.抜き出した重要なポイントを、自分の言葉で簡潔に繋いで短い文章にする。
6.元の文章と照らし合わせ、意味が変わっていないか、余分な情報が入っていないか確認する。
最初は難しくても、短い文章から始めたり、家族や学校の先生に添削してもらったりしながら続けると、文章の骨組みを見抜く力が驚くほど伸びます。

【必須】語彙力を爆発的に増やすためのインプット・アウトプット法
現代文をスラスラ読むためには、言葉の意味を知っている「語彙力」が必須です。
単語の意味が分からないと、文章全体の理解も難しくなります。
語彙力を「爆発的に」増やすには、インプット(覚える)とアウトプット(使う)をセットで行うのがコツです。
・インプット(覚える)
文章を読んでいて分からない言葉に出会ったら、必ずチェックし、辞書で意味を調べましょう。ただ意味を見るだけでなく、例文を読んで「どんな文脈で使われるか」を理解することが重要です。自分だけの単語ノートや単語カードを作るのも良いでしょう。スキマ時間を活用して、何度も見返す習慣をつけましょう。
・アウトプット(使う)
覚えた言葉を、自分で文章を作る際に使ってみましょう。日記を書く、調べた言葉を使って短い文を作る、音読の際にその言葉を意識するなど、実際に使うことで記憶に定着しやすくなります。
新しい言葉に出会うたびに、「自分の言葉」にしていく意識を持つことが、語彙力アップの最大の秘訣です。

【実践】問題演習(過去問・参考書)で「読み方」を鍛えるステップ
学んだ読み方のコツが、実際の入試問題などで通用するかを確認し、使える力にするためには、問題演習が不可欠です。
【問題演習の効果的なステップ】
1.時間を計って解く: 本番と同じ時間制限で取り組み、時間内に解き切る練習をします。
2.自力で解答の根拠を探す: 解答を見る前に、なぜその答えになるのか、文章中のどこが根拠になるのかを必ず自分の頭で考え、印をつけましょう。
3.答え合わせと自己採点: 正誤を確認します。
4.【重要】間違えた問題・根拠不明な問題の分析: なぜ間違えたのか?自分がどこを読み間違えたのか?正しい根拠は文章のどこにあったのか?を徹底的に分析します。
解答解説を読むだけでなく、自分の「読み方」に立ち返って問題点を見つけます。
解くこと自体が目的ではなく、「学んだ読み方を使ってみる」「自分の読み方の弱点を見つける」ことを意識して取り組みましょう。

参考記事:現代文の種類を学ぶと読解力アップの近道!大学入試を突破しよう【現代文とは】
【復習法】解けなかった問題から読み方のどこに問題があったかを分析する
問題演習は、「解く」よりも「復習」がはるかに重要です。
特に、間違えたり、正解したけれど根拠があやふやだった問題から、学ぶべきことがたくさんあります。
【効果的な復習のステップ】
1.自分の間違いを分類する
・単語や文法が分からなかった → 語彙力不足
・指示語や接続詞を追えなかった → 論理把握の練習不足
・筆者の主張や結論を取り違えた → 文章構造の把握不足
・具体例と抽象の区別がついていなかった → 読み方の定着不足
・自分の感情や先入観で読んでしまった → 客観的な読解ができていない
2.正しい読み方で読み直す
解説や模範解答を参考にしながら、どうすれば正しく読めたのか、正しい根拠はどこだったのかを文章中で確認します。
3.問題点と対策をメモする
「このタイプの問題は、〇〇の読み方ができていなかった」「比喩が出てきたら、△△に注意する」のように、具体的な問題点と、次にどうすれば良いかを記録しておきます。
この「分析」と「対策のメモ」こそが、次に同じ間違いを繰り返さないための、最も効果的な復習法です。
これを積み重ねることで、あなたの「読み方」そのものが洗練されていきます。
【おすすめオンライン塾】
現役東大生のノウハウが凝縮
受験の勝ち方を熟知した!
東大生・早慶生が徹底サポート
現代文の読み方で多くの人が陥る【よくある間違い】と対策

ここまで、現代文を正しく読むための考え方や具体的なコツ、効果的な勉強法を見てきました。
しかし、これらの方法を知っていても、多くの人が無意識のうちに陥ってしまう「落とし穴」があります。
これらの「よくある間違い」を知っておくことで、無駄な失点を減らし、効率よく読解力を伸ばすことができます。
「あれ?自分もこれ、やってるかも…」と感じたら、すぐに読み方を見直すチャンスです。
ここでは、多くの受験生がつまずくポイントと、その対策をご紹介します。
「なんとなく」の感覚で読み進めてしまう間違い
知らない単語や分からない箇所で立ち止まりすぎる間違い
本文に根拠がない「自分の意見」で解答してしまう間違い
「なんとなく」の感覚で読み進めてしまう間違い
現代文を読むとき、文章の表面だけを追ってしまい、「だいたいこんなことが書いてあるんだろう」と「なんとなく」の感覚で読み進めてしまう人が非常に多いです。
簡単な文章ならそれでも通用するかもしれませんが、論理が複雑に絡み合った文章や、細かい部分を問われる問題になると、途端に歯が立たなくなります。
これは、筆者がどのように考えを展開しているか、論理の繋がりを意識できていないために起こります。
【対策】
・論理の目印を追う:接続詞(しかし、だから、つまり等)や指示語(これ、それ等)に常に注意し、文章の流れを意識しましょう。
・「なぜ?」「つまり?」の問いかけ:文章を読みながら、「なぜ筆者はこう言っているのだろう?」「この段落で言いたいことは結局何だろう?」と自問自答する癖をつけましょう。
・段落ごとに区切る:長文を一気に読まず、段落ごとに立ち止まって、その段落の役割や中心的な内容を確認しましょう。

知らない単語や分からない箇所で立ち止まりすぎる間違い
文章中に知らない単語や、何度読んでも意味が掴めない箇所が出てくると、そこでフリーズしてしまい、先に進めなくなってしまうことがあります。
全ての単語の意味を知っている必要はありませんし、現代文の多くは文脈から意味を類推できることが多々あります。
一部の分からない箇所に固執しすぎると、文章全体の流れを見失ってしまったり、限られた試験時間内で最後まで読み切れなくなったりするリスクが高まります。
【対策】
・まずは最後まで読む:分からない単語や箇所に線や印だけつけて、まずは文章全体を最後まで読み切りましょう。文章全体を読むことで、分からなかった箇所の意味が後から理解できることもあります。
・文脈からの類推:前後の文脈から、その言葉がどんな意味で使われているかを推測する練習をしましょう。
・重要度で判断:文章の理解にどうしても必要不可欠な単語や箇所だけ、後から辞書などで調べるようにしましょう。全てを完璧に理解しようとせず、全体像を掴むことを優先する割り切りも必要です。

参考記事:現代文で出題される論説文の解き方!たった5つのコツで論説文が解ける!
本文に根拠がない「自分の意見」で解答してしまう間違い
特に小説の登場人物の心情を問う問題や、筆者の考えを問う問題などで、文章中に書かれていることからではなく、「自分ならこう思うから」「一般的にはこう考えるだろう」といった「自分の意見」や「個人的な感想」で解答を作成してしまう間違いです。
現代文の入試問題やテストは、必ず文章中に正解の「根拠」が存在します。
筆者が書いたこと、登場人物の言動や描写から客観的に読み取れることだけが正解の根拠となります。
あなたの豊かな感性は素晴らしいですが、テストでは本文に書かれた情報のみを頼りに解答を導き出す必要があります。
【対策】
・解答の根拠を本文に見つける:問題を解く際は、「なぜこの答えになるのか?」その根拠となる部分を必ず文章中から探し、線や印をつけましょう。
・設問の意図を確認:設問が「筆者の考え」を問うているのか、「登場人物の心情」を問うているのか、「傍線部の内容の説明」を求めているのかなど、何が問われているかを正確に把握しましょう。
・客観的な視点を持つ:自分の感情や先入観を排除し、本文に書かれている情報だけを使って論理的に考える訓練を繰り返しましょう。解説を読んで、なぜ自分の考えが間違っていたのか、根拠がどこにあったのかを分析することが重要です。
【おすすめオンライン塾】
現役東大生のノウハウが凝縮
受験の勝ち方を熟知した!
東大生・早慶生が徹底サポート
現代文の読み方向上に役立つ【おすすめ教材・ツール】

正しい読み方を知り、勉強法を理解したら、いよいよ実践です。
ここでは、あなたの現代文学習を強力にサポートしてくれる、具体的に「これ!」という教材やツールをいくつかご紹介します。
自分に合ったものを見つけて、効率よくレベルアップを目指しましょう。
文章構造が理解できる参考書
実践練習に最適な問題集
語彙力強化のためのツール・アプリ
1.文章構造が理解できる参考書
単なる問題集ではなく、「どう読めば文章の構造や筆者の意図が掴めるのか」という、読み方そのものをイチから解説してくれるタイプの参考書です。
『現代文読解力の開発講座』(霜栄 著 / 河合出版)
現代文の論理的な読み方を体系的に学べる超定番参考書です。文章の構造把握、指示語や接続詞の役割、言い換えや対比の捉え方など、現代文を読む上での「型」が詳しく解説されています。やや硬派な内容ですが、これ一冊をやり込めば、現代文を読む上での盤石な基礎が築けます。多くの受験生に支持されています。
『田村のやさしく語る現代文』(田村秀行 著 / 旺文社)
現代文が苦手な人でも取り組みやすいように、語りかけるような優しい言葉遣いで書かれている参考書です。現代文を読む上での基本的な心構えから始まり、段落ごとの読み方、設問へのアプローチなど、順を追って丁寧に解説しています。専門用語が少なく、スラスラ読めるので、「どこから始めればいいか分からない」「現代文に苦手意識が強い」という高校生にとって、現代文学習の最初の一歩として非常におすすめです。
2. 実践練習に最適な問題集
学んだ読み方を実際の文章で使い、問題を解く練習を積むための問題集です。様々なレベルやテーマのものがあります。
大学入学共通テスト対策問題集(Z会、河合塾、駿台など主要予備校・出版社)
共通テスト形式の現代文に慣れるための必須アイテムです。本番を意識した時間配分で解く練習ができます。複数の出版社から出ており、それぞれ解説の詳しさや問題の質に特徴があるので、書店で比較検討するのがおすすめです。最新版(その年度用)を選ぶようにしましょう。
レベル別問題集・参考書(例: 船口明の現代文、田村秀行の現代文など、講師名やシリーズ名を冠したもの)
特定の講師が執筆・監修しているシリーズは、その講師の提唱する読み方や解き方に沿って問題が構成されていることが多いです。解説が非常に丁寧で、なぜその答えになるのか、どう読めばよかったのかが分かりやすいのが特長です。自分のレベルに合ったシリーズから始めてみましょう。(例: 船口の現代文 読解・記述のルールなど)
志望校の過去問(いわゆる「赤本」)
入試直前期になったら、志望校の過去問で演習することが最も重要です。大学によって出題形式や文章の傾向が異なるため、志望校対策としてはこれ以上の教材はありません。ただし、解説が簡潔なものも多いため、基礎力がついてから取り組むのがおすすめです。

3. 語彙力強化のためのツール・アプリ
現代文に頻出する難しい言葉や抽象的な概念を効率的に学ぶためのツールやアプリです。
辞書アプリ・オンライン辞書(例: Goo辞書、Weblio辞書、Kotobank など)
文章を読んでいて分からない単語が出てきたら、すぐに調べられるように、スマートフォンの辞書アプリやオンライン辞書を活用しましょう。意味だけでなく、用例(例文)を確認することで、言葉の使い方がより深く理解できます。複数の辞書を横断検索できる機能があると便利です。
現代文キーワード集アプリ
評論などで頻出する哲学や社会、科学などの分野の「思想用語」や「キーワード」に特化した学習アプリも存在します。これらのキーワードは文章のテーマを理解する上で非常に重要なので、アプリで手軽に覚えるのも効果的です。大学受験用の語彙アプリや、JLPT(日本語能力試験)N1/N2レベルの語彙アプリなども参考になります。
単語学習アプリ(例: Anki, Quizlet など – 汎用的なもの)
特定の現代文単語集というよりは、自分で調べた言葉を登録して、効率的に復習できる汎用的な単語学習アプリです。忘却曲線に合わせて繰り返し出題してくれる機能などがあり、語彙の定着に役立ちます。自分で分からない言葉を登録して、オリジナルの単語帳を作成するのに最適です。
【教材選びのポイント】
・レベルに合っているか:優しすぎず、難しすぎないものを選びましょう。
・解説が詳しいか:なぜそうなるのか、納得できる解説があるかが重要です。
・続けられそうか:デザインや構成、文章のテーマなど、自分が取り組みやすいものを選びましょう。
・新しい版か:特に受験対策用の問題集や参考書は、最新の傾向に合わせて改訂されているか確認しましょう。
可能であれば書店で実際に手に取って中身を確認し、自分に合う「相棒」を見つけて、現代文の学習に役立ててください。
現代文の読み方・解き方に関するよくある質問
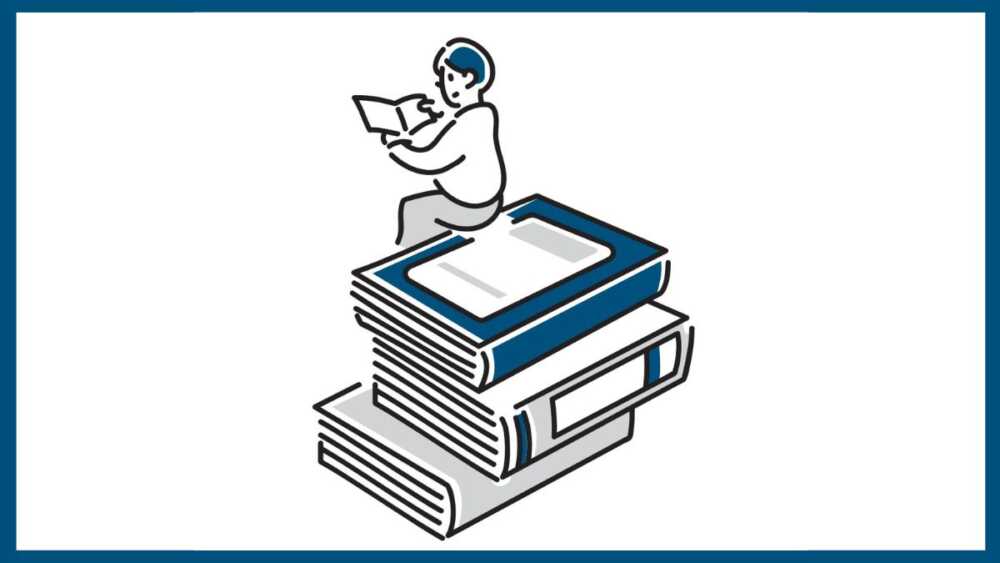
現代文の読み方や勉強法について、ここまで様々な角度から解説してきました。
でも、もしかしたら「こんな場合はどうなの?」「この言葉の意味は?」といった、まだ解消されていない疑問があるかもしれませんね。
このセクションでは、現代文の学習に取り組む中で多くの高校生や保護者の方が抱きやすい、よくある質問にお答えします。
あなたの疑問も、きっとここで解決するはずです。
現代文の解き方の流れは?
早稲田の現代文は難しいですか?
「現国」の読み方は?
現代文の精読とは?
現代文の解き方の流れは?
現代文の問題を解くとき、闇雲に取り組むのではなく、効率的な流れを知っておくことが重要です。
一般的な解き方のステップは以下のようになります。
1.設問全体に目を通す:まずは設問を見て、「何が問われているか」「解答形式(選択式か記述式か)」「解答の字数制限」などを把握します。
2.文章全体を「正しく」読む: これまでに学んだ読み方のコツ(論理構造、接続詞、指示語、筆者の主張意識など)を使いながら、文章全体を読み進め、大まかな内容と構造を掴みます。
3.設問ごとの根拠を探す:各設問に戻り、問いに対応する内容や根拠が文章のどこに書かれているかを探し、線を引いたりメモしたりします。
4.根拠に基づいて解答を作成・選択する:見つけた根拠を元に、設問の要求に合うように解答を作成します。(選択式なら)根拠と合わない選択肢を消去していくのが効果的です。
5.解答・根拠を見直す:自分の解答が本当に本文中の根拠に基づいているか、設問に正確に答えているかを確認します。
この流れを意識することで、迷子にならず、時間内に効率よく問題を解けるようになります。

早稲田の現代文は難しいですか?
大学入試の現代文の中でも、早稲田大学の現代文は一般的に「難しい」と言われることが多いです。その難しさの理由はいくつかあります。
・文章そのものが高度:哲学や思想など、抽象度が高く、普段馴染みのないテーマの文章が出題される傾向があります。
・問題形式の多様さ:選択肢問題でも紛らわしいものが多く、また記述問題では本文の内容を正確にまとめる力が求められます。
・時間制限:文章量に対して解答時間が短い場合が多く、速く正確に読む力が必要です。
難しいからといって対策ができないわけではありません。
高度な文章に慣れる練習、過去問を徹底的に研究して出題形式に慣れること、そして日頃から速読力・精読力の両方を鍛えることが、早稲田の現代文攻略には不可欠です。

「現国」の読み方は?
「現国」(げんこく)というのは、「現代国語」を略した、高校生の間でよく使われる言葉ですね。
「現国の読み方」というのは、まさにこの記事全体で解説している「現代文の正しい読み方」のことを指しています。
具体的には、
・単語や文法だけでなく、文章全体の「論理構造」や「筆者の意図」を読み取ること。
・筆者の「主張」や「結論」は何かを常に意識すること。
・接続詞や指示語、対比や言い換えといった「論理のルール」を手がかりに読むこと。
・自分の感情や先入観を排除し、本文に書かれていることだけを根拠に考えること。
などが「現国の読み方」のポイントです。
「なんとなく」ではなく、これらの客観的で論理的な読み方を身につけることが、「現国」の成績アップに繋がります。

現代文の精読とは?
「精読」(せいどく)とは、現代文の勉強法の一つで、「文章を細部まで丁寧に、正確に読み込むこと」を意味します。
ただ速く大量に読む「多読」や、声に出して読む「音読」とは異なり、一つの文章に時間をかけて深く向き合うのが精読です。
精読では、以下のような点を徹底的に行います。
・一文一文の構造を丁寧に分析し、意味を正確に取る。
・分からない単語や表現があれば、すぐに辞書などで調べ、意味を完全に理解する。
・指示語が何を指しているか、接続詞が示す論理関係を正確に追跡する。
・筆者がなぜここでこの言葉や表現を使ったのか、その意図を深く考える。
精読は時間がかかりますが、文章を正確に理解する力を養うには非常に効果的です。
特に難解な文章や、じっくり内容を理解したい文章に取り組む際に有効な学習法です。
まとめ:【現代文の読み方・解き方】劇的に変わる7つのコツと最強の勉強法

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「【現代文の読み方・解き方】劇的に変わる7つのコツと最強の勉強法」は参考になりましたでしょうか?
まとめ:【現代文の読み方・解き方】劇的に変わる7つのコツと最強の勉強法
この記事では、あなたが現代文を難しいと感じる「根本的な理由」から、文章を読む上で軸となる「たった一つの考え方」、「劇的に変わる7つの読み方のコツ」、そしてそれらを定着させる「効果的な勉強法」までを詳しく解説しました。
多くの人が陥りがちな「間違い」や、あなたの学習を助ける「おすすめ教材」についてもご紹介しました。
現代文は、やみくもに問題を解くだけではなかなか成績が上がりません。しかし、今回ご紹介したように、文章を論理的に理解するための「正しい読み方」を知り、それを日々の学習で実践・定着させていくことで、誰でも必ず得意にできる科目です。
この記事で学んだ読み方のコツや勉強法を、ぜひ今日からあなたの学習に取り入れてみてください。最初は難しく感じるかもしれませんが、根気強く続けることで、きっと文章が以前よりもずっとクリアに見えてくるはずです。
あなたの現代文学習が実りあるものになるよう、心から応援しています!頑張ってください!
国語の勉強は学習管理型の塾に通ってやる気アップ
学習塾の指導形式で大きく分けると、「集団指導」、「個別指導」、「家庭教師」、「オンライン指導」そして、「学習管理型の塾」に分けられます。
最近注目されている学習管理型の塾とは、一般的に科目の指導はしていません。
具体的には、生徒の志望大学に合格するための学習計画を作成して、学習の進捗管理がメインとなります。
学習計画には、年間、月間、週間、毎日のやるべきことが細かく指示され、計画通りに学習を進めていくと志望大学に合格できる仕組み。
毎日の学習は、指示された市販の参考書を使い、自学自習というスタイルで受験勉強に取り組みます。
受験勉強では、自分の志望校に合わせた対策が必要であり、そのためには自らが率先して学ぶ、自学自習のスタイルがとても大切。
実は、受験生の勉強時間を見てみると、自分で理解したり、自分で問題を解いたりする自学自習の時間が最も長いのです。
学習管理型の塾では、自学自習の仕方、勉強時間の効率的な使い方、取り組むべき参考書を決めてくれるため、学習計画に沿って勉強が進められるようになるでしょう。
| 項目 | 学習管理型の塾 | 通常の塾 |
| 勉強計画策 | ○ | △ |
| 学習の進捗管理 | ○ | △ |
| 質問対応 | ○ | △ |
| 実力測定テスト | ○ | ○ |
| 科目ごとの授業 | △ | ○ |
以上、大学合格を目指して、学習管理型の塾を検討してみるのも、おすすめです。
完全1対1のオンライン個別指導:キミノスクール
※週5日の個別指導で偏差値が平均で14.8もアップする!
講師は全員現役東大生のコーチング塾:東大先生
※オンラインだから全国対応!東大生の指導で未来が変わる!
難関私大に逆転合格!「逆転コーチング」
※早慶・MARCH・関関同立に合格できる強力なノウハウとは?
東大生に毎日勉強を教えてもらえる!東大毎日塾!
※24時間質問し放題!オンライン自習室使い放題でこの価格!
現役の東大・旧帝大・早慶生が指導|スタディコーチ
※東大式「逆授業」で学力を伸ばす!夢の志望校合格へ!
合格実績が豊富な学習管理型の塾!STRUX
※オンライン対応!志望校合格まで受験パーソナルトレーナーが徹底指導!
現代文の成績を上げるおすすめ記事
古文の成績を上げるおすすめ記事

