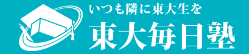高校中退から大学受験!逆転合格する5つのルートとは?高卒認定だけじゃない
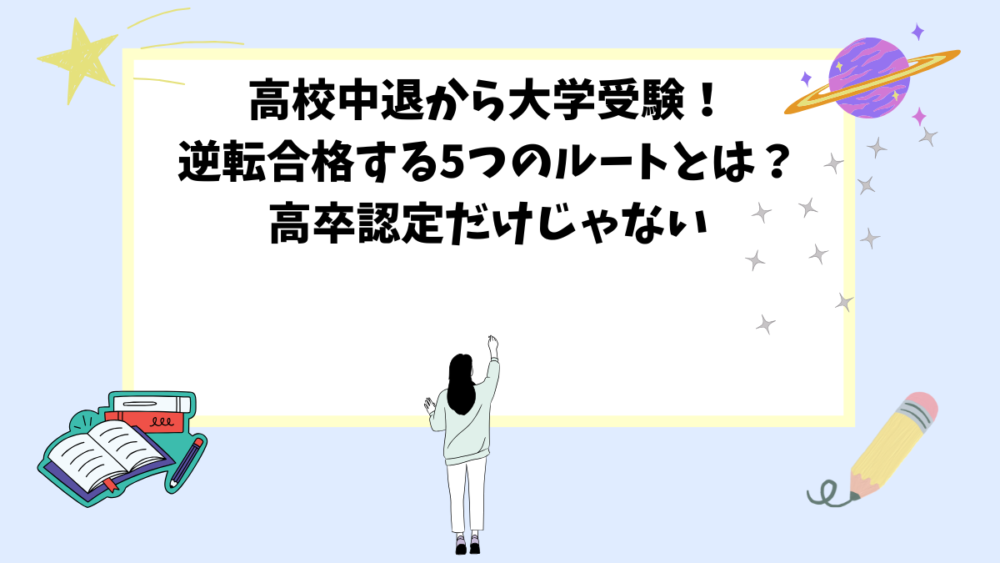
「※この記事には一部PRが含まれます」
監修:進路アドバイザー資格保有者
長年の進路相談経験と、進路アドバイザー資格に基づく専門知識を活かし、この記事では高校中退からの大学受験に関する実践的なアドバイスを監修しています。
こんにちは、受験生を応援する教育メディア、予備校オンラインドットコムです。
受験生の悩みを解決して、勉強に役立つ情報を発信しています。
今回のお悩みはこちら。
高校中退者の大学受験する方法は?
高校を中退してしまっても、大学進学の夢を諦める必要はありません。
実は高校中退者が大学に進学するためのルートは複数存在します。
この記事では、高卒認定試験だけでなく、通信制高校、定時制高校、専修学校高等課程など、多様な選択肢について詳しく解説します。
あなたに最適な進路選択のためのガイドとして、ぜひ参考にしてください。
高校中退者が大学進学を目指すための複数のルート
各ルートのメリット・デメリットと、自分に合ったルートの選び方
高卒認定試験の仕組み、難易度、勉強法、出願から合格までの流れ
高校中退からの大学受験に関するよくある疑問とその回答
難関大学にあなたも逆転合格できる
圧倒的な合格率が本物の証
難関私大に合格する完璧なノウハウ
志望大学の先生があなたをサポート
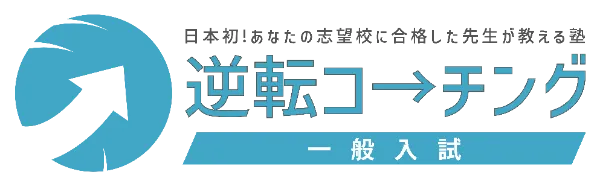
「友だち追加」で無料コーチング
勉強計画を無料で作成
↓↓↓
Contents
高校中退でも大学進学は諦めないで!可能性はゼロじゃない
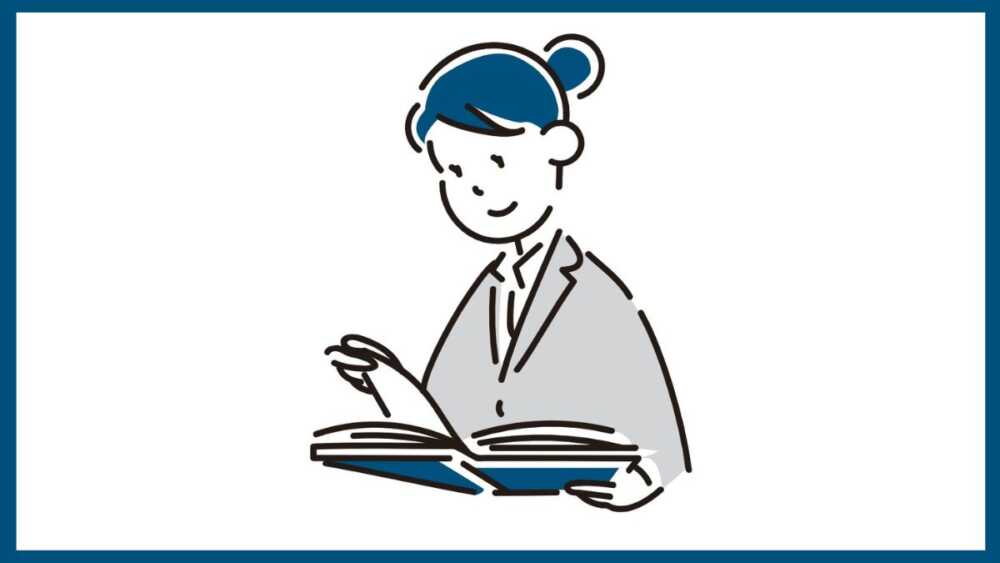
高校を中退したことで、大学への道が閉ざされたと感じるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
むしろ、様々な選択肢があり、自分に合った方法で大学受験に挑戦できます。
高校中退後も大学進学を目指す方法は複数あり、それぞれのルートには特徴とメリットがあります。
あなたの状況や目標に合わせて最適な道を選べば、大学合格も十分可能です。
この記事を読めばわかること:大学受験への道筋と選択肢
「高校を辞めたら大学は無理?」多くの人が抱える不安
「高校を中退したら、もう大学には行けないのでは?」という不安を抱えている方は少なくありません。
実際、高校卒業資格がなければ一般的な大学受験資格を得られないことは事実です。
高校を中退したこと自体が大学進学の可能性を完全に奪うわけではないということを知っておくことが大切です。
様々な事情で高校を続けられなくなったとしても、別のルートから大学受験資格を取得できる制度が整っています。

この記事を読めばわかること:大学受験への道筋と選択肢
この記事では、高校中退後に大学を目指すために必要な「大学入学資格」の取得方法や、その後の受験対策までをわかりやすく解説します。
具体的には、
・高卒認定試験の仕組みと勉強法
・通信制・定時制高校を活用した大学受験への道筋
・専修学校高等課程という選択肢
・受験対策や学費の問題など実践的なアドバイス
が含まれます。
自分に合った選択をするための判断材料として役立ててください。
高校中退者が大学受験で直面する「壁」とは?

高校中退から大学進学を目指す際には、いくつかの障壁があります。
最も大きなハードルは「大学入学資格」の取得です。
通常の高校卒業生とは異なる準備や対策が必要になるため、その全体像を理解することが重要です。
それぞれの壁を一つずつ理解し、計画的に乗り越えていくことで、大学合格への道が開けていきます。
「高校中退」という経歴は受験で不利になる?
調査書がない場合はどうすればいい?
まず必要になる「大学入学資格」とは何か?
大学に入学するためには、「大学入学資格」が必要です。
通常、高校卒業がこの資格にあたりますが、高校を中退した場合はこの資格を別途取得する必要があります。
【大学入学資格を得る主な方法】
・高卒認定試験(旧大検)に合格する
・通信制・定時制高校に再入学して卒業する
・大学入学資格付与指定を受けた専修学校高等課程を修了する
いずれかの方法で大学入学資格を取得できれば、大学受験のスタートラインに立つことができます。

「高校中退」という経歴は受験で不利になる?
多くの方が気にされる点ですが、高校中退の経歴自体が大学受験で直接的に不利になることはありません。
大学側は「大学入学資格」を持っているかどうかで判断するためです。
通常の高校生と比べると、以下の点で違いがあります。
・高校の授業で培われる基礎学力の部分を自力で補う必要がある
・調査書(内申点)がない場合が多い
・学校推薦型選抜(旧推薦入試)の利用が限られる
これらの点を意識して対策を立てることが重要です。

調査書がない場合はどうすればいい?
通常、大学受験では出身高校が発行する「調査書」(内申書)が必要です。
高校中退者の場合、この調査書がないか、中退時点までの情報しかないことがあります。
対応方法として、
・高卒認定試験合格者は「合格成績証明書」を提出
・通信制・定時制高校に再入学した場合は、その高校の調査書を使用
・一部の選抜方法では調査書不要の場合もある
各大学の入試要項で調査書に関する扱いを確認することが重要です。
参考記事:コーチング塾とは?高校生におすすめ!オンラインコーチング塾20選
高校中退から大学受験資格を得る!5つの主なルート

高校中退後に大学を目指すルートは大きく分けて5つあります。
それぞれのルートにはメリット・デメリットがあり、自分の状況や目標に合わせて選択することが大切です。
時間的な制約や学習スタイルの好み、将来の進路なども考慮して、最適なルートを見つけましょう。
ルート2:通信制高校に再入学して卒業する
ルート3:定時制高校に再入学して卒業する
ルート4:大学入学資格が付与される専修学校高等課程を修了する
ルート5:全日制の高校に転校
ルート1:高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)に合格する
高卒認定試験は、高校卒業と同等の学力があると認められれば大学受験資格を得られる国の制度です。
年2回(4月と7月)実施され、比較的短期間で大学受験資格を取得できるメリットがあります。
【高卒認定試験のポイント】
・最短ルートで受験資格が得られる(合格から数カ月)
・自分のペースで学習できる
・費用負担が比較的少ない(受験料のみ)
高校の授業内容を独学で学ぶ必要があるため、計画的な学習姿勢が求められます。

ルート2:通信制高校に再入学して卒業する
通信制高校は、自宅などで学習し、スクーリング(面接指導)を組み合わせて単位を取得する学校制度です。
高校中退後に通信制高校に入り直して卒業するという選択肢があります。
【通信制高校のメリット】
・高校卒業資格が得られる
・学校のサポートを受けながら学べる
・高校生活を経験できる
卒業までに最低でも1年以上かかるため、すぐに大学受験を目指す場合は時間がかかることを考慮する必要があります。

ルート3:定時制高校に再入学して卒業する
定時制高校は、通常夜間や特定の時間帯に授業が行われる高校です。
働きながら学べる環境が整っており、高校中退後の選択肢として検討できます。
【定時制高校のメリット】
・教師の直接指導を受けられる
・クラスメイトと一緒に学べる
・高校卒業資格を得られる
定時制高校は通常3〜4年で卒業しますが、単位制を導入している学校では早期卒業の可能性もあります。

ルート4:大学入学資格が付与される専修学校高等課程を修了する
専修学校高等課程のうち、文部科学大臣が指定した学校を修了すると大学入学資格が得られます。
特定の専門分野を学びながら大学受験資格も取得できる選択肢です。
【専修学校高等課程のメリット】
・専門的な技術や知識を身につけられる
・将来の進路に関連した学びができる
・高校とは異なる環境で学べる
修了までには通常3年程度かかるため、時間的な余裕がある場合の選択肢となります。

ルート5:全日制の高校に転校
5つ目は、全日制高校に転校して、卒業することで大学資格を得る方法。
一度でも高校に入学したことのある人は、別の高校に転校や編入する手続きが取れます。
具体的には、既に高校を中退している場合は編入、高校中退を検討している方は転入と呼ばれます。
今の学校が嫌で中退を検討していても、転入により環境が変われば全日制高校を卒業でき、卒業資格が得られるでしょう。
しかし、全日制の高校から、全日制の高校に転校することは、あまりおすすめできません。
なぜなら、中途退学者向けの募集は、枠が限られており、入学へのハードルが非常に高いからです。
あくまで、「全日制の高校に通いたい」という、強い意思がある場合にのみ、この選択が良いでしょう。
【徹底解説】ルート1:高卒認定試験(高認)で大学を目指す

高卒認定試験は、高校中退者が大学受験資格を得るための最も一般的なルートです。
高卒認定試験の仕組みを理解し、効率的に合格を目指すための方法を知ることで、大学受験への道のりがよりクリアになります。
高卒認定試験を活用して、最短ルートで大学進学を実現する方法を詳しく解説します。
試験科目と難易度、合格に必要なこと
高卒認定の勉強法:独学と予備校、どちらを選ぶ?
高卒認定試験の出願から合格までの流れ
高卒認定合格後の大学受験:調査書の代わりは?
高卒認定試験とは?制度の概要とメリット
高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)は、以前は「大検」と呼ばれていた国の制度です。
高校を卒業していなくても、この試験に合格すれば大学入学資格が得られます。
【高卒認定試験の特徴】
・年2回(4月と7月)実施
・16歳以上であれば誰でも受験可能
・最短2か月で合格可能(必要な科目にすべて合格した場合)
高校を卒業するよりも短期間で大学受験資格を得られることが最大のメリットです。

試験科目と難易度、合格に必要なこと
高卒認定試験は複数の科目から構成されており、必要な科目に合格する必要があります。
【試験科目と合格要件】
・試験科目
国語、地理歴史(地理・歴史)、公民(公共)、数学、理科(科学と人間生活・物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎)、英語
※理科の科目の選択方法:理科の科目の選び方で、合格に必要な科目の数が変わります。「科学と人間生活」の1科目と、「基礎」を付した科目のうち1科目(合計2科目)「基礎」を付した科目のうち3科目(合計3科目)
・合格要件
高認に合格するには、上記の科目のうち、8〜9科目に合格する必要があります。
・科目合格
科目ごとに合格・不合格が決まります。一度合格した科目は、その後免除されます。
難易度は高校1〜2年生レベルで、各科目40点以上(100点満点)が合格の目安となります。

引用:文部科学省・高等学校卒業程度試験
高卒認定の勉強法:独学と予備校、どちらを選ぶ?
高卒認定試験の勉強法には大きく分けて独学と予備校の利用があります。
それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選びましょう。
独学で合格を目指す場合のポイントと注意点
独学のメリットは費用を抑えられ、自分のペースで学習できることです。
【独学成功のポイント】
・市販の高卒認定試験対策問題集を活用する
・過去問を繰り返し解く
・スケジュールを立てて計画的に学習する
わからないところを質問できる相手がいないため、自己解決能力が求められます。
予備校や塾を活用するメリット・デメリット
予備校を利用すれば、専門家の指導を受けながら効率的に学習できます。
【予備校利用のメリット】
・プロの講師による指導が受けられる
・仲間と一緒に学べるモチベーション維持に効果的
・質問できる環境がある
費用がかかることと、通学時間が必要になることがデメリットです。オンライン予備校も選択肢として検討すると良いでしょう。

参考記事:勉強計画を立ててくれる塾おすすめ14選!コーチング塾は効果あるの?大学受験生必見
高卒認定試験の出願から合格までの流れ
1.受験案内を入手
・文部科学省のウェブサイトからダウンロード、または郵送で請求できます。
・受験資格、試験日程、出願方法などの重要な情報が記載されています。
2.出願書類を準備
・受験願書、写真、本人確認書類など、必要な書類を揃えます。
・科目免除を申請する場合は、単位修得証明書も必要です。
3.出願
・出願書類を全て揃え、受験案内に挟み込まれている指定の封筒に入れ、出願期間内に郵便局の窓口から簡易書留で郵送します。
・出願期間を過ぎると受け付けられないので、注意が必要です。
4.受験票を受け取る
・試験日の約1か月前に、受験票が発送されます。
・試験会場、時間割などが記載されているので、必ず確認しましょう。
5.試験を受ける
・試験会場で、受験票に記載された時間割に従って受験します。
・遅刻すると受験できない場合があるので、時間に余裕を持って会場へ向かいましょう。
6.合格発表
・試験後、約1か月後に合格発表があります。
・文部科学省から、合否結果通知書が郵送されます。
・合格者には合格証書、一部科目合格者には科目合格通知書が送付されます。
7.合格後の手続き
・全科目合格者は、特に手続きの必要はありません。
・大学・短大・専門学校への進学、就職などで証明書が必要な場合は、文部科学省に申請します。
【注意点】
・出願書類に不備があると、受験できない場合があります。
・受験票は試験当日まで大切に保管してください。
・試験結果について不明な点があれば、文部科学省に問い合わせましょう。
【高認合格後の進路】
高認に合格すると、大学・短大・専門学校への進学、就職など、様々な進路を選択できます。
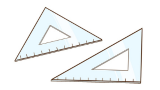
高卒認定合格後の大学受験:調査書の代わりは?
高卒認定試験合格者は、通常の高校卒業生とは異なる書類を提出します。
【提出する主な書類】
・高卒認定試験合格成績証明書(調査書の代わり)
・各大学が指定する出願書類
大学側は高卒認定試験の成績を調査書の代わりとして評価します。
一部の大学では高卒認定試験合格者向けの特別な入試制度を設けているところもあるので、志望校の入試要項を確認することが重要です。
【選択肢を広げる】ルート2, 3, 4:高校卒業資格や他の資格で大学を目指す

高卒認定試験以外にも、通信制高校や定時制高校に再入学する方法、あるいは専修学校高等課程を修了する方法があります。
それぞれのルートの特徴や選ぶ際のポイントを理解し、自分に最適な選択をするための情報を提供します。
特に学習のサポート体制や専門性の有無などの観点から比較検討することが大切です。
専修学校高等課程(大学入学資格付与校)から大学受験を目指す場合
通信制高校・定時制高校から大学受験を目指す場合
通信制・定時制高校は、高校中退後に再び高校卒業資格を目指す代表的な選択肢です。
それぞれの特徴を理解して選択することが重要です。
メリット・デメリットと選び方のポイント
【通信制高校のメリット・デメリット】
・メリット:時間や場所に縛られず学習できる、自分のペースで進められる
・デメリット:自己管理能力が必要、卒業までに最低1年以上かかる
【定時制高校のメリット・デメリット】
・メリット:教師の対面指導を受けられる、学校生活を送れる
・デメリット:決まった時間に通学する必要がある、卒業まで3〜4年かかることが多い
選ぶ際のポイントは、自分の生活スタイル(働きながら学びたいかなど)や学習スタイル(自分で進められるか、指導が必要か)を考慮することです。
学習スタイルとサポート体制
通信制高校と定時制高校では、学習スタイルやサポート体制に大きな違いがあります。
【通信制高校の学習スタイル】
・レポート提出とスクーリング(面接指導)が基本
・最近はオンライン学習システムを導入している学校も増加
・サポート体制は学校によって差がある(手厚いサポートを提供する私立もある)
【定時制高校の学習スタイル】
・通常は夜間に授業があるが、昼間部もある
・高校と同じ教科書や教材を使用
・教師に直接質問できる環境がある
自分に合った学習スタイルとサポート体制を選ぶことが成功の鍵です。

専修学校高等課程(大学入学資格付与校)から大学受験を目指す場合
専修学校高等課程のうち、文部科学大臣が指定した学校は大学入学資格を付与されています。
この選択肢は特定の専門分野に興味がある場合に適しています。
「特徴と注意点」
【専修学校高等課程の特徴】
・専門的な技術や知識を学べる(美容、調理、工業など)
・高校と同じ3年間の課程が一般的
・専門分野の資格取得を目指せる
【注意点】
・すべての専修学校が大学入学資格を付与されているわけではない
・入学前に「大学入学資格付与指定校」であることを確認する必要がある
・一般的な高校よりも専門教科の授業が多く、大学受験科目の学習時間は限られる
専門性を身につけながら大学進学を目指したい場合に検討する価値があります。

参考記事:大学受験勉強をやめたいと思った時にちょっとだけ読んでほしい記事
参考記事:キミノスクールに興味のある方必見!【口コミ・評判・料金】を徹底調査!おすすめできるオンライン塾?
どのルートを選んでも共通!大学合格に向けた準備と対策

高校中退から大学を目指す場合、どのルートを選んでも共通して必要な受験対策があります。
志望校選びから受験勉強の計画、資金面の準備まで、大学合格に向けた実践的なアドバイスを提供します。
早めに準備を始め、計画的に進めることが合格への近道です。
受験勉強の計画の立て方と効率的な進め方
高校中退者が活用できる費用面のサポート:奨学金・教育ローン情報
アルバイトと勉強の両立は可能?
志望校・学部選びで後悔しないためのポイント
志望校選びは合格後の学生生活に大きく影響するため、慎重に行うことが重要です。
【志望校選びのポイント】
・自分の興味・関心と学部・学科の内容が合致しているか
・学力レベルと合っているか(難易度だけでなく、学びたい内容で選ぶ)
・高校中退者向けの入試制度があるか(AO入試や総合型選抜など)
・通学可能な距離か、一人暮らしが必要か(費用面も考慮)
オープンキャンパスへの参加や大学のウェブサイト閲覧など、積極的に情報収集することをおすすめします。

受験勉強の計画の立て方と効率的な進め方
どのルートを選んでも、受験勉強は計画的に進めることが重要です。
【効果的な学習計画のポイント】
・現在の学力を把握する(模試や過去問で自己診断)
・志望校の入試科目と配点を確認
・逆算して学習計画を立てる(重点科目に時間を配分)
・定期的に進捗を確認し、計画を見直す
特に基礎が不安な場合は、高校1年生レベルからしっかり学び直すことをおすすめします。焦らず、着実に進めていくことが大切です。

高校中退者が活用できる費用面のサポート:奨学金・教育ローン情報
大学進学には学費など多額の費用がかかります。
高校中退者も活用できる経済的サポートを知っておきましょう。
【利用できる主な制度】
・日本学生支援機構の奨学金(給付型・貸与型)
・大学独自の奨学金制度
・高等教育の修学支援新制度(条件を満たせば利用可能)
高校中退者でも、高卒認定試験合格者や高校卒業資格を得た場合は、一般の高校卒業生と同様に奨学金制度を利用できます。
早めに情報収集を始めることが重要です。

アルバイトと勉強の両立は可能?
多くの高校中退者は経済的な理由からアルバイトをしながら受験勉強を進める必要があります。
【両立のコツ】
・週の勤務時間を20時間程度に抑える
・学習効率の良い時間帯は勉強に充てる
・シフトが固定できる仕事を選ぶ
・勉強と仕事の切り替えを明確にする
無理なく継続できる計画を立てることが成功の鍵です。
体調管理にも気を配りましょう。
高校中退からの大学受験、よくある疑問と不安を解消!Q&A

高校中退から大学受験を目指す方々がよく抱える疑問や不安について、Q&A形式で答えます。
実際の経験者の声も参考にしながら、具体的なアドバイスを提供します。
あなたが一人ではないこと、同じ道を歩んで成功した先輩たちがたくさんいることを知ってもらいたいと思います。
Q. ブランクがあるけど大学の授業についていける?
Q. 周囲の目が気になる…モチベーションを保つには?
Q. 大学以外の進路(専門学校・就職)と比較してどう?
Q. 面接で高校中退の理由を聞かれたらどう答える?
面接で高校中退について質問されることは珍しくありません。
誠実に対応することが大切です。
【回答のポイント】
・事実を簡潔に伝える(詳細を話す必要はない)
・中退後にどう成長したかを伝える
・これからの学びへの意欲を示す
例えば「体調を崩して高校を中退しましたが、その後は健康管理に気をつけながら高卒認定試験の勉強に取り組み、合格することができました。
この経験から学んだことを大学でも生かしていきたいと考えています」といった答え方が効果的です。

Q. ブランクがあるけど大学の授業についていける?
学習ブランクがあることへの不安は多くの方が抱えています。
【対応策】
・入学前から基礎学力の復習をする
・大学の補習クラスや初年次教育を活用する
・わからないことをすぐに質問できる習慣をつける
・同じような境遇の友人や先輩とつながる
多くの大学では、高校からの接続をスムーズにするためのサポート体制が整っています。
積極的に活用しましょう。

Q. 周囲の目が気になる…モチベーションを保つには?
高校中退という経歴に対する周囲の目が気になる方も多いでしょう。
【モチベーション維持のコツ】
・同じ境遇の仲間や先輩とつながる
・小さな目標を設定して達成感を味わう
・成功した高校中退者の体験談を読む
・自分の選択に自信を持つ
高校中退から大学に進学し、成功している人は数多くいます。
自分の道を信じて進むことが大切です。

Q. 大学以外の進路(専門学校・就職)と比較してどう?
大学進学以外にも、専門学校への進学や就職という選択肢もあります。
【各進路の比較】
| メリット | デメリット |
|---|---|
・幅広い教養が身につく ・就職先の選択肢が広がる ・学士号が取得できる | ・費用と時間がかかる ・専門性の深さは学部による |
・実践的な技術が身につく ・比較的短期間で資格取得可能 ・就職サポートが充実 | ・学士号は取得できない ・転職時に不利な場合も |
・すぐに収入が得られる ・社会経験を積める ・働きながら学ぶ選択も | ・学歴が求められる職種には応募困難 ・キャリアアップに制限も |
自分の目標や価値観に合った選択をすることが大切です。
どの道を選んでも、努力次第で道は開けます。
まとめ:高校中退から大学受験!逆転合格する5つのルートとは?高卒認定だけじゃない

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「高校中退から大学受験!逆転合格する5つのルートとは?高卒認定だけじゃない」は参考になりましたでしょうか?
まとめ:高校中退から大学受験!逆転合格する5つのルートとは?高卒認定だけじゃない
高校を中退したいと思ったら、まずは冷静に自分の状況を見つめ直しましょう。
高校中退するデメリットとメリットをよく考えて、本当に中退するべきかどうかを判断してください。
高校中退のデメリットは、以下のようなものがあります。
・大学進学が難しくなる
・就職が難しくなる
・収入が低くなる
・社会的な信用が低くなる
・将来の選択肢が狭くなる
高校中退のメリットは、以下のようなものがあります。
・自由な時間が増える
・自分の好きなことをすぐに始められる
・失敗を恐れずに挑戦できる
高校中退を決断する際には、上記のデメリットとメリットをよく比較検討し、自分の将来にとって最善の選択をしてください。
高校中退を決断した場合は、その後の人生設計を慎重に行う必要があります。高校卒業資格がなければ、就職や進学が難しくなるため、高校卒業資格を取得するための方法を検討する必要があります。また、高校中退者向けの就職支援制度や教育支援制度などを活用できます。
高校中退は、決してマイナスなことではありません。自分の将来にとって最善の選択をするために、高校中退を決断するかどうかを慎重に検討してください。