私立大学併願パターンの王道!受験で失敗しない戦略と併願校の選び方
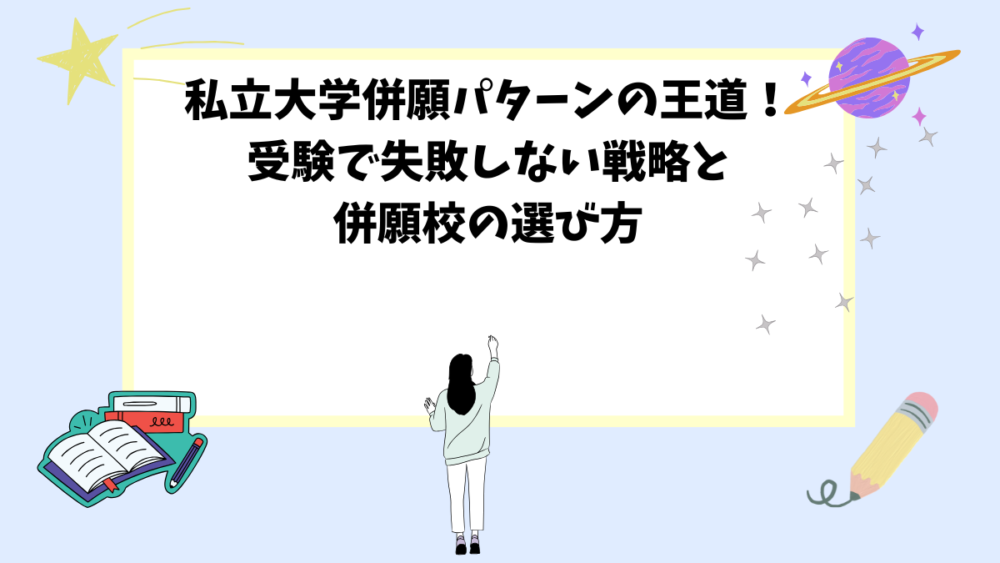
「※この記事には一部PRが含まれます」
監修:進路アドバイザー資格保有者
本記事は、高校生の進路指導において豊富な経験と専門知識を有する、進路アドバイザー資格保有者の監修のもと作成されています。
皆さんが自信を持って納得のいく進路を見つけられるよう、具体的かつ分かりやすい情報をお届けします。
「第一志望は決まったけど、他の大学をどうやって受ければいいんだろう…?」「併願ってよく聞くけど、具体的に何校くらい、どんな大学を選べばいいのか分からない…」
大学受験を控えたあなたや、お子様をサポートする保護者の方は、今まさにこのような悩みを抱えているのではないでしょうか。
大学受験は、第一志望校に合格することだけがゴールではありません。
万が一の事態に備え、納得のいく進学先を確保するための「併願戦略」こそが、現役合格を掴み取るための鍵となります。
この記事では、27年以上学習塾業界で多くの受験生を指導してきた進路アドバイザーが、大学受験における併願の基本から、文系・理系別の具体的な併願パターン、失敗しない併願校の選び方、さらには受験スケジュールの組み方まで、専門家が徹底的に解説します。
この記事を読めば、あなたにぴったりの併願パターンが見つかり、自信を持って受験本番に臨めるようになります。
併願の基本は「チャレンジ校・実力相応校・安全校」のバランス
「共通テスト利用」と「一般選抜」の組み合わせが王道戦略
後悔しない併願校選びは、偏差値だけでなく「行きたいか」が重要
費用と体力を考慮した受験校数・日程管理が成功の鍵
【おすすめオンライン塾】
現役東大・旧帝大・早慶生が徹底指導
学習法から受験戦略まで“合格の勝ち方”を伝授
無料体験で「逆授業」を体感する価値あり!
学習状況の相談・体験授業・最適コースの
ご案内がすべて無料
\今すぐ資料請求&体験授業/
↓↓↓
[スタディコーチの公式サイトはこちら]
Contents
私立大学併願パターンの基本戦略

まずは、すべての受験生が知っておくべき併願の基本的な考え方から解説します。
この土台を理解することが、最適な併願プランを立てるための第一歩です。
チャレンジ校・実力相応校・安全校の定義
併願のメリットとデメリット
大学受験における併願とは?
「併願(へいがん)」とは、複数の大学・学部を受験することを指します。
大学受験において、たった1校しか受験しない「専願」の受験生はごく少数派です。
なぜなら、大学入試には当日の体調や問題との相性など、予測不可能な要素がつきものだからです。
併願は、第一志望校に不合格だった場合のリスクを分散し、進学先を確保するための重要な保険の役割を果たします。

チャレンジ校・実力相応校・安全校の定義
効果的な併願戦略の基本は、受験する大学を学力レベルに応じて3つのグループに分類することです。
長年の進路指導の中で、このバランスを間違えて失敗するケースを数多く見てきました。
| 区分 | 合格可能性の目安 | 模試判定の目安 | 特徴・位置づけ |
|---|---|---|---|
| チャレンジ校(挑戦校) | 50%未満 | D〜E判定 | 第一志望や憧れの大学。合格できたら嬉しいという気持ちで挑戦する大学。 |
| 実力相応校(実力校) | 50%〜80%程度 | B〜C判定 | 現在の学力で順当に合格できる可能性が高い大学。第二志望以下が該当。 |
| 安全校(滑り止め) | 80%以上 | A判定、または過去問で安定合格 | 万が一不合格が続いても進学を前提にできる大学。合格の可能性が非常に高い「最後の砦」。 |
この3つのレベルの大学をバランス良く組み合わせることが、併願戦略の最大のポイントです。

併願のメリットとデメリット
併願には多くのメリットがありますが、同時に注意すべきデメリットも存在します。
両方を理解した上で、自分に合った計画を立てましょう。
【併願のメリット】
1.合格のチャンスが増える:受験する大学の数だけ、合格の可能性が広がります。
2.精神的な安定につながる:「安全校」に合格しておくことで、心に余裕が生まれ、本命のチャレンジ校の試験にリラックスして臨めます。
3.受験本番の雰囲気に慣れる:早い日程で安全校や実力相応校の試験を経験しておくことで、試験会場の独特の緊張感に慣れることができます。
【併願のデメリット】
1.受験費用がかさむ:1校受験するごとに、受験料や交通費、宿泊費などが発生します。
2.体力・精神的な負担が大きい:試験が続くと、移動や連日の緊張で心身ともに疲弊します。
3.対策時間が増える:大学ごとに試験の傾向は異なるため、併願校が増えるほど過去問対策などに時間がかかります。
難関大学にあなたも逆転合格できる
圧倒的な合格率が本物の証
難関私大に合格する完璧なノウハウ
志望大学の先生があなたをサポート
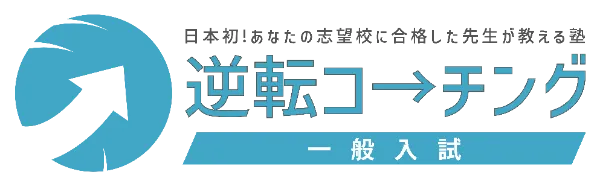
「友だち追加」で無料コーチング
勉強計画を無料で作成
↓↓↓
【文理別】私立大学の併願パターン例

ここでは、志望校のレベルや文理別に、具体的な併願パターンの例をご紹介します。
あくまで一例として、ご自身の状況に合わせてアレンジしてみてください。
※偏差値は【パスナビ/スタディサプリ/河合塾】等の目安をもとにしています。※合格可能性は一般的な模試判定(A~E)に基づいた想定です。※受験方式は、大学・学部により細かく分かれるため、出願前に最新の募集要項を必ず確認してください。
文系・中堅私立大学の併願例
理系・難関私立大学の併願例
理系・中堅私立大学の併願例
国公立大学との併願パターン
共通テスト利用と一般選抜の組み合わせ
文系・難関私立大学の併願例
第一志望が早稲田大学や慶應義塾大学、上智大学などの最難関私立大学の場合のパターンです。
| 区分 | 大学名(学部) | 偏差値(目安) | 合格可能性(模試判定) | 主な受験方式 |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジ校 | 早稲田大学(政治経済学部) | 70〜72 | D〜E判定(〜50%未満) | 一般方式(英語外部利用あり) |
| 慶應義塾大学(法学部) | 70〜72 | D〜E判定(〜50%未満) | 一般方式(独自試験) | |
| 実力相応校 | 明治大学(政治経済学部) | 62〜65 | B〜C判定(50%〜80%) | 全学部/学部個別方式 |
| 立教大学(法学部) | 60〜63 | B〜C判定(50%〜80%) | 全学部/個別日程 | |
| 青山学院大学(国際政治経済学部) | 60〜64 | B〜C判定(50%〜80%) | 全学部/個別日程 | |
| 安全校(滑り止め) | 法政大学(法学部)※共通テスト利用 | 57〜60 | A判定(80%以上) | 共通テスト利用方式 |
| 成蹊大学(法学部) | 55〜58 | A判定(80%以上) | 共通テスト利用/一般方式 |

文系・中堅私立大学の併願例
第一志望がGMARCHや日東駒専レベルの場合のパターンです。
| 区分 | 大学名(学部) | 偏差値(目安) | 合格可能性(模試判定) | 主な受験方式 |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジ校 | 明治大学(商学部) | 63〜65 | D〜C判定(〜50%前後) | 全学部/学部別方式 |
| 立教大学(経営学部) | 65〜67 | D判定(〜50%未満) | 全学部日程/個別日程 | |
| 実力相応校 | 法政大学(経営学部) | 60〜62 | B〜C判定(50〜80%) | 全学部/個別日程/共通テスト利用 |
| 日本大学(商学部) | 55〜58 | B判定(60〜70%程度) | N全学統一/学部別日程 | |
| 東洋大学(経営学部) | 55〜58 | B判定(60〜70%程度) | 全学部/共通テスト利用 | |
| 安全校(滑り止め) | 駒澤大学(経営学部)※共通テスト利用 | 52〜55 | A判定(80%以上) | 共通テスト利用 |
| 専修大学(商学部) | 50〜53 | A判定(80%以上) | 共通テスト利用/一般方式 |

理系・難関私立大学の併願例
第一志望が早慶上理や難関理系大学の場合のパターンです。
| 区分 | 大学名(学部) | 偏差値(目安) | 合格可能性(模試判定) | 主な受験方式 |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジ校 | 早稲田大学(先進理工学部) | 67〜70 | D〜E判定(〜50%未満) | 一般方式(学部独自試験) |
| 慶應義塾大学(理工学部) | 67〜70 | D〜E判定(〜50%未満) | 一般方式(数学・英語・物理/化学) | |
| 実力相応校 | 東京理科大学(理工学部) | 60〜65 | B〜C判定(50%〜80%) | 一般方式/共通テスト併用方式 |
| 明治大学(理工学部) | 60〜63 | B〜C判定(50%〜80%) | 全学部日程/個別学部日程/共通テスト利用 | |
| 安全校(滑り止め) | 芝浦工業大学(工学部) | 55〜60 | A判定(80%以上) | 一般方式/共通テスト利用 |
| 法政大学(デザイン工学部)※共通テスト利用 | 55〜58 | A判定(80%以上) | 共通テスト利用方式 |

理系・中堅私立大学の併願例
第一志望が四工大や日東駒専の理系学部の場合のパターンです。
| 区分 | 大学名(学部) | 偏差値(目安) | 合格可能性(模試判定) | 主な受験方式 |
|---|---|---|---|---|
| チャレンジ校 | 芝浦工業大学(システム理工学部) | 58〜60 | D〜C判定(〜50%前後) | 一般方式(独自試験)/共通テスト利用 |
| 東京都市大学(理工学部) | 57〜60 | C判定(50〜60%) | 一般方式/共通テスト利用 | |
| 実力相応校 | 日本大学(理工学部) | 55〜58 | B〜C判定(50〜70%) | N方式(全学統一)/学部個別方式 |
| 工学院大学(先進工学部) | 53〜56 | B判定(60〜70%) | 一般方式/共通テスト利用 | |
| 安全校(滑り止め) | 東洋大学(理工学部) | 50〜54 | A判定(80%以上) | 共通テスト利用/一般方式 |
| 千葉工業大学(工学部)※共通テスト利用 | 48〜52 | A判定(80%以上) | 共通テスト利用方式 |
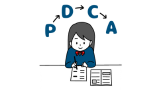
国公立大学との併願パターン
国公立大学が第一志望の場合、私立大学の併願は必須です。
国公立の試験日(前期2月25日〜)より前に合否が判明する私立大学を組み合わせるのが基本戦略です。
これまで多くの国公立志望者を指導してきましたが、私立の併願戦略が成否を分けると言っても過言ではありません。
| 区分 | 大学・方式の例 | 偏差値(目安) | 合格可能性(模試判定) | 主な受験方式 |
|---|---|---|---|---|
| 第一志望(チャレンジ) | 国公立大学(前期日程) | 60〜70(大学により異なる) | C〜D判定(〜60%未満) | 共通テスト+2次試験(記述・論述) |
| 実力相応校 | 共通テスト利用:明治・立教・同志社・関学など(GMARCH・関関同立) | 58〜65 | B〜C判定(50〜75%) | 共通テスト利用方式 |
| 一般選抜:青山学院・中央・立命館・関西大学など | 58〜63 | B〜C判定(50〜75%) | 一般方式(学部個別・全学部) | |
| 安全校(滑り止め) | 共通テスト利用:日東駒専(日本・東洋・駒澤・専修)、産近甲龍 | 50〜55 | A判定(80%以上) | 共通テスト利用方式 |
国公立志望者は、共通テストの結果で受験できる私立大学を確保しておくことが、精神的な安定につながります。

共通テスト利用と一般選抜の組み合わせ
「共通テスト利用入試」と「一般選抜」を組み合わせることは、現代の大学受験における王道パターンです。
【共通テスト利用入試】
共通テストの成績のみで合否が決まる方式。多くの大学で一般選抜より早く出願・合格発表が行われます。安全校や実力相応校の一部を共通テスト利用で確保し、早い段階で合格を勝ち取るのが理想です。
【一般選抜】
大学独自の試験を受ける方式。第一志望のチャレンジ校や、共通テスト利用ではボーダーラインに届かなかった実力相応校に挑戦するために活用します。
この2つをうまく使い分けることで、効率的かつ戦略的に受験を進めることができます。
失敗しない併願校・滑り止めの決め方

併願校を選ぶ際は、闇雲に決めるのではなく、いくつかの重要なポイントを押さえることが肝心です。
私の長年の経験から、多くの受験生が陥りがちな落とし穴を避け、最適な併願校を見つけるためのアドバイスをお伝えします。
第二志望以下の大学の決め方
滑り止め大学の選定基準
入学金納付締切日の確認
自己分析と学力レベルの把握
まずは自分の現在地を正確に知ることが重要です。
進路アドバイザーの指導経験から、この自己分析を怠った生徒ほど、受験直前になって焦る傾向にあります。
【模試の結果を客観的に分析する】
偏差値だけでなく、合格判定(A〜E判定)を重視しましょう。B判定以上であれば実力相応、A判定なら安全校と考えて良いでしょう。
【過去問との相性を確認する】
偏差値が同じくらいの大学でも、出題傾向は全く異なります。実際に過去問を解いてみて、問題との相性や合格最低点との距離を確認することが非常に重要です。

第二志望以下の大学の決め方
安全校や実力相応校は、ただ合格しやすいという理由だけで選んではいけません。
「もし第一志望がダメでも、この大学なら4年間通ってもいい」と心から思えるかが重要な基準です。
以下の視点で大学を調べてみましょう。
・学びたい学部・学科、カリキュラムがあるか
・キャンパスの立地や雰囲気は自分に合っているか
・就職実績やサポート体制はどうか
・留学制度やサークル活動は充実しているか

滑り止め大学の選定基準
「滑り止め」という言葉の響きから、安易に選んでしまいがちですが、ここをしっかり固めることが受験成功の鍵です。
【過去問で合格最低点を安定して超えられる】
直近3年分ほどの過去問を解き、どの年度でも合格最低点を余裕でクリアできるレベルが理想です。
【共通テスト利用でA判定が出ている】
共通テスト利用入試でA判定(合格可能性80%以上)が出ている大学は、有力な安全校候補です。
【得意科目で受験できる】
自分の得意な科目だけで受験できる方式や、配点が高い方式を選ぶと、より合格の可能性が高まります。

入学金納付締切日の確認
これは併願戦略において最も注意すべきポイントの一つです。
多くの私立大学では、入学金や前期授業料の納付締切日が、第一志望の国公立大学や他の私立大学の合格発表日よりも前に設定されています。
これを「入学金地獄」と呼び、進学しない可能性のある大学に数十万円の入学金を支払わなければならないケースが発生します。
各大学の入試要項を必ず確認し、合格発表日と手続き締切日を一覧表にまとめておくことを強くおすすめします。
最近では、入学金の納付を合格発表後まで待ってくれる「入学金延納制度」を設けている大学もあるため、そうした大学を併願校に選ぶのも賢い方法です。
大学受験で受ける併願校数の目安と費用

併願校の数について、多くの受験生や保護者の方が「何校くらいがベストなのだろう?」と悩まれます。
多すぎても負担が大きいし、少なすぎても不安が残ります。
ここでは、長年の経験を持つ進路アドバイザーとして、最適な併願校数の見つけ方と、その判断基準を解説します。
併願数を決める際の経済的側面:受験料と入学金のリアルな負担
受験対策と試験スケジュールから考える無理のない併願校数
受験料を抑える出願方法
現役受験生の併願数の平均と、あなたに合った目安
私がこれまでの指導で見てきた中で、一般的に多くの受験生が併願する私立大学の数は、3~6校程度が平均的です。
これには、第一志望校の他に「実力相応校」や「滑り止め校」が含まれます。
しかし、この平均はあくまで目安です。
あなたにとっての最適な併願数は、個々の状況によって大きく異なります。
・学力レベル: 安定して高得点が取れる生徒は少なめでも良いかもしれません。
・志望校の難易度: 非常に難易度の高い大学を狙う場合は、チャレンジ校と安全校のバランスを考慮し、数を増やすこともあります。
・経済的な余裕: 受験料や入学金、交通費などの負担を考慮する必要があります。
・対策時間: 多くの大学を併願すれば、それだけ対策時間が分散します。
・体力・精神力: 試験が続くことによる疲労度も考慮に入れる必要があります。
最も大切なのは、あなた自身の状況を客観的に見つめ、無理なく 「対策ができる」「受験できる」 範囲で決めることです。
私がアドバイスする際には、まず「絶対にここだけは行きたい」という大学を洗い出し、それから「もしもの時のためにここがあれば安心」という大学を数校検討するように伝えています。

併願数を決める際の経済的側面:受験料と入学金のリアルな負担
併願数を決める上で、経済的な側面は避けて通れない重要な問題です。
受験料だけでなく、合格した場合の入学金も大きな負担となります。
◆ 大学別|受験料の目安(1校あたり)
| 項目 | 費用の目安 | 補足 |
|---|---|---|
| 私立大学(一般入試) | 約30,000円~35,000円 | 学部によってはさらに高額なケースもあり |
| 国公立大学(二次試験) | 約17,000円 | 共通テスト受験が前提 |
| 大学入学共通テスト | 約18,800円(3教科以上)令和7年度入試の場合 | 科目数によって若干変動あり |
◆ 要注意:「二重払い」のリスクとは?
多くの私立大学では、合格発表から入学手続き締切までの期間が短く、国公立の合格発表前に「仮押さえ」として入学金を支払わなければならないことがあります。
この場合、第一志望(国公立)に合格しても、既に支払った私立の入学金は返ってこないため、「二重払い」となってしまうリスクがあります。
◆ 後悔しないために今すぐやるべきこと
| アクション | 内容 |
|---|---|
| 家族で経済的な上限額を話し合う | 「どこまで負担できるか」を明確に |
| 併願校の入学手続き日程をチェック | 国公立の発表より前に支払いが必要かを確認 |
| 奨学金制度や延納制度も調べておく | 家計に優しい制度があるかを事前確認 |
併願数が多いほど安心感は得られますが、その分費用も確実に増加します。
入学金の「仮押さえ」や「二重払い」のリスクを見越して、戦略的かつ現実的な併願プランを立てることが、経済的にも精神的にも安定した受験生活につながります。

参考記事:文系高2、受験勉強「何から?」合格への年間計画と先輩の実践ロードマップ
受験対策と試験スケジュールから考える無理のない併願校数
併願校の数を決める際、「本当にすべての対策ができるのか」という視点を持つことが非常に重要です。
いくら多くの大学を併願しても、それぞれの対策が中途半端になってしまっては、合格の可能性は高まりません。
たとえば、志望校と併願校の入試科目が大きく異なる場合、それだけ多くの科目を勉強しなければならず、時間的な負担は計り知れません。
試験日程が過密すぎると、体力的・精神的な疲労が蓄積し、本来の力を発揮できない可能性があります。
・第一志望校の対策に集中できるか
・併願校それぞれの過去問対策を十分に行えるか
・試験が連日にならないか、移動時間は確保できるか
これらの点を考慮し、「自分が現実的に対応できる範囲」で併願校数を決めることが、合格への近道となります。
私の指導では、「これ以上増やしたら、一つ一つの対策が薄くなるよ」というラインを一緒に考え、無理のない範囲で最大限の効果を狙う併願を提案しています。

参考記事:【大学の志望校の決め方】偏差値・将来性・やりたいこと・後悔しない選び方
受験料を抑える出願方法
少しでも費用を抑えたい場合、以下のような方法を検討しましょう。
【共通テスト利用入試を積極的に活用する】
一般選抜よりも受験料が安く、交通費・宿泊費もかかりません。
【全学部日程を利用する】
一度の試験で複数の学部・学科に出願できるため、個別に受けるより割安になる場合があります。
【併願割引制度を利用する】
同じ大学の複数の学部を併願する場合に、2出願目以降の受験料が割引になる制度です。
併願を成功させる受験日程の組み方

学力や併願校選びが完璧でも、日程の組み方を間違えると実力を発揮できません。
最後に、併願を成功に導くスケジューリング術を解説します。
連続受験は避けるべきか?体力面の考慮
合格発表と手続き締切の管理方法
入試方式の選び方(全学部・個別日程)
受験スケジュールの基本原則
・試験日程を時系列で書き出す
出願期間、試験日、合格発表日、手続き締切日をカレンダーや手帳にすべて書き込み、全体像を可視化しましょう。
・移動時間を考慮に入れる
試験会場までの移動時間や交通手段を事前に確認し、無理のない計画を立てます。特に首都圏では、朝のラッシュも考慮に入れる必要があります。
・試験日の間隔を空ける
可能な限り、試験と試験の間には休息日を設けましょう。

連続受験は避けるべきか?体力面の考慮
結論から言うと、連続での受験は可能な限り避けるべきです。
特に体力に自信がない人は、連続受験は最大でも3日までに留めるのが賢明です。
長年、塾で受験生を見てきましたが、体力や集中力のピークを保つためには、適度な休息が不可欠です。
試験は想像以上に集中力と体力を消耗します。連戦が続くと、後半の試験で本来の力を発揮できなくなるリスクが高まります。
理想は「受験→休み→受験」というサイクルです。

合格発表と手続き締切の管理方法
前述の通り、手続き締切日の管理は非常に重要です。
・一覧表を作成する
大学名、学部名、合格発表日、発表方法(Web/郵送)、手続き締切日、納付金額を一覧にまとめ、いつでも確認できるようにしておきましょう。
・リマインダーを設定する
スマートフォンのカレンダーアプリなどを活用し、締切日の数日前に通知が来るように設定しておくと安心です。

入試方式の選び方(全学部・個別日程)
多くの私立大学では、複数の入試方式が用意されています。
【全学部日程(T方式、全学統一など)】
・メリット
同じ試験問題で複数の学部に出願でき、全国各地に試験会場が設けられることが多いです。
・デメリット
募集人数が少なく、倍率が高くなる傾向があります。
【個別日程(A方式、学部個別など)】
・メリット
募集人数が最も多く、合格のチャンスが広いです。学部独自の特色ある問題が出題されます。
・デメリット
大学のキャンパスまで行かなければ受験できません。
第一志望の学部は、募集人数の多い個別日程で受験するのが基本です。
全学部日程は、実力試しや併願校の選択肢として活用すると良いでしょう。
私立大学の併願パターンに関するよくある質問
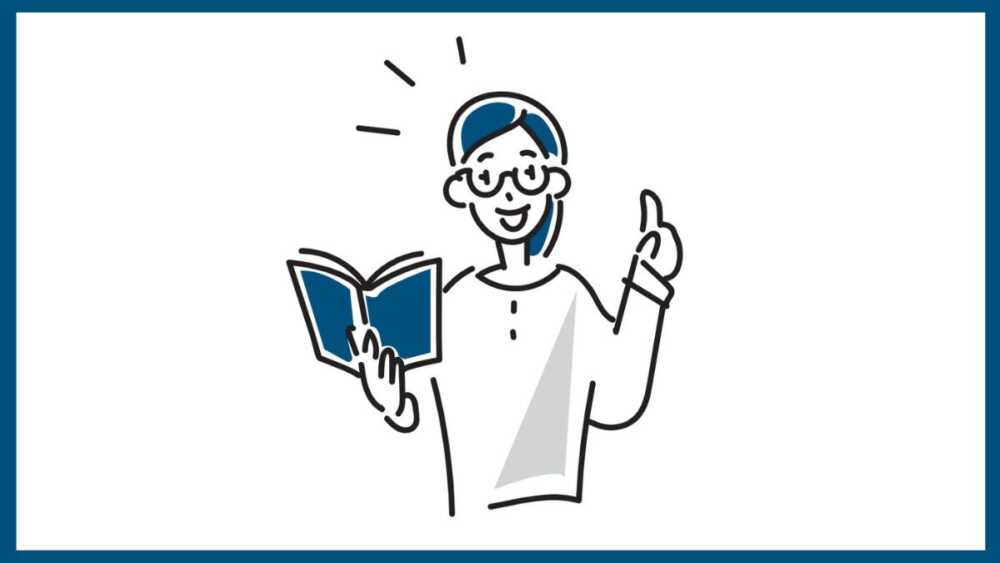
\図書カード!もれなくプレゼント!/
↓↓↓ 《高校生注目》スタディサプリ進路で学校パンフをまとめて請求
大学受験の併願に関して、生徒さんや保護者の方からよく聞かれる質問があります。
ここでは、学習塾経験に基づいて、それらの疑問に一つひとつお答えしていきます。
専願で2校受けられますか?
併願校はいつまでに決めるのがベスト?
受験する大学の順番は合否に影響する?
不合格が続いた時、どう気持ちを切り替えるべきか?
保護者からよく聞かれる併願の疑問点とその回答
併願校の過去問対策はいつから始める?
同じ大学の複数学部を受験するメリットは?
絶対受かる大学」は必要か?
浪人を避けるための併願戦略とは?
専願と併願どちらが受かりやすいですか?
一般的に、専願の方が合格しやすい傾向があります。
専願入試は「この大学に入学することを前提に受験する」制度であり、大学側もその熱意を評価しやすく、合格率がやや高くなるケースが多いです。
併願は複数の大学に出願できる自由さがありますが、専願に比べて倍率や競争が激しくなりがちです。
専願であっても基準に達していなければ合格は難しいため、自分に合った出願戦略を立てることが大切です。

専願で2校受けられますか?
基本的に専願は「その大学に合格したら必ず入学する」ことが条件となっているため、2校以上の専願出願はできません。
万が一、2つの専願校に合格してしまうと、どちらかの入学を辞退することになり、専願のルール違反になる恐れがあります。
そのため、専願で出願する場合は、他の大学は原則として受けられません。
専願にする場合は「本当にその大学に行きたいか」をよく考えて決めましょう。
不安がある場合は併願型入試を選ぶのが安全です。

併願校はいつまでに決めるのがベスト?
併願校を決める時期は、一般的には高校3年生の夏休みから秋にかけて、遅くとも年内にはおおまかに決めておくことをおすすめします。
◆ 併願校を決めるおすすめスケジュールとやるべきこと
| 時期 | やるべきこと | ポイント・アドバイス |
|---|---|---|
| 高校3年 夏休み | オープンキャンパスに参加、大学情報を集める | ・「興味のある大学」の幅を広げる・実際に大学の雰囲気を知ることが大切 |
| 秋〜冬(9月〜12月) | 模試の結果をもとに併願候補を絞る入試情報・日程を確認 | ・自分の学力に合った大学を見極める・募集要項で入試科目・配点・方式をチェック |
| 年明け〜出願直前 | 最終的な併願校を決定出願書類の準備開始 | ・出願方法(インターネット or 郵送)や提出書類を確認・調査書や写真の準備も早めに進める |
私の経験上、直前になって併願校を決めるのは避けるべきです。
情報収集が不十分になったり、対策が間に合わなかったりする可能性があります。
早めに候補をいくつか決めておき、じっくりと検討する時間を持つことが、後悔のない併願戦略には不可欠です。

受験する大学の順番は合否に影響する?
受験する大学の順番が、直接的に合否に影響することはありません。
しかし、精神面や体調面には大きな影響を与える可能性があります。
たとえば、自信のある安全校を先に受験し、合格を勝ち取っておくことは、その後の第一志望校の試験に臨む際の精神的な安定につながります。
私も多くの生徒に、第一志望の前に「合格の可能性が高い大学」を一つ受験することを勧めてきました。
逆に、チャレンジ校ばかりを先に受験して不合格が続くと、精神的なダメージを受け、その後の試験にも悪影響が出てしまうことがあります。
試験が連日続くような過密スケジュールも、体力的な負担が大きく、集中力を維持するのが難しくなります。
そのため、合否に直接影響はしなくても、「心理的な影響」や「体調面の影響」を考慮して、無理のないスケジュールを組むことが非常に大切です。

不合格が続いた時、どう気持ちを切り替えるべきか?
併願校の試験で不合格通知が届くと、誰でも落ち込んでしまうものです。
特に、合格を期待していた大学からの不合格は、大きな精神的なダメージとなるでしょう。
ここで「落ち込みすぎないこと」、そして「早めに気持ちを切り替えること」が、次の試験に臨む上で非常に重要です。
・一時的に落ち込むのは当然: まずは、落ち込んでいる自分を認め、少しだけ時間を置いて気分転換をしましょう。無理に明るく振る舞う必要はありません。
・結果を受け止める: 不合格になった事実を受け止め、なぜそうなったのかを軽く分析することは大切ですが、深く原因を追究しすぎないようにしましょう。
・「結果は最後まで分からない」と心に留める: たとえ併願校が全滅でも、第一志望校に合格する可能性はゼロではありません。過去には、併願校が全滅したにも関わらず、最後まで諦めずに努力した結果、第一志望に合格した生徒もいます。
・次の試験に集中: 気持ちを切り替えたら、すぐに次の試験の対策に集中しましょう。不合格の悔しさをバネに、残りの試験に全力を尽くすことが大切です。
保護者の方には、この時期の生徒さんの精神的なサポートを特に手厚くお願いしています。
「頑張ったね」「次があるよ」といった温かい声かけが、生徒さんの大きな力になります。

保護者からよく聞かれる併願の疑問点とその回答
保護者の皆さんから、併願に関してよく聞かれる疑問とその回答をまとめました。
Q. 併願校の受験料や入学金が高額で心配です。どうすればいいですか?
A. 事前に、受験料や入学金、交通費、宿泊費など、併願にかかる費用の総額を計算し、家庭内でどこまで負担できるかを話し合うことが最も重要です。入学金延納制度の有無も確認し、必要であれば活用を検討しましょう。場合によっては、受験数を絞ることも視野に入れる必要があります。
Q. 子どもが併願校選びで悩んでいます。どのようにアドバイスすれば良いでしょうか?
A. まずは、お子さんの「本当に学びたいこと」や「将来の目標」を尊重し、それを軸に併願校を一緒に検討しましょう。模試の判定や大学の立地、就職実績など、現実的な情報も提示しつつ、お子さんの意見を第一に聞く姿勢が大切です。無理に親の希望を押し付けると、かえってモチベーションを下げてしまうこともあります。
Q. 併願校のオープンキャンパスに行った方がいいですか?
A. はい、強くおすすめします。ウェブサイトやパンフレットだけでは分からない大学の雰囲気や学びの内容を肌で感じることができ、入学後のミスマッチを防ぐ上で非常に有効です。「もしここに通うことになったら」という視点で参加してみましょう。
これらの疑問は、多くの保護者が抱えるものです。
お子さんとのコミュニケーションを密にし、一緒に併願戦略を立てていくことが、成功への鍵となります。

併願校の過去問対策はいつから始める?
第一志望校の対策を優先しつつ、秋(10月〜11月頃)から少しずつ始めるのが一般的です。
第一志望の対策を固めることが最優先です。
その上で、併願校の過去問に最低3年分は目を通し、出題傾向や時間配分を掴んでおきましょう。
安全校については、1〜2年分解いて合格最低点をクリアできるか確認しておけば十分な場合もあります。

同じ大学の複数学部を受験するメリットは?
合格の可能性を高められる点と、受験料の割引制度が使える場合がある点です。
同じ大学であれば問題の傾向が似ているため、対策しやすいというメリットもあります。
その大学にどうしても行きたいという強い意志がある場合は、複数の学部を受験することでチャンスを広げることができます。

「絶対受かる大学」は必要か?
精神的な安定剤として、1校は確保しておくことを強くおすすめします。
「全落ちするかもしれない」という不安は、受験本番でのパフォーマンスに悪影響を与えます。
早い時期に一つでも合格を手にしていると、「行く場所がある」という安心感が生まれ、その後のチャレンジ校の受験に集中できます。
本当に行きたくない大学を無理に受ける必要はありません。

浪人を避けるための併願戦略とは?
安全校のレベル設定を慎重に行い、確実に合格を勝ち取ることです。
プライドが邪魔をして、安全校のレベルを高く設定しすぎる受験生がいますが、これは危険です。
模試でA判定が出ている、過去問で安定して高得点が取れるなど、客観的なデータに基づいて「確実に合格できる」大学を最低1〜2校は受験することが、浪人を避けるための最も重要な戦略です。
私も過去に、安全校の選定を誤ったばかりに、浪人という結果になってしまった生徒を何人も見てきました。
難関大学にあなたも逆転合格できる
圧倒的な合格率が本物の証
難関私大に合格する完璧なノウハウ
志望大学の先生があなたをサポート
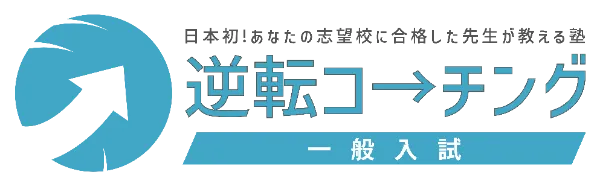
「友だち追加」で無料コーチング
勉強計画を無料で作成
↓↓↓
まとめ:私立大学併願パターンの王道!受験で失敗しない戦略と併願校の選び方

最後までご覧いただき、ありがとうございます。
今回の記事、「私立大学併願パターンの王道!受験で失敗しない戦略と併願校の選び方」は参考になりましたでしょうか?
学習塾経験から導く、納得のいく大学受験を成功させる併願戦略
最後に、この記事の重要なポイントを振り返ります。
・ 併願の基本は「チャレンジ校」「実力相応校」「安全校」の3つをバランス良く組み合わせること。
・「共通テスト利用」と「一般選抜」を使い分け、早い段階で安全校の合格を確保するのが王道パターン。
・ 併願校は偏差値だけでなく、「本当に行きたいと思えるか」という視点で選ぶことが後悔しないための鍵。
・受験校数の平均は4〜6校。費用や体力を考慮し、自分に合った校数を見つける。
・合格発表日と「入学金納付締切日」の管理を徹底し、無駄な出費を避ける。
・連続受験は3日まで。休息日を設けて、万全の体調で本番に臨む。
併願戦略に「唯一の正解」はありません。
大切なのは、この記事で得た知識をもとに、あなた自身の学力、性格、そして経済状況に合わせた「自分だけの最適な併願プラン」を立てることです。
周りの情報に流されすぎず、自分と向き合い、納得のいく受験計画を立ててください。
あなたの努力が最高の結果に結びつくことを心から応援しています。

