理系受験生の理科選択はどれが有利?共通テスト・新課程(理科探究)を解説!
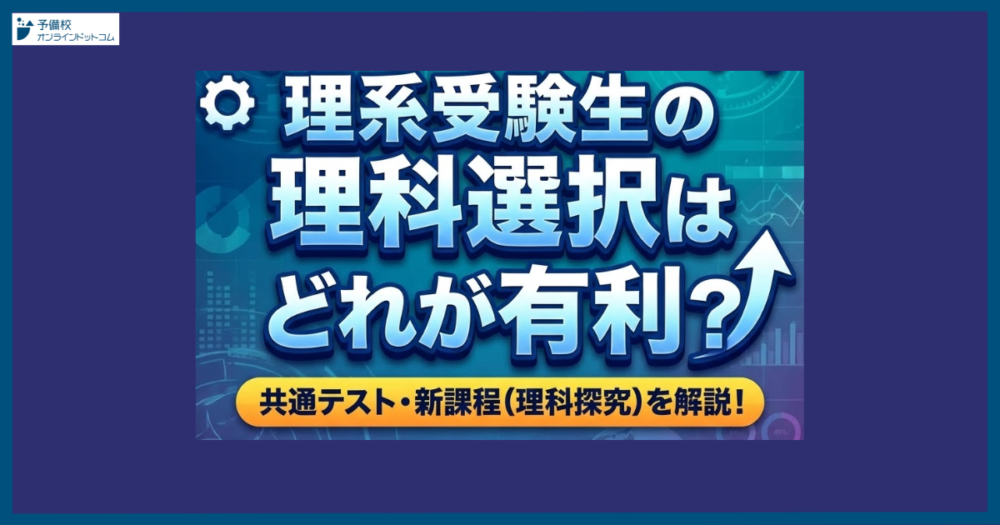
「※この記事には一部PRが含まれます」
「理系の受験で理科は何を選べばいいの?」「物理と化学、どっちが有利?」「新課程で何が変わったの?」
そんな疑問を持つ理系受験生や保護者の方も多いのではないでしょうか。
新課程に対応した「理科探究(物理探究・化学探究・生物探究・地学探究)」が本格スタートしています。
これまでの「物理・化学・生物・地学」とは内容も出題傾向も大きく変わり、思考力や実験・考察力が重視される入試に進化しています。
この記事では、「理系受験生が必要な理科の数と組み合わせ」「新課程(理科探究)の出題内容と特徴」「各科目の選び方と注意点」を、教育専門メディア「予備校オンラインドットコム編集部」がわかりやすく解説します。
理系の進路選びに迷っている方は、この記事を読むことで「自分に合った理科科目」がきっと見つかります。
新課程「理科探究」で理科選択は?
理系受験生に必要な理科の科目数と組み合わせを理解する
各理科探究科目(物理・化学・生物・地学)の特徴と選び方
理科探究4科目の受験者数・平均点(令和7年度=新課程)
Contents
理系受験生が選択する理科とは?

理系受験生が大学入試で必要とする理科は、進学する学部や大学によって大きく異なります。
共通テストや二次試験で求められる科目数、そしてどの科目を選ぶかによって、受験戦略が変わります。
ここでは、理系の理科の基本的な概要と、大学ごとの科目数の違いをわかりやすく説明します。
必要な理科の科目数
志望大学によって違う科目数
理科探究4科目の出題範囲と構成
理系理科の概要
理系の高校生は、高校2年生になる前に文理選択を行う際に、理科の科目を決めることが多いです。
新課程では、理科は「物理探究」「化学探究」「生物探究」「地学探究」の4科目に分かれています。
旧課程の「物理」「化学」「生物」「地学」に対応していますが、実験・考察・データ分析など探究的な学びが重視されるようになりました。
例えば、工学系や理学系を目指すなら物理探究・化学探究、医療・薬学系を目指すなら生物探究・化学探究が中心です。
理科選択は大学入試の土台となる重要な判断なので、早めに情報を集めて計画を立てることが成功のカギです。

必要な理科の科目数
理系受験生が受験で必要とする理科は、1〜2科目です。
共通テストでは、国公立大学を志望する場合は理科2科目が基本ですが、私立大学では1科目で受験できることもあります。
特に注意すべきなのは、「基礎科目(物理基礎など)」ではなく、「物理」「化学」などの発展科目が指定されている点です。
例えば、化学を選ぶと受験できる大学が広がるなど、選ぶ科目によって受験の幅が変わることを理解しておきましょう。

志望大学によって科目数が違う
国公立大学を志望する場合、共通テストでは理科探究を2科目受験するのが基本です。
例えば、東京大学や京都大学といった旧帝大クラスでは、二次試験でも理科探究を2科目課すことが多く、深い理解力が求められます。
一方、私立大学では理科1科目で受験できる大学が大半です。
ただし、早稲田大学・慶應義塾大学の一部学部や医学部では、理科探究を2科目必要とするケースもあります。
医学部受験では、国公立・私立ともに理科探究2科目(化学探究+生物探究など)を課す大学が多い点にも注意しましょう。
共通テストでは今後、「探究的な学び」を重視した出題が増えており、単なる暗記ではなく実験データやグラフを読み解く力が問われます。
同じ大学でも学部・入試方式によって条件は異なりますので、志望校の入試要項を早めに確認することが最も重要です。

理科探究4科目の出題範囲と構成
| 科目名 | 主な出題範囲 | 問題構成・出題形式 | 特徴・学習ポイント |
|---|---|---|---|
| 物理探究 | 力学、波動、電磁気、熱、原子分野など。 探究活動としての実験設計やデータ分析問題を含む。 |
大問数:3〜4題程度。 実験データの解釈・グラフ読解問題が中心。 |
数式の理解+論理的思考力が求められる。 公式の暗記だけでなく、現象の理由を説明できる力が必要。 |
| 化学探究 | 物質の構造、化学反応、熱化学、電池・電気分解、有機化学など。 | 大問数:3〜4題程度。 化学実験データの考察問題が増加。 |
観察→仮説→検証のプロセス重視。 グラフ・表を用いた定量分析力が問われる。 |
| 生物探究 | 細胞、生殖と発生、遺伝、代謝、生態系など。探究課題に基づいた考察問題を出題。 | 大問数:4題程度。 図表・グラフから読み取って説明する形式が中心。 |
暗記+思考力型。観察結果を根拠に結論を導く力が必要。 |
| 地学探究 | 地球の構造、気象、天体、プレート運動、地球史など。観測データをもとに考察する問題を含む。 | 大問数:3〜4題程度。 地震波解析・気象データ分析などが中心。 |
データ読解力・考察力が重要。数値計算よりも情報整理・推論重視。 |
新課程(理科探究)で理科選択はどう変わる?

2025年度からの新課程では、理科が「理科探究」に変わりました。
これまでの「物理・化学・生物・地学」が「物理探究・化学探究・生物探究・地学探究」となり、思考力や実験力を重視する出題形式に移行しています。
単なる暗記ではなく、データの読み取りや考察が必要な問題が増えており、受験生には新しい学び方が求められます。
理科探究とは?旧課程との違い
探究科目で求められる力(思考力・実験力)
各探究科目の特徴一覧(物理探究・化学探究・生物探究・地学探究)
理科探究4科目の受験者数・平均点(令和7年度=新課程)
理科探究とは?旧課程との違い
理科探究は、旧課程の理科科目を発展させた新しい教科で、「探究的な学び」=自分で考えて答えを導く力を育てることが目的です。
これまでのように公式や用語を暗記するだけでなく、実験や観察から得たデータをもとに分析・説明する力が求められます。
例えば、共通テストでは「実験結果のグラフを読み取って考察する問題」や「条件を変えた場合の結果を予測する設問」が増える傾向です。
つまり、理科探究では“考える理科”への転換が進んでおり、学習方法も「理解と応用」が重視されます。

探究科目で求められる力(思考力・実験力)
理科探究で重視されるのは、思考力・実験力・表現力の3つです。
これまでの暗記型学習だけでは対応できない出題が多くなるため、日頃から「なぜこうなるのか」を意識して学ぶことが大切です。
具体的には以下のような力が問われます。
・思考力:データや現象をもとに論理的に説明する力
・実験力:実験条件を考え、結果を予測・分析する力
・表現力:考察を言葉や図で正確に伝える力
化学探究では「反応の進み方をグラフ化して説明する問題」、生物探究では「観察データをもとに仮説を立てる問題」などが出題される可能性があります。

各探究科目の特徴一覧(物理探究・化学探究・生物探究・地学探究)
新課程では、4つの理科探究科目が設定されています。
それぞれの科目の特徴と、向いているタイプを以下にまとめました。
| 科目 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 物理探究 | 力・エネルギー・波動などを扱い、数式や理論を使って現象を説明する。 | 数学や計算が得意な人、論理的に考えるのが好きな人。 |
| 化学探究 | 物質の性質や反応を扱い、実験や観察を通して法則を導く。 | バランスよく暗記と理解を進めたい人。 |
| 生物探究 | 生命現象を観察・分析し、グラフやデータから考察する。 | 観察力があり、暗記が得意な人。 |
| 地学探究 | 地球・宇宙・気象などを総合的に学ぶ。 | 自然や地球の仕組みに興味がある人。 |
探究科目は、大学や学部によって必要な組み合わせが異なるため、早い段階で志望校の入試要項を確認しておくことが大切です。
新課程の理科では、単なる知識よりも「考えて説明できる力」が合格のカギになります。
理系受験生の理科の選び方とは?

理系の受験生にとって、どの理科科目を選ぶかは大学合格を左右する大切なポイントです。
選ぶ科目によって、受験できる大学や学部、学習の負担も変わります。
ここでは、理科の選択方法と、地学・生物・物理・化学のそれぞれの特徴をわかりやすく紹介します。
理科はどの科目を選択する?
地学探求の特徴
生物探求の特徴
物理探究の特徴
化学探究の特徴
理科はどの科目を選択する?
理系の理科には「物理探究」「化学探究」「生物探究」「地学探究」の4つがあります。
どの科目を選ぶかは、志望する大学・学部、そして自分の得意分野で決めるのが基本です。
例えば、工学部や理学部では物理探究・化学探究の組み合わせが多く、医学部や薬学部では化学探究・生物探究が主流です。
まだ志望校が決まっていない場合は、受験できる大学が多い「物理探究+化学探究」を選んでおくと安心です。
| 科目名 | 暗記量 | 計算量 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 物理探究 | 少ない | 多い | 数学的な思考が必要で、論理的に考えるのが得意な人向け。現象を数式で説明する問題が多い。 |
| 化学探究 | 普通 | 普通 | 暗記と計算のバランスが取れており、幅広い理系学部で必要。実験考察やグラフ読解問題が増加傾向。 |
| 生物探究 | 多い | 少ない | 暗記が中心だが、グラフやデータを分析して考察する力が求められる。医学・薬学・農学系志望に適している。 |
| 地学探究 | 普通 | 少ない | 地球・気象・宇宙など幅広いテーマを扱う。データ読解が中心で、自然現象に興味がある人におすすめ。 |

地学探求の特徴
地学探究では、地球の構造や気象、宇宙などを学びます。
大学入試で地学探究を受験科目に指定している大学は少なく、共通テストでも選択者が非常に少ないのが現状です。
参考書や問題集の数も限られているため、独学では対策が難しい面もあります。
地球科学や天文学に強い興味がある人以外には、選択しにくい傾向にあります。

生物探求の特徴
生物探究では、生命現象や遺伝、進化などを扱います。
暗記量が多い科目で、実験結果やグラフを読み取る問題も出題されます。
農学部や医学部、薬学部など、生物に関係する学部を目指す人にはおすすめの科目です。
出題内容が広く、考察型の問題も増えているため、興味と継続力が必要な科目ともいえます。

物理探究の特徴
物理探究は、自然界の法則を数学的に表して理解する科目です。
新課程では、単なる公式暗記ではなく、実験データから関係式を導く力や、現象の理由を考える力が重視されます。
数学が得意な人や、論理的に考えるのが好きな人に向いている科目です。
苦手な人は計算の多さに戸惑うこともあるため、基本公式の意味を理解して使えるようにしておくと良いでしょう。

化学探究の特徴
化学探究は、物質の構造や反応のしくみを理解し、法則を見つける科目です。
新課程では、化学反応を暗記するだけでなく、実験データやグラフから反応の規則性を見つける力が求められます。
暗記と計算のバランスが取れており、工学・理学・薬学など幅広い学部で必須科目となっています。
化学探究は他の理科科目と組み合わせやすく、受験範囲が広いため、早めに基礎を固めておくと有利です。
理系受験生が理科を2科目選択する時の注意点

理系受験生の多くは、国公立大学や医学部を目指す際に理科を2科目選択します。
2科目を選ぶときは、受験要件・学習負担・得意分野のバランスをしっかり考えることが大切です。
ここでは代表的な組み合わせ例と、各科目の相性や特性の違いを整理して解説します。
2科目の組み合わせ例(物理+化学/生物+化学)
科目特性の違い(暗記量・計算量・相性)
2科目の組み合わせ例(物理+化学/生物+化学)
理系の受験では、最も多い組み合わせが「物理探究+化学探究」です。
工学系・理学系・情報系など幅広い学部で対応できるため、進路の選択肢が広がります。
医学部や薬学部・農学部では「生物探究+化学探究」の組み合わせが主流です。
生物は暗記中心、化学は思考・計算のバランス型なので、得意分野を活かせる利点があります。
志望校が未定の場合は「物理+化学」、医療系志望なら「生物+化学」を選んでおくと安心です。

科目特性の違い(暗記量・計算量・相性)
理科2科目を選ぶときは、暗記量と計算量のバランスを意識しましょう。
例えば、物理探究は計算が多く論理的思考を求められますが、暗記は少なめです。
生物探究は暗記中心で計算は少なめ。
化学探究はその中間に位置します。
| 科目 | 暗記量 | 計算量 | 相性・特徴 |
|---|---|---|---|
| 物理探究 | 少ない | 多い | 数学が得意な人に向く |
| 化学探究 | 普通 | 普通 | 幅広い学部で必須 |
| 生物探究 | 多い | 少ない | 医療・生命系に適している |
| 地学探究 | 普通 | 少ない | データ分析中心、独学が難しい場合も |
理系受験生が理科を選択する時のポイント

理系受験生が理科を選ぶときは、「大学で必要な科目」「自分の得意分野」「将来の進路」を総合的に考えることが大切です。
共通テストや大学ごとの出題傾向も異なるため、早い段階から情報を集めることが成功のカギです。
ここでは、理科選択で失敗しないための5つのポイントを紹介します。
大学進学先の要件に合わせる
自分の得意分野を重視する
将来の進路に合わせる
過去問などで傾向を分析する
先生や塾に相談して決める
理科探究4科目の受験者数・平均点(令和7年度=新課程)
大学進学先の要件に合わせる
大学や学部によって、受験で必要な理科の科目数や組み合わせは異なります。
国公立大学では理科探究を2科目必要とする場合が多く、私立大学では1科目のみのケースが主流です。
例えば、東京大学・京都大学などの難関大や医学部は「物理探究+化学探究」など2科目が必須となることが多いです。
入試要項を必ず確認し、志望大学で必要な理科科目を早めに把握しておくことが重要です。

自分の得意分野を重視する
理科の成績を上げるには、自分が理解しやすく興味を持てる科目を選ぶことがポイントです。
例えば、計算が得意な人は物理探究や化学探究、暗記が得意な人は生物探究が向いています。
苦手な分野を無理に選ぶと、勉強のモチベーションが下がりやすくなります。
得意分野を活かせば、共通テストでも安定して高得点を狙うことができます。

将来の進路に合わせる
将来の職業や学びたい分野に合わせて理科を選ぶことも大切です。
例えば、医療・薬学・生物系を志望するなら「生物探究+化学探究」、工学・情報・理学系を志望するなら「物理探究+化学探究」が基本です。
将来の目標がまだ定まっていない場合は、どの理系学部にも対応できる化学探究を軸に選ぶと安心です。

過去問などで傾向を分析する
共通テストや志望校の入試問題を分析することで、どの科目が得点しやすいかがわかります。
例えば、物理探究は計算問題が多く、慣れると安定して点が取れる一方、化学探究は年度によって難易度の差があります。
過去問を数年分チェックし、自分の得点傾向や相性を把握して科目を決めるのがおすすめです。

先生や塾に相談して決める
理科の選択で迷ったら、学校や塾の先生に相談することが一番確実です。
先生は過去の受験データや生徒の傾向を把握しているため、あなたの学力や志望校に合ったアドバイスをしてくれます。
オンライン塾やコーチング塾では、学習計画や志望校戦略を個別にサポートしてくれるサービスもあります。
一人で悩まず、信頼できる専門家の意見を参考に決めましょう。

理科探究4科目の受験者数・平均点(令和7年度=新課程)
| 科目名 | 受験者数 | 平均点(100点満点) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 物理探究 | 144,761人 | 58.9点 | 計算問題中心だが、探究課題を含む出題構成。 |
| 化学探究 | 183,154人 | 45.3点 | 難易度が高く、受験者数も多い傾向。 |
| 生物探究 | 57,985人 | 52.2点 | データ分析・考察問題が多く、得点差が大きい。 |
| 地学探究 | 2,365人 | 41.6点 | 受験者数が少なく、記述理解力を問う設問が中心。 |
出典:大学入試センター「令和 7年度大学入学共通テスト 実施結果の概要」
【編集部からのアドバイス】
・「物理探究」「化学探究」「生物探究」「地学探究」の4科目に完全移行。
・各科目で実験データ・グラフ読解・考察型問題が増加。
・平均点は旧課程とほぼ同水準だが、探究的思考を要する問題で差がつく傾向。
・化学探究の平均点が特に低下しており、思考型問題の難化が見られる。
![]()
まとめ:理系受験生の理科選択はどれが有利?共通テスト・新課程(理科探究)を解説!

ここまで読んで、理科選択が単に「得意・不得意」だけでなく、志望校や残り時間によって戦略が変わることが分かったと思います。
ただ実際には、「今の成績でどの科目を選ぶのが現実的か」「この選択で受験全体のバランスは崩れないか」といった点で、最後まで迷ってしまう受験生も少なくありません。
理科の選択は、志望校や他科目との兼ね合いを含めた受験全体の設計が重要です。
一人で判断するのが不安な場合は、学習計画や科目戦略を整理してくれる第三者の視点を取り入れるのも一つの方法です。
受験全体の戦略や選択肢をまとめて整理したい方は、▶ コーチング塾おすすめ15選【2026最新】専門家が比較 も参考にしてください。
最後に、理科科目そのものに「有利・不利」はありません。志望校の入試科目や配点をよく確認したうえで、自分が継続して取り組める科目を選ぶことが、結果的に最良の選択につながります。
今回の記事を参考に、自分にとって最適な理科科目をじっくり考えてみてください。
理系受験生の理科選択
理系学部を目指す受験生が理科の科目を選ぶときには、いくつかのポイントに注意が必要です。
まず、自分の興味関心や将来の目標を明確にすることが大切です。
理科には「物理」「化学」「生物」「地学」などさまざまな分野があります。
自分の興味に合った分野を選ぶことで、学習のモチベーションも上がり、勉強がより楽しく続けられるでしょう。
将来の進路を意識することで、必要な理科科目を絞ることができます。
例えば、医学部を目指す場合は「生物」と「化学」が必須となるケースが多いです。
理科選択では、大学ごとに入試科目が異なる点にも注意が必要です。
大学によっては2科目選択を課している場合もあるため、自分の得意科目や将来の方向性を踏まえて慎重に選びましょう。
理科の選択は、受験勉強の成果を大きく左右する重要な要素です。
自分の興味・目標・志望校の条件を考慮しながら、後悔のない選択をしてください。
もし迷ったときは、学校や塾の先生に相談するのがおすすめです。
あなたの学力や志望校に合わせて、最適なアドバイスをしてくれるでしょう。
執筆者のプロフィール
【執筆者プロフィール】
予備校オンラインドットコム編集部

予備校オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営経験者、ファイナンシャルプランナー、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。高校生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。
予備校オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram
中学受験や高校受験に向けた塾選び、日々の家庭学習でお悩みの方には、姉妹サイトの「塾オンラインドットコム」がおすすめです。小・中学生向けの効率的な勉強法や、後悔しない塾の選び方など、保護者さまが今知りたい情報を専門家が分かりやすく解説しています。ぜひ、あわせて参考にしてください。
