読書感想文の本の選び方【高校生向け】失敗しない5つの基準をプロが解説
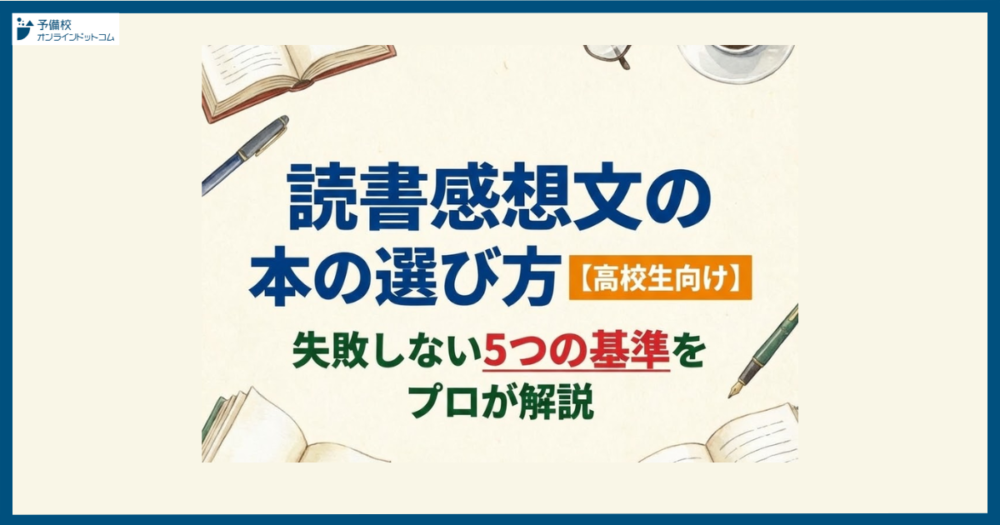
「※この記事には一部PRが含まれます」
「読書感想文の宿題が出たけれど、そもそも何を選べばいいの?」と本選びで止まっていませんか。
実は、感想文を短時間でスムーズに終わらせる秘訣は「文章力」ではなく「本選び」にあります。
27年以上、多くの高校生の学習指導をしてきた私たちが、失敗しないための正しい判断基準をわかりやすくお伝えします。
・自分の「興味・関心」を言語化できる本を選ぶ
・「変化・成長」のプロセスが明確なストーリーを探す
・「社会問題」や「多様な価値観」をテーマにした作品に注目する
・完読を目的とせず「自分自身の体験」を重ねやすい一冊に決める
Contents
- 1 はじめに|読書感想文は「本選び」で9割決まる?
- 2 結論先出し|高校生が失敗しない読書感想文用の本の選び方
- 3 基準① 高校生の今の生活と重ねられるテーマか
- 4 基準② テーマが一言で説明できる本を選ぶ
- 5 基準③ 登場人物と構成がシンプルな本か
- 6 基準④ 読み終わったあと感情が動くか
- 7 基準⑤ 最後まで無理なく読み切れる分量か
- 8 高校生が避けるべき読書感想文向きではない本
- 9 迷ったときの最終判断|本屋・図書館での決め方
- 10 【チェックリスト】これで決めていいんだ!最後の安心チェック
- 11 よくある質問|高校生の読書感想文本選びQ&A
- 12 まとめ:読書感想文の本の選び方【高校生向け】失敗しない5つの基準をプロが解説
- 13 執筆者のプロフィール
はじめに|読書感想文は「本選び」で9割決まる?

▶本が決まったあとに迷わないために、高校生の読書感想文の書き方(構成・始め方・NG例) もあわせて確認しておくと安心です。
読書感想文を「苦行」だと感じてしまう最大の理由は、自分に合わない本を選んでいることにあります。
無理に難しい本を選んで、原稿用紙の1枚目で挫折してしまった生徒を私たちは何度も見てきました。
逆に言えば、「自分にとって書きやすい本」を手に取った瞬間に、宿題の9割は終わったも同然です。
本選びは単なる趣味ではなく、アウトプットを前提とした戦略的な準備だと考えてください。
ここで正しいルールを知れば、もう本屋で何時間も迷う必要はなくなります。
結論先出し|高校生が失敗しない読書感想文用の本の選び方

結論から言うと、高校生が選ぶべきなのは「自分が一番ツッコミを入れやすい本」です。
評価を気にしすぎて自分と接点のない本を選ぶのではなく、今のあなたの「本音」が動き出す本を見つけることが、最短で宿題を終わらせる正解ルートになります。
本選びを間違えると最後まで書けなくなる理由
自分の興味や理解を超えた本を選ぶと、書きたいことが全く湧いてこないからです。
例えば、時代背景が複雑すぎる古典を選んでしまうと、内容を説明するだけで力尽き、肝心の「自分の感想」が書けなくなります。
・理解に時間がかかりすぎて執筆時間がなくなる
・あらすじをなぞるだけの「薄い文章」になる
「背伸びをしないこと」こそが、失敗を避けるための第一歩です。
■ 指導現場で見かけた失敗例
以前、ある男子生徒が「評価が高そうだから」と、読んだこともない難解な海外の哲学小説を手に取りました。設定を理解するだけで3日かかり、結局「何を言っているのかわからない」と、期限前日に白紙の原稿用紙を抱えて相談に来ました。
今回の基準ならこう選ぶべきだった:男子生徒はサッカー部だったので、哲学よりも「スポーツマンの葛藤」を描いた現代の物語を選ぶべきでした。
そうすれば、自分の部活での経験と重ねて、1日で書き上げられたはずです。
基準① 高校生の今の生活と重ねられるテーマか

最も書きやすいのは、今のあなたと「似たような状況」にある物語です。
自分の日常生活と重なる部分が多いほど、特別な文章テクニックがなくても、スラスラと言葉があふれてきます。
戦争・社会問題の本は「自分との接点」があるかが重要
部活・友人関係・将来不安がテーマの本は書きやすい
主人公があなたと同じ悩みを持っていると、自分自身の体験談と結びつけやすいからです。
部活での挫折や、友人への言えない本音、進路へのぼんやりとした不安など、自分のリアルな感情を本に重ねて書くことができます。
・ 野球部なら野球の物語、受験生なら勉強の物語を選ぶ
・「もし自分だったら……」と想像しやすい場面が多い
「自分の日常の延長線上」にある本を探してみることをおすすめします。

戦争・社会問題の本は「自分との接点」があるかが重要
重いテーマの本であっても、どこかに「自分との接点」があれば書き切ることができます。
例えば戦争の話なら、「もし今の自由な生活が奪われたら」と仮定することで、自分の価値観を論理的にまとめやすくなります。
・SNS上のトラブルを「現代の争い」として捉え直す
・ニュースで見た出来事と本のテーマを結びつけてみる
「遠い世界の話」で終わらせず、自分の生活と無理なく繋げられる本を選びましょう。
■ 指導現場で見かけた失敗例
歴史が苦手な生徒が、知識がないまま「定番だから」と第2次世界大戦の戦記物を選びました。当時の地名や武器の名前が難しすぎて、状況を把握するだけで精一杯になり、「怖かった」以外の感想が書けなくなってしまったのです。
今回の基準ならこう選ぶべきだった: 戦争そのものではなく、「当時の若者の日常」や「恋愛」にスポットを当てた物語を選べば、今の自分の恋愛観と比較して、もっと具体的な文章が書けたはずです。
基準② テーマが一言で説明できる本を選ぶ

「この本は何について書かれた本か」と聞かれたときに、一言で答えられるものを選びましょう。
テーマが明確であればあるほど、感想文の「軸」がブレなくなり、説得力のある文章が完成します。
青春・恋愛・戦争などテーマ別の考え方
テーマが曖昧な本が感想文で失敗しやすい理由
テーマがぼんやりしていると、結局何を伝えたかったのかがわからず、文章が散漫になってしまうからです。
雰囲気は良いけれど「結局、何が言いたかったの?」と迷う本は、感想文という目的においては非常に難易度が高いといえます。
・何について書くか迷うだけで時間が過ぎてしまう
・一貫性のない、支離滅裂な文章になりやすい
「友情の大切さ」「努力の価値」など、核心がはっきりした一冊を選んでください。

青春・恋愛・戦争などテーマ別の考え方
ジャンルごとに「何について書くか」をあらかじめイメージしておくのがコツです。
例えば青春ものなら「成長」、恋愛なら「他者への理解」というように、自分が書きやすい得意なテーマを決めておくと、本選びのフィルターになります。
・自分の好きな映画やマンガに近いテーマから探す
・「勇気をもらいたい」「社会を知りたい」などの目的を持つ
テーマを一つに絞り込むことが、迷いから抜け出す近道になります。
■ 指導現場で見かけた失敗例
情景描写がとても美しい「雰囲気重視」のエッセイを選んだ女子生徒がいました。読んでいる間は楽しそうでしたが、いざ書く段階になると「美しい」以外に何を書けばいいのか分からず、文字数が全く伸びませんでした。
今回の基準ならこう選ぶべきだった: 美しい文章であることに加えて、明確な「事件」や「変化」が起きる物語を選べば、その変化に対して自分の意見を述べるだけで原稿用紙が埋まったでしょう。
基準③ 登場人物と構成がシンプルな本か
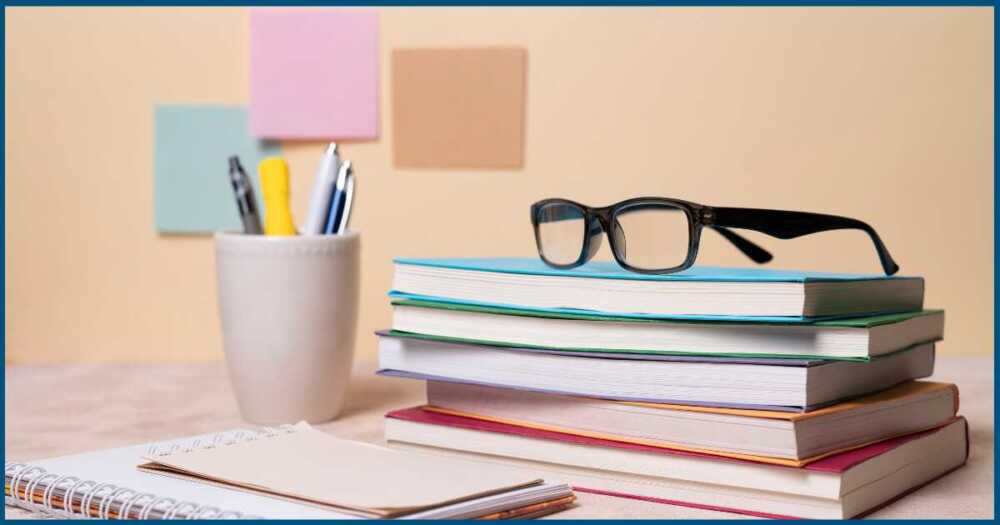
登場人物が多すぎたり、時系列が入り組んでいたりする本は避けましょう。
読解に使うエネルギーを最小限に抑え、その分を「自分の考えをまとめること」に充てられる本が理想的です。
短い小説・短編集が高校生向きな理由
登場人物が多い小説が書きにくい理由
人物相関図が必要なほどの設定だと、誰に感情移入していいかわからなくなるからです。
誰が誰かを説明するだけで原稿用紙を使い切ってしまい、あなたの「本音」を書くスペースがなくなってしまうという失敗がよくあります。
・主人公が固定されている物語を選ぶ
・関係性が「友人」「親子」などシンプルであること
「一人の主人公の心の変化」を追いかけられる本が、最も書きやすい本です。

短い小説・短編集が高校生向きな理由
「全部を読まなければならない」というプレッシャーを減らせるからです。
特に短編集なら、収録されている話の中から一番心に刺さった一編だけに絞って感想を書くことができるため、読書時間を劇的に短縮できます。
・数ページで一つの山場が来るので飽きにくい
・気になったエピソードだけに集中して深掘りできる
忙しくて時間がない時こそ、あえて短いものを選ぶ戦略を持ってみましょう。
■ 指導現場で見かけた失敗例
「10人の視点が切り替わる群像劇」を書き始めた生徒がいました。しかし、1人ずつのあらすじを紹介するだけで原稿用紙が終わってしまい、「先生、これ感想を書く場所がありません」と困り果てていました。
今回の基準ならこう選ぶべきだった:主人公がはっきりしている本、あるいは短編集の中から「この1話だけについて書く」というスタイルを取れば、もっと深みのある考察ができたはずです。
基準④ 読み終わったあと感情が動くか

読み終わった直後に、心の中に「何かしらのトゲ」が残る本を選んでください。
「面白かった」だけでなく、「悔しい」「納得いかない」「救われた」といった強い感情こそが、感想文のエンジンになります。
知恵袋で失敗例が多い本の共通点
「共感できる本」と「評価されやすい本」の関係
実は「共感(わかる!)」よりも「違和感(えっ?)」がある本の方が、評価されやすい文章になります。
なぜ自分はそう感じたのかを掘り下げる過程で、あなた独自の鋭い視点や思考の深さが自然と表れるからです。
・「自分ならこうはしない」という反論ポイントを探す
・心が大きく揺れた場面に付箋を貼ってみる
「心がざわついた瞬間」を大切にできる本を選んでください。

知恵袋で失敗例が多い本の共通点
ネットでよく「おすすめ」されている名作を選び、内容が難しすぎて書けなくなったという悩みが後を絶ちません。
どんなに評判が良くても、あなたの心が一ミリも動かなければ、それはあなたにとっての「ハズレ本」になってしまいます。
・他人の評価よりも「今の自分の興味」を優先する
・あらすじを読んでワクワクしない本は勇気を持って見送る
「他人の正解」ではなく「あなたの正解」で選ぶことが大切です。
■ 指導現場で見かけた失敗例
「先生に褒められそうな真面目な本」を選んだものの、一言も共感できなかった生徒がいました。結局、無理やり「素晴らしいと思いました」と嘘を書いてしまい、内容に矛盾が出てやり直しになってしまいました。
今回の基準ならこう選ぶべきだった:100%賛成できなくてもいいんです。むしろ「この主人公の行動はおかしい」と怒りを感じるような本の方が、その理由を書くだけで熱のこもった感想文になります。
基準⑤ 最後まで無理なく読み切れる分量か

「本を読み終わること」は、感想文を書くための最低条件です。
自分の今の集中力で、最後まで走りきれる厚さの本を選んでください。
読み切ったという達成感が、執筆への自信に繋がります。
忙しい高校生でも間に合う本の見極め方
「短い=楽」ではない本選びの注意点
ページ数が少ないからといって、必ずしも書きやすいとは限りません。
中には非常に難解なテーマが凝縮されている本もあるからです。分量だけで決めるのではなく、言葉の選び方が自分に合っているかを確認することが重要です。
・1ページあたりの文字数や行間をチェックする
・自分が普段読んでいる本の厚さを基準にする
「これなら読み切れそうだ」という直感を信じることが正解です。

忙しい高校生でも間に合う本の見極め方
提出期限から逆算して、今の自分に許される読書時間を把握しましょう。
私たちは指導の現場で、「読書に2日、執筆に1日」といった計画を立てさせますが、そのためには1〜2時間で読み切れる本を選ぶのが最も現実的です。
・持ち運びやすく、隙間時間で読み進める本
・物語の展開がスピーディーで一気に読める本
無理な計画を立てず、確実に終わらせられるサイズ感を重視しましょう。
■ 指導現場で見かけた失敗例
意気込んで分厚い上下巻の大作を借りてきた生徒がいましたが、上巻を読み終わったところで夏休みが終了。下巻の内容を知らないまま書くわけにもいかず、結局泣きながら短い本を読み直すハメになりました。
今回の基準ならこう選ぶべきだった:自分の読書スピードを甘く見ず、「1時間で何ページ読めるか」をテストしてから本を選ぶべきでした。見通しを立てることは、勉強と同じくらい重要です。
▶具体的にどんな本が当てはまるのか知りたい人は、読書感想文が書きやすい本15選【高校生向け】 を参考にしてください。
高校生が避けるべき読書感想文向きではない本

「良書」とされる本の中にも、感想文には向かない「落とし穴」のある本が存在します。
27年の経験から、高校生が選びがちだけれど苦労するパターンを整理しました。
難解な小説・抽象的すぎる本の落とし穴
名作・有名作品が必ずしも正解ではない理由
古い時代の名作は、当時の価値観や言葉遣いが今の私たちと離れすぎており、共感するのが難しいからです。
無理に「良い感想」を書こうとして、どこかの解説の受け売りになってしまうと、あなたらしさが消えてしまいます。
・時代背景の解説を読まないと理解できない本
・教科書に載っているような「正しい」結論が見えすぎる本
「優等生な感想」を書こうとせず、等身大で向き合える本を選びましょう。

難解な小説・抽象的すぎる本の落とし穴
雰囲気はカッコいいけれど、結局何が起きたのかが曖昧な「芸術的な本」は感想が書きにくいです。
自分の体験と結びつけるポイントが見つからず、結局「よくわからなかった」という一言で終わってしまう危険があります。
・主人公の目的がはっきりしない物語
・セリフが少なく、風景描写ばかりが続く本
「何が起きて、どうなったか」が明確な本の方が、感想は断然書きやすいです。
迷ったときの最終判断|本屋・図書館での決め方

最後は、実際に足を運んで本を手に取ってみましょう。
ネットの情報だけで決めるよりも、実物を見た時の「直感」の方が、あなたにとっての「書きやすさ」を正確に教えてくれます。
「この本で何を書けそうか」を即決するコツ
最初の数ページで判断していい理由
最初の数ページを読んで「言葉がスッと入ってくるか」が、その本との相性を決定づけるからです。
たとえテーマが良くても、文章のリズムが自分に合わない本を読み切るのは苦痛です。この違和感は最後まで消えません。
・文字の大きさや改行の多さが自分に合っているか
・最初の場面描写で、情景が頭に浮かぶか
「この文章なら疲れない」と感じる本を選ぶことが、完走のコツです。

「この本で何を書けそうか」を即決するコツ
本を開きながら、「あの時の自分と似ているな」「この意見には納得できないな」と1つでも思えたら、その本は合格です。
その瞬間に、感想文のメインパートとなる「あなたの意見」がすでに生まれているからです。
・付箋を貼りたくなる箇所が最初の方にあるか
・誰かに「これ面白いよ(変だよ)」と教えたくなるか
「書くネタが1つでも見つかったら決める」というルールで選んでみましょう。
【チェックリスト】これで決めていいんだ!最後の安心チェック

ここまで読んでも、「本当にこの本でいいのかな?」と不安になるかもしれません。
でも、大丈夫です。
以下の5つの項目に1つでもチェックが付けば、その本でしっかりと感想文を書き上げることができます。
自信を持ってレジへ(あるいはカウンターへ)向かいましょう。
| チェック項目 | 判断のポイント(具体例) |
| 1. 主人公に共感できるか | 「自分も同じだ(わかるな)」だけでなく、「自分なら絶対こうしない(ありえない)」という反発でもOK。 |
| 2. 自分の体験を思い出せるか | 本のテーマに近い部活、友達、家族などの具体的なエピソードが1つでも浮かぶか。 |
| 3. 無理なく読み切れるか | 本の厚さに圧倒されず、2時間程度で最後まで読み切れるイメージが持てるか。 |
| 4. 誰かに話したくなるか | 驚いた場面や「誰かに教えたい」と思うシーンが少なくとも1つはあるか。 |
| 5. 自分の意見が浮かぶか | 読み終えたあとに、賛成・反対、あるいは「自分はこう思う」といった意見が1つ以上出てくるか。 |
もしチェックが2つ以上付くなら、それはあなたにとっての「神本」です。
迷わずその1冊で進めましょう。
よくある質問|高校生の読書感想文本選びQ&A

現場でよく受ける質問に、本音で答えます。みんな同じところで不安になっています。
プロのアドバイスを参考にして、最後の一押しにして下さい。
Q.戦争がテーマの本は高校生でも大丈夫?
Q.短い本を選ぶと評価は下がる?
Q.知恵袋で紹介されている本は信用していい?
Q.友達と同じ本を選んでも問題ない?
読み始めて「合わない」と感じたら変えてもいい?
Q.読書感想文に一番おすすめの本のジャンルは?
「現代の青春小説」です。
あなたと年齢が近く、使っている言葉も同じなので、理解のスピードが最も速いからです。
自分の学校生活と比べやすく、「もし自分だったら……」という感想文の王道パターンを簡単に作ることができます。

Q.戦争がテーマの本は高校生でも大丈夫?
もちろん大丈夫ですが、「自分なりの意見」を持てるかどうかを基準にして下さい。
単に「悲しかった」で終わらせず、現代のニュースや自分の周囲にある争いと結びつけて考えられる一冊を選べば、非常に深い内容の感想文になります。

Q.短い本を選ぶと評価は下がる?
全く下がりません。
先生が評価するのは「本の厚さ」ではなく「あなたがどれだけ深く考えたか」です。
分厚い本をあらすじだけで埋めるよりも、短い本を深く読み込んで自分自身の変化をしっかり書く方が、圧倒的に高い評価に繋がります。

Q.知恵袋で紹介されている本は信用していい?
参考にするのは良いですが、最後は必ず自分の目で確かめて下さい。
知恵袋で絶賛されていても、それが今のあなたにとって「書きやすい」とは限りません。
ネットの評判よりも、あなたの「これなら書けそう」という直感を信じてあげて下さい。

Q.友達と同じ本を選んでも問題ない?
全く問題ありません。
むしろ同じ本を読んだ方が「自分はこう思ったけれど、友達はそう思ったんだ」という比較ができ、より深い考察に繋がることもあります。
ただし、内容は自分の言葉で書くことが大切です。
人によって感じ方は必ず違うので、気にする必要はありません。

読み始めて「合わない」と感じたら変えてもいい?
はい、早めに変えるのが正解です。
「せっかくここまで読んだから」と無理に続けるのが、最も時間を無駄にするパターンです。
10分読んで手が止まる本は、感想文を書く段階でも苦労します。
早めに切り替えることは「失敗」ではなく「賢い選択」だと思ってください。
▶本を決めたら、高校生の読書感想文の例文(800字・2000字・5枚) を見て、完成イメージをつかんでから書き始めましょう。
まとめ:読書感想文の本の選び方【高校生向け】失敗しない5つの基準をプロが解説

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
読書感想文は、正しい「基準」で本を選びさえすれば、決して難しい宿題ではありません。
自分に合った一冊を見つけることは、自分自身を深く知ることにも繋がります。
「おすすめ本」より「選び方」を知ることが最大の近道
誰かが決めた「おすすめ1位」を探すよりも、あなた自身のフィルターで「これだ」と思える本を選ぶ方が、結果的に執筆時間は短くなります。
今日お話しした5つの基準は、あなたが宿題の悩みから解放されるための「地図」だと思って活用して下さい。
本が決まったら次にやるべきこと
本が決まったら、あとはペンを片手に読み始めるだけです。
でも、ただ読むだけではもったいない!以下の3点を意識するだけで、書き始めのスピードが激変します。
・読みながら「心が動いた場所」に線を引く、または付箋を貼る
・読後のメモは「驚いたこと」「納得したこと」「自分の体験」の3つだけで十分
・最初は「正しい感想」ではなく「本への違和感」から書き始めてみる
これだけで、原稿用紙の半分は埋まったも同然です。まずは今日、本屋や図書館へ行って、あなたを助けてくれる「運命の一冊」を決めてしまいましょう。
執筆者のプロフィール
【執筆者プロフィール】
予備校オンラインドットコム編集部

予備校オンラインドットコム編集部は、教育業界や学習塾の専門家集団です。27年以上学習塾に携わった経験者、800以上の教室を調査したアナリスト、オンライン学習塾の運営経験者、ファイナンシャルプランナー、受験メンタルトレーナー、進路アドバイザーなど、多彩な専門家で構成されています。高校生・受験生・保護者の方々が抱える塾選びや勉強の悩みを解決するため、専門的な視点から役立つ情報を発信しています。
予備校オンラインドットコム:公式サイト、公式Instagram
中学受験や高校受験に向けた塾選び、日々の家庭学習でお悩みの方には、姉妹サイトの「塾オンラインドットコム」がおすすめです。小・中学生向けの効率的な勉強法や、後悔しない塾の選び方など、保護者さまが今知りたい情報を専門家が分かりやすく解説しています。ぜひ、あわせて参考にしてください。
